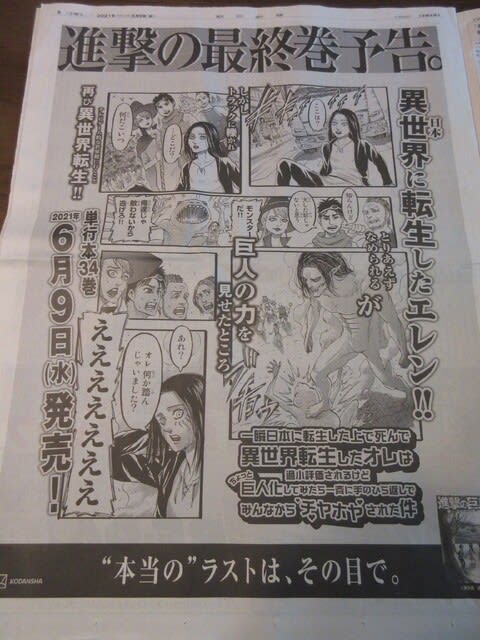「大豆田とわ子」識者はこう見る
「坂元さんは確信犯」
放送中のドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」(フジ系、火曜夜9時)が15日に最終回を迎えます。脚本は、「最高の離婚」「カルテット」などを手がけた坂元裕二さんによるオリジナルで、ドラマ好きをうならせています。
識者はどう見るのか。メディア文化評論家で、多くのドラマ評論を手がける碓井広義さんは、その過去作から「ホップ・ステップ・ジャンプした」と言います。そのわけは――。(8話までのネタバレになる内容が含まれています)
ストーリーよりセリフ
――「大豆田とわ子と三人の元夫」の印象は。
坂元さんの「実験作」であるというのが全体の印象です。ドラマ作りの固定観念に縛られないことを意図してやっているように思えます。
――どういう点が実験作なのですか。
一つは「脱ストーリー」という点です。このドラマは極端に言えば、起承転結がなく、粗筋に意味はありません。ストーリーに頼らないドラマに挑戦しているからです。
どんなドラマでも、例えば、何かが起きて恋が生まれたり、何かの危機にさらされて乗り越えたりといった起伏があるものです。しかし、その辺をとっぱらっている印象です。
ストーリーに代わって、全力投球している印象を受けるのが、登場人物のセリフです。セリフは、人物のそれぞれの個性と関係性から生まれるもの。「ストーリーを追っかけるよりも、セリフを聞いてくれよ」「彼らの関係性を面白がってくれよ」。そんな坂元さんの声が聞こえるような気がします。
――他に新しい点はありますか。
「脱ストーリー」の次に挙げるとしたら、「脱ジャンル」です。
個性的な登場人物たちから生まれる関係性は、恋愛ドラマでもないし、お仕事ドラマとも言いがたい。ジャンルにとらわれないドラマだと言えるでしょう。個性的な登場人物がいて、日常にこそドラマがあることを映し出しているのではないでしょうか。
視聴者を共犯者に
――俳優の伊藤沙莉(さいり)さんが癖になるナレーションをしています。ドラマの冒頭、今週あった出来事として全体の説明をしますが、どんな意図があると思いますか。
最近は、なくなってしまいましたが、「火曜サスペンス劇場」といった2時間ドラマで使われていた「アバンタイトル」ですね。最初に見どころなどをダイジェスト的に見せて、視聴意欲をかき立てます。しかし、このドラマでは、それを見て展開を予想しても、裏切られる。面白い試みです。
――大豆田とわ子がタイトルコールをします。どんな意味があるのでしょうか。
これも画期的なのですが、タイトルコールは、松たか子さんではなく、ドラマの架空の人物、大豆田とわ子が視聴者に語りかけています。
なぜか。思うにこのドラマは、単なるフィクションではないと視聴者に伝えているんだと思います。物語の登場人物が語りかけるのは、「あなたは私のことを見ているけれど、私もあなたのことを見ているわよ」ということ。つまり、ある種の風刺や教訓とかが入った寓話(ぐうわ)だと捉えてほしいのです。
人によっては引いてしまうかもしれないけれど、一方で目が離せなくなる人もいる。視聴者を目撃者、共犯者にする効果があるのでは。
固定観念に縛られない関係性
――坂元さんの過去作と比較して、今作はどういう位置付けにありますか。
「最高の離婚」(フジ系、2013年)「カルテット」(TBS系、17年)、そして「大豆田とわ子と三人の元夫」の流れで見ています。
「最高の離婚」はキャッチフレーズのように言えば「離婚から始まる好き」。坂元さんはずっと「結婚は恋愛のゴールですか?」と投げかけている。
「カルテット」は、舞台のようなセリフ劇をドラマでどこまで成立させられるか挑戦したものでした。しかも、サスペンスの要素も入っていたので、登場人物の言動の不一致が、ハラハラドキドキ感を生み、視聴者は一生懸命、言葉の裏側を読み取ろうとしました。
そして今放送中の「大豆田とわ子と三人の元夫」です。「最高の離婚」に続き、「男女が恋愛をし、結婚して家庭を築く」といった固定観念に縛られない関係性を描いている。その象徴の一人が、亡くなってしまったとわ子の親友・かごめだと思うんですよね。
かごめは男性に好意を寄せられても、こんなセリフを言います。「恋愛が邪魔。女と男の関係がめんどくさいの。私の人生にはいらないの。そういう考えがね、寂しいことは知ってるよ。実際たまに寂しい。でもやっぱり、ただ、ただ、それが、私なんだよ」(4話)
かごめという人物は、男女の関係が面倒くさいという今の若者の気持ちをすくい取っているのかもしれません。1人でいることは孤独ではないし、孤独は悪ではない。男と女の関係も同性同士の関係性も、決まった正解などないと示唆しています。
また、「カルテット」で試みたセリフだけで、どれだけ人間関係を含めて人間の本性というか描けるかという実験もある。「カルテット」では、サスペンス要素がストーリーを構成しましたが、今回はとっぱらってしまった。関係性とセリフだけでドラマを作っていて、過去2作からホップ・ステップ・ジャンプしたと考えています。
「無意識過剰」の人たち
――松田龍平さん、角田晃広さん、岡田将生さんが演じる元夫たちの描き方はどうでしょうか。
他人の目を過剰に気にすれば自意識過剰と言われますが、このドラマに登場する人物はみんな逆です。周りからどう見られるか、あまり気にしていない「無意識過剰」の人たち。一方で、元夫たちとかかわりをもった、3人の女性たち(石橋静河(しずか)ら)の自意識とは異なりますよね。
――元夫たちは社会的な地位が高いといわれそうな職に就いています。
とわ子は社長で、最初の元夫・田中(松田)はレストランのオーナー、2人目の佐藤(角田)はファッションカメラマン、3人目の中村(岡田)は弁護士です。はたから見たら、うらやましい生活であり、社会的な地位や階層は高いかもしれない。皆どこか高等遊民的な部分があり、周りからどう見られるか、あまり気にしていない人物で、とわ子を含め4人は、周りから少しずつはみ出している部分がある。
そこをどう感じるかによります。「面白いな」「いとおしいな」と思えた人は、はまってしまう。逆に、面倒だと敬遠する人もいる。それが視聴率にも表れているのではないでしょうか(8話までの関東地区の世帯視聴率は5・5~7・6%、ビデオリサーチ調べ)。
ストーリーがなくて、登場人物もとらえどころがない。このドラマの楽しみ方がわからないと言う人がいてもおかしくありません。逆に、はまった人はそれらが魅力に感じる。つまり、こんなドラマは今までにないじゃんと。民放のドラマで可能なギリギリを攻めている坂元さんは確信犯だと思っています。【宮田裕介】
(朝日新聞デジタル 2021.06.09)