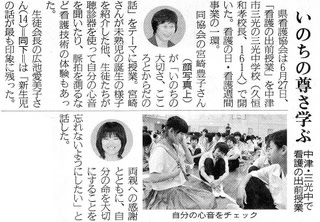布団より紫陽花の花の美しさ
布団より紫陽花の花の美しさ折れそうになる心を戻す

病気と闘っている身近な方が2人います。2人とも突発的なことでしたので、本人はもちろん、ご家族の方も心配されていると思います。
自分自身も30になったころ、外傷で入院を余儀なくされ、いろんな思いの中から、手術に踏み切りました。場所が場所だけに家族は不安な状況に陥りました。結果として、今思えば、思い切って、手術に踏み切ってよかったと感じます。
それは、今のいい状態を創りあげてくれたことです。
しかしそれ以上にそこには、温かい職場、応援してくれた受け持ちの子どもたち、関係する方々、家族・・・たくさんの人に支えられ、今でも感謝の気持ちでいっぱいです。
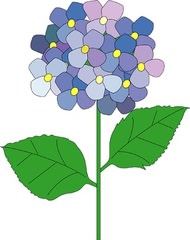
点として考えれば、苦しいことも多くありました。退院してすぐに仕事に復帰しました。薬を片手に教壇に立ちました。体が弱っている時は、子どもたちのエネルギーを真っ正面から受けとめることができないことを痛切に思いました。そして、生活の時間の流れの速さについていけない自分に対するジレンマも感じました。
点として考えると、乗り越える苦しさを感じますが、線として考えると、時間が解決して治癒できて、数年先に健康を感じた喜びに出会えると思います。
先日、病気と闘っている苦しさを話してくれました。そのきつさは本人でないとわからない部分が多いです。
健康で活動をしているときは、感じなかったものが、今、病気になり、健康、家族、周囲のこと・・・また改めて、「たいせつなもの」を想っていることでしょう。
一日も早く、回復されて、勤務できる日を待っています。いっぱいぐちをこぼして、いっぱい悩んで、いっぱい・・・そして、いつか前向きに歩いて行ける日がくることを祈っています。