この夏の上州路旅行で
たまたま牧水の像と歌碑を
見る機会がありました。
上野(かみつけ)の草津の湯より
沢渡(さわたり)の湯に越ゆる路
名も寂し暮坂峠
この暮坂峠にあるものでありました。
今でもひっそりとしたこの峠に
非常に雰囲気良く
建っている歌碑でありましたので、
なべさんは、気に入ってしまいました。
旅行から帰って、若山牧水の
「みなかみ紀行」
を読んでみました。
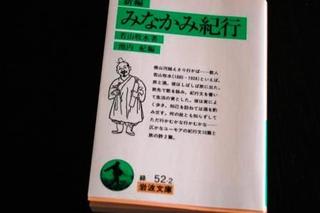
牧水といえば
「幾山河越えさり行かば…」
程度しか知らなかったのですが。
これがなかなか面白いのです。
大正12年の旅は、
佐久・小諸から草津温泉、花敷温泉、
沢渡温泉、四万温泉、法師温泉、
それから片品川を遡って
老神温泉、丸沼へ行き、
金精峠を越えて
日光湯元へ抜けています。
なべさん、花敷温泉を除くと
ほとんど足を運んだことがあるところでした。
(登山のついでですが…)
大正12年の牧水の旅が
どんな風であるか、
自分の行ったことのある風景と
照らし合わせながら読んでいると
ことさら興味深いのであります。
牧水は行く先々で主催する歌誌の
同人達に歓待され、入れ替わり立ち替わり
それらの人が旅の同行者となったり、
はたまた、皆去って一人旅になったりします。
江戸時代の俳諧師の旅が、
その土地の豪農・名士の家に
豪奢に歓待されて旅するのと違って、
牧水を歓待する同人達は
孤独に歌を詠む地方の
農民達であったりします。
何処で歌を作るのかと問われて、
「何処ということもありません、
山ででも野良ででも作ります。」
と言う。
地方で孤独に歌を詠む農民にとって
歌を詠むということは
遠く離れた広い世間への
細いつながりの糸だったようです。
それが何ともしみじみと好ましいです。
「吾妻の渓から六里が原へ」
の紀行文では
泥道の峠をはいずり回るように、
ほうほうの体で登っていく様が
何ともユーモラスであります。
これは哀切感があって、名文ですね。
この夏、出かけた四万温泉では、
牧水さん、随分ひどい目にあったらしい。
牧水さんにこんな風に書かれて、
旅館たむらも100年も記録が
残って悔しいでしょうね。
件の暮坂峠の所は
意外とあっさり書かれているのですが、
大正時代から、今や、
あちこちの風景が変わってしまった現在、
あの暮坂峠は、路こそ舗装されているものの
今でも昔の名残を残して(たぶん)
寂しげにひっそりしているのでありました。
そう思うと、実に絶妙なところに
牧水さんの像と歌碑を建てているものだと
改めてしみじみ思うのでありました。
(なべさん、いつかはまた
牧水さんの旅の後をたどって…
行きたいものでありますね。)




















































































































