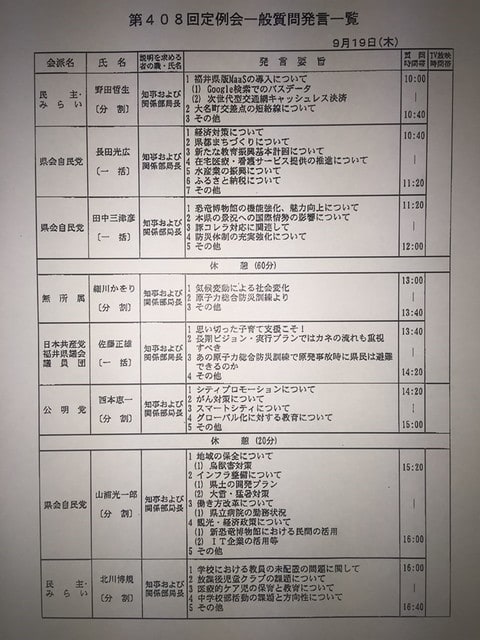2019年7月19日におこなわれた県議会予算決算特別委員会での佐藤正雄委員の質疑です。
「杉本知事の基本姿勢について(教育・新幹線・原子力に関して)」佐藤 正雄 委員
上中中学校での新任教諭の過労自殺事件
◯佐藤委員 日本共産党の佐藤正雄である。
きょうは福井空襲から74年ということであるが、福井空襲では死者1,576人、重軽傷6,400人余ということで、あのような悲惨なことを繰り返してはならないということをまた改めて誓う日だなというように思っている。
質問は、教育行政、新幹線問題、原子力行政ということで、平たく言えば前知事と対決してきたテーマを、きょうは杉本新知事であるので、3つ選ばせていただいて、議論をしたいというように思っている。
それで、西川県政のもとで10年間で10名の教員が自死するなど、現場の教員への過重な負担が異常事態を引き起こしていたというように思う。上中中学校での新任教諭の過労自殺事件は、福井地裁の判決でも校長の安全配慮義務違反が断罪され、賠償命令が下されたところである。知事は、若狭町とともに控訴しないと、判決を受け入れると、こういう態度を表明された。これも評価できると思う。私も総務教育常任委員会で、明らかな過重労働があったということであるので、県としては争うべきではないということを主張した。その翌日に、控訴断念ということが報道された。
そこでお尋ねをしたいのだが、この判決について、知事の率直な受けとめと、このような事態を引き起こした教育現場の実態の問題点の認識、今後の改善方向について知事の見解をお尋ねする。
◯知 事 まずもって、今お話があった上中中学校で自死された先生の冥福をお祈り申し上げるとともに、親族に対してお悔やみを申し上げたいと思う。
今あった上中中学校における先生については、私が伺っているところでは、日ごろから非常に熱心に教育を行っていらっしゃった、4年間臨時教員をやられてから1年目だったというふうに伺っているところである。今回は、その先生が判決によれば過重労働、ある意味1人にされて、その中で悩みながら心を病まれて亡くなられたのかなというふうに思っているけれども、そういうようなことになって、なったということで、判決を重く受けとめて控訴しないという結論を出させていただいたところである。
これについては、やはり福井の先生方というのは非常に熱心に生徒指導をしていただく、これは結果今の学力、体力日本一というような状況にもなっているわけであるけれども、ただ社会環境的にも、先生がやるべきことの範囲がどんどん広がっている。そういう中で先生個人としての時間がなかなか持てなくなっている。そういうことの結果でもあったなというふうに、改善をしていかなければいけない、そういうふうに思っているところである。
また、先生がそういう状況では、子供たちの伸び伸びと育っていく、そういう環境をつくることもできない、こういうことでもあると思う。そういうことで、この2月には業務改善方針をつくって、今取りかかってきているわけであって、私としてもこれを、私、県庁はもちろんであるけども、県教委もそうであるし、市や町の教育委員会、各学校現場である、というものに周知徹底しながら、その方向に沿って改善をしていきたいというふうに思っている。
◯佐藤委員 今、知事、1人でということをおっしゃったのだが、これは1人でというわけでもなくて、要するに指導した教員がおられて、行き過ぎた指導もあったというのをお聞きしているので、その辺の改善も必要だろうというふうに思っている。
ちょっと実務的な話でお尋ねしたいのだが、マスコミの報道によれば、賠償金を若狭町が全額払うのだという報道があったのだが、この辺の仕組みを教えていただきたいというように思う。
◯教育長 上中中学校の事案であるけれども、町立の中学校ということであるので、町の服務監督の下にあったということであるので、国家賠償法の建前から県と町と両方被告になっていたが、損害賠償を実際に行うのは町ということである。
◯佐藤委員 法律のたてつけはそういうことなのだろうけど、その校長先生を任命したのは県の教育委員会の人事だということでもあるので、ちょっと一般県民としては、6,000万円であるか8,000万円であるか、そういう金額を若狭町が単独で負うというのはいかがなものかなと、県としても責任を感じているのであれば、それなりに若狭町と、負担割合はいろいろあるだろうけど、やはり応じるべきではないかなというのは、県民感情としてあるがいかがだろうか。
◯教育長 詳細にいろいろ検討したが、もう最高裁の判例等、それから過去の判例も数件あって、全て町のほうでということになっているので、設置者のほうで負担するということになっているので、それに従わせていただいた。
◯佐藤委員 小さい若狭町がこれだけの8,000万円ぐらいであるか、延滞金も含めれば、巨額のそういう賠償責任を現実的には負うということであるから、ある意味では県の教育委員会も、やっぱりこういうことが二度と起こさないように心して取り組んでいただきたいというふうに思う。
それで、池田中学校では生徒の学校内での自死事件があった。これは事実上の指導死事件として全国的にも議論を巻き起こし、文科省が通知まで出したわけである。2つの事件に共通することの1つは、遺族が初動を含めて学校当局の対応に強い憤りを抱いているということだと思うのである。私自身も、上中中学校の先生の遺族ともお会いしたし、池田の亡くなった生徒さんの遺族とも直接お会いしたけれども、要するに学校側に責任はないのだということが、最初ばーんと遺族に返されるというようなところから、非常に遺族を傷つけたというように思っている。今回は裁判によって、自死の真相を明らかにしたいということで真相が明らかになったわけである。
知事は、福井県の教育界を揺るがしたこの2つの事件について、学校側の対応の問題点、課題をどのように認識し、今後改善を進めるか。お尋ねをする。
◯知 事 最初に、池田中学校で2年生の生徒さんが亡くなられた。この方についても、心から冥福をお祈り申し上げるとともに、遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げる。
その上で、2つの事件について、事案についてのどういう原因であるかといったこと等についてお答えを申し上げる。
まず、池田町の事案については、第三者委員会のほうで明らかにされているのは、担任と副担任がまず生徒さんに対する理解が十分でなかったということ、それから教職員間でそういった状況についての情報の共有ができていなかった、さらには管理職の側で指導監督責任が果たされていなかったということの報告がされているところである。
また、上中中学校の事案については、今回の判決によると、管理職が長時間にわたる勤務実態を認識しながら、業務内容を変更したり負担軽減を図ったり、そういうことをしていなかったということが原因というふうに言われているところである。
児童生徒の指導については、これはもう日ごろからほかの場合も含めてであるけれども、担任一人に任せてしまうと、やはり先生一生懸命やれば先生のほうも疲れるし、また今のお話で担任と児童生徒の間がうまくいっていないと、生徒のほうに物すごくストレスが来る、そういうことになりかねないわけであるので、やはり管理職を中心に、チームの中で生徒を育てていく、そういう、主担当はもちろん担任の先生いるわけであるけれども、そういう中で育てていく、問題があればそれを管理職を中心に解決をしていく、こういうような体制をしっかりとつくっていく必要がある。そのためにも、情報が周りに共有できるような体制にしておくことが必要だと考えているところである。
また、教職員の業務についても、これについては管理職が先生方お一人お一人の勤務の実態、それから精神的な状況も含めて、もしくは仕事の内容そのものも把握をしながら運営をしていくということは重要であるということを考えているところであって、熱心だから任せているとどうしてもそこに集中していくというのは、これはほかの組織もそうだけれども、そういうことになりかねないわけであって、そういうことがないように、これも管理職がしっかりと全体を見渡しながらやっていく。そういったことで私どもも、全体の勤務時間を削減する、そういうような業務の改善方針を持ちながら、さらにはこういったことを学校現場、それから管理職に対して徹底もしていきたいと思っている。
◯佐藤委員 上中中学校の先生には、校長OBの指導教官がついていたわけであるが、校長OBだからといってきちんとした新任教諭に対して指導が適切にできるかといったらやっぱりそうではないと思うのである。必要な研修というのはきちんとやっていくということが必要だというように思っている。
それから、こういう事件も受けて県議会の意見書も出されたが、やはり学力偏重の問題ということで、これは個々の中学校の校長の責任がある、あるいはこちらの中学校の担任、副担任の責任があると、これは個別の案件であるから、そういうことで裁判になったり、報告書でまとめられるわけであるけども、しかしそのベースとして、やはり学力偏重ということで、例えば土日も学校でそういう補習がやられるとか、あるいは上中中学校の先生の例で言えば、もう本当にいわゆる指導する、いわゆる授業の内容のまとめたやつを繰り返し書き直しさせられるというようなことで、やっぱりもちろん指導教官も熱心の余り、あるいは担任、副担任も熱心の余りいろいろそういうことにはなるのだろうが、やはりその背景には、うちの中学校は学力下げちゃいけないと、そういう校長なり担任に対するプレッシャーというのも、これはあったと思うのである。
だから、ここをどうしても脱却をしていかないと、やはりこういう問題というのはなくなっていかないのでは。つまり、労働時間を軽減していくだけで、学力は引き続き全国トップクラスを目指すのだということを、やっぱり現場に圧力をかけ続けて、こういうマニュアルでちゃんとやれという押しつけでは、この問題に解決にならないのじゃないかというように思うが、知事、教育長、どちらでも結構であるが、見解をお尋ねする。
◯教育長 学力トップクラスを維持するためにこうやっているということは決してなくて、それはあくまでも結果であって、やっぱり先生が一人前というか、若い先生であるので、一人前に育つためにいろんな指導が行われたのだと思うけれども、それはどういうふうな授業が子供にとって最適かということを考えたあげくの親心というか、そういう指導もあったのだろうと私は理解しているので、必ずしも初任者に対する研修が行き過ぎていたというばかりではないのではないかと。今一番適切な指導がどうなのだということで、行われた分があったけれども、ただ言葉が行き過ぎたとかそういう面はあったのかもわからないが、それについてはもう知る由もないということであるので、判決をしっかりと我々としては現場の先生に伝えていきたいというふうに思っている。
◯佐藤委員 教育長、そういうことでは本当に判決を真剣に受けとめているのかということも問われてくるし、失礼な言い方になるかもしれないけども、指導が厳しい方だったというように、教育関係の方から聞いている。であるからやはり、そういうことをきちんとしないとやっぱりいけないというように思うのである。だからやっぱり、その背景には一体何があったのかということを見ていかないと、その個人の校長の責任だ、個人の担任の責任だということだけでは問題、根本的な問題の解決にはつながらないと。やはり、福井県のテストテストテストというような、そういう体制の見直しというのを改めて強く求めたいというように思っている。
バス路線の廃止状況は
次に、新幹線の問題であるが、きのうからも議論になっているように、少子高齢化時代ということになっているわけであるが、新幹線と第三セクター鉄道に、今現在、これからも巨額の財政負担ということになってくる。これよりも、本来はそういう少子高齢化時代だからこそ、身近な公共交通の維持、発展のために一層力を尽くすということが必要ではないかと思うのである。
そこでまず、この5年間で廃止され、また現在廃止計画のあるバス路線は何本か、うち福井市内は何本かをお尋ねする。あわせて、もしそれらの路線を維持するとすれば、運行経費というのは年間幾らぐらいかかるのかというのをお尋ねする。
◯地域戦略部長 生活バス路線の廃止であるが、5年間というお尋ねがある。統合とかルートの変更とか、いろんな形があるので、5年全部を把握するというのは結構難しいものがあって、直近1年でお答えをさせていただきたいと思う。
直近1年で申し上げると、利用者の減少に伴う生活路線の廃止については14路線あって、うち福井市内は10路線ということである。これらの路線の欠損額、もし続けていこうとすればこのぐらいの赤字補填をしなきゃいけないという、そういう額として理解いただきたいと思うが、全体の14路線で言うと、その欠損額は約1億円。福井市内の10路線で言うと、約7,000万円というような状況である。
これらの廃止された路線については、全て市町のほうで乗り合いタクシーであるとかコミュニティーバスというふうな形で転換をしているということである。
◯佐藤委員 今、お話があったように、1年だけでも県内全体で14路線、福井市内だけでも10路線が廃止されるということで、これはやっぱり生活環境に大きな影響が出ているというふうに思うのである。であるから、これを全部、今全て県の財政でどうのという話に短絡はできないけれども、やっぱりいろんな公共交通という場合に、新幹線にお金をどれぐらい使っていくのか、在来線の三セク化にどれぐらいお金を使ってくのか、今実際に毛細血管となって動いている身近なバス路線に幾らお金を使っていくのかということを、県民に示していかないと、もうとにかく新幹線と第三セクターはもう何千億円でも使うよということでは、これはなかなか議論としては県民生活、中心部以外のところはどんどん毛細血管であるバス路線もなくなっていく、中心部でもバス路線がなくなっていくということでは、これはいかんのではないかなというように思う。
新幹線の負担はどれだけになるのか
そこで新幹線であるが、新幹線と第三セクターであるけれども、総務教育常任委員会でも質疑したように、第三セクターに関する総事業費はいまだに明らかになっていない。こういう状況のまま、あとで高額の請求書が県民に届くというやり方は、大体大きな問題があるというように思っている。
新幹線の事業費についてであるが、質問の通告で、現在この北陸、信越の管内で言えば、長野、新潟、富山が一応全線新幹線の開業をしているので、そこの総事業費とか自治体負担額を、ちょっと質問通告で出したのだが、それは福井県としてはわからないというように事前に回答があった。であるから、わからないというのはよその県に聞いても教えてくれないのかどうかわからないけれども、それできょうお配りした資料であるが、私のほうで調べさせていただいた。
これは各県庁に、それぞれの日本共産党の県会議員さんから問い合わせをしていただいたという資料である。これを見ていただいたらわかるように、長野県は自治体負担額は654億円と、県民1人当たり3万2,700円と。新潟県は自治体負担額1,384億円と、県民1人当たり6万200円と。富山県は自治体負担額1,889億円と、県民1人当たり18万8,900円ということなのである。石川県と福井県は今工事中であるので、事業費負担額が確定しているわけではないが、石川県庁はざっと1,600億円ということであるので、県民1人当たり13万9,100円ということになる。福井県はどうかということで、また後で答弁もいただきたいのだが、1)、2)とあるのは、1)は富山県と同じ負担割合、約3割弱である、とした場合。2)は石川県と同じ2割程度の負担割合とした場合である。いずれにしても、1)の富山県と同じ負担割合とすれば、県民1人当たり32万5,400円、石川県と同程度とすれば24万1,000円というように、県民1人当たりに換算すれば、要するに長野、新潟と比べるともう大きな、10倍とかそれぐらいの県民1人当たりの負担額ががーっと今膨らんできていると。これも、距離もあるし、工事費の高騰もある。それからいろいろ事情はあるだろうが、結論としてはこういう大きな県民負担になっているということは、これは明らかにしなきゃいけないというように思っているのである。
そこでお尋ねをするが、今、敦賀以西も進めようということでやっておられるわけであるが、敦賀以西の建設も含めて、現在のスキームと建設単価で推計すると、福井県内区間の総事業費は幾らになるのかと。自治体負担額と県民1人当たりの負担は、1人当たりの負担というか、1人当たりの額はそれぞれ幾らになるのか、お尋ねをする。
◯地域戦略部長 お答えする。
まず、金沢-敦賀間の工事における福井県内の総事業費である。これは約9,400億円であって、貸付料2分の1というふうに想定すると、地方負担額は約1,600億円というふうになる。この地方負担については、9割を地方交付税措置のある地方債で賄うというようなことを考えているので、実質的な県の負担ということで言うと、約700億円と見込んでいる。これを人口で割って、県民1人当たりの負担とすると、約9万円と。これは県の実質負担の金額を割っているが。それから県内区間、新大阪まで伸びた場合、石川県境から京都府の県境までということであるが、県内の総事業費については約1兆4,600億円、地方負担については約2,500億円と試算をしている。交付税措置後の実質負担については、約1,000億円というふうになって、県民1人当たりの負担は約14万円、これは全区間という形になるけれども。
以上である。
◯佐藤委員 交付税のことはいろいろこれまでの議会で答弁いただいているが、これはほかの県も同様だと思うのだが、ほかの県はそういうことも含めてこういう数字を回答いただいているので、同じ水準で比較をすればこういうことになると。要するに、長野県は3万2,700円、新潟県は6万200円、福井県の場合は20万円を超えるという、1人当たりの負担になるということだと、いうことは明確にしておきたいというように思っている。
新幹線敦賀開業と在来線特急存続
そこで、これだけの負担なのだということを考えて、さっき言ったようにバランスである。地域の公共交通のバランスを考えていかないと、新幹線ができればそれでいいという話にはならないというように思う。前期の県議会でも、この新幹線については敦賀開業時の特急存続に関して、意見書が全会一致で上げられた。フリーゲージトレインがなくなることにより、とりわけ嶺北地域の利用者には料金アップと乗りかえ不便という大きな問題が生じるわけである。
承知のように、金沢-敦賀間の北陸新幹線の建設B/Cが1.1と、辛うじて1を超えた要因には、フリーゲージトレインによる乗りかえ利便性確保があった。しかし、フリーゲージトレインがなくても1倍であったわけで、不認可にはならなかったというように思うのである。
ところが、承知のように二千数百億円事業費がふえた。そうすると、これ1倍を下回るわけである。であるから、いろんなマスコミでも、おかしいじゃないかというようにたたかれているわけであるけれども、本来なら経済合理性がなく認められなかった公共事業という本質が一面あらわになったというように思っている。
国は当然もう現状の対策、敦賀駅乗りかえで問題がないという考えのようであるが、これでは国民理解、県民理解にはほど遠いと思う。大事なことは、新幹線敦賀駅での乗りかえ利便性の確保と、そしてフリーゲージトレインの代替措置としての在来線特急存続と、これは合わせ技で利用者の利便性を確保すると、このことが必要だと思うが、見解をお尋ねする。
◯知 事 新幹線の福井-敦賀開業については、おっしゃられるとおり在来の特急の存続をどうするか、乗り継ぎをどうしていくのかということは非常に大きな問題だというふうに考えている。その中で、まず第一に大切なことは、敦賀でいずれにしても全てはそのままいくというわけにいかないので、乗り継ぎの利便性をよくしていく、着いたらすぐ特急が出ていくような、そういうような体制をつくっていただく、これはJRに日ごろから、国に対してもお願いをしているというところである。
その上で、またフリーゲージトレインについては、北陸新幹線でフリーゲージトレインを前提として整備を進めるという事実があったことは間違いない。これは国が主導でやっていたわけであるので、私も東京へ行って、6月25日には石井国土交通大臣や、それから自民党の三役の皆さんにも、そのことで国が何とかフリーゲージトレインにかわるもの、これを考えていただくように強く申し上げているところである。
一方で、現実の問題として、既存の特急を、在来線の特急を存続させるということになると、日ごろからも答弁申し上げているけれども、貨物の線路の使用料、これの大幅な減額があるということもあるし、それから新幹線の貸付料も影響を受けてくるということがある。さらには、実際の運用上も、じゃあ車両をどうするのか、運転士さんをどうするのか、こういった問題もあるわけであって、これについてはJRともしっかりと話もしていかなければいけない、そうしないと運転士の確保もできない、こういうような状況にあるわけである。
全ての特急電車を存続させるというのは、正直申し上げても難しい状況なのかなというふうに思う。そういう中で、少しでも利便性を確保する、そういう方法がないのか、こういったことを私どもとしても工夫をしながら、またJRにも協力を求めながら、方法論をこれからもしっかりと考えていきたい、できるだけ存続できるような方向でこれからも交渉していきたいというふうに思っているところである。
◯佐藤委員 実際、その際、国はフリーゲージトレインの開発費用として300億円余りを見込んでいたわけである。開発中止を受けて、単純ではないのだけれど、国の予算であるから。平たく言えば残余のお金もあるということであれば、これを適切に活用して、特急存続への予算措置を求めるべきではないか。
◯地域戦略部長 フリーゲージトレインの整備費として約300億円を用意していたということであるが、その内訳であるけれども、フリーゲージトレイン、またはフル規格の車両、いずれの場合でも使う、走らせる予定の留置線の整備費というのが大層を占めているというような現状である。約8割ぐらいを占めていて、フリーゲージトレイン専用の設備ということで言うと、北陸本線と新幹線の線路を結ぶアプローチ線、その整備費として35億円ということを考えていたというような状況である。
しかし、昨年8月に北陸へのフリーゲージトレインの導入が断念されたということであって、このアプローチ線として考えていた35億円については、工事実施計画から削除されているというような状況である。
このため、現時点では工事実施計画にフリーゲージトレインの整備費というのは含まれていないということであって、今、特急存続のためのお金が別途用意されているというような状況にはないということである。
◯佐藤委員 そんなことはわかっているのである。だけど、実際に35億円、敦賀のために、敦賀というかこの福井のフリーゲージトレインのためにもしお金があった、予定していたのであれば、さっきの貨物、貨物のお金が減るとかいろいろおっしゃるのであれば、そういうお金もこっちに回してくれよということぐらい交渉したらどうだということを言っているわけなのである。
新線基金も活用して小浜線の利便性向上を
現在でも、北陸本線と小浜線の接続の悪さというのは、通勤・通学など利用者、観光客などから指摘されている。新幹線敦賀開業を見据えて、北陸本線、新幹線と小浜線の接続の改善というのが、小浜若狭地域の観光振興あるいはふだんの県民の利便性にとっても不可欠となると思う。
そこで新線基金も活用して、まず運行本数をふやすことによって、現行の接続の改善など、JRに具体的な改善策を示して協議するべきではないか。
◯地域戦略部長 JR小浜線についてであるが、今後の新幹線の開業を見据えて、具体的に関係市町、JRといろいろ協議をしているところである。
主な内容であるけれど、路盤の改良などの強靭化である、降雨とか風が強い日にとまってしまうというような、そういったこともあるので、そういったところの強靭化対策というのが必要であるということ。さらには、高速化を図るという、こういう対策として、が必要ではないかということである。さらには、接続改善のための増便あるいは快速列車、観光列車の運行、こういったことについて具体的に協議をしているところであって、先日も知事が直接JR西日本の来島社長様に増便についても依頼を申し上げたというところである。
その上で、さらには地元の地域が鉄道利用の意識啓発を図ると、いわゆるマイレールというような形であるが、そういったことを地域で示していくことによって、JRに対してそういうアクセス改善の本体を促していきたいというふうに考えている。
◯佐藤委員 JRは民間の企業であるから、もうからないところになかなか列車を走らせないと。だから、乗らないところは便数をどんどん減らすということになってきていると思うのである。であるから、便数が減る、不便になる、またお客さんが減るというこの悪循環を、これやっぱり新幹線開業を見据えてとめないといかんということで、こういう提案もしたので、それは具体的な、ただJRやってくれよというだけではだめなので、そういういろんな財政的なことも含めて協議の俎上にのせたらどうかということは提案をしておきたいというように思う。
老朽原発再稼働と県民への説明責任
最後に、原子力問題であるが、東日本大震災、福島原発事故があった。ああいう事故を二度と繰り返してはならないというのは、杉本知事も私も思いは同じなわけであるが、そこから先がちょっと展開が違ってくるというところはあるのだけれども、いずれにしてもいまだに4万人、5万人とも言われる皆さんのふるさとの生活が取り戻せていないと。小学校も中学校も商店街もなくなり、神社やお寺もお参りの人がいなくなったと、本当に原発事故というのは本当に罰当たりだというように思う。
知事にお尋ねをする。原発の危険性を知った者が原発に依存しない社会を目指すことは、人として将来の子々孫々への責務ではないか。一旦事故が起これば、家族も地域も産業も文化も全て失いかねない原子力発電に依存する政策の転換を求めるが、知事の見解をお尋ねする。
◯知 事 委員指摘のとおり、原子力発電については福島の事故、ああしたことを二度と起こさないということを肝に銘じて、私も県民の安全を第一、最優先ということで、これからもさまざまな課題に対応していきたいと、まず思っているところである。 その上で、原子力発電についてはやはり国民の生活の安定であるとか産業の振興、それからエネルギーの安全保障、こういったような意味で、国が中心になって担っている、そういう安全、原子力政策である。そういう意味で、私どもとしては国にもっとしっかりと自分の役割を果たすようにということで、今のエネルギー基本計画の中でも、原子力の比率を20~22に下げていく、こういうようなことをうたっているわけであって、それに対してまたそういう道筋をどうしていくのかということをしっかり早く明らかにするようにということで、申し上げているわけである。これも、私も国の審議会の委員もさせていただいているので、これからも引き続き強く訴えていきたいと思っている。
また、県内の原子力発電については、私は現実の問題として、40年以上福井県の皆さんは、特に立地地域の皆さんを中心にして、志をもとにこれを、安全に運転を守ってきた、そういう歴史があると思う。その結果として、原子力産業と言えるものが嶺南地域を中心にあって、これらが直接、間接に地域経済、もしくは地域の産業、電気代なんかが安くなるということも含めて、潤わせているということは間違いのない事実である。そういう意味では、こういったことも念頭に置きながら、ただしやはり原子力発電に依存してやっていく、そういう地域経営ではいずれ原子力発電というのはだんだん少なくなっていく、そういうことはエネルギー基本計画の中でも明らかになっているわけであるので、私としては今原子力発電やっている間に、そうした核燃料税やいろんな交付金なんかも活用しながら、地域の振興、永続できる地域、発展できる地域、そういうことをつくっていく必要があると考えているところである。
そういう意味で、原子力発電、CO2フリーのエネルギーであるので、例えば再生可能エネルギーをさらにふやしていく、また廃炉をビジネス化していく、そういうこともあると思う。
また、省エネルギーをそういう地域だからこそさらに進めていく、こういうこともあって、地域全体でスマートコミュニティーみたいなものをつくっていく、こういうことも必要だと思う。それは依存しない地域社会に少しでも近づけるように、今後とも、例えばエネルギー・コーストというような構想も持ちながら進めさせていただきたいと思っているところである。
◯佐藤委員 原発にいつまでも依存すべきではないというのは、知事も認識されていると思うのである。ただそれがもうすぐにやるのか、一定期間を置いてやるのかという違いはあるのだろうけども、やっぱりこれは事故の危険性がある以上、これはやっぱり前倒しでやるべきだというように思っている。
最後の質問になるかもしれないが、知事は一般質問の答弁で、美浜3号機、それから高浜1、2号機の40年超運転については、まず国が運転の必要性、プラントの安全性について国民、県民に対してしっかりと説明をしていただく、そして理解をいただく、そのことが重要だというように答弁された。これは、原子力発電史上初めて未曽有の領域、40年超運転ということに入っていくわけであるから、高浜、美浜という地元での説明は当然である。当然であるが、加えて県民全体の説明の観点ということから、福井市など一定の地域で国と関西電力による責任ある説明会の開催を求めるべきではないか。
◯知 事 40年超運転については、私も先月の25日に、国に対して、立地地域だけではなくて、消費地も含めて必要性それから安全性について国として十分に理解を求めるようにということを申し入れもさせていただいた。
また、関西電力の岩根社長に対しても、同様に立地地域以外も含めて、今申し上げたプラントの安全性それから必要性について、こういったことも安全性について特にしっかりと説明するようにということも申し入れているところである。
私も、県民への理解活動は大変重要なことだというふうに思っている。今後とも、国、事業者、それぞれにおいて福井市などの消費地も含めて、しっかりと説明をしていくように求めていきたいと思っているところである。
~以 上~