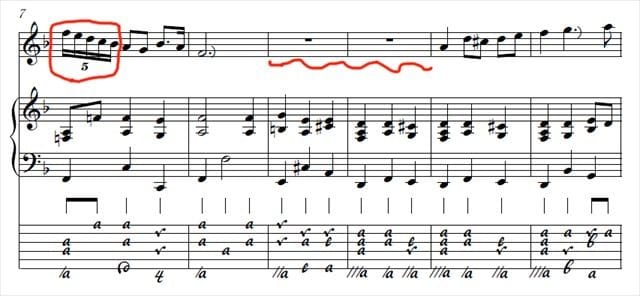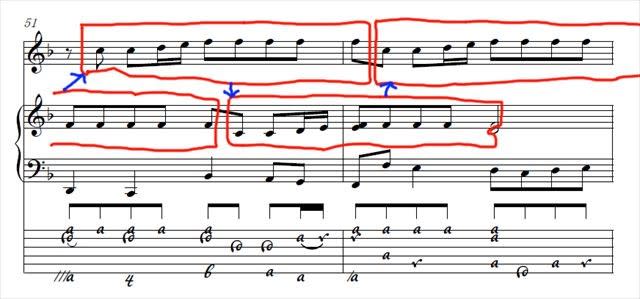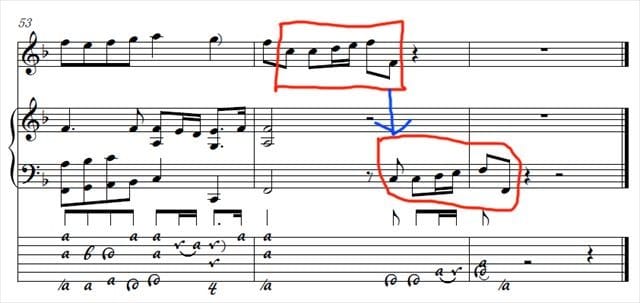最近のスマホで使うイヤホンはBlutooth接続で、左右もワイヤレスで同期をとったタイプのものが主流です。わずらわしいケーブルが全くないのでそれは快適だろうと思います。
ただ落としたり失わないかなぁと思っていましたらやはりそういうケースが結構あるようです。

これはJR東日本の広告ですが、駅のホームから線路にイヤホンを落とす人が結構いるようです。街を歩いているときに落とした場合はすぐ拾えばいいのですが、ホームから線路に落とした場合は拾いに行くわけにもいかず泣く泣く放置ということになるのでしょう。
昔は線路によくタバコのポイ捨てがあって、それを拾うためのマジックハンドがありましたが、そのマジックハンドではイヤホンは掴みにくいそうで、結局そのままになっているのが多いらしいです。
解決策は落ちないようイヤホンの左右をストラップとか紐で繋ぐしかないと思うのですが、そうやっている人は少ないみたいです。
私は街を歩くときに音楽を聴きながら歩くのは怖くてできませんが、電車に乗っているときとかジムでマシンを使っているときなんかはイヤホンで音楽を聴くときがあります。こういうので聴いています。

Shure535というイヤホンを同じくShureの BT2に繋ぎ、Bluetoothで右隣のDAP(Astel & KernのSR15)にワイアレス接続をします。これだとイヤホンを落とすことは絶対にありませんが、BT2に接続するケーブルが首回りにありますので鬱陶しいと言えば鬱陶しいです。でもDAPとはワイアレス接続ですのでまぁ快適かなとは思います。
ただ落としたり失わないかなぁと思っていましたらやはりそういうケースが結構あるようです。

これはJR東日本の広告ですが、駅のホームから線路にイヤホンを落とす人が結構いるようです。街を歩いているときに落とした場合はすぐ拾えばいいのですが、ホームから線路に落とした場合は拾いに行くわけにもいかず泣く泣く放置ということになるのでしょう。
昔は線路によくタバコのポイ捨てがあって、それを拾うためのマジックハンドがありましたが、そのマジックハンドではイヤホンは掴みにくいそうで、結局そのままになっているのが多いらしいです。
解決策は落ちないようイヤホンの左右をストラップとか紐で繋ぐしかないと思うのですが、そうやっている人は少ないみたいです。
私は街を歩くときに音楽を聴きながら歩くのは怖くてできませんが、電車に乗っているときとかジムでマシンを使っているときなんかはイヤホンで音楽を聴くときがあります。こういうので聴いています。

Shure535というイヤホンを同じくShureの BT2に繋ぎ、Bluetoothで右隣のDAP(Astel & KernのSR15)にワイアレス接続をします。これだとイヤホンを落とすことは絶対にありませんが、BT2に接続するケーブルが首回りにありますので鬱陶しいと言えば鬱陶しいです。でもDAPとはワイアレス接続ですのでまぁ快適かなとは思います。