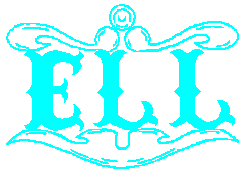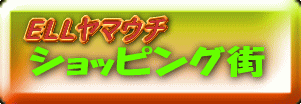日々のパソコン案内板
【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)
【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】
【PDFの簡単セキュリティ】
【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】
【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】
【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】
【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】
【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】
【手書きで書くように分数表記する方法】
【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】
【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】
【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】
iPS細胞を使ったパーキンソ病の治験がようやく始まります!
ただし、重度の患者には効果が薄いらしく、今回は中程度の患者が対象のようですね・・・
まだまだ乗り越えなければならない課題も多いらしいのですが、
保険適用をにらんだ治験には大賛成です。
一人でも多くの患者さんの苦痛が取り除けたらいいですね!
今朝は、この治験に関する記者会見に関する記事を転載してみようと思います。
~以下、7月31日読売新聞朝刊より抜粋~
人のiPS細胞(人工多能性細胞)から脳の神経細胞を作り、パーキンソン病患者に移植する世界初の臨床試験(治験が京都大で始まる。保険適用を見据えた治験とあって早期実用化の期待が高まるが、安全性や効果には未知の部分も多い。脳という人体の中枢に直接注入するため、一層の慎重さが求められる。(大阪科学医療部 諏訪智史、藤沢一紀)

記者会見する京都大iPS細胞研究所の高橋淳教授(左)ら(30日午後、京都市左京区で)=長沖真未撮影

iPS脳移植
安全性見極め
臨床研究と治験
動物実験の結果などを踏まえて、人間を対象に実施する医学研究が「臨床研究」だ。なかでも、薬や医療機器の候補などを使って治療を行い、有効性や安全性を調べる研究は臨床試験と呼ぶケースが多い。このうち、新しい薬や医療機器を保険が適用される一般的な診療で使えるよう国に承認してもらうため、データを集める試験が「治験」だ。iPS細胞を使うような高度な再生医療の臨床研究は、国のチェックを経て実施される決まりになっている。京大治験へ
パーキンソン病 副作用も課題

◆ 自信
「有効性や安全性の評価に関して、これでもかというくらいやってきた自負がある」。京大iPS細胞研究所の高橋淳教授(脳神経外科)は30日、記者会見で治験への自信をのぞかせた。パーキンソン病は脳の神経細胞が減り、運動の指令を伝える物質「ドーパミン」が十分作られなくなる難病。手足のふるえや筋肉のこわばりなどの症状が出る。
治療法としては、ドーパミンの分泌を促す薬の服用が主流だが、症状が進んで神経細胞がさらに減るにつれ、効果も徐々に薄まる。
ドーパミンを出す細胞を脳に移植すれば、病気が進行する前の状態に回復できる可能性があるとして、細胞移植も試みられてきた。
人の神経細胞を得るのは困難で、欧米では中絶した胎児の脳の神経細胞を用いた移植が1980年代以降、400例以上行われている。胎児の細胞は定着しやすく、移植後20年以上、効果が見られたケースが報告されている。
ただ、倫理的な問題から日本では行われてこなかった。ドーパミンを分泌する患者本人の首の神経細胞などを脳に移植する臨床研究が実施されたことはあるが、移植できる細胞数に限りがあり、普及しなかった。
パーキンソン病に詳しい岡山大の伊達勲教授(脳神経外科)は「iPS細胞なら大量に増やせて倫理面の問題も少ない。漸く移植に適した細胞が使えるようになった」と話す。
◆ がん化の恐れ
課題もある。患者は国内に約16万人いるが、治験の対象は薬が切れると自力歩行が困難になる中程度の患者だ。寝たきりなどの重症患者は、移植をしても効果が薄いとみられる。患者の安全確保も焦点になる。iPS細胞から神経細胞になり損ねた不完全な細胞が混じると、がん化する恐れがある。先行して始まった理化学研究所などによる目の難病治療では、移植した細胞を外から観察できたが、今回は脳に移植するための確認が難しい。移植した細胞ががん化した場合、がんを取り除く手術も必要になる。
移植した細胞がドーパミンを出しすぎると、手足が勝手に動く不随運動が起きるリスクもある。この副作用は薬でも起きるが、専門家からは「量を減らして調節できる薬と違い、細胞移植では調節できない」という声も出ている。
移植で病気そのものを治せるわけではないのも課題の一つ。患者の脳では、移植後も病気の原因とされる異常たんぱく質がたまり続け、移植した神経細胞もいずれ死んでしまう恐れがあるためだ。
望月秀樹・大阪大教授(神経内科)は「将来的に期待できる治療法だが、移植した細胞がずっと生き残るのか、長期間安全なのかを慎重に判断する必要がある」と指摘する。