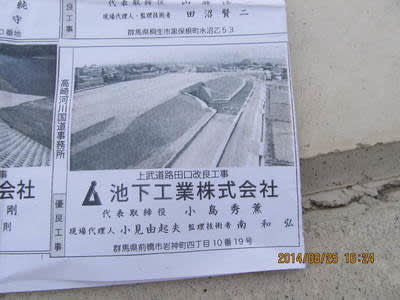■かつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯だった群馬県ですが、この地で22年間オンブズマン活動に従事した経験では、我々の「血税」であっても、役所では「打ち出の小槌」とばかりに、ただ使い切ればよく、その中身は情報不開示にすれば、納税者である県民になど、実態が分かるはずがない、などとする考え方が一向に抜け切れていない様子を感じ取ることができます。我々市民オンブズマン群馬は、役所における税金の無駄遣い廃絶の観点から、原則として地方自治法第2条第14項および地方財政法第4条第1項に定められた「最小経費で最大効果」の観点から、税金の正しい使い方を指南することを活動目的の柱の一つにしてます。
一方、県庁5階に鎮座ましましている県庁記者クラブは、我が国のジャーナリズムの象徴でもありますが、記者クラブについてはこれまでにも「閉鎖的である」「自分で取材しようとせずに聞いたことだけ、ただ、報道している」などというイメージが一般に取りざたされています。そのような“偏見”を振り払うべく、日本新聞協会は開かれた記者クラブを目指すとしており、記者クラブの役割を「公的情報の的確・迅速な報道」「公権力の行使を監視し、一層の情報公開を迫る」「誘拐事件など人命・人権を優先するための取材・報道の調整」「市民からの情報提供の共同の窓口」を目指すとしています。
こうした、いわば2つの権力同士が、毎年懇願会を年中行事的に開催していることについては、議論をもっと尽くす必要があります。
■そのことはさておいて、今回は、この懇談会に群馬県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならでは血税浪費で参加していることについて焦点を当てつつ、住民監査請求に踏み切りました。
これまでの経緯は、2017年1月30日に住民監査請求書を群馬県監査委員あてに提出後、2月10日付で群馬県監査委員から補正命令が送られてきたので、2月15日午前10時過ぎに補正書を群馬県監査委員事務局の窓口に提出したところ、2月21日付で、受理確認と合わせて、証拠の提出及び陳述の機会について通知されました。そして、本日2月27日午後4時から監査委員の前で当会のメンバーが陳述を行いましたので、報告いたします。
報告の趣旨は概ね次の通りです。但し実際には請求人の代理として出席した当会副代表の発言にならいます。
**********
陳 述 書
2017年2月27日(月曜日)16時
請求人:市民オンブズマン群馬代表 小川賢
代理人:市民オンブズマン群馬副代表 大河原宗平
請求人は、本日どうしても都合により出席できないので、代理人である私から陳述をさせていただきます。
それでは、これから陳述を開始します。
群馬県ではかつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯事だったことがあります。
こうした実態は1996年に市民団体の活動から発覚しました。
1996年11月に市民オンブズマン群馬による指摘が発端となり、全庁的に発覚したもので、日帰り出張なのに宿泊したとする手口で裏金を作り、残業代の不足分の手当や備品購入、中央官僚の接待費などに充てていたことが明るみにでました。
当時、庁内の調査で不正だと認められた金額は、調査対象とした1994年度と1995年度の2年間で、合計約7億1700万円に上ったのでした。
当時の副知事が「自主的に返還する」と呼びかけ、職員有志から拠出金をつのった結果、県民も含め、幹部職員と退職者ら約3千人から約9億8700万円が集まりました。
さらに県職員労組がカンパや闘争資金から取り崩した約1億5千万円と合わせ、2年間の不正支出額に利子分5千万円を上乗せした計7億6700万円が、1997年2月に自主返納というかたちで県に返されたのでした。
差額の約3億7千万円は、当時の小寺県知事が「出資者は不特定多数。気持ちをそんたくし、県民も納得する形で使わせて頂きたい」として、とりあえず1996年当時、県職員から寄付を募る窓口だった「県職員公費支出改革会議」の預金通帳に保管されることになりました。
この通帳の管理はその後も歴代の総務課長が引き継いだとされて、10年後の2006年2月の時点で、残高は約3億7600万円となっていたことがわかっています。つまり、カラ出張発覚後10年間、残額の約3億7千万円はほかの使途や返金などを決めずに、事実上放置されていたことになります。
しかもこうした事実や経緯について、1997年の庁内広報紙に一度掲載されましたが、その後は職員らにはもとより、県民への説明は全く行われてきませんでした。
ちなみに、この残高のその後の使途や状況については、現在に至ってもなお、群馬県から県民に対して説明や報告がなされたということを聞いておりません。
こうした中、「カラ出張」問題発覚から10年あまりが経過したころ、県民の知らぬうちに、庁内ではまたもや裏金づくりが行われるようになっていました。
新たな不正経理発覚のきっかけとなったのは2008年10月に会計検査院が指摘した群馬県における不正経理処理問題でした。「経費の使途を正しく申告する」という地方自治法や地方財政法で定められた当たりまえの基本的なことができていなかったことが判明したのでした。
これは架空発注した物品の購入費を業者にプールする「預け金」や、「記またぎ」「差し替え」といった不正経理をおこなうことで、裏金をつくりだす体質が、本質的に群馬県庁内に、はびこっていることを示す結果となりました。
当時の事件の概要については、当会の代表の次のブログ記事をご覧ください。
⇒2009年5月18日付「捜査の端緒に期待して、群馬県の不正経理問題を県警に告発」http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/252.html
それからまた10年近い歳月が経過しています。市民オンブズマン群馬として、群馬県庁内の裏金づくりの体質が少しでも改善されたかどうか、常に関心事として捉えています。
今回の記者クラブと県幹部との懇談会は、本来権力とは一線を画すべき立場にあるマスコミ関係者と、各種権限を有する群馬県行政マンの癒着という社会的に重要な問題に加えて、当会は税金の無駄遣いの観点から注目しています。
なぜなら経費支出に関する県庁内の長年の悪(あ)しき慣習が、10年毎に発覚しており、オンブズマンとしてはこうした体質をひきずっている群馬県の庁内組織の膿(うみ)を定期的に出し尽くさなければならないと考えているからです。
今回提起した住民監査請求では、記者クラブ
主催の懇談会の目的が「大沢知事をはじめ県幹部の皆様方と、これからの県政に関する意見交換を行わせていただきたい」という趣旨であることを踏まえて、次の疑問を払拭することが狙いです。
記者クラブが県庁周辺の宴会場やレストランで毎年開催している知事ら県幹部との懇談会なのに、なぜ群馬県の総務部の課長以下の職員が、準備や設営のために参加できるのか?
庁内では部長クラスは「交際費」という費目で、こうした懇談会の会費を支出しているようだが、課長以下の職員の場合、会費の支出はどのようなかたちで行われているのか?
上記(1)については、主催者の記者クラブ側から総務部の課長以下の職員らの参加を求められているという事実は、開示された資料、つまり今回の住民監査請求で提出させていただいた事実証明書を精査する限り、確認できておりません。
ということは、庁内側で懇談会への参加予定者としてリストアップし、事前に主催者である記者クラブ側に連絡していたことになります。課長以下の参加者は全て総務部に所属していることから、参加予定の職員の選抜は、最終的に総務部長の承認を得なければならないと考えられます。
となれば、表面上は記者クラブが主催する形に見えますが、懇談会の準備や設営を群馬県職員が担当するということは、実質上は群馬県側が会場の設定や交渉、当日の受付業務、会の進行などを主体的に執り行っていることが伺えます。このことは、権限を有する監査委員の皆さんでないと調べることができません。監査委員事務局にまかせっきりにしないで、ぜひ、監査委員の皆さんが直接、関係者から事情聴取をして、証拠の提出を求めて、事実関係を明らかにしてください。
上記(2)については、懇談会に参加した群馬県の課長以下の職員らの会費がどのような形で支出されたのか、ということが監査の重要なポイントだと思われます。
冒頭に述べた通り、群馬県庁内では常に裏金づくりの体質が根強く存在しています。今回、部長クラスの場合には、「交際費」という形で支出されたことは、ホームページに掲載された情報から確認できます。ただし、領収書の写しがホームページ上に掲載されていないため、会費7000円が知事と同様に主催者の記者クラブに支払われたのか、それとも、自ら県で会の準備や設営をしたことから、会場のフォンティーヌに支払われたのかが判然としません。この点について確認が必要かもしれません。
それよりも、今回の住民監査請求では、総務部から参加した広報課、秘書課、財政課の3名の課長と、準備・設営担当の広報課と財政課の4名の職員の合計7名の会費がどこからどのような形で支出されたのか、について明らかにすることが求められます。
請求人は、職員措置請求書の中で、県幹部ではない総務部所属の課長クラス以下7名について、会費一人当たり7000円として、7名で4万9千円が不当に「社会参加費」から支払われたとして、それを決裁したと思われる総務部長に対して、返還させるように群馬県知事に勧告を出すよう求めています。
事実証明書12として「群馬県・総務部の交際費・社会参加費28年4月」という情報を職員措置請求書と共に提出してあります。
その後、監査委員事務局を通じて指摘を受けた「補正」でも述べさせていただいたように、県のホームページにある総務部の「社会参加費」を詳しくチェックしてみても、28年4月分の会費として、件数10、支出額98,000円としか記載がなく、本当にこの中から7名の職員の会費が支出されたのかどうか、定かではありません。
市民オンブズマン群馬で行政の税の無駄遣いを長年、追及している者として、請求人は、こうした不透明な支出についてはきちんと県民に説明し、不正経理の温床をたちきることが最重要視されるべきだと考えています。
さもないと、今回の職員7名の会費が、裏金を原資として支出された可能性が懸念されるからです。
また「社会参加費」から支出された場合、ホームページには、支出項目として「会費」とか「懇談」「賛助会員」「香典」「供花」「見舞い」「お祝い」「記念品等」としか示されておらず、個々の支出先や支出額、支出日についても、全く記載されていません。
やはり、監査委員の皆さんから、知事に対して、こうした不明朗な支出が疑われないように、詳しい支出情報、あるいは領収書をホームページ上に掲載して公表できるよう改善を勧告していただくようお願いする次第です。
そもそも、この「社会参加費」というのは、意味不明な呼称です。群馬県のホームページを見ても、「社会参加費」の執行基準のような情報はどこにも見当たらないからです。
さらに、この「社会参加費」という呼び方について、他の都道府県ではどこもこのような名称を使っていないようです。なぜなら、通常は「交際費」あるいは「食糧費」として支出されるべきものだからです。
このように、今回の住民監査請求では、金額的には5万円以下の少額かもしれませんが、「社会参加費」が裏金で支出されている可能性も否定できない状況なので、監査委員の皆さんには、ぜひ、徹底的に監査をしていただき、県民の目の届かないところで、裏金づくりに励みたがる庁内の悪(あ)しき体質を白日の下にさらしてもらいたいと願っております。
そうすることにより、群馬県庁のDNAとなっている不正経理の温床を、こんどこそ断ち切って、群馬県民、納税者に対して少しでも信頼を取り戻すための、スタートの一歩になるかもしれないです。
以上で、請求人の陳述をおわります。
**********
■上記の陳述内容で、「請求人」「会計検査院」「社会参加費28年4月」など3点ほど監査委員から誤字として指摘がありましたが、概ね陳述内容については理解してもらえたようです。
なお、当日、監査委員で出席したのは代表監査委員の丸山委員と議会選出の須藤委員の2名のみでした。このことについて、監査委員事務局は「陳述人の小川さんが出席するかどうかわからなかったため」などと説明していましたが、この問題について監査委員事務局が十分重要性を認識していないのではないか、と思わせる発言です。
監査委員による監査結果は、おそらく新年度の4月上旬までに当会に通知されるものと思われます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
一方、県庁5階に鎮座ましましている県庁記者クラブは、我が国のジャーナリズムの象徴でもありますが、記者クラブについてはこれまでにも「閉鎖的である」「自分で取材しようとせずに聞いたことだけ、ただ、報道している」などというイメージが一般に取りざたされています。そのような“偏見”を振り払うべく、日本新聞協会は開かれた記者クラブを目指すとしており、記者クラブの役割を「公的情報の的確・迅速な報道」「公権力の行使を監視し、一層の情報公開を迫る」「誘拐事件など人命・人権を優先するための取材・報道の調整」「市民からの情報提供の共同の窓口」を目指すとしています。
こうした、いわば2つの権力同士が、毎年懇願会を年中行事的に開催していることについては、議論をもっと尽くす必要があります。
■そのことはさておいて、今回は、この懇談会に群馬県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならでは血税浪費で参加していることについて焦点を当てつつ、住民監査請求に踏み切りました。
これまでの経緯は、2017年1月30日に住民監査請求書を群馬県監査委員あてに提出後、2月10日付で群馬県監査委員から補正命令が送られてきたので、2月15日午前10時過ぎに補正書を群馬県監査委員事務局の窓口に提出したところ、2月21日付で、受理確認と合わせて、証拠の提出及び陳述の機会について通知されました。そして、本日2月27日午後4時から監査委員の前で当会のメンバーが陳述を行いましたので、報告いたします。
報告の趣旨は概ね次の通りです。但し実際には請求人の代理として出席した当会副代表の発言にならいます。
**********
陳 述 書
2017年2月27日(月曜日)16時
請求人:市民オンブズマン群馬代表 小川賢
代理人:市民オンブズマン群馬副代表 大河原宗平
請求人は、本日どうしても都合により出席できないので、代理人である私から陳述をさせていただきます。
それでは、これから陳述を開始します。
群馬県ではかつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯事だったことがあります。
こうした実態は1996年に市民団体の活動から発覚しました。
1996年11月に市民オンブズマン群馬による指摘が発端となり、全庁的に発覚したもので、日帰り出張なのに宿泊したとする手口で裏金を作り、残業代の不足分の手当や備品購入、中央官僚の接待費などに充てていたことが明るみにでました。
当時、庁内の調査で不正だと認められた金額は、調査対象とした1994年度と1995年度の2年間で、合計約7億1700万円に上ったのでした。
当時の副知事が「自主的に返還する」と呼びかけ、職員有志から拠出金をつのった結果、県民も含め、幹部職員と退職者ら約3千人から約9億8700万円が集まりました。
さらに県職員労組がカンパや闘争資金から取り崩した約1億5千万円と合わせ、2年間の不正支出額に利子分5千万円を上乗せした計7億6700万円が、1997年2月に自主返納というかたちで県に返されたのでした。
差額の約3億7千万円は、当時の小寺県知事が「出資者は不特定多数。気持ちをそんたくし、県民も納得する形で使わせて頂きたい」として、とりあえず1996年当時、県職員から寄付を募る窓口だった「県職員公費支出改革会議」の預金通帳に保管されることになりました。
この通帳の管理はその後も歴代の総務課長が引き継いだとされて、10年後の2006年2月の時点で、残高は約3億7600万円となっていたことがわかっています。つまり、カラ出張発覚後10年間、残額の約3億7千万円はほかの使途や返金などを決めずに、事実上放置されていたことになります。
しかもこうした事実や経緯について、1997年の庁内広報紙に一度掲載されましたが、その後は職員らにはもとより、県民への説明は全く行われてきませんでした。
ちなみに、この残高のその後の使途や状況については、現在に至ってもなお、群馬県から県民に対して説明や報告がなされたということを聞いておりません。
こうした中、「カラ出張」問題発覚から10年あまりが経過したころ、県民の知らぬうちに、庁内ではまたもや裏金づくりが行われるようになっていました。
新たな不正経理発覚のきっかけとなったのは2008年10月に会計検査院が指摘した群馬県における不正経理処理問題でした。「経費の使途を正しく申告する」という地方自治法や地方財政法で定められた当たりまえの基本的なことができていなかったことが判明したのでした。
これは架空発注した物品の購入費を業者にプールする「預け金」や、「記またぎ」「差し替え」といった不正経理をおこなうことで、裏金をつくりだす体質が、本質的に群馬県庁内に、はびこっていることを示す結果となりました。
当時の事件の概要については、当会の代表の次のブログ記事をご覧ください。
⇒2009年5月18日付「捜査の端緒に期待して、群馬県の不正経理問題を県警に告発」http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/252.html
それからまた10年近い歳月が経過しています。市民オンブズマン群馬として、群馬県庁内の裏金づくりの体質が少しでも改善されたかどうか、常に関心事として捉えています。
今回の記者クラブと県幹部との懇談会は、本来権力とは一線を画すべき立場にあるマスコミ関係者と、各種権限を有する群馬県行政マンの癒着という社会的に重要な問題に加えて、当会は税金の無駄遣いの観点から注目しています。
なぜなら経費支出に関する県庁内の長年の悪(あ)しき慣習が、10年毎に発覚しており、オンブズマンとしてはこうした体質をひきずっている群馬県の庁内組織の膿(うみ)を定期的に出し尽くさなければならないと考えているからです。
今回提起した住民監査請求では、記者クラブ
主催の懇談会の目的が「大沢知事をはじめ県幹部の皆様方と、これからの県政に関する意見交換を行わせていただきたい」という趣旨であることを踏まえて、次の疑問を払拭することが狙いです。
記者クラブが県庁周辺の宴会場やレストランで毎年開催している知事ら県幹部との懇談会なのに、なぜ群馬県の総務部の課長以下の職員が、準備や設営のために参加できるのか?
庁内では部長クラスは「交際費」という費目で、こうした懇談会の会費を支出しているようだが、課長以下の職員の場合、会費の支出はどのようなかたちで行われているのか?
上記(1)については、主催者の記者クラブ側から総務部の課長以下の職員らの参加を求められているという事実は、開示された資料、つまり今回の住民監査請求で提出させていただいた事実証明書を精査する限り、確認できておりません。
ということは、庁内側で懇談会への参加予定者としてリストアップし、事前に主催者である記者クラブ側に連絡していたことになります。課長以下の参加者は全て総務部に所属していることから、参加予定の職員の選抜は、最終的に総務部長の承認を得なければならないと考えられます。
となれば、表面上は記者クラブが主催する形に見えますが、懇談会の準備や設営を群馬県職員が担当するということは、実質上は群馬県側が会場の設定や交渉、当日の受付業務、会の進行などを主体的に執り行っていることが伺えます。このことは、権限を有する監査委員の皆さんでないと調べることができません。監査委員事務局にまかせっきりにしないで、ぜひ、監査委員の皆さんが直接、関係者から事情聴取をして、証拠の提出を求めて、事実関係を明らかにしてください。
上記(2)については、懇談会に参加した群馬県の課長以下の職員らの会費がどのような形で支出されたのか、ということが監査の重要なポイントだと思われます。
冒頭に述べた通り、群馬県庁内では常に裏金づくりの体質が根強く存在しています。今回、部長クラスの場合には、「交際費」という形で支出されたことは、ホームページに掲載された情報から確認できます。ただし、領収書の写しがホームページ上に掲載されていないため、会費7000円が知事と同様に主催者の記者クラブに支払われたのか、それとも、自ら県で会の準備や設営をしたことから、会場のフォンティーヌに支払われたのかが判然としません。この点について確認が必要かもしれません。
それよりも、今回の住民監査請求では、総務部から参加した広報課、秘書課、財政課の3名の課長と、準備・設営担当の広報課と財政課の4名の職員の合計7名の会費がどこからどのような形で支出されたのか、について明らかにすることが求められます。
請求人は、職員措置請求書の中で、県幹部ではない総務部所属の課長クラス以下7名について、会費一人当たり7000円として、7名で4万9千円が不当に「社会参加費」から支払われたとして、それを決裁したと思われる総務部長に対して、返還させるように群馬県知事に勧告を出すよう求めています。
事実証明書12として「群馬県・総務部の交際費・社会参加費28年4月」という情報を職員措置請求書と共に提出してあります。
その後、監査委員事務局を通じて指摘を受けた「補正」でも述べさせていただいたように、県のホームページにある総務部の「社会参加費」を詳しくチェックしてみても、28年4月分の会費として、件数10、支出額98,000円としか記載がなく、本当にこの中から7名の職員の会費が支出されたのかどうか、定かではありません。
市民オンブズマン群馬で行政の税の無駄遣いを長年、追及している者として、請求人は、こうした不透明な支出についてはきちんと県民に説明し、不正経理の温床をたちきることが最重要視されるべきだと考えています。
さもないと、今回の職員7名の会費が、裏金を原資として支出された可能性が懸念されるからです。
また「社会参加費」から支出された場合、ホームページには、支出項目として「会費」とか「懇談」「賛助会員」「香典」「供花」「見舞い」「お祝い」「記念品等」としか示されておらず、個々の支出先や支出額、支出日についても、全く記載されていません。
やはり、監査委員の皆さんから、知事に対して、こうした不明朗な支出が疑われないように、詳しい支出情報、あるいは領収書をホームページ上に掲載して公表できるよう改善を勧告していただくようお願いする次第です。
そもそも、この「社会参加費」というのは、意味不明な呼称です。群馬県のホームページを見ても、「社会参加費」の執行基準のような情報はどこにも見当たらないからです。
さらに、この「社会参加費」という呼び方について、他の都道府県ではどこもこのような名称を使っていないようです。なぜなら、通常は「交際費」あるいは「食糧費」として支出されるべきものだからです。
このように、今回の住民監査請求では、金額的には5万円以下の少額かもしれませんが、「社会参加費」が裏金で支出されている可能性も否定できない状況なので、監査委員の皆さんには、ぜひ、徹底的に監査をしていただき、県民の目の届かないところで、裏金づくりに励みたがる庁内の悪(あ)しき体質を白日の下にさらしてもらいたいと願っております。
そうすることにより、群馬県庁のDNAとなっている不正経理の温床を、こんどこそ断ち切って、群馬県民、納税者に対して少しでも信頼を取り戻すための、スタートの一歩になるかもしれないです。
以上で、請求人の陳述をおわります。
**********
■上記の陳述内容で、「請求人」「会計検査院」「社会参加費28年4月」など3点ほど監査委員から誤字として指摘がありましたが、概ね陳述内容については理解してもらえたようです。
なお、当日、監査委員で出席したのは代表監査委員の丸山委員と議会選出の須藤委員の2名のみでした。このことについて、監査委員事務局は「陳述人の小川さんが出席するかどうかわからなかったため」などと説明していましたが、この問題について監査委員事務局が十分重要性を認識していないのではないか、と思わせる発言です。
監査委員による監査結果は、おそらく新年度の4月上旬までに当会に通知されるものと思われます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】