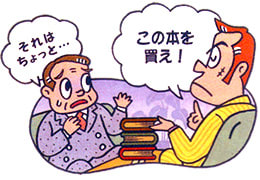■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、昨年末迄に事実上竣工し、本年2月から本格運転が開始され、4月24日には行政関係者を招いて完成披露式=開所式まで開かれてしまいました。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起し、10月26日(金)10時30分から前橋地裁で第11回弁論準備が開かれます。こうした時期に、突然、群馬県が関電工との間で環境アセス免除に関する密約を示す文書が存在しないと主張したことは「正しい」とする審査会の判断をもとに、群馬県知事から、住民の審査請求を棄却する旨の通知が送られてきました。その内容を見てみましょう。

*****審査請求裁決書*****PDF ⇒ 201810161srrp17.pdf
201810162srrp814.pdf
県セ第40-54号
平成30年10月12日
羽鳥 昌行 様
群馬県知事 大澤 正明
(県民センター)
平成28年10月13日付け審査請求に対する裁決書謄本の送付について
あなたから平成28年10月13日に提起のあった審査請求について、別添謄本のとおり裁決をしたので送付します。
担当:生活文化スポーツ部県民センター
情報公関係
電話:027-226-2271(ダイヤルイン)
=====裁決書=====
<P1>
裁 決 書
審査請求人
住所 前橋市鼻毛石町1991-42
氏名 羽鳥 昌行
処 分 庁 群馬県知事
審査請求人が平成28年10月13日に提起した処分庁による群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第18条第2項の規定に基づく公文書不存在決定に対する審査請求について、次のとおり裁決する。
主 文
本件審査請求を棄却する。
第1 事案の概要
1 公文書開示請求
審査請求人(以下「請求人」という。)は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「処分庁」という。)に対し、平成28年9月26日付けで、「前橋バイオマス発電に関し、環境アセスメントの実施の協議に関電工が来た日待及び協議内容。また、アセスメントを実施しなくても良いと報告した、報告手段と通告日、県通告者、関電工被通告者」の開示請求(以下「本件請求j という。)を行った。
2 処分庁の決定
処分庁は、平成28年10月7日、本件請求に係る公文書について存在しないことを確認し、公文書不存在決定(以下「本件処分」という。)を行い、不存在の理由を次のとおり付して、請求人に通知した。
(不存在の理由)
<P2>
環境影響評価は、「群馬県環境影響評価条例」及び「群馬県環境影響評価条例施行規則」に定める事業の種類ごとに、「群馬県環境影響評価条例」及び「群馬県環境影響評価条例施行規則」で定める規模要件等を勘案し、環境影響評価を行うべき事業に該当するか否かを事業者が自ら判断する制度となっている。したがって、環境影響評価に関する手続きの要否について、県に対して書類を提出することや協議することは必要とされていないことから、当該請求に係る文書を保有していないため。
3 審査請求
請求人は、処分庁に対して、本件処分を不服として平成28年10月13日付けで審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。
4 弁明書の送付
処分庁は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の規定に基づき、平成28年11月18日付けで弁明書を作成し、その副本を請求人に送付した。
5 反論書の提出
請求人は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の規定に基づき、平成28年12月23日付け反論書を作成し、処分庁に提出した。
6 諮問
処分庁は、条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成29年1月13日、本件審査請求事案の諮問を行った。
7 意見書の提出
請求人は、条例第32条の規定に基づき、平成29年1月25日付け意見書を作成し、審査会に提出した(諮問庁の閲覧に供することは適切でない旨の意見が提出されており、諮問庁に対して写しの送付はされていない。)。
8 諮問に対する審査会の答申
審査会は、処分庁に対して平成30年9月28日、本件処分は妥当であり取り消す必要はない旨を答申した。
第2 審理関係人の主張の要旨
1 審査請求書における請求人の主張要旨
(1)不存在決定通知書で「環境影響評価を行うべき事業に該当するか否かを事業者が
自ら判断する制度となっているJという主張は、まさに自ら定めた条例や規則を自
<P3>
ら無視したかたちとなり、県民を愚弄する考え方である。
(2)(2)株式会社関電工(以下「関電工」という。)らが事業の事前報告として、平成27年6月下旬ごろに群馬県に提出した文書によると、「平成27年1月に群馬県と環境アセスメントの実施の有無について協議を開始し、同年3月に『実施しなくてよい』と群馬県から回答を受けた」と記載されている。群馬県環境影響評価条例で示された排ガス量が基準を超えたことで、第1種事業に該当する事業であるにも関わらず、環境アセスメントを回避したい関電工は、群馬県と協議を開始したことになる。
(3)これほどまでに重要なテーマに関する話し合いが、関電工と群馬県の聞で何の文書も交わさないで行われたこと自体、我々県民にとって驚きであり、あり得ないことである。
2 弁明書における処分庁の主張要旨
(1)請求内容から、対象公文書は、関電工が前橋市に建設を予定している前橋バイオマス発電施設の環境影響評価に関して、群馬県環境政策課(以下「環境政策課」という。)と関電工が行った協議についての公文書と判断したが、存在しない。不存在決定をした文書は、作成または取得していないものである。
(2)環境影響評価は、環境影響評価法や群馬県環境影響評価条例に定める規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、同法や同条例に基づく環境配慮、手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な対応を行う制度である。したがって、対象事業ごとの規模要件の該当の有無についても、同条例及び同条例施行規則に定める事業の種類ごとに、同条例及び同評価を行うべき事業に該当するか否かを事業者が自ら判断する制度となっている。
そのため、環境影響評価に関する手続きの要否について、県に対して書類を提出することや協議することは必要とされておらず、同条例及び同条例施行規則にもそのような規定はない。
(3)事業者から、訪問や電話等により、環境影響評価の対象事業や規模要件等に関する問合せがあった場合にも、通常は口頭による説明で解決するケースが多く、全ての問合せについて対応記録を作成しているものではない。
(4)平成26年度、関電工から環境政策課に対し、建設を予定している発電施設に関して、群馬県環境影響評価条例及び群馬県環境影響評価条例施行規則で定める規模要件等について問い合わせがあった模様であるが、これら問い合わせ内容については、口頭にて説明したのみであり、「環境影響評価を実施しなくてもよい」と伝達
<P4>
したわけではなく、また、その際の対応記録は作成しなかったものである。
3 反論書における請求人の主張要旨
(1)開示請求公文書の特定について
ア 「無いものは無い」と言われてしまうと元も子もない。しかし、「無いことはないハズである」。それは群馬県が行っていることが、全て関電工の行動にリンクしているからである。したがって、公文書がないという事自体が、役人として問題であるとしか言えないのではないか。関電工の行動を時系列で追うと、平成27年1月に環境政策課と環境アセスメントの実施について協議を開始したと、事業計画書に明記されているからである。そじて、平成27年3月に環境政策課から、「環境アセスメントを実施しなくてよろしいJと回答をもらっている。
イ これを受け、群馬県は、平成27年3月30日に群馬県環境影響評価条例の運用の変更を起案し翌31日に決裁されているが、その内容は、木質バイオマスに限っては、排ガス量を2割減で計算できるようにし、前橋バイオマス発電所が環境アセスメントを実施しなくても良いように画策している。しかも、この文書には担当者の印と日付印しか押印されておらず、協議状況、公印、施行年月日等何も記入されておらず、これが本当に公文書の体を成しているのか、後から作成された文書である可能性だって考えられる。そして、前出のように、関電工だけに、運用開始前に情報を提供し、どこにも審議、報告のないまま、ファイリングされた。したがって、この工作作業は、環境政策課と関電工しか知らない話である。
(2)不存在の解釈について
弁明書によると、「公文書を保有していない」ことの類型のうち、「作成又は取得していない」という類型に該当しているから、非開示の決定になったことのようであるが、環境アセスメントを実施するかどうかの、重要なテーマで何度かにわたり協議をしているのだから、役人のメモだって重要な政策判断になるはずであるが、「公文書に該当しない」という類型には、一切触れていない。メモはあるのかどうか、あっても出さないのか、はっきりとさせるべきである。
(3)公文書が存在しない理由に対する意見について
ア 群馬県環境影響評価条例及び群馬県環境影響評価条例施行規則のどこを見ても、環境影響評価の実施について、事業者自らがその要否も含め、自主的に判断できる制度である旨は書かれていない。同条例第3条には、「群馬県の責務」が書かれている。群馬県は、この責務を全く果たしておらず、果たそうともせず、環境影響評価の重要性の認識が欠知している。
<P5>
イ ここで、群馬県環境基本条例の基本理念を確認しておく。それは、第3条に書かれている。そして、第4条には、群馬県の責務が書かれている。つまり、同条例の3条、4条を見ても、実施対象事業者が、環境影響評価を実施しないことは有り得ず、その指導を行っている群馬県には重大な過失がある。さらに、同条例の6条には事業者の責務が書かれている。したがって、前橋バイオマス発電株式会社は、群馬県環境基本条例の基本理念を無視し、第6条で定めた事業者の責務を全く果たしていない。
ウ 群馬県環境影響評価条例施行規則の別表第1によると、「6 工場又は事業場の新設又は増設の事業については、・・・第1種事業の規模要件については、総排出ガス量・・が4万立方メートル以上・・」とはっきりと明記されている。この時点で、関電工が、環境アセスメントの実施の必要性について群馬県と協議をすること自体が非常に不自然であり、前橋バイオマス発電の排ガス量は、環境政策課からのメールでの回答によると42,000m3/hであり、第1種事業となることは明白である。
エ 群馬県環境影響評価条例の第3章には、「第一種事業に係る環境影響評価に関する手続等」が書かれ、「方法書」の作成義務や、環境影響評価の実施義務が明文化されている。この条文のどこをとっても、事業者が自ら判断できる制度にはなっておらず、群馬県と実施事業者の癒着そのものである。
オ 「環境アセスメント制度のあらまし(環境省)」を見ると、環境影響評価法と条例との関係が示されている。そこには、「条例で環境アセスメントの義務付けができる」とはっきり明記されており、これを見ても、事業者自らの判断に委ねるということは、環境影響評価法に違反している。
カ 関電工と群馬県との関係について、癒着ではないかという疑問について整理しておく。まず、平成27年6月下旬頃に群馬県に提出された事業計画の事前資料によると、関電工は、「平成27年1月に群馬県と環境アセスメントの実施の必要性について協議を開始した」と書かれている。そして、同年3月に群馬県より「環境アセスメントは実施しなくてよい」と回答を得ている。また、弁明書には、「平成26年度、関電工から環境政策課に対し、建設を予定している発電施設に関して、群馬県環境影響評価条例及び群馬県環境影響評価条例施行規則で定める規模要件等」について問い合わせがあった模様であるが、これら問い合わせ内容については、口頭にて説明したのみであり、「環境影響評価を実施しなくてもよい」と伝達したわけで、なく、また、その際の対応記録は作成していなかったものであ
<P6>
る。」とあり、群馬県は白を切っているが、ここでいくつか疑問が起こる。
(ア)なぜ関電工は、条例により環境アセスメントを実施しなければならないのに群馬県と協議したのか。その協議はいつ、どのような内容だったのか。
(イ)群馬県は、結論を出すのに、どうして2ヶ月もかかったのか。
(ウ)群馬県は関電工より「問い合わせがあった模様」と他人事のように言い、また、「口頭で説明した」とあるが、だれが、いつ、どのような内容を説明したのか全く分からない。
(エ)環境アセスメントの実施については、事業者の自主的判断でよいとするものを、運用まで変更し、関電工を守ろうとしたのか。このようなことは、記録メモや口頭でのやり取り全てをまとめ、公開されるべきである。
4 .審査会での口頭説明における処分庁の主張要旨
処分庁と関電工との間で、以下の応対があったとのことである。
(1)平成27年の1月頃に関電工の担当者とその上司が2名で来課して、県の担当者と係長の2名が対応した。
やりとりの内容は、事業の概要を聞いて、その当時の県の条例アセスメント制度の内容及び、関電工の事業内容は条例施行規則の別表第1のどこに該当し、規模要件がどうなっているのかということを説明した。
(2)未利用の木質バイオマスを燃料とする場合、排ガス量の計算にあたり、乾量基準含水率を20%として計算できる、とする運用が3月31日に決裁され、1月からのやりとりを踏まえて、県の担当者が関電工の担当者に電話で連絡を取り、運用の内容を伝えた。なお、事業の内容に関してアセスメントの実施の要否等の判断は県で、は行っていない。
(3)時期についての記憶は確かではないが、関電工から前橋バイオマス発電施設に係る資料を、県の担当者が参考として受け取った可能性がある。
受け取った時期については平成27年1月の来課時かもじれないし、そうではないかもしれず、記憶が暖昧である。
メールで資料を受け取ったという可能性もあるが、現在、メールも資料も存在していない。また、担当者にははっきりとした時期や手段についての詳細な記憶はなく、資料がメールへのPDFなどの添付によるものか、直接受け取ったのかについては、定かではない。なお、通常の事務としては、個人のメールボックスの容量が一杯になると削除することもあるので、メールで受け取っていたとしても、その後に削除した可能性がある。
<P8>
(4)運用に基づいて関電工が計算した結果、排出ガス量は3万9千m3/時余りであり、条例アセスメントの規模要件に該当しないということを県が知ったのは、詳細は定かではないが、平成27年4月以降に関電工の担当者から電話連絡をいただいた時である。
(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)、以外に、関電工と協議なり情報のやりとりがあったということについて、担当者には詳細な記憶はない。関電工が他の所属を訪ねた折に、環境政策課に立ち寄ったということもあったようであるが時期ははっきりしない。あるいは、電話をいただいたこともあったかもしれないとのことだが、時期、回数等についての記憶は定かではない。
話の内容も定かではないが、事業概要についての話をしたのではないかとのことである。
(6)県と関電工の担当者とのやりとりについて、県の担当者が個人のノート等にメモ書きした可能性はあるが、ノート等は既に廃棄をしてしまい、内容等を含めて確認することはできない。
(7)一般的に環境アセスメントについての問い合わせがあった時、書類を残す場合と残さない場合の違いは、当時の判断がどうだったかは分からないが、現状では、条例施行規則別表第1だけでただちに判断できずに確認や検討した上で対応する必要がある場合など、制度の案内だけでは対応できないような案件があった場合に、今後の参考とするためにメモを残すようにしている。
(8)運用に関して、各都道府県・関係市あてにアンケートを行ったのは平成26年の7月だが、木質バイオマス発電に係る条例アセスメントの適用についての検討は、アンケートを行う前から始めており、関電工の来課以前から検討は開始していたものである。
運用が決まってから、県の担当者が関電工の担当者に伝えたが、これは、その時期に相談があった関電工に伝えたということである。
第3 裁決の理由
1 審査会の判断
本件審査請求に対する審査会の判断(平成30年9月28日付け答申第205号)は次のとおりである。なお、以下において実施機関とは処分庁のことをいう。
(1)争点(本件請求に係る公文書を不存在とした決定について)
ア 本件請求に係る公文書が、関電工が前橋市に建設を予定している前橋バイオマ
<P7>
ス発電施設の環境影響評価に関して、環境政策課と関電工が行った協議についての公文書であることについて、双方に争いはない。
請求人は、これほどまでに重要なテーマに関する話し合いが、関電工と群馬県の聞で何の文書も交わさないで行われたことはあり得ないことである等と主張している。一方、実施機関は、本件請求に係る公文書を作成文は取得していないと主張しているので、以下、本件請求に係る公文書が実施機関における事務処理において作成又は取得されたのか否かを検討する。
イ 本件請求に係る公文書が作成文は取得されたかの検討
(ア)本件請求に係る公文書が作成又は取得されたとすれば、関電工の木質バイオマス発電事業の実施に関して実施機関と関電工が協議又は報告を行ったことが前提となる。
実施機関の説明によれば、前記第4 4(1)から(5)のとおり、関電工の木質バイオマス発電事業の実施に関して実施機関と関電工の担当者の間で接触が複数回行われたとのことであるが、公文書は作成又は取得していないとのことである。
(イ)前記第4 2(2)の実施機関の説明によれば、環境影響評価の要否を判断するに際して、群馬県環境影響評価条例及び同条例施行規則では、事業者が県に対して協議することや書類を提出ずることは必要とされていないとのことである。また、同条例では、県が環境影響評価の要否を判断することを求められてはおらず、必要な手続きではないことから文書も作成されていないとのことである。
群馬県環境影響評価条例及び同条例施行規則を見分すると、県が事業者から資料等の提出を受けてその要否を判断すると読み取ることはできないから、実施機関の説明に不合理な点はない。
(ウ)請求人は、群馬県は、群馬県環境影響評価条例の運用の変更を起案し、木質バイオマス発電事業に限っては、排出ガス量を2割減で計算できるようにし、前橋バイオマス発電所が環境アセスメントを実施しなくても良いように画策している等と主張するが、実施機関の説明では、水蒸気量の算定に関する運用を定めるに当たっては、関電工から事業実施についての相談が行われた平成27年1月より前の平成26年7月に全国の都道府県に対し文書による照会を行い検討を開始したとのことである。審査会としても環境政策課においてこの全国への照会に関する文書の検証を行い、そういった状況にあったことを確認した。
<P9>
このことから、関電工からの事業実施についての相談は、運用を定めるための端緒となったと認めることはできず、その内容を記録に残す必要性は低かったとする実施機関の説明に不合理な点はない。
ウ メモについて
請求人は「メモはあるのかどうか、あっても出さないのか、はっきりとさせる
べきである」と主張する。
このことに関して、実施機関の口頭説明によれば、事業者から、環境影響評価の対象事業や規模要件等に関する問合せがあった場合には、口頭による規則の説明だけでは済まないような案件など、後の参考となる事案の場合には、メモを残すようにしているとのことである。今回の案件について個人で使用していたノート等にメモを作成した可能性はあるが、メモを記載した可能性があるノート等は既に廃棄をしてしまったとのことである。
廃棄が行われたことに関しては、個人のノート等に作成されたメモであることや、当時の担当者が既に他部署に異動していることを考慮すれば、メモが記載されたノート等を廃棄したとの実施機関の説明に不合理な点はない。
エ 審査会の調査について
本件審査請求を受け、当審査会は、実施機関に対して条例第30条第4項に基づく調査を実施し、本件請求に係る公文書が作成又は取得されたのか否かを確認するため、環境政策課において公文書の確認を行ったが、本件請求に係る公文書として改めて特定すべき文書の存在は認められなかった。したがって、本件請求に係る実施機関が作成又は取得した公文書が発見できない以上、当審査会としては実施機関が当該文書を作成文は取得していると判断することはできない。
オ 以上のことから、本件請求に係る公文書を不存在とした実施機関の決定に、特
段の不合理な点は認められない。
(2)結論
以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
また、請求人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。
2 当庁の判断及び結論
当庁の判断の理由は、前記1の審査会の判断と同じであることから、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により、主文のとおり裁決する。
<P10>
平成30年10月11日
審査庁 群馬県知事 大澤 正明
<P11>
教 示
1 この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以(訴訟において群馬県を代表する者は群馬県知事となります。)、裁決の取消しの訴えを提起することができます。
ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。
処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。
2 ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した後で、あっても裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
<P12>
この裁決書の謄本は原本と相違ないことを証明する。
平成30年10月12日
群馬県知事 大澤 正明
*********
■今回の裁決書に先立ち、群馬県公文書開示審査会から処分庁に対して出された答申内容は次のとおりです。
※PDF ⇒ 20180928_asses_jouhou_fusonzai_sinsakai_toshin.pdf
群馬県のHPで、公文書開示審査会の会議の開催状況をチェックしましたが、9月28日の会議で答申案が採択されたことは、まだ記事として載っていないようです。
※参考URL「群馬県公文書開示審査会」↓
http://www.pref.gunma.jp/07/c0110028.html
現在の群馬県公文書開示審査会の構成メンバーは、次のとおりです。本件を審査したのは第二b会です。
<委員>
人数 6人
任期 2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
<氏名等>
公文書開示審査会委員名簿一覧
氏名 職業・役職 担当
青木 美穂子 群馬県スクールカウンセラー (第二部会委員)
久保田 寿栄 弁護士(会長) (第一部会長)
宮武 優 弁護士 (第一部会委員)
村上 大樹 弁護士(職務代理者) (第二部会長)
茂木 三枝 中小企業診断士 (第一部会委員)
山崎 由恵 弁護士 (第二部会委員)
※ 五十音順 敬称略 (男性3名、女性3名)
(※注):「崎」は「山へんに竒」だが、機種依存文字のため「崎」と表記
(任期:平成28年10月15日~平成30年10月14日)
■この公文書開示審査会が2年間を費やしてたどり着いた結論というのが、次の内容だというのですから、なんともはや。
「公文書が作成又は取得されたとすれば、木質バイオマス発電事業の実施に関して実施機関と関電工が協議又は報告を行ったことが前提となる。」⇒この大前提に争いは無い。
「実施機関の説明によれば、事業実施に関して実施機関と関電工の担当者の間で接触が複数回行われたが、公文書は作成又は取得していないとのことである。」⇒関電工にも確認したのか??
「実施機関の説明によれば、環境影響評価の要否を判断するに際して、群馬県環境影響評価条例及び同条例施行規則では、事業者が県に対して協議することや書類を提出ずることは必要とされていないとのことである。」⇒いったい何のための条例なのだ??
「また、同条例では、県が環境影響評価の要否を判断することを求められてはおらず、必要な手続きではないことから文書も作成されていないとのことである。」⇒県が要否を判断せずに誰がする??
「群馬県環境影響評価条例及び同条例施行規則を見分すると、県が事業者から資料等の提出を受けてその要否を判断すると読み取ることはできないから、実施機関の説明に不合理な点はない。」⇒環境アセスの要否の判断が事業者なら、アセス条例は無用の長物を意味する。
「実施機関の説明では、水蒸気量の算定に関する運用を定めるに当たっては、関電工から事業実施についての相談が行われた平成27年1月より前の平成26年7月に全国の都道府県に対し文書による照会を行い検討を開始したとのことである。審査会としても環境政策課においてこの全国への照会に関する文書の検証を行い、そういった状況にあったことを確認した。」⇒この照会は水蒸気量とは無関係なのにどうやって確認できたのか??
「このことから、関電工からの事業実施についての相談は、運用を定めるための端緒となったと認めることはできず、その内容を記録に残す必要性は低かったとする実施機関の説明に不合理な点はない。」⇒運用について関電工のみに伝えた事実については、わざと棚上げ。
「メモについて、実施機関の口頭説明によれば、事業者から、環境影響評価の対象事業や規模要件等に関する問合せがあった場合には、口頭による規則の説明だけでは済まないような案件など、後の参考となる事案の場合には、メモを残すようにしているとのことである。」⇒行政の都合の良しあしでメモを廃棄!!
「個人で使用していたノート等にメモを作成した可能性はあるが、メモを記載した可能性があるノート等は既に廃棄をしてしまったとのことである。」⇒証拠隠滅の追認!!
「個人のノート等に作成されたメモであり、当時の担当者が既に他部署に異動していることを考慮すれば、メモが記載されたノート等を廃棄したとの実施機関の説明に不合理な点はない。」⇒笑止千万!!
「環境政策課において公文書の確認を行ったが、本件請求に係る公文書として改めて特定すべき文書の存在は認められなかった。」⇒証拠隠滅を追認!!
「公文書が発見できない以上、実施機関が当該文書を作成文は取得していると判断することはできない。」⇒行政べったりの審査会!!
■アセス条例の特例運用がなされ、その裨益に預かった事業者(関電工ら)とのやりとりに関する情報が存在しなければならないのに、「廃棄したから無い」とする役所の言い分をそのまま鵜吞みにして、「無いものは無い」という判断を中立の立場の審査会がしたこと自体、既に審査会の存在意義を自己否定したことを意味します。
これでは行政の事務事業の正当性を検証する術がありません。こうした行政システムがまかり取っているのが現在の実態です。こんなひどい組織に税金を払わされているかと思うと、情けなくなります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

*****審査請求裁決書*****PDF ⇒ 201810161srrp17.pdf
201810162srrp814.pdf
県セ第40-54号
平成30年10月12日
羽鳥 昌行 様
群馬県知事 大澤 正明
(県民センター)
平成28年10月13日付け審査請求に対する裁決書謄本の送付について
あなたから平成28年10月13日に提起のあった審査請求について、別添謄本のとおり裁決をしたので送付します。
担当:生活文化スポーツ部県民センター
情報公関係
電話:027-226-2271(ダイヤルイン)
=====裁決書=====
<P1>
裁 決 書
審査請求人
住所 前橋市鼻毛石町1991-42
氏名 羽鳥 昌行
処 分 庁 群馬県知事
審査請求人が平成28年10月13日に提起した処分庁による群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第18条第2項の規定に基づく公文書不存在決定に対する審査請求について、次のとおり裁決する。
主 文
本件審査請求を棄却する。
第1 事案の概要
1 公文書開示請求
審査請求人(以下「請求人」という。)は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「処分庁」という。)に対し、平成28年9月26日付けで、「前橋バイオマス発電に関し、環境アセスメントの実施の協議に関電工が来た日待及び協議内容。また、アセスメントを実施しなくても良いと報告した、報告手段と通告日、県通告者、関電工被通告者」の開示請求(以下「本件請求j という。)を行った。
2 処分庁の決定
処分庁は、平成28年10月7日、本件請求に係る公文書について存在しないことを確認し、公文書不存在決定(以下「本件処分」という。)を行い、不存在の理由を次のとおり付して、請求人に通知した。
(不存在の理由)
<P2>
環境影響評価は、「群馬県環境影響評価条例」及び「群馬県環境影響評価条例施行規則」に定める事業の種類ごとに、「群馬県環境影響評価条例」及び「群馬県環境影響評価条例施行規則」で定める規模要件等を勘案し、環境影響評価を行うべき事業に該当するか否かを事業者が自ら判断する制度となっている。したがって、環境影響評価に関する手続きの要否について、県に対して書類を提出することや協議することは必要とされていないことから、当該請求に係る文書を保有していないため。
3 審査請求
請求人は、処分庁に対して、本件処分を不服として平成28年10月13日付けで審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。
4 弁明書の送付
処分庁は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の規定に基づき、平成28年11月18日付けで弁明書を作成し、その副本を請求人に送付した。
5 反論書の提出
請求人は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の規定に基づき、平成28年12月23日付け反論書を作成し、処分庁に提出した。
6 諮問
処分庁は、条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成29年1月13日、本件審査請求事案の諮問を行った。
7 意見書の提出
請求人は、条例第32条の規定に基づき、平成29年1月25日付け意見書を作成し、審査会に提出した(諮問庁の閲覧に供することは適切でない旨の意見が提出されており、諮問庁に対して写しの送付はされていない。)。
8 諮問に対する審査会の答申
審査会は、処分庁に対して平成30年9月28日、本件処分は妥当であり取り消す必要はない旨を答申した。
第2 審理関係人の主張の要旨
1 審査請求書における請求人の主張要旨
(1)不存在決定通知書で「環境影響評価を行うべき事業に該当するか否かを事業者が
自ら判断する制度となっているJという主張は、まさに自ら定めた条例や規則を自
<P3>
ら無視したかたちとなり、県民を愚弄する考え方である。
(2)(2)株式会社関電工(以下「関電工」という。)らが事業の事前報告として、平成27年6月下旬ごろに群馬県に提出した文書によると、「平成27年1月に群馬県と環境アセスメントの実施の有無について協議を開始し、同年3月に『実施しなくてよい』と群馬県から回答を受けた」と記載されている。群馬県環境影響評価条例で示された排ガス量が基準を超えたことで、第1種事業に該当する事業であるにも関わらず、環境アセスメントを回避したい関電工は、群馬県と協議を開始したことになる。
(3)これほどまでに重要なテーマに関する話し合いが、関電工と群馬県の聞で何の文書も交わさないで行われたこと自体、我々県民にとって驚きであり、あり得ないことである。
2 弁明書における処分庁の主張要旨
(1)請求内容から、対象公文書は、関電工が前橋市に建設を予定している前橋バイオマス発電施設の環境影響評価に関して、群馬県環境政策課(以下「環境政策課」という。)と関電工が行った協議についての公文書と判断したが、存在しない。不存在決定をした文書は、作成または取得していないものである。
(2)環境影響評価は、環境影響評価法や群馬県環境影響評価条例に定める規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、同法や同条例に基づく環境配慮、手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な対応を行う制度である。したがって、対象事業ごとの規模要件の該当の有無についても、同条例及び同条例施行規則に定める事業の種類ごとに、同条例及び同評価を行うべき事業に該当するか否かを事業者が自ら判断する制度となっている。
そのため、環境影響評価に関する手続きの要否について、県に対して書類を提出することや協議することは必要とされておらず、同条例及び同条例施行規則にもそのような規定はない。
(3)事業者から、訪問や電話等により、環境影響評価の対象事業や規模要件等に関する問合せがあった場合にも、通常は口頭による説明で解決するケースが多く、全ての問合せについて対応記録を作成しているものではない。
(4)平成26年度、関電工から環境政策課に対し、建設を予定している発電施設に関して、群馬県環境影響評価条例及び群馬県環境影響評価条例施行規則で定める規模要件等について問い合わせがあった模様であるが、これら問い合わせ内容については、口頭にて説明したのみであり、「環境影響評価を実施しなくてもよい」と伝達
<P4>
したわけではなく、また、その際の対応記録は作成しなかったものである。
3 反論書における請求人の主張要旨
(1)開示請求公文書の特定について
ア 「無いものは無い」と言われてしまうと元も子もない。しかし、「無いことはないハズである」。それは群馬県が行っていることが、全て関電工の行動にリンクしているからである。したがって、公文書がないという事自体が、役人として問題であるとしか言えないのではないか。関電工の行動を時系列で追うと、平成27年1月に環境政策課と環境アセスメントの実施について協議を開始したと、事業計画書に明記されているからである。そじて、平成27年3月に環境政策課から、「環境アセスメントを実施しなくてよろしいJと回答をもらっている。
イ これを受け、群馬県は、平成27年3月30日に群馬県環境影響評価条例の運用の変更を起案し翌31日に決裁されているが、その内容は、木質バイオマスに限っては、排ガス量を2割減で計算できるようにし、前橋バイオマス発電所が環境アセスメントを実施しなくても良いように画策している。しかも、この文書には担当者の印と日付印しか押印されておらず、協議状況、公印、施行年月日等何も記入されておらず、これが本当に公文書の体を成しているのか、後から作成された文書である可能性だって考えられる。そして、前出のように、関電工だけに、運用開始前に情報を提供し、どこにも審議、報告のないまま、ファイリングされた。したがって、この工作作業は、環境政策課と関電工しか知らない話である。
(2)不存在の解釈について
弁明書によると、「公文書を保有していない」ことの類型のうち、「作成又は取得していない」という類型に該当しているから、非開示の決定になったことのようであるが、環境アセスメントを実施するかどうかの、重要なテーマで何度かにわたり協議をしているのだから、役人のメモだって重要な政策判断になるはずであるが、「公文書に該当しない」という類型には、一切触れていない。メモはあるのかどうか、あっても出さないのか、はっきりとさせるべきである。
(3)公文書が存在しない理由に対する意見について
ア 群馬県環境影響評価条例及び群馬県環境影響評価条例施行規則のどこを見ても、環境影響評価の実施について、事業者自らがその要否も含め、自主的に判断できる制度である旨は書かれていない。同条例第3条には、「群馬県の責務」が書かれている。群馬県は、この責務を全く果たしておらず、果たそうともせず、環境影響評価の重要性の認識が欠知している。
<P5>
イ ここで、群馬県環境基本条例の基本理念を確認しておく。それは、第3条に書かれている。そして、第4条には、群馬県の責務が書かれている。つまり、同条例の3条、4条を見ても、実施対象事業者が、環境影響評価を実施しないことは有り得ず、その指導を行っている群馬県には重大な過失がある。さらに、同条例の6条には事業者の責務が書かれている。したがって、前橋バイオマス発電株式会社は、群馬県環境基本条例の基本理念を無視し、第6条で定めた事業者の責務を全く果たしていない。
ウ 群馬県環境影響評価条例施行規則の別表第1によると、「6 工場又は事業場の新設又は増設の事業については、・・・第1種事業の規模要件については、総排出ガス量・・が4万立方メートル以上・・」とはっきりと明記されている。この時点で、関電工が、環境アセスメントの実施の必要性について群馬県と協議をすること自体が非常に不自然であり、前橋バイオマス発電の排ガス量は、環境政策課からのメールでの回答によると42,000m3/hであり、第1種事業となることは明白である。
エ 群馬県環境影響評価条例の第3章には、「第一種事業に係る環境影響評価に関する手続等」が書かれ、「方法書」の作成義務や、環境影響評価の実施義務が明文化されている。この条文のどこをとっても、事業者が自ら判断できる制度にはなっておらず、群馬県と実施事業者の癒着そのものである。
オ 「環境アセスメント制度のあらまし(環境省)」を見ると、環境影響評価法と条例との関係が示されている。そこには、「条例で環境アセスメントの義務付けができる」とはっきり明記されており、これを見ても、事業者自らの判断に委ねるということは、環境影響評価法に違反している。
カ 関電工と群馬県との関係について、癒着ではないかという疑問について整理しておく。まず、平成27年6月下旬頃に群馬県に提出された事業計画の事前資料によると、関電工は、「平成27年1月に群馬県と環境アセスメントの実施の必要性について協議を開始した」と書かれている。そして、同年3月に群馬県より「環境アセスメントは実施しなくてよい」と回答を得ている。また、弁明書には、「平成26年度、関電工から環境政策課に対し、建設を予定している発電施設に関して、群馬県環境影響評価条例及び群馬県環境影響評価条例施行規則で定める規模要件等」について問い合わせがあった模様であるが、これら問い合わせ内容については、口頭にて説明したのみであり、「環境影響評価を実施しなくてもよい」と伝達したわけで、なく、また、その際の対応記録は作成していなかったものであ
<P6>
る。」とあり、群馬県は白を切っているが、ここでいくつか疑問が起こる。
(ア)なぜ関電工は、条例により環境アセスメントを実施しなければならないのに群馬県と協議したのか。その協議はいつ、どのような内容だったのか。
(イ)群馬県は、結論を出すのに、どうして2ヶ月もかかったのか。
(ウ)群馬県は関電工より「問い合わせがあった模様」と他人事のように言い、また、「口頭で説明した」とあるが、だれが、いつ、どのような内容を説明したのか全く分からない。
(エ)環境アセスメントの実施については、事業者の自主的判断でよいとするものを、運用まで変更し、関電工を守ろうとしたのか。このようなことは、記録メモや口頭でのやり取り全てをまとめ、公開されるべきである。
4 .審査会での口頭説明における処分庁の主張要旨
処分庁と関電工との間で、以下の応対があったとのことである。
(1)平成27年の1月頃に関電工の担当者とその上司が2名で来課して、県の担当者と係長の2名が対応した。
やりとりの内容は、事業の概要を聞いて、その当時の県の条例アセスメント制度の内容及び、関電工の事業内容は条例施行規則の別表第1のどこに該当し、規模要件がどうなっているのかということを説明した。
(2)未利用の木質バイオマスを燃料とする場合、排ガス量の計算にあたり、乾量基準含水率を20%として計算できる、とする運用が3月31日に決裁され、1月からのやりとりを踏まえて、県の担当者が関電工の担当者に電話で連絡を取り、運用の内容を伝えた。なお、事業の内容に関してアセスメントの実施の要否等の判断は県で、は行っていない。
(3)時期についての記憶は確かではないが、関電工から前橋バイオマス発電施設に係る資料を、県の担当者が参考として受け取った可能性がある。
受け取った時期については平成27年1月の来課時かもじれないし、そうではないかもしれず、記憶が暖昧である。
メールで資料を受け取ったという可能性もあるが、現在、メールも資料も存在していない。また、担当者にははっきりとした時期や手段についての詳細な記憶はなく、資料がメールへのPDFなどの添付によるものか、直接受け取ったのかについては、定かではない。なお、通常の事務としては、個人のメールボックスの容量が一杯になると削除することもあるので、メールで受け取っていたとしても、その後に削除した可能性がある。
<P8>
(4)運用に基づいて関電工が計算した結果、排出ガス量は3万9千m3/時余りであり、条例アセスメントの規模要件に該当しないということを県が知ったのは、詳細は定かではないが、平成27年4月以降に関電工の担当者から電話連絡をいただいた時である。
(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)、以外に、関電工と協議なり情報のやりとりがあったということについて、担当者には詳細な記憶はない。関電工が他の所属を訪ねた折に、環境政策課に立ち寄ったということもあったようであるが時期ははっきりしない。あるいは、電話をいただいたこともあったかもしれないとのことだが、時期、回数等についての記憶は定かではない。
話の内容も定かではないが、事業概要についての話をしたのではないかとのことである。
(6)県と関電工の担当者とのやりとりについて、県の担当者が個人のノート等にメモ書きした可能性はあるが、ノート等は既に廃棄をしてしまい、内容等を含めて確認することはできない。
(7)一般的に環境アセスメントについての問い合わせがあった時、書類を残す場合と残さない場合の違いは、当時の判断がどうだったかは分からないが、現状では、条例施行規則別表第1だけでただちに判断できずに確認や検討した上で対応する必要がある場合など、制度の案内だけでは対応できないような案件があった場合に、今後の参考とするためにメモを残すようにしている。
(8)運用に関して、各都道府県・関係市あてにアンケートを行ったのは平成26年の7月だが、木質バイオマス発電に係る条例アセスメントの適用についての検討は、アンケートを行う前から始めており、関電工の来課以前から検討は開始していたものである。
運用が決まってから、県の担当者が関電工の担当者に伝えたが、これは、その時期に相談があった関電工に伝えたということである。
第3 裁決の理由
1 審査会の判断
本件審査請求に対する審査会の判断(平成30年9月28日付け答申第205号)は次のとおりである。なお、以下において実施機関とは処分庁のことをいう。
(1)争点(本件請求に係る公文書を不存在とした決定について)
ア 本件請求に係る公文書が、関電工が前橋市に建設を予定している前橋バイオマ
<P7>
ス発電施設の環境影響評価に関して、環境政策課と関電工が行った協議についての公文書であることについて、双方に争いはない。
請求人は、これほどまでに重要なテーマに関する話し合いが、関電工と群馬県の聞で何の文書も交わさないで行われたことはあり得ないことである等と主張している。一方、実施機関は、本件請求に係る公文書を作成文は取得していないと主張しているので、以下、本件請求に係る公文書が実施機関における事務処理において作成又は取得されたのか否かを検討する。
イ 本件請求に係る公文書が作成文は取得されたかの検討
(ア)本件請求に係る公文書が作成又は取得されたとすれば、関電工の木質バイオマス発電事業の実施に関して実施機関と関電工が協議又は報告を行ったことが前提となる。
実施機関の説明によれば、前記第4 4(1)から(5)のとおり、関電工の木質バイオマス発電事業の実施に関して実施機関と関電工の担当者の間で接触が複数回行われたとのことであるが、公文書は作成又は取得していないとのことである。
(イ)前記第4 2(2)の実施機関の説明によれば、環境影響評価の要否を判断するに際して、群馬県環境影響評価条例及び同条例施行規則では、事業者が県に対して協議することや書類を提出ずることは必要とされていないとのことである。また、同条例では、県が環境影響評価の要否を判断することを求められてはおらず、必要な手続きではないことから文書も作成されていないとのことである。
群馬県環境影響評価条例及び同条例施行規則を見分すると、県が事業者から資料等の提出を受けてその要否を判断すると読み取ることはできないから、実施機関の説明に不合理な点はない。
(ウ)請求人は、群馬県は、群馬県環境影響評価条例の運用の変更を起案し、木質バイオマス発電事業に限っては、排出ガス量を2割減で計算できるようにし、前橋バイオマス発電所が環境アセスメントを実施しなくても良いように画策している等と主張するが、実施機関の説明では、水蒸気量の算定に関する運用を定めるに当たっては、関電工から事業実施についての相談が行われた平成27年1月より前の平成26年7月に全国の都道府県に対し文書による照会を行い検討を開始したとのことである。審査会としても環境政策課においてこの全国への照会に関する文書の検証を行い、そういった状況にあったことを確認した。
<P9>
このことから、関電工からの事業実施についての相談は、運用を定めるための端緒となったと認めることはできず、その内容を記録に残す必要性は低かったとする実施機関の説明に不合理な点はない。
ウ メモについて
請求人は「メモはあるのかどうか、あっても出さないのか、はっきりとさせる
べきである」と主張する。
このことに関して、実施機関の口頭説明によれば、事業者から、環境影響評価の対象事業や規模要件等に関する問合せがあった場合には、口頭による規則の説明だけでは済まないような案件など、後の参考となる事案の場合には、メモを残すようにしているとのことである。今回の案件について個人で使用していたノート等にメモを作成した可能性はあるが、メモを記載した可能性があるノート等は既に廃棄をしてしまったとのことである。
廃棄が行われたことに関しては、個人のノート等に作成されたメモであることや、当時の担当者が既に他部署に異動していることを考慮すれば、メモが記載されたノート等を廃棄したとの実施機関の説明に不合理な点はない。
エ 審査会の調査について
本件審査請求を受け、当審査会は、実施機関に対して条例第30条第4項に基づく調査を実施し、本件請求に係る公文書が作成又は取得されたのか否かを確認するため、環境政策課において公文書の確認を行ったが、本件請求に係る公文書として改めて特定すべき文書の存在は認められなかった。したがって、本件請求に係る実施機関が作成又は取得した公文書が発見できない以上、当審査会としては実施機関が当該文書を作成文は取得していると判断することはできない。
オ 以上のことから、本件請求に係る公文書を不存在とした実施機関の決定に、特
段の不合理な点は認められない。
(2)結論
以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
また、請求人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。
2 当庁の判断及び結論
当庁の判断の理由は、前記1の審査会の判断と同じであることから、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により、主文のとおり裁決する。
<P10>
平成30年10月11日
審査庁 群馬県知事 大澤 正明
<P11>
教 示
1 この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以(訴訟において群馬県を代表する者は群馬県知事となります。)、裁決の取消しの訴えを提起することができます。
ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。
処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。
2 ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した後で、あっても裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
<P12>
この裁決書の謄本は原本と相違ないことを証明する。
平成30年10月12日
群馬県知事 大澤 正明
*********
■今回の裁決書に先立ち、群馬県公文書開示審査会から処分庁に対して出された答申内容は次のとおりです。
※PDF ⇒ 20180928_asses_jouhou_fusonzai_sinsakai_toshin.pdf
群馬県のHPで、公文書開示審査会の会議の開催状況をチェックしましたが、9月28日の会議で答申案が採択されたことは、まだ記事として載っていないようです。
※参考URL「群馬県公文書開示審査会」↓
http://www.pref.gunma.jp/07/c0110028.html
現在の群馬県公文書開示審査会の構成メンバーは、次のとおりです。本件を審査したのは第二b会です。
<委員>
人数 6人
任期 2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
<氏名等>
公文書開示審査会委員名簿一覧
氏名 職業・役職 担当
青木 美穂子 群馬県スクールカウンセラー (第二部会委員)
久保田 寿栄 弁護士(会長) (第一部会長)
宮武 優 弁護士 (第一部会委員)
村上 大樹 弁護士(職務代理者) (第二部会長)
茂木 三枝 中小企業診断士 (第一部会委員)
山崎 由恵 弁護士 (第二部会委員)
※ 五十音順 敬称略 (男性3名、女性3名)
(※注):「崎」は「山へんに竒」だが、機種依存文字のため「崎」と表記
(任期:平成28年10月15日~平成30年10月14日)
■この公文書開示審査会が2年間を費やしてたどり着いた結論というのが、次の内容だというのですから、なんともはや。
「公文書が作成又は取得されたとすれば、木質バイオマス発電事業の実施に関して実施機関と関電工が協議又は報告を行ったことが前提となる。」⇒この大前提に争いは無い。
「実施機関の説明によれば、事業実施に関して実施機関と関電工の担当者の間で接触が複数回行われたが、公文書は作成又は取得していないとのことである。」⇒関電工にも確認したのか??
「実施機関の説明によれば、環境影響評価の要否を判断するに際して、群馬県環境影響評価条例及び同条例施行規則では、事業者が県に対して協議することや書類を提出ずることは必要とされていないとのことである。」⇒いったい何のための条例なのだ??
「また、同条例では、県が環境影響評価の要否を判断することを求められてはおらず、必要な手続きではないことから文書も作成されていないとのことである。」⇒県が要否を判断せずに誰がする??
「群馬県環境影響評価条例及び同条例施行規則を見分すると、県が事業者から資料等の提出を受けてその要否を判断すると読み取ることはできないから、実施機関の説明に不合理な点はない。」⇒環境アセスの要否の判断が事業者なら、アセス条例は無用の長物を意味する。
「実施機関の説明では、水蒸気量の算定に関する運用を定めるに当たっては、関電工から事業実施についての相談が行われた平成27年1月より前の平成26年7月に全国の都道府県に対し文書による照会を行い検討を開始したとのことである。審査会としても環境政策課においてこの全国への照会に関する文書の検証を行い、そういった状況にあったことを確認した。」⇒この照会は水蒸気量とは無関係なのにどうやって確認できたのか??
「このことから、関電工からの事業実施についての相談は、運用を定めるための端緒となったと認めることはできず、その内容を記録に残す必要性は低かったとする実施機関の説明に不合理な点はない。」⇒運用について関電工のみに伝えた事実については、わざと棚上げ。
「メモについて、実施機関の口頭説明によれば、事業者から、環境影響評価の対象事業や規模要件等に関する問合せがあった場合には、口頭による規則の説明だけでは済まないような案件など、後の参考となる事案の場合には、メモを残すようにしているとのことである。」⇒行政の都合の良しあしでメモを廃棄!!
「個人で使用していたノート等にメモを作成した可能性はあるが、メモを記載した可能性があるノート等は既に廃棄をしてしまったとのことである。」⇒証拠隠滅の追認!!
「個人のノート等に作成されたメモであり、当時の担当者が既に他部署に異動していることを考慮すれば、メモが記載されたノート等を廃棄したとの実施機関の説明に不合理な点はない。」⇒笑止千万!!
「環境政策課において公文書の確認を行ったが、本件請求に係る公文書として改めて特定すべき文書の存在は認められなかった。」⇒証拠隠滅を追認!!
「公文書が発見できない以上、実施機関が当該文書を作成文は取得していると判断することはできない。」⇒行政べったりの審査会!!
■アセス条例の特例運用がなされ、その裨益に預かった事業者(関電工ら)とのやりとりに関する情報が存在しなければならないのに、「廃棄したから無い」とする役所の言い分をそのまま鵜吞みにして、「無いものは無い」という判断を中立の立場の審査会がしたこと自体、既に審査会の存在意義を自己否定したことを意味します。
これでは行政の事務事業の正当性を検証する術がありません。こうした行政システムがまかり取っているのが現在の実態です。こんなひどい組織に税金を払わされているかと思うと、情けなくなります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】