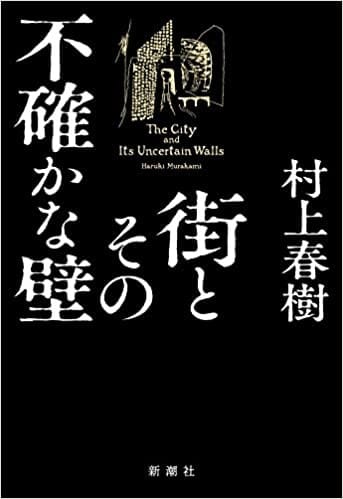
GWの3日間はこの本を読んで過ごした。最初の1日、5月1日に350ページまで読んだ。実は4月30日の夜、冒頭の50ページまで読んでいる。少年と少女の出逢いから始まる。彼は16歳、彼女は15歳。高校生だ。初々しいラブストーリーになる。1年後、ふたりは17歳と16歳になった。当然だが。話はそこから始まる。
第一部は長い長い導入で、いつまで経っても話が始まらない。いいかげんうんざりしてしまう。それは184ページまで続く。そしてお話は第二部から始まる。少年は40代後半、中年男になっている。長年勤めていた仕事を辞めて無職になる。同じように無職の僕はそれだけで、なんだかドキドキしてしまう。そして彼は福島県の田舎町の小さな図書館の館長になる。僕も昔1年だけ図書館の館長をしたことがある。高校の図書主任を任された。いつものようにクラス担任でよかったのに校長から頼まれたから仕方なく引き受けた。本は好きだから、1年くらいの期間ならいいかぁと思ったけど、退屈だった。毎月図書便りを書くことが求められたが、読んだ本の感想ばかりを綴っていた。しかも、印刷せずに、コピーして教室に掲示してもらった。印刷して全員配布なんておこがましい。紙がもったいないし。読みたい人だけが、立ち止まって読めばいい。
さて、この本である。1日で半分くらいまで読んだ。2日は1日映画に行っていたからあまり読めてない。(重たいから持ち運びするのは嫌なので家に置いていったし)3日に残りの200ページを読み切った。660ページまで。
と、ここまで書いたが、実はまだ今日は2日の朝で、今「その街に行かなくてはならない」と16歳のイエローサブマリンの少年が言ったところまで読んだところだ。とても天気がいい火曜日の朝。これから映画を3本見てくるところだ。
改めて、これは村上春樹の最新刊だ。しかも久しぶりの長編である。40年前に書いた(まま、単行本には収録しなかった)中編小説を1200枚の長編として完成させた。コロナ禍の3年で書いた(と、後書きにはある)から、僕はこのコロナ明け(たぶん)のGWの3日で読むことにした。
ということで、今ちゃんと読み切った。5月3日の朝8時30分。今日もいい天気だ。蝋燭の火を吹き消すラストまで、3日間で。とても面白かった。昨日見た3本の映画も面白かったが、そこで見た映画がたまたまこの小説と同じような映画だった。不思議な話だ。2018年の中国映画『郊外の鳥たち』。このGWにようやく日本でも公開されたばかりだ。後でじっくりこの作品についても書くけど、今はまず村上春樹だ。
これだけの長編を読んだのに、あまりそんな感じ(長かった、という)はしない。第二部のラスト、「わたしたちは二人とも、ただの誰かの影に過ぎないのよ。」という彼女のことばでお話はすべては終わっている。そこから始まる第三部は再び壁の街に戻るが、これは少し長いエピローグでしかない。彼は現実の世界でコーヒー店の女性と出会い、ゆっくりと付き合い始める。ありきたりのラブストーリーになる。それが人生だ。特別なんてない。あるとすれば、すべての出来事は特別なことだ、ということである。現実の世界と夢の中の世界。ふたつの世界を往還する男。実態と影。ふたつがセットになって人は実在する。だが、そのふたつが分断されたなら。
お話は図書館が舞台になっている。そこでも壁の街の図書館と現実世界の図書館とふたつ。でも、そのふたつは実は表裏一体となっている。夢読みとして、本のない図書館に通う。館長として実務をこなす。16歳の少女、子易さん、イエローサブマリンの少年は、意識と心が統合されていない存在なのかもしれない。主人公はそんな彼らと向き合う。彼は第1部の終わりで影と離別したはずなのに影に導かれて現実世界に戻ってきた。気づくと意識と心(実態と影)は一体化されていたからだ。
3つの小説を読んだ気分だ。それは繋がっているけど、独立した作品でもある。中編、長編、短編の3作品。合計したら660ページに及ぶ大長編だ。だから3日かかった。まだまだ書きたいことはあるし、まだ、何も書いていない。

























