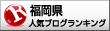(つづき)
北九州市小倉南区の「中谷」バス停。
写真は、西鉄中谷営業所構内にひっそりと立つ「田川快速」の区間便と「34番」のためだけののりばである。
「34番」は、営業所を出て国道322号を小倉都心方面(北)ではなく田川方面(南)に向かい、石原町、新道寺、母原、志井車庫、下志井、山手一丁目、守恒、北方、三萩野、紺屋町、平和通り、小倉駅バスセンターを経由して砂津に至る。
営業所を出ていきなり都心とは反対の方角に向かうという意味では、福岡地区でいうと「那珂川営業所」から出る現人橋経由の「61番」「66番」にも似ている(ただし、那珂川営業所ののりばは構内ではなく、道路に出て、営業所の対面側に停車する)。
中谷営業所と那珂川営業所は、上記の件以外にも、都心部との位置関係、道路との位置関係、敷地内の建物の配置、ローカル線の廃止状況(平尾台・頂吉・合馬と佐賀橋・大山)、鉄道駅への路線開設とその衰退(モノレール駅への「8番」と博多南駅への「無番」)…など、共通点が多く、以前から「似ているなぁ」という印象を持っている(他方、高速バスや都市間快速バスの停車の有無や、インターチェンジの存在など、決定的な違いも結構ありますが)。
バス停の名称は、「中谷営業所」ではなく「中谷」、一方、那珂川のほうは「那珂川営業所」である。
福岡地区では、営業所構内や営業所前のバス停には、「○○営業所」「○○営業所前」という名称をそのまま付けるか、「能古渡船場」(愛宕浜営業所)、「野方」(壱岐営業所)、「新宮・緑ケ浜」(新宮営業所)のように営業所とは全く別の名前を付けるか、という主に2パターンがあり、ここ「中谷」のように、単に「営業所」の文字を外して営業所構内や営業所前のバス停の名前にするというケースは見られない(福岡地区の「金武」「柏原」「新宮」の各バス停は、営業所とは全く別の場所にある)。
北九州地区の場合は、「中谷」以外にも、浅野営業所の前に「浅野」バス停があり、このあたりは文化の違いなのだろうか…(営業所よりも前からバス停があったか、という要素で決まる側面が強そうであり、「文化の違い」というほどたいそうなことではなさそうですけどね)。
(つづく)
北九州市小倉南区の「中谷」バス停。
写真は、西鉄中谷営業所構内にひっそりと立つ「田川快速」の区間便と「34番」のためだけののりばである。
「34番」は、営業所を出て国道322号を小倉都心方面(北)ではなく田川方面(南)に向かい、石原町、新道寺、母原、志井車庫、下志井、山手一丁目、守恒、北方、三萩野、紺屋町、平和通り、小倉駅バスセンターを経由して砂津に至る。
営業所を出ていきなり都心とは反対の方角に向かうという意味では、福岡地区でいうと「那珂川営業所」から出る現人橋経由の「61番」「66番」にも似ている(ただし、那珂川営業所ののりばは構内ではなく、道路に出て、営業所の対面側に停車する)。
中谷営業所と那珂川営業所は、上記の件以外にも、都心部との位置関係、道路との位置関係、敷地内の建物の配置、ローカル線の廃止状況(平尾台・頂吉・合馬と佐賀橋・大山)、鉄道駅への路線開設とその衰退(モノレール駅への「8番」と博多南駅への「無番」)…など、共通点が多く、以前から「似ているなぁ」という印象を持っている(他方、高速バスや都市間快速バスの停車の有無や、インターチェンジの存在など、決定的な違いも結構ありますが)。
バス停の名称は、「中谷営業所」ではなく「中谷」、一方、那珂川のほうは「那珂川営業所」である。
福岡地区では、営業所構内や営業所前のバス停には、「○○営業所」「○○営業所前」という名称をそのまま付けるか、「能古渡船場」(愛宕浜営業所)、「野方」(壱岐営業所)、「新宮・緑ケ浜」(新宮営業所)のように営業所とは全く別の名前を付けるか、という主に2パターンがあり、ここ「中谷」のように、単に「営業所」の文字を外して営業所構内や営業所前のバス停の名前にするというケースは見られない(福岡地区の「金武」「柏原」「新宮」の各バス停は、営業所とは全く別の場所にある)。
北九州地区の場合は、「中谷」以外にも、浅野営業所の前に「浅野」バス停があり、このあたりは文化の違いなのだろうか…(営業所よりも前からバス停があったか、という要素で決まる側面が強そうであり、「文化の違い」というほどたいそうなことではなさそうですけどね)。
(つづく)