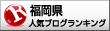(つづき)
前回掲載した速達系統の一覧表、少なくとも「4番」「40番」「58番」が抜けているので、いずれ修正します。
また、市内路線では基本的に「急行」表記はなくなると当初書いたのですが、先に触れた「急行K」や「新宮急行」以外でも、「急行303番」(マリノアシティ)も引き続き「急行」のままのようです(Kや新宮は市内路線ではない、という見方もできますが)。
・「54-1番」などのさらなる変更
昨年の改正で、停車停留所は変わらないままで「快速」という表記をやめた「54番」「54-1番」「59番」だが、今回は、停車停留所を変えたうえで再び「快速」表記が復活する。

具体的には、新たに一本木と新川町に停車するようになり、その一方で、市役所北口・アクロス福岡前、東中洲、土居町、蓮池に停車しなくなる(渡辺通二丁目には改正前後ともに非停車のまま)。
「速達運行区間」という観点でいうと、これまでは「平尾~天神間」だったものが「渡辺通一丁目~千代町間」に変わる、ということになる。
もともと「59番」の登場は、旧「20番」(現在の「20番」の先代の先代)廃止により、薬院地区から明治通り方面への足がなくなることの救済の意味もあったのだが、今回、明治通り区間で非停車となるバス停が増えることにより、当初の開設意図は薄れてしまうこととなる(利用動向からみてそれが適切と判断したのだろうから、それを問題視するつもりはありません)。

これは、「54-1番」が、運行区間内でどういう種別、番号で運行されるかを示したもの。
上り(福岡タワー→天神方面)で特にめまぐるしく変わることになるが、特筆すべきは、上りの福岡タワー→梅光園口間が「快速」ではなく「普通」で運行されることである。
快速区間が終わった後に「普通」になることは、一般の人の思考パターンからしても合理的だと思うのだが、快速区間に入る前に「普通」を掲げることは合理性がある場合もあればリスクを伴うこともある(全部のバス停に停まると思って乗ったのに通過するバス停があった、というケースが発生する可能性があるという意味で)。
以前の記事で、
この「54-1番」は全便一応「快速」なのだが、通過するバス停は、平尾~天神南間の「一本木」「新川町」「渡辺通二丁目」だけという、長い運行区間のうちのごく一部であることから、快速区間に関係ないエリアでは、「快速」という表示を見て、“自分が行きたいバス停に停まらないのではないか?”という余計な予断を与えてしまい、乗客の取りこぼしが発生するのでは?という懸念については以前指摘したところだが、「54-1番」登場以降、特筆すべき改善は見られない(逆に、より「快速」を強調する方向に向かっている感もあり)。
と書いた。
今回の「梅光園口まで普通で、笹丘一丁目から快速」という判断は、わかりにくさを軽減して乗客のとりこぼしを防ぐ、賢明な判断であるように思える。
「快速39番」などでも、同様の工夫を期待したいところ。
・「特快151番」「特快152番」の新設
現在の「急行151番」と「急行152番」は、停車停留所はそのままで「快速151番」「快速152番」に種別が変更となる。
これに加え、さらに野間四丁目、那の津口、中央市民プール前、伊崎、福浜二丁目にも停車しない「特別快速151番」「特別快速152番」が新設される。

これは、「特別快速151番」が、運行区間内でどういう種別、番号で運行されるかを示したもの。
上り(福岡タワー行き。「54-1番」ではタワー行きは下りでした、と蛇足)で、天神高速バスターミナル前では「特別快速W1」だが、天神北では「快速W1」となっている。
天神北だけ「快速」にする意味があるのでしょうか、それとも単なる間違い?(おわかりになる方、ご教示ください)。

「市内急行」の中では長く生き延びた「152番」でした。
(つづく)
前回掲載した速達系統の一覧表、少なくとも「4番」「40番」「58番」が抜けているので、いずれ修正します。
また、市内路線では基本的に「急行」表記はなくなると当初書いたのですが、先に触れた「急行K」や「新宮急行」以外でも、「急行303番」(マリノアシティ)も引き続き「急行」のままのようです(Kや新宮は市内路線ではない、という見方もできますが)。
・「54-1番」などのさらなる変更
昨年の改正で、停車停留所は変わらないままで「快速」という表記をやめた「54番」「54-1番」「59番」だが、今回は、停車停留所を変えたうえで再び「快速」表記が復活する。

具体的には、新たに一本木と新川町に停車するようになり、その一方で、市役所北口・アクロス福岡前、東中洲、土居町、蓮池に停車しなくなる(渡辺通二丁目には改正前後ともに非停車のまま)。
「速達運行区間」という観点でいうと、これまでは「平尾~天神間」だったものが「渡辺通一丁目~千代町間」に変わる、ということになる。
もともと「59番」の登場は、旧「20番」(現在の「20番」の先代の先代)廃止により、薬院地区から明治通り方面への足がなくなることの救済の意味もあったのだが、今回、明治通り区間で非停車となるバス停が増えることにより、当初の開設意図は薄れてしまうこととなる(利用動向からみてそれが適切と判断したのだろうから、それを問題視するつもりはありません)。

これは、「54-1番」が、運行区間内でどういう種別、番号で運行されるかを示したもの。
上り(福岡タワー→天神方面)で特にめまぐるしく変わることになるが、特筆すべきは、上りの福岡タワー→梅光園口間が「快速」ではなく「普通」で運行されることである。
快速区間が終わった後に「普通」になることは、一般の人の思考パターンからしても合理的だと思うのだが、快速区間に入る前に「普通」を掲げることは合理性がある場合もあればリスクを伴うこともある(全部のバス停に停まると思って乗ったのに通過するバス停があった、というケースが発生する可能性があるという意味で)。
以前の記事で、
この「54-1番」は全便一応「快速」なのだが、通過するバス停は、平尾~天神南間の「一本木」「新川町」「渡辺通二丁目」だけという、長い運行区間のうちのごく一部であることから、快速区間に関係ないエリアでは、「快速」という表示を見て、“自分が行きたいバス停に停まらないのではないか?”という余計な予断を与えてしまい、乗客の取りこぼしが発生するのでは?という懸念については以前指摘したところだが、「54-1番」登場以降、特筆すべき改善は見られない(逆に、より「快速」を強調する方向に向かっている感もあり)。
と書いた。
今回の「梅光園口まで普通で、笹丘一丁目から快速」という判断は、わかりにくさを軽減して乗客のとりこぼしを防ぐ、賢明な判断であるように思える。
「快速39番」などでも、同様の工夫を期待したいところ。
・「特快151番」「特快152番」の新設
現在の「急行151番」と「急行152番」は、停車停留所はそのままで「快速151番」「快速152番」に種別が変更となる。
これに加え、さらに野間四丁目、那の津口、中央市民プール前、伊崎、福浜二丁目にも停車しない「特別快速151番」「特別快速152番」が新設される。

これは、「特別快速151番」が、運行区間内でどういう種別、番号で運行されるかを示したもの。
上り(福岡タワー行き。「54-1番」ではタワー行きは下りでした、と蛇足)で、天神高速バスターミナル前では「特別快速W1」だが、天神北では「快速W1」となっている。
天神北だけ「快速」にする意味があるのでしょうか、それとも単なる間違い?(おわかりになる方、ご教示ください)。

「市内急行」の中では長く生き延びた「152番」でした。
(つづく)