
(つづき)
北九州市八幡東区の「槻田校前」バス停。
「浅野~小倉駅バスセンター~三萩野~南小倉駅前~三叉路~到津の森公園前~槻田校前~(一部、八幡高校)~七条~大蔵~中央町~八幡駅~祗園三丁目~黒崎~引野口~下上津役~小嶺車庫~千代四丁目~香月営業所」を結ぶ「43番」と(八幡駅~香月間の本数は少ない)、平日朝一本だけ「砂津→山路」を走る「54番」のルートとなっている。
「槻田校」というのは、近くにある槻田小学校のことだと思われるが、「槻田小学校前」ではなく「槻田校前」である。
このような例は、「中原校前」「鳥飼校前」「福地校前」「長行校下」…などほかにもあって、いずれも昔からある古いバス停である。
“昔からある古いバス停”というのも、かなり曖昧な表現だと思うのだが、あくまで私の感覚が基準なので、「私が物心ついた時点よりもずっと前から」ありそうなバス停であれば、“昔からある古いバス停”ということになるので、その点はご容赦ください。
「~校前」と同様に、「熊西局前」「土井局前」「福間局前」「草野局前」…のように、郵便局を「局」で表すケースもある。
もし今、全くの白紙の状態からバス停の名前を付けるとすると、「~校前」「~局前」のような名前の付け方はなされそうにない。
「~小学校前」「~郵便局前」や、もっと位置関係を厳密にして「~小学校西口」とか「~郵便局入口」…などになってしまいそうである。
たしかに「~校前」「~局前」では、バス停の近くにある施設が「小学校」なのか「中学校」なのか、「郵便局」なのか「電話局」なのか「放送局」なのか…などは何もわからず、“説明力”に欠ける面は否めない。
ただ、「西南分校前」が「分校」からかなり離れていても「前」のように(現在「分校」に相当するものはない)、「~校前」「~局前」には、“バス停の名前は簡潔なほうが美しい”という「美意識」や、“長ったらしくしたってしょうがない”という「潔さ」「大らかさか」のようなものを感じざるを得ず、バス停の名前を「観賞」するという観点では、とてもポイントが高いと思うでのある。
(つづく)
北九州市八幡東区の「槻田校前」バス停。
「浅野~小倉駅バスセンター~三萩野~南小倉駅前~三叉路~到津の森公園前~槻田校前~(一部、八幡高校)~七条~大蔵~中央町~八幡駅~祗園三丁目~黒崎~引野口~下上津役~小嶺車庫~千代四丁目~香月営業所」を結ぶ「43番」と(八幡駅~香月間の本数は少ない)、平日朝一本だけ「砂津→山路」を走る「54番」のルートとなっている。
「槻田校」というのは、近くにある槻田小学校のことだと思われるが、「槻田小学校前」ではなく「槻田校前」である。
このような例は、「中原校前」「鳥飼校前」「福地校前」「長行校下」…などほかにもあって、いずれも昔からある古いバス停である。
“昔からある古いバス停”というのも、かなり曖昧な表現だと思うのだが、あくまで私の感覚が基準なので、「私が物心ついた時点よりもずっと前から」ありそうなバス停であれば、“昔からある古いバス停”ということになるので、その点はご容赦ください。
「~校前」と同様に、「熊西局前」「土井局前」「福間局前」「草野局前」…のように、郵便局を「局」で表すケースもある。
もし今、全くの白紙の状態からバス停の名前を付けるとすると、「~校前」「~局前」のような名前の付け方はなされそうにない。
「~小学校前」「~郵便局前」や、もっと位置関係を厳密にして「~小学校西口」とか「~郵便局入口」…などになってしまいそうである。
たしかに「~校前」「~局前」では、バス停の近くにある施設が「小学校」なのか「中学校」なのか、「郵便局」なのか「電話局」なのか「放送局」なのか…などは何もわからず、“説明力”に欠ける面は否めない。
ただ、「西南分校前」が「分校」からかなり離れていても「前」のように(現在「分校」に相当するものはない)、「~校前」「~局前」には、“バス停の名前は簡潔なほうが美しい”という「美意識」や、“長ったらしくしたってしょうがない”という「潔さ」「大らかさか」のようなものを感じざるを得ず、バス停の名前を「観賞」するという観点では、とてもポイントが高いと思うでのある。
(つづく)










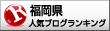





















































それから、10年あまり、京都でバスに乗ると、「北白川校前」というバス停があるのです。さらに乗り歩いていると、「乾隆校前」、「衣笠校前」などにも出くわしました。あぁ、「慶徳校前」と似たような名前の付け方もあるものだ、と。
で、これらはすべて“小学校”なのです。
私の想像ですが、明治時代になり近代教育制度が整備された時、真っ先に「尋常小学校」が全国津々浦々に配置され、皆が「~校」と呼ぶようになったのではないでしょうか。「中学校」、「高等学校」はやや遅れて、しかも拠点拠点にしか置かれなかったから、「~校」と呼ぶ対象にはならなかった。
同じように「~局」という施設も、「郵便局」こそが最も早く、しかも全国漏らさずどこの集落にも配置され、「~局」と省略され、親しまれたのではないでしょうか。民営化されても、「郵便局」という名称は変わりませんでしたね。
学校関係で最もシュールな駅名と私が思うのは、甘木線の「学校前」です。
>私の想像ですが、明治時代になり近代教育制度が整備された時、真っ先に「尋常小学校」が全国津々浦々に配置され、皆が「~校」と呼ぶようになったのではないでしょうか。
>「中学校」、「高等学校」はやや遅れて、しかも拠点拠点にしか置かれなかったから、「~校」と呼ぶ対象にはならなかった。
私も、「~校」というのは旧制時代の学校と関係があるのかもなぁとは漠然と思っておりました(文章にするほどの確信はなかったのですが)。
なので、Tokyo Chikushiさんの説に賛成であります。
「~校前」というコトバが、バス(鉄道)会社側の名付けのツールだったというよりは、「~校」というコトバ自体が一般に定着していたと考えたほうがよさそうですね。
>同じように「~局」という施設も、「郵便局」こそが最も早く、しかも全国漏らさずどこの集落にも配置され、「~局」と省略され、親しまれたのではないでしょうか。
>民営化されても、「郵便局」という名称は変わりませんでしたね。
たしかに。
親しみが込められた略称が「正式な」名称となりうる点が、バス停や電停の特徴(特長)かもしれませんね。
ただ、大きな流れとしては、略称は用いられない方向に向かいつつあるような感じもしています。
もし今、全く新たにバス停の名前を付けるとすると「修猷館前」「福高前」でなく「修猷館高校前」「福岡高校前」などになりそうな気もします。