伊東温泉競輪場で4月29日に行われた共同通信社杯の決勝。並びは新田-成田の福島,深谷に岩津-小倉の中四国,稲垣-村上-南の近畿で平原は単騎。
深谷がスタートを取って前受け。4番手に稲垣,平原を挟んで8番手から新田という周回に。残り3周のホームを過ぎると新田が上昇開始。バック過ぎに深谷を叩いて先頭に。稲垣がすぐにこれを叩き,残り2周のホームから早くも先行態勢。平原も続き,5番手が内の新田と外の深谷で併走。打鐘から深谷は発進。南がブロック,さらに村上もブロックし,深谷は浮いて圏外。ただ深谷マークの岩津がうまく内に潜り込み,稲垣の番手に入ったので,村上も苦しくなりました。この様子を窺っていた新田が発進するとバックでは稲垣を捲りきり,追走の成田と直線勝負。差は詰められたものの差されるという感じはなく,新田の優勝。1車輪差の2着が成田で福島ワンツー。うまく立ち回った岩津が2車身差の3着。
優勝した福島の新田祐大選手は3月の松山記念以来の優勝でビッグは2010年暮れのSSカップみのり以来の2勝目。二次予選でバンクレコードを叩き出したように今開催は非常に好調であったよう。もちろん調子が良ければ勝てるほどビッグは甘いものではありませんが,展開も向きました。一頃感じられた勝負弱さから完全に脱したような印象なので,これからが楽しみなのですが,制裁による長期欠場に入ってしまうのが残念でなりません。
朝倉の問題意識のうちには,松田のいう二重因果性の問題が含まれています。『概念と個別性』ではそれが探求されていますので,その論旨を詳しくみていきましょう。

ゲルーの主眼点は,主要な原因による決定と主要ではない原因による決定ないしは道具による決定は,数的に区別可能であるということです。松田は前者を永遠の相の因果性,後者を持続の相の因果性といい換えました。そして朝倉は前者を垂直の因果性,後者を水平の因果性とさらにいい直しています。朝倉はこのいい方はヨベルYirmiyahu Yovelなどに典型的にみられるいい回しとしていますが,ここでは朝倉の論旨をみていきますので,このいい方に倣うことにします。というか,スピノザの研究者の間で最も一般的に使われているはこのいい回しなのではないかと僕は思っています。
ゲルーMartial Gueroultは垂直の因果性については第一部定理二六を,水平の因果性に関しては第一部定理二八を援用しました。朝倉の場合,水平の因果性についてはゲルーと同じですが,垂直の因果性に関しては第一部定理二一と二二,そして第一部定理二三を援用しています。ただし,この相違については問題にする必要はないと僕は思います。松田がゲルーの分類を,永遠の相と持続の相と分類し直したのは,そうしたいい方の方がゲルーの主張を正確に反映させていると考えたからだといえます。すると持続の相に該当する因果性を代表するのが第一部定理二八になるのは当然で,だからこの点についてはゲルーと朝倉との間でも一致しています。一方,永遠の相の因果性に関しては,朝倉のように第一部定理二一から二三までを援用する方が自然であるといえるでしょう。
おそらくゲルーは,因果性そのものよりも,神の決定が数的に二種類に類別されるということを主張したかったので,決定ということばが用いられているふたつの定理Propositioに分類したものと僕は推測します。しかしこの考察では決定ということにこだわらずに,単純に因果性の数的な類別だけを主眼点として捕えています。なので第一部定理二六よりも,永遠ということばが用いられている第一部定理二一から二三を援用する方が適当でしょう。
深谷がスタートを取って前受け。4番手に稲垣,平原を挟んで8番手から新田という周回に。残り3周のホームを過ぎると新田が上昇開始。バック過ぎに深谷を叩いて先頭に。稲垣がすぐにこれを叩き,残り2周のホームから早くも先行態勢。平原も続き,5番手が内の新田と外の深谷で併走。打鐘から深谷は発進。南がブロック,さらに村上もブロックし,深谷は浮いて圏外。ただ深谷マークの岩津がうまく内に潜り込み,稲垣の番手に入ったので,村上も苦しくなりました。この様子を窺っていた新田が発進するとバックでは稲垣を捲りきり,追走の成田と直線勝負。差は詰められたものの差されるという感じはなく,新田の優勝。1車輪差の2着が成田で福島ワンツー。うまく立ち回った岩津が2車身差の3着。
優勝した福島の新田祐大選手は3月の松山記念以来の優勝でビッグは2010年暮れのSSカップみのり以来の2勝目。二次予選でバンクレコードを叩き出したように今開催は非常に好調であったよう。もちろん調子が良ければ勝てるほどビッグは甘いものではありませんが,展開も向きました。一頃感じられた勝負弱さから完全に脱したような印象なので,これからが楽しみなのですが,制裁による長期欠場に入ってしまうのが残念でなりません。
朝倉の問題意識のうちには,松田のいう二重因果性の問題が含まれています。『概念と個別性』ではそれが探求されていますので,その論旨を詳しくみていきましょう。

ゲルーの主眼点は,主要な原因による決定と主要ではない原因による決定ないしは道具による決定は,数的に区別可能であるということです。松田は前者を永遠の相の因果性,後者を持続の相の因果性といい換えました。そして朝倉は前者を垂直の因果性,後者を水平の因果性とさらにいい直しています。朝倉はこのいい方はヨベルYirmiyahu Yovelなどに典型的にみられるいい回しとしていますが,ここでは朝倉の論旨をみていきますので,このいい方に倣うことにします。というか,スピノザの研究者の間で最も一般的に使われているはこのいい回しなのではないかと僕は思っています。
ゲルーMartial Gueroultは垂直の因果性については第一部定理二六を,水平の因果性に関しては第一部定理二八を援用しました。朝倉の場合,水平の因果性についてはゲルーと同じですが,垂直の因果性に関しては第一部定理二一と二二,そして第一部定理二三を援用しています。ただし,この相違については問題にする必要はないと僕は思います。松田がゲルーの分類を,永遠の相と持続の相と分類し直したのは,そうしたいい方の方がゲルーの主張を正確に反映させていると考えたからだといえます。すると持続の相に該当する因果性を代表するのが第一部定理二八になるのは当然で,だからこの点についてはゲルーと朝倉との間でも一致しています。一方,永遠の相の因果性に関しては,朝倉のように第一部定理二一から二三までを援用する方が自然であるといえるでしょう。
おそらくゲルーは,因果性そのものよりも,神の決定が数的に二種類に類別されるということを主張したかったので,決定ということばが用いられているふたつの定理Propositioに分類したものと僕は推測します。しかしこの考察では決定ということにこだわらずに,単純に因果性の数的な類別だけを主眼点として捕えています。なので第一部定理二六よりも,永遠ということばが用いられている第一部定理二一から二三を援用する方が適当でしょう。













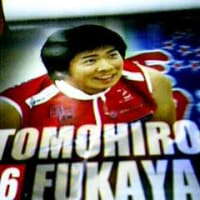

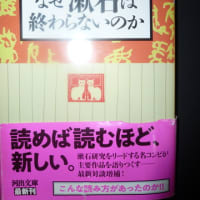

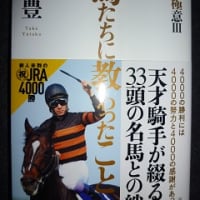
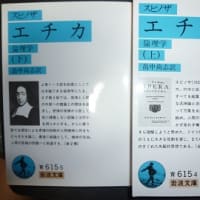






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます