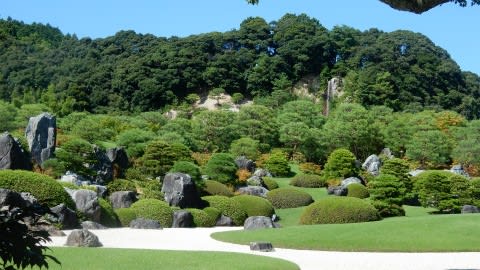4月に入った今日、我が郷は今年初の夏日になった。前月3月も暖かい日が続いたがその1日(22日)を使い滋賀県までドライブに出掛けた。目的は滋賀県の神社に群生すると言う花を見んがためである。訪れたのは滋賀県甲賀市にある瀧樹神社だ。甲賀市も”こうかし”で間違いやすいが、この神社名も難しい、タギ神社が正しいようだ。


目的は群生すると言うユキワリイチゲ(雪割一華)だ。神社鳥居横の駐車場らしき広場に車を止め、鳥居を潜る。木々に覆われた参道をかなり歩く。群生地がよくわからない。と、神社矢の建物から下がった場所に人の姿が見える。あそこか、とそちらに向かう。木漏れ日に白い花が見える。これだー!


キクザキイチゲと言う花があるがこれに似ている。が、花弁が重なっていて八重の花に見える。白い花弁に薄い紫色のすじでかかった、何とも可憐な花だ。


夢中で写真を撮っているとオヤッと思う花が。カタバミ(片喰)のようだ。カタバミは広く咲くユキワリイチゲの一角に重なるように咲いていた。


ユキワリイチゲが群生する傍に水は殆ど流れていない川があった。暖かさに誘われて川堤防を歩く。そこから帰り難くもう1度、群生地に戻り再度写真を撮りながら本殿に向かう。参拝をして瀧樹神社を後にした。


帰り道になる1号線に入る信号に戻ると右方向の矢印と共に”田村神社 4Km”の看板を見つけた。田村神社が滋賀県にあるのを知り、参拝に訪れたのはかれこれ30数年前になる。”それは行かなければ”と帰る方角とは逆だがそちらに曲がる。ここが入り口、灯篭に”田村社”の文字が見える。鳥居には”正一位田村大明神”の文字。この神社は坂上田村麻呂が祀られている。車のハンドルに付いていた30数年前のお守りを神社に返し、新しいお守りを頂いた。


今回の旅、車のナビで“瀧樹神社”を入力したが出てこず住所で目的地入力した。ナビは名神を草津まで行き、そこから新名神に入り向かうコースの案内だった。近年、あまり車で遠出をしていないこともありナビの通りに走ったが遠く感じた。で、帰り道は以前と言っても30数年前に田村神社を参拝した時に八日市から行ったことを思い出し、ナビで八日市インターを入れて走った。一般道だが広い道で走りやすい上に距離的には随分近く感じた。岐阜から行く場合は八日市で降りて向かうのが正解のように感じた。田村神社で健康お守りを入手し、お詣りは30数年のお礼とともに今後、頭痛が少なくなることをお願いした。来年にお礼参りが出来ることを切に願った春の一日旅だった。