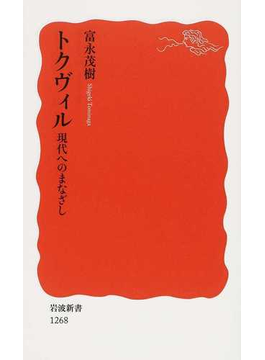天保11年(1840)11月1日、幕府は川越藩、庄内藩および長岡藩の3藩に対し三方領地替えを命じた。
江戸時代に三方領地替えは11回あり、また四方領地替えも複数回あるので、幕府の大名統治政策として珍しいことではない。
ところが天保11年の三方領地替えが、数ある領地替えの中で飛びぬけてよく知られているのは、いったん発令した幕府の命令が、前代未聞の御沙汰止みになり、幕府の権威を著しく低下させたことにある。
この当時、財政破綻状態にあった川越藩は、藩主松平斉典(なりつね)が11代将軍・徳川家斉(いえなり)の25男斉省(なりさだ)を養子に迎え、裕福な庄内への転封を狙っていた。
幕閣は無論のこと、将軍の親戚ということで大奥まで巻き込んで領地替えを画策したのである。
そして強引に三方領地替えを進める中心となる人物が、浜松藩主の老中水野忠邦である。
19歳で唐津藩主になった忠邦は、幕閣での出世を夢見て、それまでの藩主では例を見ない行動に出た。
それはかって徳川家康の居城であり、当時も幕閣への登竜門である浜松藩への国替えを申し出たのである。
文化14年(1817)、板倉藩、唐津藩および浜松藩の 三方領地替えで、唐津から念願の浜松に移った忠邦は、とんとん拍子で出世し、ついには筆頭老中に上り詰め、天保の改革を進めたのである。
今回の川越藩の願いをかなえるには、自らが夢を実現させた三方領地替えの妙案が、脳裏に浮かんだのも、あながち不思議なことではない。
幕府の命により、忠実な譜代大名である庄内藩主・酒井忠器(ただたか)は長岡へ、そして長岡藩主・牧野忠精(ただきよ)もまた川越へ移る準備を始めた。
ところが庄内の領民が、三方領地替えに異をとなえたことで、これは幕府が注目する事件へと発展した。
川越藩は表高15万石であるが実高は4~5万石で、借財も23万両と藩財政は破綻の状態にある。
一方の庄内藩は表高14万石実高は19万石で、商人の本間家に藩の実質経営を委託し、年間黒字3~4万両の豊かな藩である。
庄内領民は転封後に起こるであろう過酷な年貢を予期し、各地で集会を持ちはじめた。
あるものは国境に出て隣国に愁訴し、あるものは江戸にでて命がけで幕閣の要人に直訴を始めた
「雖為百姓、不仕二君」(百姓といへども二君に仕へず)を旗印に、もはや一発即発の一揆に近い状態であった。
結城秀康を祖とする、親藩の名門である川越藩主松平斉典のとんでもないおねだりと、老中水野忠邦の改革に名を借りた、強引な政治に嫌気がさしていた幕閣の要人は、直訴にきた庄内の領民を、幕府の裁きに突き出すのではなく、彼らの行いを褒め称えて庄内藩に渡した。
国を思う気持ちからの行動は、現代の中国にも通じていそうだが、本来はご法度の直訴にもかかわらず、庄内藩もまた直訴した領民を厳しく罰してはいない。
ここに二人の人物が登場する。一人は庄内藩出身の江戸の公事師(くじし)で財政家の佐藤藤佐(とうすけ)で、もう一人は江戸南町奉行の矢部定謙(さだのり)である。
庄内の領民は江戸で佐藤に相談し、やがて佐藤からの訴えは、南町奉行が取り調べることになる。
月番の江戸町奉行所は、北町奉行が遠山金四郎で知られる遠山景元、南町奉行が矢部定謙で、共に名奉行と誉が高い。
佐藤藤佐の吟味は矢部が担当し、正式な訴えとした公式書面「佐藤藤佐口書」に残された。
命がけで矢部はこの口述書を、老中堀田備中守および老中真田信濃守を経由し、筆頭老中水野忠邦に上申した。
天保12年(1841)閏1月、 大御所政治を続けていた家斉は亡くなり、また川越藩が養子縁組で迎えた松平斉省も、同年5月に相い次いで亡くなっていた。
水野忠邦から南町奉行所の調べを聞いた第12代将軍・徳川家慶(いえよし)は、父親の大御所政治が終わっていたこともあり、三方領地替えの取り下げを命じた。
ここから水野忠邦の矢部に対する反撃が始まった。
腹心の鳥居耀蔵(ようぞう)を使い、諌言により矢部を追い落とした。
矢部家はお取りつぶしとなり、桑名藩預かりとなった矢部は、桑名城の座敷牢で食を絶ち、正座のまま息を引き取ったという。
なおこの桑名藩も名君松平定信の時代に、三方領地替えにより白河から桑名に戻っていた。
桑名→高田→白河→桑名と転封を重ね、念願の旧領地に戻ったのである。
三方領地替の駒に使われた長岡藩も、水野の最後の毒牙を食らうことになる。
それは天保14年(1843)に、水野忠邦がお庭番川村修就(ながたか:清兵衛)を暗躍させ、長岡藩領新潟港の上知を実現させた。
さて三方領地替えはここまでであるが、事件の関係者のその後を見てみよう。
川越藩、庄内藩、長岡藩はそのまま幕末を迎えた。
いや厳密に言えば川越藩松平越前家(松平大和守家)は、慶応3年(1867)川越藩領前橋に移り前橋藩を興した。
そして翌年に明治維新を迎えた。
川越藩には松平松井家が入った。喜多院にある霊廟は、越前家のものである。
一方、水野忠邦は強引な改革の反発と三方領地替えの失策で一旦は失脚し、再び筆頭老中に帰り咲くも、かっての力はなく隠居を言い渡され、懲罰的な意味を持つ浜松から酒田へ転封となった。
鳥居耀蔵は矢部を追い落とした功績により、矢部の後釜の南町奉行に破格の出世をした。
しかし水野が老中に帰り咲くと、自分を裏切った鳥居を許さず、罪人として丸亀藩預けとなり幕末を迎えた。
新潟港上知のお庭番(隠密)の川村修就は、上知直後の新潟奉行から奈良奉行、大阪町奉行、そして長崎奉行などの要職に転進する。
最後は矢部家であるが、水野と鳥居が失脚すると、定謙の無実がわかり、子供にお家の再興が認められた。
庄内では定謙は国を救った恩人と、崇め奉られているという。
(参考資料)
義民が駆ける(藤沢周平)、気骨の幕臣矢部定謙(中村彰彦)、
下級武士の米日記(加藤淳子)