「女性ヘルプネットワーク」*1という団体が、2010年度から、「性的虐待体験者が性産業で働く理由とその実態調査」を
そして、継続して調査が行われ、「性的虐待経験者が性産業で働く理由とその実態調査 支援編」という冊子にまとめられました。
前半は、支援団体の聞き取り調査で、10団体の活動報告が掲載しています。
重要なのは、後半の当事者への聞き取り調査です。今までの研究報告や、性暴力の専門書ではなかなか目に触れにくい*2サバイバーの声を拾い上げようとしています。
「専門家の支援」への疑い、ワンストップサービス偏重への疑念や中長期支援の必要性、警察からの二次加害の深刻な問題、当事者が支援者になることの困難と希望、自助グループと支援者の緊張関係、加害者支援に対する被害者支援者の取り組みの必要性、男性被害者の声、「女性限定の支援」に対するセクシュアルマイノリティからの批判などなど、繊細な問題が提起されています。
そして、表題にもある「性産業で働く」ことについての当事者の話が、支援団体・支援者に向けて語られています。ある人は、「性産業がトラウマを持った人をケアする役割を果たしており、必要だ」ということを、自分の経験を通して明らかにしています。それと同時に、「自分を商品として見る」というある種の冷めた視線をことができないと、稼げないという現実も指摘しています。
また、別の人は夜に眠れないから、キャバクラで朝まで働くことで、自分を保つことができたと述べています。「規則正しい生活」を支援機関から押し付けてられていたら、潰れていたかもしれないと語ります。
この聞き取り調査からはっきり伝わってくるのは、支援側に対する、当事者からの、「被害者像を押し付けるのはやめてくれ」「正しい回復の仕方なんてない」というメッセージです。前半が、支援団体の報告であり、後半は、当事者からの支援団体への批判を含む内容になっているのは、なかなかすごいな、と思いました。
性産業と性暴力の問題を、同時に扱うのは難しいことです。セックスワーカーは差別され続けており、「性産業で働く=性暴力被害の影響」と決めつけられたり、「あの人たちはトラウマのせいで、あんなことをする」と勝手な周囲の思い込みで憐れまれたりして、不快な経験をさせられています。
性産業と性暴力を結びつけた調査は、そうしたセックスワーカーに対するステロタイプ化を強化する恐れもあります。その一方で、実際に、性暴力被害者の中には、性産業に従事する中で、コントロールかできなくなり、うまく働けない経験、傷ついた経験をする人たちがいます。
その人たちを念頭において、性暴力被害の支援者は、セックスワークを「逸脱行為」だとみなして、性産業から離れることを回復だとみなしたりすることがあります。セックスワークは、対価を得て生活をしていくための仕事なのですが、「被害の再演*3」だと一律に病理化して、ケアしようとする支援者さえいるのです。こうした支援側の思い込みを解くためには、多様な経験をつまびらかにした調査が有用でもあると思います*4。もちろん、支援側が、目の前の人の話をそのまま受け取って、性産業で働く人の話に耳を傾けることができれば、この調査も必要ありません。でも、目の前の人の話を聞くというのは難しいことでもあるので、報告書を通して、少しでも支援が変わっていくといいな、と思います。
裏表紙の見返しが、高橋りりすの「サバイバーよ、勇気を出すな」だったのもよかったです。
結局は、この調査でも、10人のサバイバーが勇気を出して語り、それを支援側に伝えることで、「なんとかしたい」と思ってがんばっているわけですが、本来はこんなことはサバイバーの仕事でも何でもありません。生き延びたこと、それだけでいいはずです。
「サバイバーよ、勇気を出すな」
DV、性被害、虐待、身体について、15年の相談活動。
女性の悩みと向き合ってきた経験生かし、性産業従事者と性被害の実態も調査
-NPO法人 女性ヘルプネットワーク
15年前から続けてきた女性からの相談は、今や年間300件にのぼる。その中で、性被害が一様ではないという事実も見えてきた。真に必要なサポートを探るために行った「性産業従事者と性被害の関係」についての調査、理想とするワンストップセンターの構想などについて聞いた。
3つのグループ。
性被害「ひなたぼっこ」、身体の悩み「ひととき」、人間関係「ひだまり」
画像:理事長 楠本 千恵子さん
理事長 楠本 千恵子さん
画像:事務局長 野口 真理子さん
事務局長 野口 真理子さん
「女性ヘルプネットワーク」の事務局長を務める野口真理子さんは、もともと北九州市で、カンボジアの女性を支援するボランティア団体の代表を務めていた。1994年 、北九州市は、9月にエジプト・カイロで開催された「国際人口開発会議」で「性と生殖に関する健康と権利」が提唱されたことを受け、北九州市にも「性と生殖」について考える女性グループを立ち上げようと提案。女性支援団体の代表でもあった野口さんに声がかかった。
95年4月には10人が集まり、「痴漢」というテーマで第1回目の勉強会を開いた。97年には市の相談員のバックアップも受け、女性専用の相談窓口を開設。「相談時間は1日2~3時間でしたが、学生時代の性被害を今も夫に言えず苦しんでいる、夫からたたかれた腹いせに子どもをたたいてしまう、といった深刻な悩みが寄せられました」
野口さんたちは相談員の勉強会はもちろん、女性を保護する公的施設や児童相談所にも足を運び勉強を重ねた。そこで意気投合したのが、現在、「女性ヘルプネットワーク」の理事長を務めている楠本千恵子さん。当時は、児童相談所の児童福祉司として働いていた。また、スタッフの田原美知子さんは、自身の経験を生かし相談業務を担っている。「夫からDVを受けて離婚した後、被害者の気持ちに寄り添えるのではないかと思い、相談員の講習を受けたんです」
野口さんはこれまでを振り返って言う。「始まった当初は、どこへ逃げればいいかというような、DV被害者からの相談が主でした。今はシェルターこそ増えましたが、『逃げたけど仕事が見つからず、うつ状態なのに精神科にもかかれず、死のうと思っている』といった相談が増え、中長期的な支援の必要性を感じています」
たとえば相談内容によって、男女共同参画センターやハローワークなどを紹介するほか、「性被害が原因で摂食障害になった」という女性に対しては、東京の自助グループからアドバイスをもらいながらサポートを続けるなど、多くの団体とも提携している。
また「女性ヘルプネットワーク」自身も、3つのグループを運営している。性被害や性的傷つき体験をもつ女性の自助グループ「ひなたぼっこ」。更年期、妊娠、出産など、女性であるがゆえの身体の悩みを抱えた女性の自助グループ「ひととき」。そして、夫婦関係や人間関係で悩んだり、生きづらさを抱えたりする女性たちをカウンセラーがサポートする「ひだまり」だ。
「性的にいやな経験」女性の83%。女性は被害と気づかないことも
写真:スタッフ 田原 美知子さん
スタッフ 田原 美知子さん
中でも「ひなたぼっこ」には、「男性が怖い」と訴える女性が多く集まっていた。ところがある時、男性とすぐに親しくなりすぎ、自分は「性的依存」ではないかと悩む女性や性産業で働く女性が入ってきた。そのことで、他の参加者は一時混乱したが、性被害の後遺症が一様ではないことをみんなが知るきっかけとなった。
「相談窓口にも性被害経験をもち性産業で働く女性から、給料不払いなどの労働問題、暴力団やストーカーがからんだ相談など、バックに異性関係の問題が潜む相談が寄せられ、どうサポートすべきか悩んでいた」と、野口さんは言う。そこで性被害体験がある人への異性や性の問題を今後のサポートに生かすために11年、ファイザープログラムの助成を受けて「性的虐待体験者が性産業で働く理由とその実態調査」を実施した。
最初に女性団体や新聞紙上での呼びかけを通して、一般女性95人に質問紙による調査を行った。その結果、83.2パーセントに当たる79人が「性的にいやな経験をしたことがある」、そのうち73人が「心身への影響がある」と答えている。また「性産業等の仕事(援助交際を含む)の経験」については18.1パーセントの17人が「ある」とし、そのうち16人が「心身への影響がある」と回答している。
続いて、性被害と性産業、両方の経験をもつ女性からの聞き取り調査を行った。プライバシーの漏洩を恐れ、直前になって断る人が続出する中、7人が応じた。性産業で働くことになったきっかけ、性被害との関係、家族との関係などについて話を聞いた野口さんは、「被害を被害として受け止めていない女性の多さに驚いた」と話す。「中には何度も痴漢行為を受け、会社でセクハラに遭い、心も傷つき痛んでいるのに『自分が警察などに訴え出ていないものは被害ではない』と思い込んで、自分が悪いと思っている女性もいました」
調査の結果、「家庭など身近なところに“性”に深くかかわる環境があり、“性”に否定的でありながらも、それを大きな存在として意識させられた子ども時代」という共通点が浮かび上がってきた。そのことが、「自らの性を売買することに違和感をもたせなくしていったのではないか」と、野口さんたちは推察する。
「性的な傷つきが心身に影響を与えて生活に支障をきたし、ほかの仕事に就くことが難しくなり、経済的な問題も含めて性産業を選ばざるを得なくなった」という構図も見えてきた。
「性産業で得たお金は摂食障害による過食を満たす食費や借金返済、生活費に消えています。彼女たちは決して着飾るためのお金がほしかったわけじゃない。その時は、厳しい暮らしを抜け出すために精いっぱい選んだ道だったんだと思う」と野口さんは言う。
過去の被害体験も相談できる「ワンストップセンター」
写真:博多に伝わる話芸の伝統芸「博多にわか」を使ったワークショップの様子
博多に伝わる話芸の伝統芸「博多にわか」を使ったワークショップの様子
さらに楠本さんは、男性とすぐに親しくなりすぎる女性の傾向として、今回の調査結果と児童相談所で子どもたちを見てきた経験から、「自尊感情の低い人が多い」との印象をもっている。
「貧困や虐待、親の離婚などを経験した少女の中には、愛されたい一心から父親に似た年配の男性に近づいていく子もいる。大事にされているという感覚がもてないから、自分の身体がどうなってもいいという考えに走ってしまうのです」
性被害体験が「非行」というかたちで表出する少女も少なくないという。「本人が何も言わなくても、周囲の大人は彼女たちのSOSに気づいて、『何かあったのではないか』という温かい目を向けてあげてほしい」と野口さんは話す。
「女性ヘルプネットワーク」では学校へ出向き、中高生を対象に「性の逸脱行動」や「デートDV」を防止する授業も行っている。授業の中では、性行為にはリスクが伴うこと、アダルトサイトに書き込みをしただけでも罪に問われる場合もあれば、性犯罪に至らなくても相手のいやがる行為があることなどを伝えている。
そして今後は、「性暴力被害者支援ワンストップセンター」の必要性についても提言を続けていくつもりだ。「ワンストップセンターといえば緊急支援がメインと考えがち。しかし長い間、心身への影響に苦しんできた人たちは、緊急支援の窓口に、たとえば10年も前の被害のことを言っても、自分たちは被害者と見なしてもらえないのではないかと不安を感じている。専門スタッフを通して、司法や医療などの支援が無料で受けられる緊急支援。過去の被害体験についても相談、法律や心理面、生活や就労などの支援が無料で受けられる中長期支援の両方が欠かせない」と野口さんは言う。
また、「性的虐待体験者が性産業で働く理由とその実態調査」の報告書は、全国の公的機関などに配布した。どこで閲覧できるかは、直接問い合わせてきた人にのみ教えている。
「性産業で働く女性の中には雇用主である業者や客から、すさまじい暴力を受けている人もいる。それは仕事だから仕方ないとか、そういう仕事をするあなたが悪いということを言わないで、助けを求めてきた時は偏見をもたず、そのままの状態を受け入れてサポートしてほしい。また、社会の中でも、そういう仕事をする人に対する偏見をもつことなく、その仕事を選ばないといけなかった状況を知ってほしい」
NPO法人 女性ヘルプネットワーク










![[山本 潤]の13歳、「私」をなくした私 性暴力と生きることのリアル](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51juAmi4hvL.jpg)
![[雪村 葉子]の私は絶対許さない 15歳で集団レイプされた少女が風俗嬢になり、さらに看護師になった理由](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51zL-v3yi8L._SY346_.jpg)
![[大塚咲]のよわむし](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/31bM6mDPDYL._SY346_.jpg)
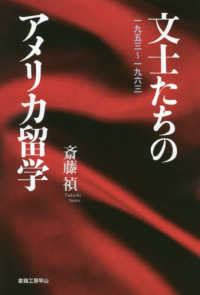



![[松本清張]の実感的人生論 (中公文庫)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41Xp1cJz3pL.jpg)




