3月31日の年度末。
今日は、来年度(もう明日ですが・・・)の準備デーです。
私のデスクには、卒業生(卒塾生)からのメッセージが・・・
🌸個人個人の方法で分かりやすくまた、
先生も一緒に考えてくれることろが
「びすぽうく」のよいところだと思います。
びすぽうくに入ってから学校でも自分の成長を感じました。
🌸自分に合う字の覚え方を教えてくれたことがよかったです。
中学校でもこのことを活かして自分なりの覚え方をして
もっと漢字を覚えていきたいです。
🌸ローマ字が分かるようになり、漢字は自信がつきました。
自分には、漢字を分解する方法が合っていて苦手な漢字も
楽しく練習できました。
🌸英語も会話ができるようになってきました。
🌸エプロンのひも結びもできるようになりました!
🌸この塾に入ってから計算の仕方が分かってきたり、
テストの読み取りで段落ごとに線を引けば分かりやすくなることが
分かってきたりしたので、これからに活かしたいです。
🌸計算力が高くなってきたのも塾のおかげです。
🌸授業がすごく楽しくて勉強するのが苦にならなかったです。
保護者の皆様からも温かいメッセージをいただきました。
🌸子どもの苦手な英語の基礎やひもの結び方などを
教えていただき、本当に感謝しています。
🌸学校にお願いがあるときに相談の仕方を事前に一緒に
考えてくださいました。
🌸進学に際しても対策を考えてくださいました。
🌸この子はLDかもしれない、とあらゆる機関に相談に行きましたが、
求める答えはもらえませんでした。
ようやくたどりついた「びすぽうく」。
先生は、子どもの個性に向き合って考えを尊重してくれました。
決して否定しないで話を聞いてくれたのも子どもに合っていました。
「毎日塾に行きたい」というくらい、楽しく通えたのも「信じられる人」が
できたことからだと思います。
小さな変化やちょっとしたこともほめられて自信がつきました。
どんなに勉強しても字は書けない、読めないと親子で絶望の淵にいた私達に
「大丈夫」と声をかけてくれたこと、ともに悩み歩んでくださったことを
本当に感謝しております。
・・・決して平たんではなくても、子どもたちの前の「道」は、
必ず未来に通じている・・・
子ども自身が道を見つけて、歩くとしても
半歩先を照らす柔らかい光になれれば・・・
そんな気持ちを新たにする3月終わり。

毎年この日には、ぽっかり胸に穴が空いたような気分になりますが、
通ってきてくれた生徒さんたちから教わったことを
4月からの自分の支援に活かしていこうと思っています。

卒業生・保護者の皆様、そしてご協力いただいた関係機関の皆様、
本当に本当に感謝おります。
お世話になりました。
びすぽうくは、子どもをとりまく場所との連携を大事にしています。
さあ、明日からもがんばらねば!
・・・ちょっと自分にご褒美💛

新年度、新たな場所で学びたい、と思うお子さんたち、
保護者の皆様、先生方
お電話をお待ちしています。
🌸個別学習塾のホームページへ🌸(線のところをクリックしてください)











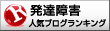








 個別学習塾びすぽうくのホームページへ(線のところをクリックしてください)
個別学習塾びすぽうくのホームページへ(線のところをクリックしてください)




 してくれるので
してくれるので













 (左のところをクリックしてください)
(左のところをクリックしてください)











 個別学習塾びすぽうくのホームページへ
個別学習塾びすぽうくのホームページへ
 )
)




 個別学習塾びすぽうくのホームページへ(線のところをクリックしてください)
個別学習塾びすぽうくのホームページへ(線のところをクリックしてください)
 ついに500回!
ついに500回!














