いつの間にか5月も末。
先日塾に来た子が「もう2か月かあ」とつぶやいていました。
新しい年度になり、新しいクラスになりもう2か月。
今日は、「作文」について考えてみようと思います。
国語の時間でも「作文」には、苦手感がある子が多いです。
書くことが浮かばない。
文がまとまらない。
漢字を使うことがいや。
小さいマス目に書くと目が疲れてしまう。
・・・・だんだん「書く」ことが嫌になってきてしまいます。
ときどき上手な子の作文を読んでもらっても自分には「無理」だな、と感じてしまう。
逆にたくさん書けるけれどもどうも冗漫になってしまい、何を言いたいのかわからなくなってしまう場合も。
「作文を書くこと」が目的になってしまい、先生しか読まないとしたら、
なかなか書く「意欲」にはなりにくいです。
でも、何か伝えたいことがあって
伝えたい相手があって
書き始めるのなら?
がんばれるかもしれないです!!
塾では、ちょっとした休憩を学習の合間に挟むのですが、「メニュー表」に
新しいものを入れたい、という子がいました。
その子と私だけで「相談」するのではなく、「他の子の意見もききたい」ということで
「アンケート」をとることにしました。
はじめは、自分の知っている漢字を使って、自分の思いで文を書いていました。
でもそのうち、「みんな」に見てもらうには、
 自分はどんな思いでアンケートをとるのか
自分はどんな思いでアンケートをとるのか
 どんな内容を提案するのか、その内容をどうやって分かってもらうのか
どんな内容を提案するのか、その内容をどうやって分かってもらうのか
 あまり小さい字だと読みにくいので字の大きさの調整が必要
あまり小さい字だと読みにくいので字の大きさの調整が必要
 長い文だと伝わりにくいが、あまり簡潔だとよくわかってもらえない
長い文だと伝わりにくいが、あまり簡潔だとよくわかってもらえない
 さらに文だけでなくイラストもあるとわかりやすい
さらに文だけでなくイラストもあるとわかりやすい
とだんだん気づいてきました。
これって、「相手」があるからこそ。
丁寧な文字を書くことも必要になってきます。
よく学校では高学年の子が委員会の活動について低学年に説明しに行く場面があります。
「相手」の学年に合わせて「わかりやすいことば・はやさ」で話したり、動作を入れたり
イラストを入れたり・・・と工夫が必要です。
作文は、原稿用紙に書くことも多いですが、相手に伝えるには、原稿用紙でなくても
画用紙でもよいわけです。
相手を意識して・相手の立場に立って
考えることができる・・・・
国語的な力の前に少し「自分を客観的にみる」ことができるようになると
作文の力も少しずつついてくるのかな、と思います。
「この書き方だと自分はわかるけど、はじめての人にはわからないかな」
句読点(点や丸)、漢字や語彙など伝えるために大切なものも確かにあります。
書いた文を身近な人に読んでもらって「これでわかるかな」ときいてみるのも大切。
そのとき「だめだし」をされると気分を害してしまう子もいるのですが、
「1ポイント」に絞ってのアドバイスだったらきいてくれるかもしれません。
それに作文の初期段階だと、「その文は自分にしか通じない」ということすら
気づかない子もいます。(話すときもそうです。)
はじめのうちは、だれかに「それ、もう少し説明して。」「自分にはわからないな」と言われて
・・・そうなんだ・・・じゃあ、もっと説明しないと、と思うことも必要かもしれません。
作文の時間に書く「練習」と、実践的な「機会」両方があって「作文力」がつくのかな。
そして、作文は、「伝えたい相手に合わせて」書く、という視点。
この辺が「きも」なのかな、と思います。
・・・・こんな話を塾でしていたら、「自分も書いてみようかな」とアンケートづくりに取り組み始めた子も
出てきました。
「なんのために書くのか」が「自分ごと」になるとがんばれるのだとしみじみ思います。
そして、だんだんと「自分の振り返りのために書く」ということもできるようになるのかな、
と思います。
日記の宿題が出ることもあると思います。先生が子どもの作文力を高めたり、
その子の日常を把握したりすることを意図していても
結局は、その文を自分で読み返して、先生のコメントを読んで
どこまで自分の思いが通じたか確かめる。
また、しばらくして読み返して「あのときの気持ちはこうだったなあ」と自分を「振り返る」ために使う手段になる
・・・・そこまでいくにはしばらく「やらされ感」があるのかな。
「書くこと自体」が苦痛にならないように
苦手な子が少しでも自主的に書いたときにほめていきたいと思います。

すべりどめがついた定規をみつけました。
 個別学習塾びすぽうくのホームページへ
個別学習塾びすぽうくのホームページへ (色のついている部分をクリックしてください)
(色のついている部分をクリックしてください)
先日塾に来た子が「もう2か月かあ」とつぶやいていました。
新しい年度になり、新しいクラスになりもう2か月。
今日は、「作文」について考えてみようと思います。
国語の時間でも「作文」には、苦手感がある子が多いです。
書くことが浮かばない。
文がまとまらない。
漢字を使うことがいや。
小さいマス目に書くと目が疲れてしまう。
・・・・だんだん「書く」ことが嫌になってきてしまいます。
ときどき上手な子の作文を読んでもらっても自分には「無理」だな、と感じてしまう。

逆にたくさん書けるけれどもどうも冗漫になってしまい、何を言いたいのかわからなくなってしまう場合も。
「作文を書くこと」が目的になってしまい、先生しか読まないとしたら、
なかなか書く「意欲」にはなりにくいです。
でも、何か伝えたいことがあって
伝えたい相手があって
書き始めるのなら?
がんばれるかもしれないです!!
塾では、ちょっとした休憩を学習の合間に挟むのですが、「メニュー表」に
新しいものを入れたい、という子がいました。
その子と私だけで「相談」するのではなく、「他の子の意見もききたい」ということで
「アンケート」をとることにしました。
はじめは、自分の知っている漢字を使って、自分の思いで文を書いていました。
でもそのうち、「みんな」に見てもらうには、
 自分はどんな思いでアンケートをとるのか
自分はどんな思いでアンケートをとるのか どんな内容を提案するのか、その内容をどうやって分かってもらうのか
どんな内容を提案するのか、その内容をどうやって分かってもらうのか あまり小さい字だと読みにくいので字の大きさの調整が必要
あまり小さい字だと読みにくいので字の大きさの調整が必要 長い文だと伝わりにくいが、あまり簡潔だとよくわかってもらえない
長い文だと伝わりにくいが、あまり簡潔だとよくわかってもらえない さらに文だけでなくイラストもあるとわかりやすい
さらに文だけでなくイラストもあるとわかりやすいとだんだん気づいてきました。
これって、「相手」があるからこそ。
丁寧な文字を書くことも必要になってきます。
よく学校では高学年の子が委員会の活動について低学年に説明しに行く場面があります。
「相手」の学年に合わせて「わかりやすいことば・はやさ」で話したり、動作を入れたり
イラストを入れたり・・・と工夫が必要です。
作文は、原稿用紙に書くことも多いですが、相手に伝えるには、原稿用紙でなくても
画用紙でもよいわけです。
相手を意識して・相手の立場に立って
考えることができる・・・・
国語的な力の前に少し「自分を客観的にみる」ことができるようになると
作文の力も少しずつついてくるのかな、と思います。
「この書き方だと自分はわかるけど、はじめての人にはわからないかな」
句読点(点や丸)、漢字や語彙など伝えるために大切なものも確かにあります。
書いた文を身近な人に読んでもらって「これでわかるかな」ときいてみるのも大切。
そのとき「だめだし」をされると気分を害してしまう子もいるのですが、
「1ポイント」に絞ってのアドバイスだったらきいてくれるかもしれません。
それに作文の初期段階だと、「その文は自分にしか通じない」ということすら
気づかない子もいます。(話すときもそうです。)
はじめのうちは、だれかに「それ、もう少し説明して。」「自分にはわからないな」と言われて
・・・そうなんだ・・・じゃあ、もっと説明しないと、と思うことも必要かもしれません。
作文の時間に書く「練習」と、実践的な「機会」両方があって「作文力」がつくのかな。
そして、作文は、「伝えたい相手に合わせて」書く、という視点。
この辺が「きも」なのかな、と思います。
・・・・こんな話を塾でしていたら、「自分も書いてみようかな」とアンケートづくりに取り組み始めた子も
出てきました。
「なんのために書くのか」が「自分ごと」になるとがんばれるのだとしみじみ思います。
そして、だんだんと「自分の振り返りのために書く」ということもできるようになるのかな、
と思います。
日記の宿題が出ることもあると思います。先生が子どもの作文力を高めたり、
その子の日常を把握したりすることを意図していても
結局は、その文を自分で読み返して、先生のコメントを読んで
どこまで自分の思いが通じたか確かめる。
また、しばらくして読み返して「あのときの気持ちはこうだったなあ」と自分を「振り返る」ために使う手段になる
・・・・そこまでいくにはしばらく「やらされ感」があるのかな。
「書くこと自体」が苦痛にならないように
苦手な子が少しでも自主的に書いたときにほめていきたいと思います。

すべりどめがついた定規をみつけました。
 個別学習塾びすぽうくのホームページへ
個別学習塾びすぽうくのホームページへ (色のついている部分をクリックしてください)
(色のついている部分をクリックしてください)










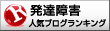


 が出ると、からだも心もすっきり!
が出ると、からだも心もすっきり!







 (色のついているところをクリックしてください)
(色のついているところをクリックしてください)



 (色のついているところをクリックしてください)
(色のついているところをクリックしてください)




