
気が付けば、1月も終わりに近づき・・・早いものです。
もう1年の12分の1が終わろうとしているなんて。
今日和菓子屋さんの店先になんと「桜餅」が並んでいました!
今日は「九九」の話。
覚えるのがすんなりだった方とそうでなかった方がいるかと思います。
小学校2年生の秋ごろから2か月ぐらいかけて1の段から9の段まで覚える・・・。
今だに学校では「唱えて覚える」場合が多いかと思います。
表にするとこんな感じ。

または、単語カードの表に 7×6と書いてうらに「42」と書く場合もあるかしら。
また九九の歌が何通りかあってからだも動かしながら覚える場合も。
歌にしろ、単語カードにしろ、
音声で
順番に覚えるのには変わりません。
7の段と4の段が覚えにくいのは、「しち」と「し」が混同したり、
ふだん「7」を「なな」、「4」を「よん」と読むからなのではと思います。
考えたら、筆算のときや暗算のときにぱっとその掛け算の答えがでてこればよいので
7×4を「しちし」ではなく「ななよん」で覚えてもぜんぜん大丈夫なはず!
子どもの中には、「音で覚えるのが得意な子」と「目でみて覚えるのが得意な子」がいます。
(どらも変わらない子もたくさんいます)
検査などをとってみると、ときどきどちらかがとっても得意で片方が苦手、というケースがあります。
音で覚えるより、「目でみて覚える」方が得意なら、

こんな九九表で覚えるのもよいかもしれないです。
(唱え方、覚え方はその子のやりやすい方法で)
九九表は教科書では、3年生のはじめにでてくるのですが、
はじめからこちらの方が覚えやすい子もいます。
(逆に覚えにくい子もいます)
覚えたところをこんなふうに

付箋で隠していくと、覚えていないところが際立ち、何回も参照することで
だんだん覚えていきます。
(覚えたのになんだっけ???になったら、付箋をとればよいのです!)
カードで覚えるタイプだっただ、覚えたカードは後ろに回して
覚えていないのだけ前に集めるのもよいかもしれないです。
本当に何年も「唱えて覚えられなかった子」が「表」でほんの数か月でおぼえたケースを知っています。
表で覚える場合、私は、同じ段を縦に同じ薄い色でぬって表の「見方」を練習します。
「表」があればよい、単語カードがあればよい、ということではなくて
「使い方」を前もって練習するという準備
が必要なのは、九九だけでなく、いろいろな場面であります。
たとえば理科でも、地面にプラスチック容器をふせておいて
しばらくすると容器の内側に水滴がつく、という実験だとしたら
「容器をかぶせたところは、他の周りのものが入らない」とか
「水がついたとしたら、それは、地面からきたものだ」
のような本当に前提のようなものが理解できていないと
結果をみてもどう解釈してよいか分からなかったりします。
それを「なぜか考えてみて」と言われても答えられなかったり・・・。
















学習だけでなく、生活でも「前もって」の練習や「説明」が本当に
必要な子どもは、教科書だけの学習では難しい場面があるのでは、と思います。
漢字練習にしても・・・。
今だに「ノートの下まで繰り返し書いてきて」のような課題がありますが、
漢字の「形」は覚えても、ことばの意味がわからなければ、テストで100点でも
実際には使えない・・・そんなことがたくさんありそうです。
意味が分からなければ、タブレットで入力するときにどの漢字を選択するか
分からなかったりします。
・・・このところそんなことを考えていて、
子どもたちの教材をつくりながら、「いきなり」でなく「準備」がいるかな?
と振り返ることも多々。
大人がたくさん想像していかないと子どものことはすぐにはわかりにくいです。
でも、日々近づけるようにと思っています。
 横浜市の個別学習塾 びすぽうくのヘームページへ(線のところをクリックしてください)
横浜市の個別学習塾 びすぽうくのヘームページへ(線のところをクリックしてください)










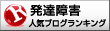

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます