寒いですね・・・・
小さいころから寒がりの私です
今日は、「自立」について考えてみたいと思います。
ときどき塾に来る子どもに訊かれます。
「この勉強って、何の役にたつの?」
足し算や引き算、そして日常買い物で使う範囲の数なら
勉強する「目的」も分かりやすいのですが、兆を超える数、
複雑な分数、三角形の角度、そして歴史の年号・・・。
確かに中には、学校で勉強する以外使わない「知識」も
あるかな・・・。
でも、その子の将来は、分からないので「使う日が来る
かもしれない」し、少なくとも、「新しいことを学ぶ姿勢」
づくりには役に立つのではと思います。

ぶんぶんごま(手首の動きの練習になります)
教員をしていたとき、「この子は今このぐらいできるけれど、
どこまでを支援したらよいのだろう?」と常に考えていました。
「見守る」態勢でよいのか、
「背中を押す」ぐらいでよいのか、
少しやり方を一緒にした方がよいのか、
もっと具体的に課題のレベルを下げた方がよいのか、
それとも目標そのものを変えた方がよいのか。
同じ子どもでも「教科」によってまた、「学習内容」によって
取り組み方や実態が変わります。
特に「初めて取り組むこと」に関しては「試してみないと」
分からないことも多くありました。

学研「国語の時間」覚えた字に色をぬっていくとモチベーション、上がります。
読みとしては、「先生の先」のように単語で覚えている子どもが多いです。
でも、どんな子どもでもだんだんに「手助けの割合を減らしていこう」と
いうことは心がけるようにしました。
(それは、今もです)
子どもの「自立」。
はじめは、教員や保護者などの手助けで。
それも少しずつ自分でできる割合を増やし、
「ここまで自分でできた!」という達成感をもてる。
最近のICTも、「自立」をするための道具。
学習だけでなく、生活面でも、
くつをそろえて脱ぐ、
上着をたたむ、
筆箱の中を整理する
トイレを出るときに自分の使った後を見る
などもその子どもなりに「自立」してできるように
なれるといいなあ、と思っています。
ただ、「なにもかもいっぺんに」がきつい子どももいることは事実。
絶対にゆずれない一つ目のものから
または、すぐ効果が上がる簡単なものから
少し大人の「ちえ」を使って
取り組めるといいですね。
「何年生だから~」「何歳だから~」ではなく、
その子がもうすぐ自分でできそうだから
少しの手助けや、やり方のヒントを出すなどで
できることが増えていくように考える。
たんに「手厚い支援」があるだけでは「自立」は難しい。
でも、「自立」に向けての「環境づくり」は
「大人」の役目だと考えます。
 個別学習塾びすぽうくのホームページへ
個別学習塾びすぽうくのホームページへ (色のついているところをクリックしてください)
(色のついているところをクリックしてください)
小さいころから寒がりの私です

今日は、「自立」について考えてみたいと思います。
ときどき塾に来る子どもに訊かれます。
「この勉強って、何の役にたつの?」
足し算や引き算、そして日常買い物で使う範囲の数なら
勉強する「目的」も分かりやすいのですが、兆を超える数、
複雑な分数、三角形の角度、そして歴史の年号・・・。
確かに中には、学校で勉強する以外使わない「知識」も
あるかな・・・。
でも、その子の将来は、分からないので「使う日が来る
かもしれない」し、少なくとも、「新しいことを学ぶ姿勢」
づくりには役に立つのではと思います。

ぶんぶんごま(手首の動きの練習になります)
教員をしていたとき、「この子は今このぐらいできるけれど、
どこまでを支援したらよいのだろう?」と常に考えていました。
「見守る」態勢でよいのか、
「背中を押す」ぐらいでよいのか、
少しやり方を一緒にした方がよいのか、
もっと具体的に課題のレベルを下げた方がよいのか、
それとも目標そのものを変えた方がよいのか。
同じ子どもでも「教科」によってまた、「学習内容」によって
取り組み方や実態が変わります。
特に「初めて取り組むこと」に関しては「試してみないと」
分からないことも多くありました。

学研「国語の時間」覚えた字に色をぬっていくとモチベーション、上がります。
読みとしては、「先生の先」のように単語で覚えている子どもが多いです。
でも、どんな子どもでもだんだんに「手助けの割合を減らしていこう」と
いうことは心がけるようにしました。
(それは、今もです)
子どもの「自立」。
はじめは、教員や保護者などの手助けで。
それも少しずつ自分でできる割合を増やし、
「ここまで自分でできた!」という達成感をもてる。
最近のICTも、「自立」をするための道具。
学習だけでなく、生活面でも、
くつをそろえて脱ぐ、
上着をたたむ、
筆箱の中を整理する
トイレを出るときに自分の使った後を見る
などもその子どもなりに「自立」してできるように
なれるといいなあ、と思っています。
ただ、「なにもかもいっぺんに」がきつい子どももいることは事実。
絶対にゆずれない一つ目のものから
または、すぐ効果が上がる簡単なものから
少し大人の「ちえ」を使って
取り組めるといいですね。
「何年生だから~」「何歳だから~」ではなく、
その子がもうすぐ自分でできそうだから
少しの手助けや、やり方のヒントを出すなどで
できることが増えていくように考える。
たんに「手厚い支援」があるだけでは「自立」は難しい。
でも、「自立」に向けての「環境づくり」は
「大人」の役目だと考えます。
 個別学習塾びすぽうくのホームページへ
個別学習塾びすぽうくのホームページへ (色のついているところをクリックしてください)
(色のついているところをクリックしてください)










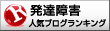











 )
)

 個別学習塾びすぽうくのホームページへ
個別学習塾びすぽうくのホームページへ

 あけましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます。



 ここ
ここ


 個別学習塾びすぽうくのホームページへ
個別学習塾びすぽうくのホームページへ




