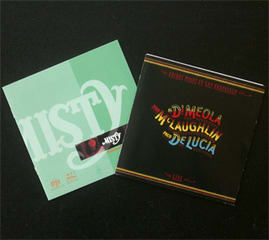4月24日(土曜日)に中野ZEROで開かれたクラシックのコンサートに行ってきました。クラシックのコンサートに行く機会は滅多にありませんが、オーディオ熱の高まりと共に生演奏に対する興味が上がってきました。奥村愛さんは、本格派というよりカジュアルな活動をされていますが、十分、素晴らしい演奏を楽しませていただきました。ちなみに演奏した曲は、
ベートーベン:ロマンスNo2
サラサーテ:カルメン幻想曲
サラサーテ:チゴイネルワイゼン
モンティ:チャルダーシュ(アンコール)
です。ご本人もブログでも述べられていますが、このラインナップで弾くことはなかなか無いとのことです(このあたりの感覚は私はよくわかっていません)。奥村愛さんの優しい雰囲気はトークは勿論、演奏にも表れていたと思います。とは言え、激しい曲調のところでは凛とした感じもあって、良かったです。
奥村愛オフィシャルブログ


結局、4月は ジャズ(Sophie Milman)とクラシックの生演奏を聴くこととなりました。ライブを聴いてあらためて思うのは、生演奏とオーディオの重なる点と重ならない点です。楽曲を楽しむ点では共通していますが、オーディオを極めた先に生演奏があるとは思いません。アーティストとの一体感、視覚を通じての感動・興奮、一期一会の感じなどは、生演奏ならではの楽しみです。一方、装置を組み合わせる、セッティングを追求する、といった聴く側の主体的な行動、創造にオーディオならではの楽しみを感じます。オーディオで生演奏に近い音が出せることもあるでしょうが、生演奏では出せないオーディオの音(勿論、素晴らしい音)もあるはずです。
ところで同じ24日の夜ですが、ヴァイオリンの女王と称される Mutter のコンサートがサントリーホールでありました。こちらは値が張るとの敷居が高くてパスしました。できればオーディオで十分予習して臨みたいです。生演奏で感動した曲をオーディオで聴き直す、あるいは事前にオーディオで聴き込んで生演奏を楽しむ、そんな感じで両方楽しめていければと思います。
ベートーベン:ロマンスNo2
サラサーテ:カルメン幻想曲
サラサーテ:チゴイネルワイゼン
モンティ:チャルダーシュ(アンコール)
です。ご本人もブログでも述べられていますが、このラインナップで弾くことはなかなか無いとのことです(このあたりの感覚は私はよくわかっていません)。奥村愛さんの優しい雰囲気はトークは勿論、演奏にも表れていたと思います。とは言え、激しい曲調のところでは凛とした感じもあって、良かったです。
奥村愛オフィシャルブログ


結局、4月は ジャズ(Sophie Milman)とクラシックの生演奏を聴くこととなりました。ライブを聴いてあらためて思うのは、生演奏とオーディオの重なる点と重ならない点です。楽曲を楽しむ点では共通していますが、オーディオを極めた先に生演奏があるとは思いません。アーティストとの一体感、視覚を通じての感動・興奮、一期一会の感じなどは、生演奏ならではの楽しみです。一方、装置を組み合わせる、セッティングを追求する、といった聴く側の主体的な行動、創造にオーディオならではの楽しみを感じます。オーディオで生演奏に近い音が出せることもあるでしょうが、生演奏では出せないオーディオの音(勿論、素晴らしい音)もあるはずです。
ところで同じ24日の夜ですが、ヴァイオリンの女王と称される Mutter のコンサートがサントリーホールでありました。こちらは値が張るとの敷居が高くてパスしました。できればオーディオで十分予習して臨みたいです。生演奏で感動した曲をオーディオで聴き直す、あるいは事前にオーディオで聴き込んで生演奏を楽しむ、そんな感じで両方楽しめていければと思います。