簿記の勉強で、「大の月、小の月」の覚え方という話題になりました。
何と一緒に勉強している30代の生徒さんは、私(あるいは我々の世代)が普通に覚えている“西向く士(サムライ)”というコトバを知らない、ということがわかりました。
2月、4月、6月、9月、11月の頭を取って“ニ・シ・ム・ク・サムライ(11の漢数字が士に似ているため)”
今は小学校でも教えていないようですね。
“士”ということばが死語になってしまったからなのかもしれません。
ちなみに今は左手のこぶしを握って、指の付け根のところに出来るこぶとその間を指差しながら大小を区別するのだそうです。すなわち、
と順番にいって、小指のところで7月、8月としてまた反対に戻ってくるという...。
ああ、ことばで説明するのは難しい。
“西向くサムライ”の方がずうっと簡単なのに。
これもジェネレーションギャップと言うのでしょうか?
追記:
私と一学年しか違わない家内は「“西向くサムライ”は学校では教わらなかった」と言い張っています。
何と一緒に勉強している30代の生徒さんは、私(あるいは我々の世代)が普通に覚えている“西向く士(サムライ)”というコトバを知らない、ということがわかりました。
2月、4月、6月、9月、11月の頭を取って“ニ・シ・ム・ク・サムライ(11の漢数字が士に似ているため)”
今は小学校でも教えていないようですね。
“士”ということばが死語になってしまったからなのかもしれません。
ちなみに今は左手のこぶしを握って、指の付け根のところに出来るこぶとその間を指差しながら大小を区別するのだそうです。すなわち、
- 人差し指(山)が1月、
- 人差し指と中指の間(谷)が2月
- 中指(山)が3月、
- 中指と薬指の間(谷)が4月
- 薬指(山)が5月、
- .
- .
- .
- 人差し指と中指の間(谷)が2月
と順番にいって、小指のところで7月、8月としてまた反対に戻ってくるという...。
ああ、ことばで説明するのは難しい。
“西向くサムライ”の方がずうっと簡単なのに。
これもジェネレーションギャップと言うのでしょうか?
追記:
私と一学年しか違わない家内は「“西向くサムライ”は学校では教わらなかった」と言い張っています。










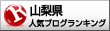



 電話台を購入することを検討しています。
電話台を購入することを検討しています。





