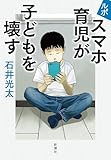某激安スーパーへ行った時の出来事です。
そのスーパーは近くに高校があるのですが、そこの学校の生徒と思われる女子高校生を何人も見かけました。あの時間はたしか午前11時頃。おそらくもうじき卒業を迎える3年生の登校日だろうと思われます。
いろいろ買い物をしながらお惣菜売り場へ向かうと、10代の女の子と思われる笑い声が聞こえてきたのです。よく見ると高校生数人と高齢の夫婦が会話をしていたのです。何を話していたのかは分かりませんでしたが、楽しそうに話していました。そして別れる際には高校生が元気よく「ありがとうございましたー」と挨拶をしていきました。その様子を見て何だか心が温まりました。
最近では赤の他人同士、特に年齢が異なると、お互い会話をすることは少なくなっています。せめて同じマンションの居住者同士で「こんにちは」と挨拶する程度でしょうか。防犯上から最近の小さな子どもたちは「知らない人に声を掛けてはダメ」と注意されていますし、高齢者も「最近の若者は何を考えているのか分からないし怖い」と感じていることでしょう。それに高校生くらいですとスマホでのやりとりは多くても、リアルではコミュニケーションが苦手な子も多いでしょう。
世の中が物騒と言われて久しいですが、同世代や年齢の異なる同士でもう少しお互いのコミュニケーションがあってもいいのではと思います。挨拶だけでもいいので声を掛け合えば犯罪も減るのでは。私が子どもの頃は小さな個人店が多く、母はお店の人ともよく会話をしていましたが、今ではセルフレジが増えてそんな会話もめっきり減りました。たしかに効率化はされますが少し寂しいですよね。
そのスーパーは近くに高校があるのですが、そこの学校の生徒と思われる女子高校生を何人も見かけました。あの時間はたしか午前11時頃。おそらくもうじき卒業を迎える3年生の登校日だろうと思われます。
いろいろ買い物をしながらお惣菜売り場へ向かうと、10代の女の子と思われる笑い声が聞こえてきたのです。よく見ると高校生数人と高齢の夫婦が会話をしていたのです。何を話していたのかは分かりませんでしたが、楽しそうに話していました。そして別れる際には高校生が元気よく「ありがとうございましたー」と挨拶をしていきました。その様子を見て何だか心が温まりました。
最近では赤の他人同士、特に年齢が異なると、お互い会話をすることは少なくなっています。せめて同じマンションの居住者同士で「こんにちは」と挨拶する程度でしょうか。防犯上から最近の小さな子どもたちは「知らない人に声を掛けてはダメ」と注意されていますし、高齢者も「最近の若者は何を考えているのか分からないし怖い」と感じていることでしょう。それに高校生くらいですとスマホでのやりとりは多くても、リアルではコミュニケーションが苦手な子も多いでしょう。
世の中が物騒と言われて久しいですが、同世代や年齢の異なる同士でもう少しお互いのコミュニケーションがあってもいいのではと思います。挨拶だけでもいいので声を掛け合えば犯罪も減るのでは。私が子どもの頃は小さな個人店が多く、母はお店の人ともよく会話をしていましたが、今ではセルフレジが増えてそんな会話もめっきり減りました。たしかに効率化はされますが少し寂しいですよね。