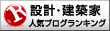リビングスペースや
ダイニングスペース、
日常的に
過ごす場所で見るテレビ画面の事。

※LDK・全体から見る壁掛けテレビ
壁掛けテレビや
テレビボードの
最適な高さや距離は
見る位置関係全体で
変わるという事。

※LDK・ソファから見るテレビボード+置型テレビ
日々のくつろぎの時間に
テレビを観る事も
あると思います。
最近はテレビといっても
ユーチューブやNetflix (ネットフリックス)
Amazonプライム等の方が
多いかと思いますが・・・・・。
もはや当たり前すぎる
その行為をさらに
快適にするには
「テレビボードの高さと視聴距離」を
見直すと良いかもしれません。

※LDK・ソファから見るテレビボード+置型テレビ
テレビはリビングにあるソファの
正面やリビングの一角に
配置していることが
多いかと思います。

※LDK・ダイニングテーブル+小上がりから見る壁掛けTV
一方で、
ダイニングテーブルが
暮らしの主流に
なることも多くなってきたなかで、
ダイニングテーブル近くにある
腰高の収納家具の上に
テレビを置いている、
あるいは
ダイニング側からソファ越しに
テレビを見るといったこともあります。
その際にテレビの視聴の
し易さについて
なんらかの不満を持っている人は
居ませんか?
「テレビの見やすさ」について
悩んでいるのであれば、
それは「高さ」と「距離」で
解決が可能です。
どこからテレビを
見ることが多いのかを考える。
テレビをどこから見るとしても
画面全体が見えるほうが
良いですよね。
ダイニングテーブルと
テレビボードの間に
ソファがあり、
椅子やソファが
邪魔してテレビが見難い、
といったことは
意外と多いものです。
テレビボードを高くすれば
解決するかもしれませんが、
そうすると
ソファからテレビを視聴する際に
テレビを見上げるような
姿勢を余儀なくされ、
疲れやすくなってしまいます。
であれば、
レイアウトそのものを
変更することで
解決策を
見出すことが可能です。
配線や家具自体の大きさも
関係するので
ボリュームの認識が重要です。
見る場所によって変わる
最適なテレビ台の高さを知る。
レイアウト変更によって
問題が解決できるなら
それで良いですが、
物理的な問題などで
それが難しい場合もあります。
その時には
ここからテレビを見ることが多いから
そこでの快適性を追求する、
テレビの画面を見る際は
この場所という意識で
LDKの構成を考えます。
そもそも人の目線は
常に少し下向きに向いています。
上を見上げるときより、
下を見るほうが
疲れにくいケースが多いです。
そのため、
テレビの画面の中心の位置が、
テレビを見る際の
目線よりも下になるような
高さだと、
長時間テレビを見ていても
疲れずに快適に
過ごすことができます。
それでは
テレビを見る場所によって
テレビ台は
どのような高さが
最適なのか?。
床に座って
テレビを観ることが多い場合の
最適な高さ。
床に座ってテレビを観る場合は、
テレビボードの高さとしては
30センチ~40センチメートル以下が
最適です。
テレビボードも
高さを抑えたタイプが
様々出ているので
選択肢も多いです。
高さが無い分、
DVDなどのソフト類や
ゲーム機器、
各種AV機器などの
収納性という点で
不満が生まれる可能性もあります。
こうした収納性との
バランスを考慮した
テレビボード選びが重要です。
ソファからテレビを観る場合、
テレビの中心が目線から
10~15度下がるように、
テレビボードは
高さ40~60cmがお薦めです。
一般的に一番多くの
選択肢が存在する
サイズでもあります。
また、
収納性も高く
様々な仕様があるタイプなので
バランスの良い
テレビボードと言えます。
将来的に引越しなど
間取りの変更があった場合でも
比較的対応力があります。
ダイニングから
テレビを観ることが
多い場合、
高さが60センチ~70センチ強ある
リビングボードなどを
テレビ台として
活用するのがお薦めです。
収納を兼ねて
テレビが設置できること、
また基本的には
ダイニングからの視聴距離を
短く設定する場合が
多いため、
狭いスペースでも
有効活用できる
という利点があります。
テレビが高い場所にあるが故に
空間への圧迫感が
増してしまう可能性があることや、
テレビが転倒しないような
地震対策を
しっかりしなければいけない点は
考慮しなければなりません。
テレビを視聴する最適な距離を知る。
最近主流となってきている
4Kテレビは、
ひと昔前のフルHDテレビと比較して
視聴距離が
約半分とされています。
メーカーでは
4Kテレビの最適視聴距離は、
画面の高さの「1.5倍」と
表示しているケースが
多く見られます。
その場合、
最近販売数の多い49V(高さ65cm前後)だと
約1mの視聴距離になります。
しかし現実的には
この考えは
最短距離と考えた方が良いです。
というのは、
メーカーの推奨する距離では
例えばカメラの動きや
被写体の動きが激しい
スポーツ番組などでは、
目が疲れてしまうことが
多分に起こってしまう
可能性は否めません。
※倍速機能付きだと
なめらかに見えますので
見やすくなります。
機能性にもよりますが
目の疲れも考慮すると、
49Vでは2.6mほどの距離から
テレビを観ることを
お勧めします。
あくまで目安ですが
32Vでは2.0m、
40vで2.3m、
55vで2.8m、
65vで3.1mくらいの距離で
テレビとの距離を取れば、
テレビの内容に対しての
適度な没入感、
同時に目の疲れも
起こりにくい距離感と言えるかと思います。
※実際には建築工事中に
リアルサイズで昇華する
打ち合わせを行います。
特に子供がいるご家庭などでは、
以前ほど距離を
とらなければならない訳では
ありませんが、
長時間視聴することによる
視力の低下、
そして目からくる疲れを
軽減させるためにも、
適度にゆとりのある距離感での
視聴が望ましいと思います。
現時点では
テレビは10年ほどのスパンで
買い替えをしていく事の多い家電です。
反面テレビボードは
素材にもよりますが
20年、30年と味わいを増しながら、
テレビが変わっても
使い続けることができます。
自宅の空間に合うテレビボードを
検討する際には
置き場所はもちろんのこと、
視聴までの距離感や
テレビのサイズまで
考えなければいけないことも
多くあります。
配置や距離、
テレビのサイズに関しても
家造りを終えるまでに
間取りと共に計画する事で
「間違い」を防ぐことが
できるようになります。
新築やリフォームの際には
設計中や現場工事中に
インテリアコーディネートとして
テレビの配置から
壁掛けTVの際には、
その周辺を整えています。
勿論テレビボードも
バランスを考えてインテリア提案します。
家をどのように
過ごす場所とするべきなのか?。
暮らしの提案と共に
家電と家具のバランスも大切に。
住まいのリフォーム・リノベーション
模様替えや増改築について
ご相談・ご質問・ご依頼は
■やまぐち建築設計室■
気軽にご連絡ください。
-------------------------------------
■やまぐち建築設計室■
建築家 山口哲央
奈良県橿原市縄手町387-4(1階)
-------------------------------------