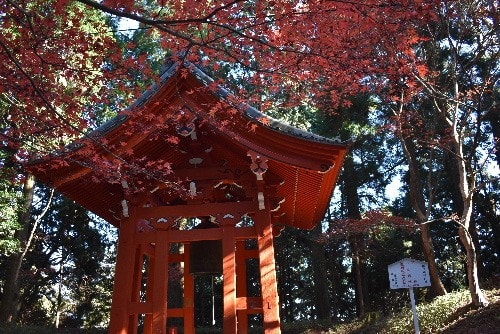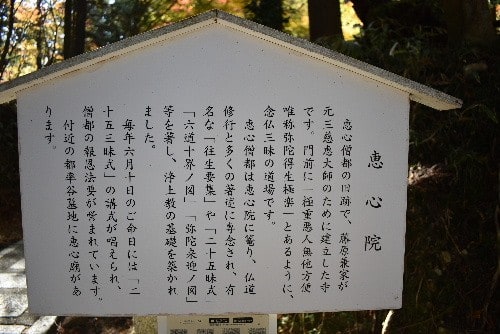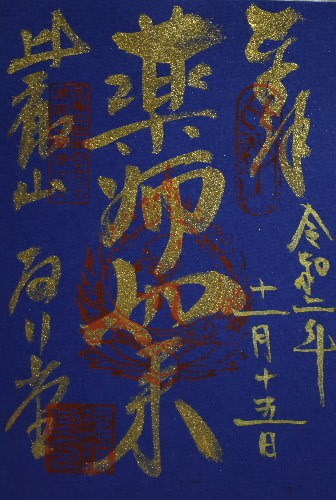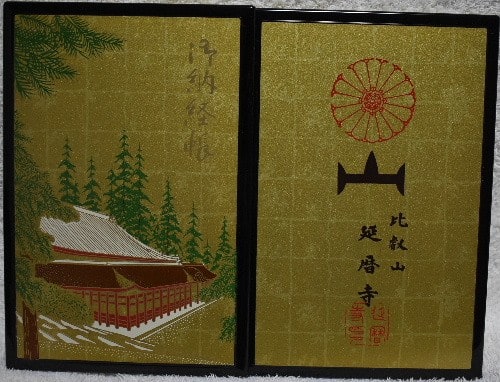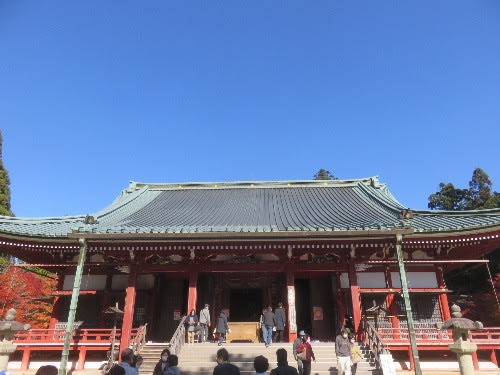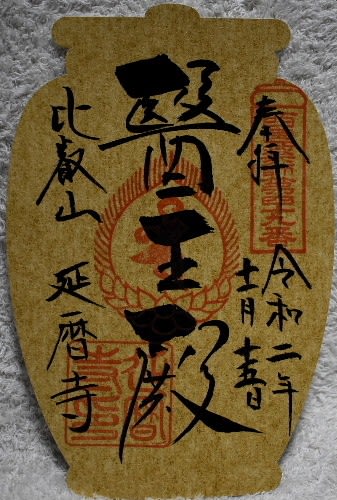延暦寺の主要箇所はだいたい参拝したので、
今日はこのぐらいにして紅葉と景色を楽しむことにしよう。
【紅葉】



横川地区の無料駐車場から見た紅葉と琵琶湖。
比叡山ドライブウェイを暫く走り、
ちびっこ広場がある夢見が丘に到着。
【風景】



駐車場に車を停めると雄大な風景が楽しめます。


標高800メートルから見る琵琶湖。
この風景を見ながら飲んだコーヒーがバリうまでした。
【夢見が丘】



ここの紅葉が見事。





一足早い紅葉を堪能した。
これから京都市内も次第に紅葉が進むでしょう。
今年はどこに行こうかな。
コロナもあるから行くか迷うな。
今日はこのぐらいにして紅葉と景色を楽しむことにしよう。
【紅葉】



横川地区の無料駐車場から見た紅葉と琵琶湖。
比叡山ドライブウェイを暫く走り、
ちびっこ広場がある夢見が丘に到着。
【風景】



駐車場に車を停めると雄大な風景が楽しめます。


標高800メートルから見る琵琶湖。
この風景を見ながら飲んだコーヒーがバリうまでした。
【夢見が丘】



ここの紅葉が見事。





一足早い紅葉を堪能した。
これから京都市内も次第に紅葉が進むでしょう。
今年はどこに行こうかな。
コロナもあるから行くか迷うな。