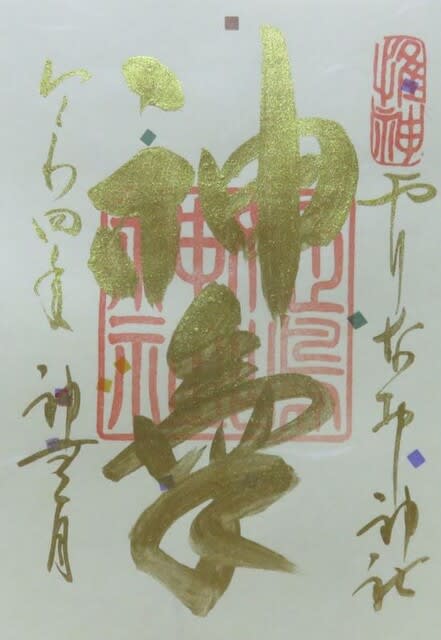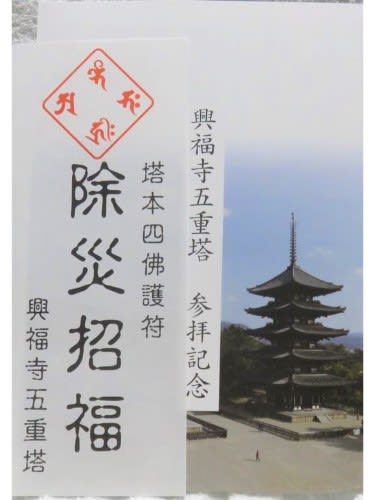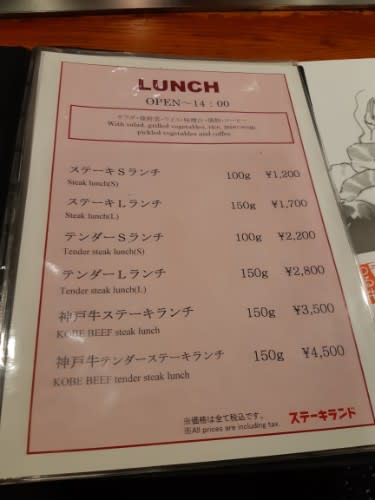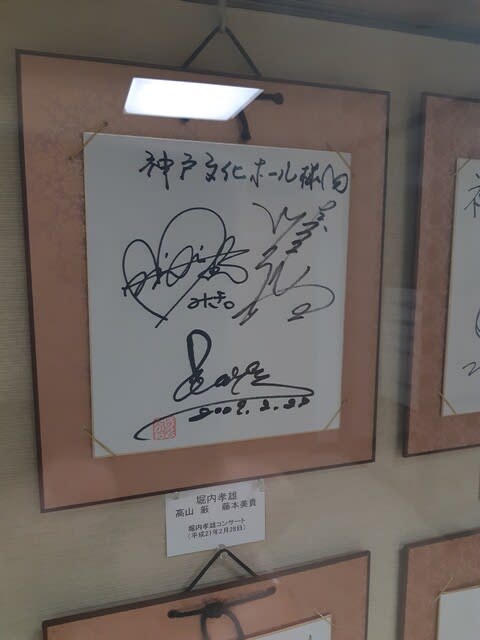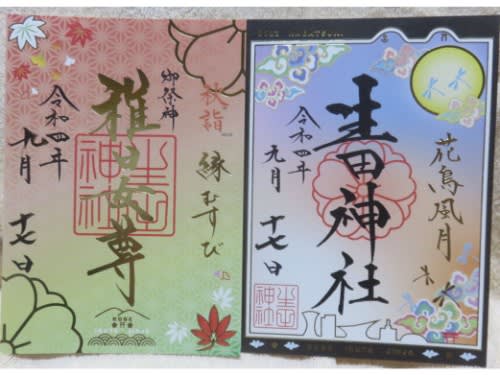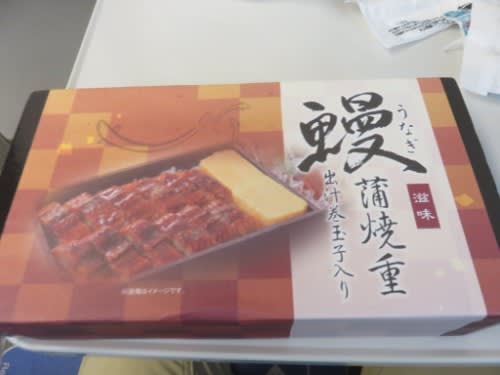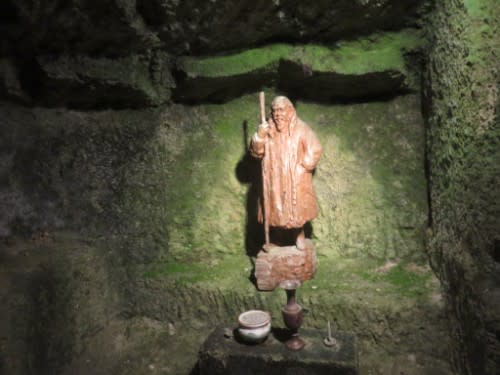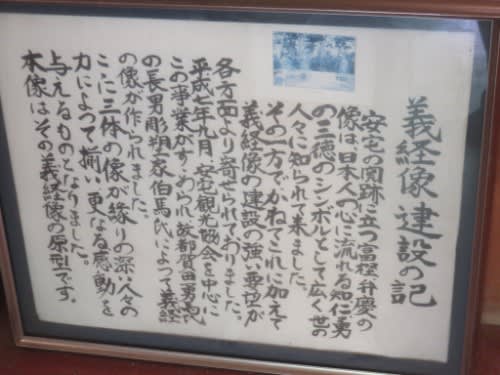今日は家族で鉄板焼を食べに大阪天満宮近くの鉄板焼 GUMPにやってきました。
ランチ、ディナーともにコースやアラカルトがありますが、
鉄板焼だとやはり目の前で肉を焼いてるのが見たいので、
黒毛和牛サーロインの大阪天満宮ランチコース(6千円)をチョイス。
こちらのお店のお肉は市場になかなか出ないという、
なにわ黒牛(A5ランク)です。
月5頭しか出荷出来ない希少純粋黒毛和牛で、
有名ホテルやミュシュラン店で使われているお肉で楽しみ。
車は近隣の有料駐車場が幾つかありましたが、
お店の隣に2台の有料駐車場が一番近いです。(笑)
所在地:大阪府大阪市北区天神橋2丁目5-3 第五新興ビル1F
予約専用番号:050-5232-9387
営業時間:【昼】11:00~14:30(最終来店時間14:00)
【夜】17:00~23:00(最終来店時間21:00)
定休日:月曜・第2,4日曜
駐車場:無し
【大阪天満宮ランチコース】
●自家製オニオンドレッシングミニサラダ
●季節のポタージュ
●鉄板ミニハンバーグ
●メイン 黒毛和牛サーロイン
(・ハラミステーキ・黒毛和牛おすすめ部位・黒毛和牛サーロイン・黒毛和牛フィレ)
●旬の焼野菜4種
●ローストオニオン
●ミニデザート
●ご飯
●1ドリンク
【店内】

店内はスタイリッシュでカウンター席と半個室のテーブル一つとなります。
【自家製オニオンドレッシングミニサラダ 】

ドレッシング美味し。
【旬の焼野菜4種・鉄板ミニハンバーグ】



焼きが始まりました。
しかしトマトを焼いたのは今までの食ったことないな。(笑)
【季節のポタージュ 】

これも美味し。
【黒毛和牛サーロイン】



鉄板焼といえばこのフランベはかかせない。

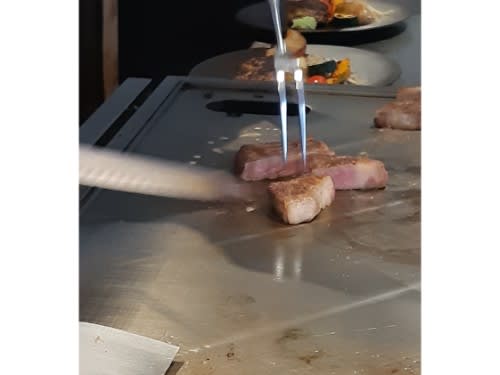

軽くシュッと切れるので食う前から肉の柔らかさが分かります。

いざ実食。
早速サーロインから。
めっちゃ柔らかくて美味すぎる。
うん、下手な神戸牛の赤身より和牛サーロインの方が美味いね。
ハンバーグは普通デミグラスソースとかが定番ですけど、
こちらは塩やポン酢で食べるスタイル。
味付け無しでも充分美味いハンバーグでした。
焼きトマトはシェフの言う通り焼くと甘かったです。
【赤ブドウジュース】

車なので赤ブドウジュースです。
他にビールやグラスワイン、ジュース等選べました。
一般的にブドウジュースは甘くて本当にジュースな感じなんですけど、
こちらのは結構ワインテーストで美味しかったです。
【デザート】

シャーベットでスッキリ。
写真は写していませんが他にご飯と汁物もあり。
ご飯はオプションでガーリックライス、和牛カレー、卵かけご飯に変更出来ます。
今回のサーロインステーキのコースは一人6千円也。
全部美味くて大変満足しました。
★5つです。(笑)