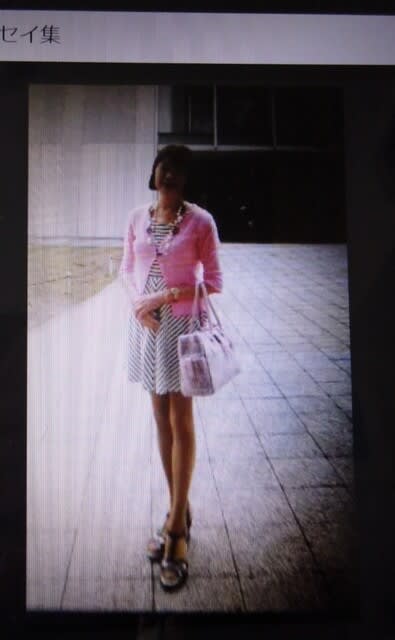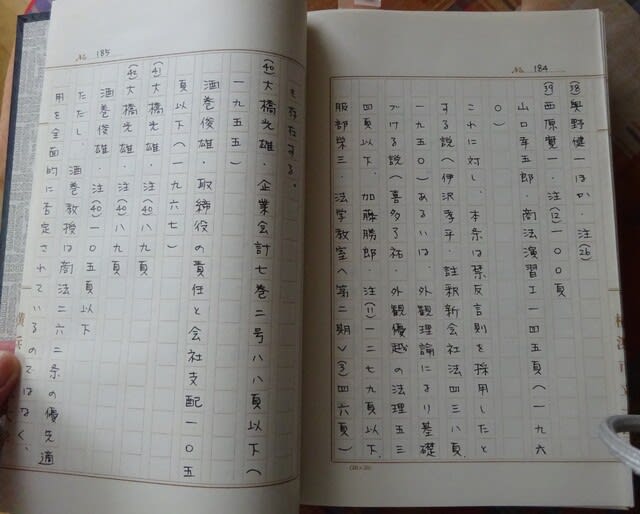かく言うこの私も、「携帯電話」を持ったのは遅い方だっただろう。
最初に「携帯電話」を見たのは電車の中だった。 乗客たちがそれぞれに携帯電話を手にして黙々とメール等々をしている様子だ。
今まで見なかったその光景を目にした時 最初感じたのは、“個々人の疎外性”だった。 いや、皆が皆一人勝手に黙々と携帯電話で用を足すのは自由だが、こうやって今後の世界は現実世界の人々皆が孤立していくんだ… のような感覚を抱かされた。
その携帯電話を次に見たのは、娘(当時小学校低学年)が習っていたバレエ教室にて、子ども達を迎えに来た母親達が同じく携帯を黙々といじる姿だった。
これに関しては、そうしてくれた方が話題の共通項が無さそうな母親達とのコミュニケーションを取らずに済んで、ラクか?? なる我が身勝手な思いが強かった。 と言うのも、何分高齢出産で我が娘を産んだ身にして、他の母親達との年齢差(下手すると私より20歳若い母親もいた)が大きいとの理由もあった。 共通の話題に苦慮するというのか??
そんな私にも携帯電話を“持たせられる”時期がやって来た。
50歳を過ぎて某学習教室の運営・指導者に応募し、採用試験を受けたところ。 10名いた採用志願者の中で私一人のみが筆記試験に合格して採用されたのだが。
担当者曰く、「指導者には強制で携帯電話を持って頂きます!」
当時はそんなものプライベートでは必要無し!と考えていた私だが、やむを得ずそれを購入した。 そうしたところ、どうしたんだ!!?! と言う程に、日々我が担当者から携帯に電話が入るではないか!!!
これじゃあ個人生活が成り立たない!、と留守を決め込んだりもしたのだが…
(どうやら採用時の学科試験で私が最高得点の満点を取ったようで、本部にかなり期待されていたようだ。 結果としては、本部の意向と我が指導者としての意向が嚙み合わず、赤字経営の挙句1年で退社と相成った。)
話題を変えて、2023.06.02付朝日新聞「ひととき」欄より、67歳女性による「どうする家電(いえでん)」と題する投稿の一部を以下に引用しよう。
私は携帯電話を持っていない。スマホはもちろん、ガラケーも手にしたことがない。 あるのは家電、固定電話のみ。 (中略)
ある日温泉に行きたいな、と思い旅行会社へ電話したら、旅の予約はスマホでの相談予約が必要とのこと。 夫に頼み、何とか温泉には行けた。
確定申告の相談もメルアドが必要だし、好きな旅番組のプレゼント応募も「固定電話ではできません」となった。スマホやメルアドがなければ、できないことばかりだ。
そう言えば在職中の終盤、ほぼ全ての連絡や報告はメールだった。 いつも優しい同僚がいて、プリントアウトしてくれた。
迷惑メールに悩む知人も多い。 思い悩みはするが、家電(いえでん)はもうダメなのか。
(以上、朝日新聞記事より一部を引用したもの。)
原左都子の私事及び私見でまとめよう。
確かに我が親ども(実母や義母たち、既に90歳を超えているが)が、スマホは使えないと訴えるのは分かる気がする。 それでも、携帯電話は今尚両人とも下手なりに活用している。
片や朝日新聞投稿者は、私と同年代!
しかも、最近まで有職者だったらしいが。
何故それ程頑なに携帯電話を自ら排除してきたのか、その理由が分かりにくい。
それがために、周囲へも迷惑を掛けて来たようだが。
この投稿文を読むと、投稿者の内面には(そんな自分だが自身の選択は間違っておらず、携帯すら持たない私も世に通用するはずだ)なる甘えた自己肯定感が漂っている辺りが、私にとっては鬱陶しい…
やはり、時代の趨勢には従って生きるべきではなかろうか?
それが叶う能力や金力があるうちは、多少無理をしてでもその関門はクリアするべきであろう。
その努力をすることなく世間の親切に甘えて生きられる程、今の時代甘くはないよ!!