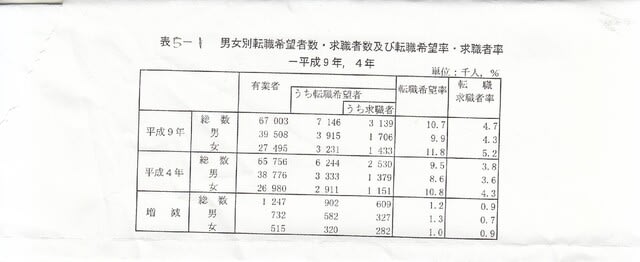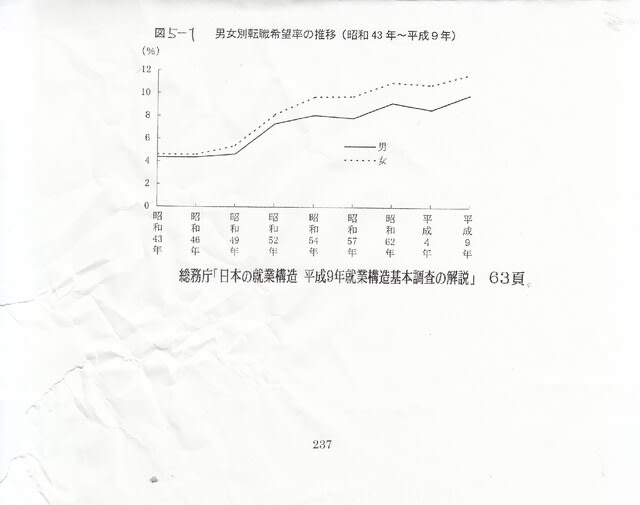マンションを購入するシングル女性は今や珍しくない。住宅金融公庫の調査によると、公庫利用者における単身女性の割合は、95年度の5.1%から02年度は8.2%と増加傾向にあり、民間の低金利に流れて公庫の利用者全体が落ち込んでいる中でも目立つ存在だ。住まいと家族の関連性を見つめ続けてきた作家の藤原智美は、女性の住宅購入と晩婚化の関係をこう説明する。「人生の支えとなる土台を結婚に期待しない代わりに、住宅を所有することで大きな“安心感”を得ている」[1] さらに、最近の動向として高層タワーマンションに人気が集まっている。その対極にある「郊外一軒家」が象徴する「一ヶ所に根を張る」ことの価値が以前より薄れていることの表れと考えられる。[2] 結婚すれば働く女性は家事と労働の二重負担を背負うことになる。これが近年の働く女性の晩婚化や出産の遅延、あるいは非婚といった背景になっていると考えられる。女性にとって永久就職と言われた結婚も、日本型雇用慣行が崩れつつある中で、生涯にわたる生活保証ではなくなってきている。一番安定していたものがリスクを抱えるものとなったのである。女性が経済的に自立可能な職業生活者である場合には、結婚から得られる利益はあまり期待できないのかもしれない、と 藤井治枝は述べている。藤井が『結婚難にみる男の意識と働き方』から引用して述べているところによれば、女性たちのなかには、企業人間の妻になるより一人でいた方がよいと考える者が増えてきていて、男性たちに戸惑いを与えている。「出生率の低下には、さまざまな背景があるが、基本的には企業社会の中に埋没している男たちを相手に家庭を作ることを女たちが拒否し、あるいは子どもを生むことを拒絶することによって、引き起こされている」のだ。[3] 例えば、女性は次のような結婚観をもっている。「私は自分のことは自分でやります。仕事もしたい。社会とのつながりも持ちたい。だから男の人も自分のことは自分でやってほしい。なぜ私が夫の身の回りの世話をしなければいけないの。自立した男と女がパートナーとして共同生活をするのが結婚ではないでしょうか」一方、男性はいまだに結婚はパートナーを選ぶというより、会社や母親のためだという。「企業人間を前提とすれば、家事を一切誰かに任せなければ。それを母親がやっていたが、いつまでも母親にやらせておくわけにはいかない。母親の代わりをやってくれて跡取りをつくるために妻を得たい」[4] が大方のサラリーマンの結婚観だとしたら、働く女性に結婚のメリットはあまりないのである。[5] 家族の位置づけが女性たちの中で変化してきている。
近年は、家族の「個人化」が進んでいる。未婚期間の延長や長寿命化、離死別による単身期間の延長など、一人で暮らす期間が人生に占める割合が大きくなっている。家族の「個人化」は、子供も配偶者ももたないなど、一生のかなりの部分を家族に属さずに生きるようなライフコースが一般化し、その結果、社会の単位が家族から個人へと変化することを意味している。言い換えれば、「個人化」は、家族が女性にとって、生涯その中で暮らしていける場でも運命共同体でもなくなったことを意味する。これまで女性と家族の関係は、生涯安心して頼れる固定的な集団で、女性はその集団の一部だと考えられてきた。女性は自分と家族を一体と思えばこそ、個としての欲求を抑えてでも家族を支える役割に徹することにメリットがあったのである。物質的、精神的両方の意味で家族のものを自分のものと考えることができる、家族からは決して見捨てられないと安心できる、などは、家族と自分が一体と思えばこそ得られるメリットである。固定的集団であればこそ老後も、いえ死後のお墓のことまで安心だった。ところが家族が固定的集団から流動的な一時的関係へと変化しつつある中で、女性にとっての家族の意味もまた大きく変化する。もはや自分を抑えて家族のために生きても、その家族はいつ解消されるかわからない、老後も子供は当てにできない、自分のことを最後まで守ってくれるものではなくなった。自分を抑えて家族のために生きることに、安心感というメリットはなくなったのである。「個」への欲求は女性の高学歴化や社会進出にかかわらず、以前から高かった。家族の「個人化」には、二つの部分の変化が考えられる。一つは、家族を一体ととらえる傾向が弱くなっていることである。家族という集団を、メンバー間に心理的・経済的境界がない一つの単位としてではなく、一人一人が単位である個人の集まりととらえる。家族同士でも、私のものは私のものだし、お互いの気持ちは言葉で伝えなければわからないと考えるのだ。もう一つは、「個人の世界」に求めるものの多様化である。趣味や友人との付き合いであったり、職業上の成果をあげることであったり、あるいはボランティアで中心的役割を担うことであったりと様々なのである。個人化は家族のあり方だけでなく、女性が何を生きがいと感じるかにも関連する。自分と家族の心理的一体感が強かったときには、家族の喜びを自分への間接的評価ととらえ、自分の喜びとすることができた。自分が影で家族を支えていたからこそ夫や子供の成功があるのだ、と思うことができたのである。しかし自分と家族を一体だと思わなくなると、家族の喜びはもちろん嬉しいには違いないけれど、それだけではなく個人としての生きがいや達成感や評価も欲しい、と考えるようになる。心理的側面での「個人化」は、女性の自己主張やわがままが強くなったということではない。家族の一体感が弱まり、女性が人生に求めるものが変化した。その結果、自分を抑えて家族を支える役割に女性は価値を見出せなくなったと考えられる。[6] だが、専業主婦は、基本的生活基盤を夫に依存している。他人に依存していると言う意味では、パラサイト・シングルと同じと言えるのではないだろうか。他人によって経済的安定を得た上での「自分さがし」ということになる。自分を食わせるために市場労働を行う必要はないのである。家事労働をどう評価するかという問題とも絡めて、経済的には自立していない専業主婦の「自分さがし」は、精神的自立に結びつくものなのだろうか。
「経済的自立なくして精神的自立はない、」と 松原惇子は言い切る。松原は日本において女性の自立が程遠い状況を次のように述べている。私のまわりにもキャリア・ウーマンと呼ばれる、外からは立派に自立して見える女性が沢山いる。しかし彼女たちのほとんどはフリーの立場の仕事をしている人ばかりで、男性と同待遇の安定した将来性のある職場で働いている女性は一人もいない。「女の時代」「女の自立」などといってヨイショしている男たち、女性を理解しているようなことを言っているが、彼らは女性の職場進出を望んでいないような気がする。男社会でさえ椅子とり競争が激しいというのに、その上女性に椅子とりゲームに参加されたらたまらない。自分の首が危うくなる。女性は家にいてほしい、と言うのが男性の本音ではないだろうか。こんなことを言うのもなんだが、男性より女性の方が頭はいいのだから。これは学生時代の男女の成績を比べれば明らかである。女性にも社会的訓練の場を男性と同様に与えてくれたら女性の管理職者はかなりの数に上ると思われる。1990年時点での話だが、続いて松原は若い女性たちの保守化傾向について次のように述べている。
最近の若い女性たち(新人類たち)の考え方は保守化している。社会にでて働くより、金持ちの男を見つけて結婚したほうがいい。こういう傾向にあるようだ。彼女たちは大人の社会を覚めた目で見、自分たちなりに計算しているのである。女性は自立からどんどん遠ざかっていく。何も私は自立したくない人にまで自立を勧める気はない。しかし自立を目指す女性にとって今の社会の受け入れ体制は余りにも狭すぎる。先進国でこんなに女性が経済的に自立しにくい国は他にあるだろうか。アメリカのように一度家庭に入ってからも再就職の道がある。資格さえあれば年齢に関係なく働き口がある。そうした社会にならない限り、今の日本で女性が経済力を持つことは困難である。経済的自立なくして精神的自立はない。これは私の持論である。現在の我が国の女性で、本当の意味で自立している人はどのくらいいるのだろうか。私には、自立しているように見えるキャリア・ウーマンも、ちょっと押せばくずれてしまう砂糖菓子のように見えてならない。[7] 日本の男性の際だった労働時間の長さや、社会のあらゆる領域における性別分業の根強さ、いわばジェンダー不平等をもたらす日本の制度、慣習、政策。女性を取り巻く環境は、女性が自立するには果てしなく遠いものである。
女だからとか夫に扶養されればいいのだからといって、自分で働いて生活していくことを否定されたら、女性は自分を扶養してくれる男性をみつけ、彼に従って生きていかなければならない。このような生き方は女性の個人の尊厳に反するものである。ゆえに、国連の女子差別撤廃条約は「全ての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」を男女平等に確保することを定めているのである。これは、わかりやすく言えば経済的自立の権利ということができる。しかし、どんな仕事でも生活できればいいというのではない。全ての人が持っている様々な能力(学力ではなく人間としての広い意味での能力)や適性を生かした職業を選ぶことも権利である。女子差別撤廃条約は「職業を自由に選択する権利」を保障しているが、国際人権規約A規約は労働の権利として「全ての者が自由に選択し又は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利を含む」(6条12項)とその内容をより具体的に表現している)。労働権を個人の権利と捉えると、現在の世帯単位の賃金や福利厚生などの見直しが必要になってくる。さらに、税制や社会保障も世帯単位から個人単位への組み替えが求められる。[8]「地位や名誉のある」職業は男性のものと言う見方は、男性はもちろん、女性の中にも根強い。表向きには女性を差別することは許されないので、それは暗黙のうちに行われる。社会全体が女性の位置は男性より低いものとみているからだ。男女の立場に対する長年の姿勢はそう簡単に消えるものではない。男性たちは、女性の上司を好まず、女性のほうも男性から師事される方が楽だと考えている。だが、権威を行使する仕事へ関心を持つ女性も少しずつ増えている。男性がほとんどいない職場も中にはあるが、それは男性に不適当と思われているだけでなく、一段低い仕事だと考えられているせいだ。男は男の仕事をしなければ、と言う意識のために、女性が多い職種に入ると、男性は「男らしさ」を発揮できないと考えてしまう。このように、男女共社会的心理的圧力があるため、旧来の男女の職域を超えにくく、個人の潜在的能力の発揮が妨げられている。[9] この言いようのない怒りをどこにぶつければいいのだろうか。遙洋子は、性別役割分業社会に対する怒りを次のように記している。
テレビドキュメンタリーで、男女雇用機会均等法の誕生までを放映していた。昭和59年にその法案が通るまでの女たちの格闘が描き出されていた。最も激しい対立は経営者団体と、女性を中心とする労働団体の戦いだった。そこに登場する女性を見た。女の戦いというと連想する、リブやフェミニズムの、私のもつイメージ通りの女性が映っていた。素顔で、男性のような髪型で、ズボンで、コブシを振り上げ、恐いオバサンが「均等法は、罰則規定をもうけなきゃ意味がない」と怒っていた。やっぱり、昔の女性運動って、こんな姿だったんだと遠いものを見るような思いで見た。そして、次の瞬間、私は涙が止まらなくなった。恐いオバサンが叫んだ。彼女の言った言葉・・・。
「でなきゃ、差別はない、とか、なにが差別かわからん、とか、皆が言う」
一瞬、ドキンと胸が痛くなり、私は言葉を失った。昭和59年の話である。恐いオバサンは私だった。彼女の叫びは時代を超えて、私の叫びになっている。金髪でチャラチャラ生きている現代の女が感じる怒りは、素顔でコブシを振り上げていたころの怒りと、一字一句変わらず生き続けていた。話すほどに孤立し、寂莫に溺れそうになる私の痛みを、等身大で理解してくれる人間とは、私が最も敬遠していた、恐いオバサンだった。現在、彼女たちが作ってくれた均等法は、改正を重ねながら今もなお働く女性の応援を続けている。怒りの言葉は変わらないけれど、私は仕事についているし、なんとか自立もできたし、少ないながらに楽しい日々も獲得できた。叫ぶ言葉は同じだけれど、あの時代からはずいぶんと変わったものも多いだろう。そして現代からまた次の時代にむけて同じ言葉を届ける私がいる。その頃にはなにが解消されているのだろう。今、ここに、この社会で、生き残るチャンスを私は皆に届けたい。その秘密の暗号は、ワ・タ・シ・ガ・ム・カ・ツ・ク・コ・トである。[10]
従来の「男女共生システム」の肯定を超えて、女性の多数が社会的な労働の場でも十分な力を発揮したいという胸に秘めた欲求を自然に表現できるようになるには、どのような運動が求められているのだろうか。
「男はいつか管理職」「女は単純補助事務」という性別役割分業にもとづく人事配置は行き詰まり始めている。女性自身が、どう働き、どう身を守るのか主体的に考え、選択していかなければならない。キャリア・ウーマンからイメージする女性像は、高学歴・高収入・総合職・自分の能力を生かしてクリエイティブな仕事をしている人、特定の階層の女性を指すことばであった。平凡な「OL」は、その対極にあるイメージ。企業の女性像としては、「無責任な腰掛女」と「男を踏み台にしたキャリア・ウーマン」という二つの非現実的な類型がまかり通ってきた。しかし、転職することも珍しくなくなった今、キャリアは特定の階層の女性だけのものではなくなってきている。一般事務というと、誰でもできる単純作業なので、これといってできることもなければ資格もない、かといって掃除婦や調理補助といった仕事はプライドが許さないのでやりたくない、といった女性が消極的に他にはやりたくないと望んで就くという場合も往々にしてある。しかし、一般事務だから「個」として生きることができないということはない。職場の家事を担うOLに求められる、専門職にはない様々な心の調整、精神労働の部分にもっと光が当てられてもいいのではないだろうか。
『日経ビジネス』の編集長野村裕知は、『日経ウーマン』の中で読者に対してこうエールを送っている。これまでの社会体系が崩れてきている今は、社会的な変革期。それまで傍流だった人が日の目を見るチャンスなんです。つまり、これまで日本社会で主流だった男性でなく、女性や若者が社会を変える「変革者」になれるということです。[11] 私たち女性が堂々と「おかしい、間違っている」と思うことを主張していく必要がある。現在でも企業はなお、性差別的な労務管理というものを女性のありように関する社会的な「常識」によって正当化しようと執拗に試みている。女性の方もまた、慣行的な規範と闘って職場生活を生き抜くことには、それなりに心の緊張と葛藤を強いられる。「規範と闘う」選択とは、たとえば家事負担の性別不平等が職場のジェンダー差別をもたらす関係を拒むこと、「女らしい仕事」への封じ込めを拒むことなどである。平等な人権というものへの鋭い感性、自立へのつよい志向、そして一定の自信や能力に恵まれなければ難しいほどに、慣行的な規範に従う軌道への誘導力は強力である。性別に基づく労務管理は、女性たちの反発や抵抗によって修正を受けるとはいえ、非常にしばしば、女性たちのなにがしかの主体的な選択がこめられた「ジェンダー化された慣行」によって受容された上で定着しているのである。けれども、その誘導力に身をまかせれば、その程度に応じてジェンダー差別は、差別と意識されなくなり、維持され再生産されるだろう。[12] 自立には経済的自立も含まれると考えれば、OLの「被差別者の自由」の享受は、日本型企業社会の性別役割分業を定着させ、女性の自立を阻むことになっている。今求められているのは、能動的な生き方だ。とはいえ、仕事に働きがいを見出すことができなければ、OLの「被差別者の自由」の享受は続いていくだろう。両親と同居のOLは、いざとなればさっさと会社を辞め、単身の女性は鬱屈を抱いたまま就業を継続させないわけにはいかない。現代社会において、働くことの意味はどこにあるのだろう。
*************
引用文献
[1] 『日経ウーマン2003年9月号』17頁、日経ホーム出版社。
[2] 『日経ウーマン2003年9月号』41頁。
[3] 「結婚難にみる男の意識と働き方」『労働経済旬報』NO.1433、1991年2月上旬号、16頁、労働経済旬報社。
[4] 前掲書、17-18頁。
[5] 藤井治枝『日本型企業社会と女性労働』331-332頁、ミネルヴァ書房、1995年。
[6] 永久ひさ子「専業主婦の焦燥感」藤田達雄・土肥伊都子編『女と男のシャドウ・ワーク』66-68頁、ナカニシヤ出版、2000年。
[7] 松原惇子『いい女は頑張らない』188-189頁、PHP文庫、1992年(原著は1990年刊。
[8] 東京都産業労働局『働く女性と労働法 2003年版』20頁、東京都産業労働局労働部労働環境課。
[9] 熊沢誠『女性労働と企業社会』岩波新書、2000年。
[10] 遙洋子『働く女は敵ばかり』182-183頁、朝日新聞社、2001年。
[11] 『日経ウーマン2002年12月臨時増刊号』122頁。
[12] 熊沢誠『女性労働と企業社会』15-17頁、岩波新書、2000年。