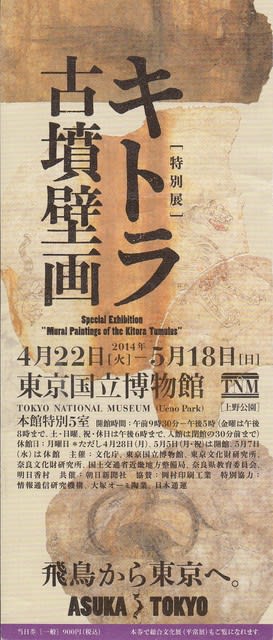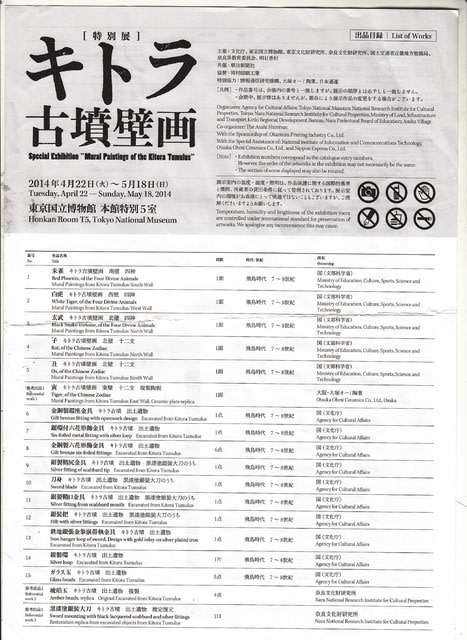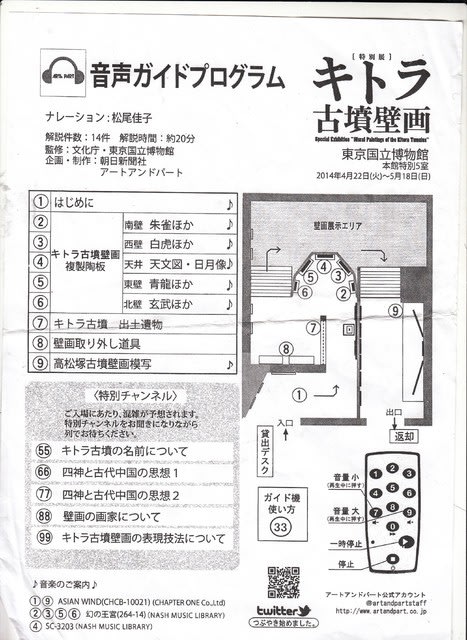会場におかれていた朝日新聞の別刷りより。
「-中国・朝鮮の文化融合-
長さ7・8メートル、高さ1・8メートル。巨大な大きな口から雲気(うんき)をふき出す。
モンゴル草原のオラーン・ヘレム墳墓(7世紀)の地下道で2011年夏に見つかった、東アジア最大級の四神(ししん)壁画「白虎(びゃっこ)」。奈良県明日香村の特別史跡、キトラ古墳(7世紀末~8世紀初め)の白虎は長さ約42センチ、高さ約24センチ。同じ白虎だが大きさや表情、体の模様などかなり違う。
オラーン・ヘレムは、トルコ系騎馬遊牧民、突厥(とっけつ)(552~744)の時代に造られたとみられる。突厥(とっけつ)は630年に唐(618~907)に服属し、以後、唐の間接統治を受ける。被葬者は唐から将軍か地方長官の地位を授けられた突厥(とっけつ)人と想定され、墓制から墓の構造、壁画まで唐様式が採用されたらしい。
オラーン・ヘレムに描かれた白虎と青竜(せいりゅう)が、唐の将軍、蘇定方(そていほう)(592~667)の墓の壁画と似ることに注目するのが、東潮(あずまうしお)・徳島大名誉教授だ。
蘇定方(そていほう)の墓の白虎・青竜は、キトラ壁画とも似ている。東はキトラ壁画について、670年前後の唐で流行した壁画構成や画風、四神の粉本(ふなぽん)(手本)が唐から直接、日本に持ち込まれた可能性が強いと指摘する。
この時代の唐の墓は地下道の入り口付近に青竜と白虎だけを表現し、玄武(げんぶ)や朱雀(すざく)は描かれなくなるが、朝鮮半島の高句麗(こうくり)と百済(くだら)では墓室の壁に四神すべてが表現される。四神すべてが墓室に描かれたキトラの図像の元は唐の粉本だったとみて、朝鮮からの基層文化に中国の影響が加わった可能性が高いとみる。
7世紀後半、日本を取り巻く国際情勢は激動していた。友好国の百済が660年に唐・新羅連合軍に滅ぼされ、その3年後、救援に向かった倭(わ)(日本)が白村江(はくそんこん)の戦いで連合軍に大敗。日中関係は極度に緊張し、遣唐使は669年を最後に702年の再開まで途絶えた。この間、新羅との関係が活発化した。
中国古代の方角の守り神「四神」を墓に描く文化は、遊牧民にも東の辺境の倭にも伝わったが、受け止め方は超大国・中国との「距離感」で異なった。東は言う。「中国と朝鮮の文化がミックスされたキトラの壁画こそ、飛鳥時代の独特な日本文化誕生の表れと言える」