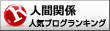礼拝宣教 ヨハネ黙示録20章1-15節
ヨハネの黙示録の「黙示」という意味については、何度かお話しましたように「覆われて見えないものが、覆いを取り除かれて見えるようになった」ということです。
それはいわば神の人類に対するご計画があらわにされた、ということでもあります。
ところが、この20章「千年間の支配」いわゆる「千年王国」についての記述は、見えるどころか読めば読むほどわかり辛いですよね。それが何時なのか?具体的にどんな形で実現されるのか?様々な説があるところですが。いずれにしても私たちは今日のヨハネの黙示録20章より、このところからでなければ受け取ることのできないメッセージをご一緒に聞きとっていきたいと願っております。
1節以降でヨハネは、「一人の天使が、底なしの淵の鍵と大きな鎖とを手にして、天から降って来るのを見た。この天使は、悪魔でもサタンでもある、年を経たあの蛇、つまり竜を取り押さえ、千年の間縛っておき、底なしの淵に投げ入れ、鍵をかけ、その上に封印を施して、千年が終わるまで、それ以上、諸国の民を惑わさないようにした」と記しています。
天使の持っている鍵と鎖は、主イエスの主権を表わします。悪魔、サタン、蛇、竜を取り押さえ、縛りあげたことは、主イエスが十字架と復活によってサタンが既に行動を制御されて敗北したことを示しています。
確かにこのヨハネの時代における初代教会の現実は未だローマ帝国による激しい迫害や弾圧が繰り返されており、完全な形での救いはとてもじゃありませんが見出せないような混沌とした情勢でありました。それにも拘わらず、ヨハネはここで千年の間の完全なキリストの統治を幻に見るのです。
旧約聖書のイザヤからエゼキエル、さらに後の時代にもユダヤの民は衰退と迫害にさらされる中で、いつかメシアが出現して民族と王国の復興を成し遂げて下さると考えてきました。ユダヤ教では国の再建と統治はメシアとその再臨に不可欠なことなのです。
その一方で、キリスト者に示されるメシア像とその統治はユダヤ教のものとかなり異なっています。
4節以降にはこのようにあります。「わたしはまた、多くの座を見た。その上には座っている者たちがおり、彼らには裁くことが許されていた。わたしはまた、イエスの証しと神の言葉のために、首をはねられた者たちの魂を見た。この者たちは、あの獣もその像も拝まず、額や手に獣の刻印を受けなかった。彼らは生き返って、キリストと共に千年の間統治した。その他の死者は、千年経つまで生き返らなかった。これが第一の復活である。第一の復活にあずかる者は、幸いな者、聖なる者である。この者たちに対して、第二の死は何の力もない。彼らは神とキリストの祭司となって、千年の間をキリストと共に統治する。」
ここには、迫害と弾圧の中でキリストへの信仰を貫き通したが故に惨殺された多くの信徒たちの魂が生き返って、キリストと共に千年の間統治している様が記されています。
まあ私たちがここを読む時、自分はこの殉教者たちの中には入らなかったら千年生き返らないのだろうか、といろいろ考えてしまうかも知れません。しかし大切なのは、殉教という行為そのものというより、その根底にあるところの、主イエスの救いに対する誠実さだと思うのです。それは何も殉教者だけでなく、神ならぬものを神として拝ませようとする様々の世の勢力に抗いつつ生き抜く信徒たちに対しても又、、主イエスと共にあり、命を得ていると、そのような励ましと希望とがここで語られているように思うのであります。
そしてそれらの者たちには、第二の死は何の力(効力)もないとあります。第二の死とは、13節14節にあるように、完全な滅びです。そんな魂の滅びに至ることはない。否、逆に、世にあって神を神とせず、偶像を拝み、主の御救いを拒んで罪を犯し続ける者には、最後の審判の座において、すべての行いが明るみに出され、それらの行いに応じて厳粛な裁きが下される。第二の死、魂の滅びを免れ得ないということであります。まさに襟を正される思いがいたしますが。
さて、7節以降において、千年の間縛られ、底なしの淵に投げ入れられて牢に封印されていたサタンがその牢から解放されると、地上の四方にいる諸国の民、ゴグとマゴグ(神に敵対する諸国)を惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わせようとする。その数は海の砂のように多い。彼らは地上の広い場所に攻め上って行って、聖なる者たちの陣営と、愛された都を囲んだと」と記されています。
ここを読んで分かりますのは、サタンは自力でその牢の鍵をこじあけて出て来たのではなく、主のゆるしのもとそこから解放されたものに過ぎないということです。
千年の間牢に閉じ込められていたサタンがどうしてまた再びそこから解放されることになったのでしょう。迫害の嵐の後の千年間の統治なのに、なぜまた、と考え込んでしまいました。
そして、そのことを考えている時、思い出しましたのは、主イエスが荒れ野でサタンの試みに遭われるという場面であります。共観福音書には共通してこのエピソードが記載されていますが。
その試みは、サタン主導でイエスさまを荒れ野に導いたのではなく、神の霊、聖霊がイエスさまを荒れ野に導いてサタンの誘惑に遭われたということが伝えられています。
それはつまり、神の御言葉、命の言葉を基として生きるか。「人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つひとつの言葉によっていきるかどうか」をお試しになられたということです。イエスさまはサタンの実に巧妙な誘惑をすべて退けて、勝利されたのですね。
そのようにこの7節以降の解放されたサタンの勢力が、再び聖なる者たちの陣営と主に愛された都とを取り囲むのですけれども。しかしそれは実に主なる神さまのご支配のもとにあってなされている。それが前提としてあるということです。
私たちは祝福と主の御業を目の当たりにして感謝と賛美でいっぱいの時もあれば、祈っているのに、礼拝を守っているのになぜ?どうしてこんなことが起こるのか、ということがあるでしょう。人生には時にまるで苦難に逃げ場もなく、囲まれているかのように思える時があるものです。
しかし、主なる神さまが私たちをご自分のものとして愛しておられるがゆえに、そのよな事態を敢えておゆるしになる、ということがあるのです。そしてそれはまた、主の愛してやまない教会とその信徒たちが、神ならざるものを神としていくような、あらゆる世のサタン的勢力に取り囲まれても、イエスさまが荒れ野で自ら示されたように、神の御言葉、命の言葉を固く守り、生きてゆくところに本当の勝利、最終的勝利が約束されているということです。
この牢から解放されて出てきたサタンの勢力が拡散していく状況を想像しますとき、それはまさに今日の時代において世界の各地で、また国内において起こっている悲惨な紛争、テロ、凶悪な犯罪、又科学技術や経済主義を神のように讃え、それに依存し神格化ている文明の罪を見るようです。まさに終末は近くに来ているという感がありますが。しかしそのように、人を滅びへと向かわせて来た勢力は、9節後半から10節に記されていますように、「天から火が降って来て、彼ら(サタンの勢力)を焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は、火と硫黄の池に投げ込まれた。そこにはあの獣と偽預言者がいる。そして、この者どもは昼も夜も世々限りなく責めさいなまれる。」
そのような終末が待っているのです。
神から人間を引き離し、罪を犯させていく働きはおびただしいのでありますが。しかしそれは終りのときが来ますと、、主が天から再び来臨なさるそのときがきますと、世に拡散し攻撃をしかけていたサタンの勢力はあっという間に敗れはてるのです。主のご支配のもとにすべてがあるということを、私たちはここから知らなければなりません。
さて、聖書はそのことを経たうえで、11節以降の「最後の裁き」の記述へと移ります。
ヨハネが見た「大きな白い玉座と、そこに座っておられる方」とは再臨の主イエス・キリストを示しています。再臨の主イエスさまによって最後の裁きがなされるのです。
ヨハネはその玉座の前において、死者たちが、大きな者も小さな者も立っていているのを見ます。そこでは幾つかの書物が開かれるのですが、そこで開かれたもう一つの書は「命の書」であり、「死者たちは、これらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれた」というのです。
これが再臨の主イエスによる「最後の審き」であります。すべての死者は例外なくこの最後の裁きを主の玉座の前で受けるというのです。主を信じて地上の生涯を全うした者も、そうでない者も、すべてが主の玉座の前に裁きを受けます。
ここで重要なことは、その裁きが「『命の書』に記録された彼らの行いに応じて裁かれる」ということです。命の書については、旧約の時代の民に向けても語られてきたものです。主の義に生きる人は命の書に名を連ねることが許されていたのです。旧約時代の義人はその義の行いによって主の裁きを受けるということでありますが。一方、新約の主イエスの御救いに与る者は、主イエスの義を身にまとうことによって、命の書にその名が記されるのです。そうして霊による新生にあずかり、主イエスに従って生きた信仰者もまた「命の書」に基づき、その行いに応じて裁かれるのですね。
しかしその行いとは何でしょうか?クリスチャンは自分の正しさや義によっては救い難い者でありますから、主イエス・キリストの義の救いに与かっる外ない存在なのです。ですから、私たちは逆に自分たちには自分を救い得るような力も愛もないという事を日々日常において思い知らされる事の方が多いのではないでしょうか。
そのようにして、自分の正しい行いによっては主の裁きの御座にでることはできないことを知っているクリスチャン、私たちでありますが。しかしだからこそ、救いの主イエスを信頼し、望みをもって従って生きていくとき、感謝のうちに証しとなる生涯とされていくのではないでしょうか。
ルカの福音書7章36節以降に、罪深い女がイエスさまの足を涙でぬらし自分の髪で拭い接吻して香油を塗ったエピソードが記録されています。イエスさまは、「この人が多くの罪を赦されたことは、わたしに示した愛の大きさで分かる」と言われました。又、「はっきり言っておく、世界中どこでも福音が宣べ伝えられる所では、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう」とおっしゃいました。
私たちそれぞれの「命の書」の記録も又、唯主の恵みによる以外ありません。その主の恵みのもとで、私たち一人ひとりがどう行動し生きていくか、その事が問われるということですね。信仰の恵みに応えて行動し、生きるその原動力は、救いの喜びをもって、主を主として生き抜く信仰です。賜物は各々に与えられており、身体が不自由になっても「祈るり」「とりなす」事はできます。それらは主の御前に意義ある尊い働き、行動です。大切なのは「何をなしたか」ではなく、「主の恵みにどう応えて生きるか」です。
今日の聖書の箇所は、私たちに終末の備えをするように促します。その日その時は誰にも分かりません。だからこそ目を覚まして祈り続け、与えられた時を生かしていきましょう。主の義を身にまとって日々生きる者には、来るべき日の希望があるということを心に留めて、主と共に命の道を歩んでまいりましょう。
「天地は滅びるが、わたしの言葉は決して滅びない。」マルコ13章31節
ヨハネの黙示録の「黙示」という意味については、何度かお話しましたように「覆われて見えないものが、覆いを取り除かれて見えるようになった」ということです。
それはいわば神の人類に対するご計画があらわにされた、ということでもあります。
ところが、この20章「千年間の支配」いわゆる「千年王国」についての記述は、見えるどころか読めば読むほどわかり辛いですよね。それが何時なのか?具体的にどんな形で実現されるのか?様々な説があるところですが。いずれにしても私たちは今日のヨハネの黙示録20章より、このところからでなければ受け取ることのできないメッセージをご一緒に聞きとっていきたいと願っております。
1節以降でヨハネは、「一人の天使が、底なしの淵の鍵と大きな鎖とを手にして、天から降って来るのを見た。この天使は、悪魔でもサタンでもある、年を経たあの蛇、つまり竜を取り押さえ、千年の間縛っておき、底なしの淵に投げ入れ、鍵をかけ、その上に封印を施して、千年が終わるまで、それ以上、諸国の民を惑わさないようにした」と記しています。
天使の持っている鍵と鎖は、主イエスの主権を表わします。悪魔、サタン、蛇、竜を取り押さえ、縛りあげたことは、主イエスが十字架と復活によってサタンが既に行動を制御されて敗北したことを示しています。
確かにこのヨハネの時代における初代教会の現実は未だローマ帝国による激しい迫害や弾圧が繰り返されており、完全な形での救いはとてもじゃありませんが見出せないような混沌とした情勢でありました。それにも拘わらず、ヨハネはここで千年の間の完全なキリストの統治を幻に見るのです。
旧約聖書のイザヤからエゼキエル、さらに後の時代にもユダヤの民は衰退と迫害にさらされる中で、いつかメシアが出現して民族と王国の復興を成し遂げて下さると考えてきました。ユダヤ教では国の再建と統治はメシアとその再臨に不可欠なことなのです。
その一方で、キリスト者に示されるメシア像とその統治はユダヤ教のものとかなり異なっています。
4節以降にはこのようにあります。「わたしはまた、多くの座を見た。その上には座っている者たちがおり、彼らには裁くことが許されていた。わたしはまた、イエスの証しと神の言葉のために、首をはねられた者たちの魂を見た。この者たちは、あの獣もその像も拝まず、額や手に獣の刻印を受けなかった。彼らは生き返って、キリストと共に千年の間統治した。その他の死者は、千年経つまで生き返らなかった。これが第一の復活である。第一の復活にあずかる者は、幸いな者、聖なる者である。この者たちに対して、第二の死は何の力もない。彼らは神とキリストの祭司となって、千年の間をキリストと共に統治する。」
ここには、迫害と弾圧の中でキリストへの信仰を貫き通したが故に惨殺された多くの信徒たちの魂が生き返って、キリストと共に千年の間統治している様が記されています。
まあ私たちがここを読む時、自分はこの殉教者たちの中には入らなかったら千年生き返らないのだろうか、といろいろ考えてしまうかも知れません。しかし大切なのは、殉教という行為そのものというより、その根底にあるところの、主イエスの救いに対する誠実さだと思うのです。それは何も殉教者だけでなく、神ならぬものを神として拝ませようとする様々の世の勢力に抗いつつ生き抜く信徒たちに対しても又、、主イエスと共にあり、命を得ていると、そのような励ましと希望とがここで語られているように思うのであります。
そしてそれらの者たちには、第二の死は何の力(効力)もないとあります。第二の死とは、13節14節にあるように、完全な滅びです。そんな魂の滅びに至ることはない。否、逆に、世にあって神を神とせず、偶像を拝み、主の御救いを拒んで罪を犯し続ける者には、最後の審判の座において、すべての行いが明るみに出され、それらの行いに応じて厳粛な裁きが下される。第二の死、魂の滅びを免れ得ないということであります。まさに襟を正される思いがいたしますが。
さて、7節以降において、千年の間縛られ、底なしの淵に投げ入れられて牢に封印されていたサタンがその牢から解放されると、地上の四方にいる諸国の民、ゴグとマゴグ(神に敵対する諸国)を惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わせようとする。その数は海の砂のように多い。彼らは地上の広い場所に攻め上って行って、聖なる者たちの陣営と、愛された都を囲んだと」と記されています。
ここを読んで分かりますのは、サタンは自力でその牢の鍵をこじあけて出て来たのではなく、主のゆるしのもとそこから解放されたものに過ぎないということです。
千年の間牢に閉じ込められていたサタンがどうしてまた再びそこから解放されることになったのでしょう。迫害の嵐の後の千年間の統治なのに、なぜまた、と考え込んでしまいました。
そして、そのことを考えている時、思い出しましたのは、主イエスが荒れ野でサタンの試みに遭われるという場面であります。共観福音書には共通してこのエピソードが記載されていますが。
その試みは、サタン主導でイエスさまを荒れ野に導いたのではなく、神の霊、聖霊がイエスさまを荒れ野に導いてサタンの誘惑に遭われたということが伝えられています。
それはつまり、神の御言葉、命の言葉を基として生きるか。「人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つひとつの言葉によっていきるかどうか」をお試しになられたということです。イエスさまはサタンの実に巧妙な誘惑をすべて退けて、勝利されたのですね。
そのようにこの7節以降の解放されたサタンの勢力が、再び聖なる者たちの陣営と主に愛された都とを取り囲むのですけれども。しかしそれは実に主なる神さまのご支配のもとにあってなされている。それが前提としてあるということです。
私たちは祝福と主の御業を目の当たりにして感謝と賛美でいっぱいの時もあれば、祈っているのに、礼拝を守っているのになぜ?どうしてこんなことが起こるのか、ということがあるでしょう。人生には時にまるで苦難に逃げ場もなく、囲まれているかのように思える時があるものです。
しかし、主なる神さまが私たちをご自分のものとして愛しておられるがゆえに、そのよな事態を敢えておゆるしになる、ということがあるのです。そしてそれはまた、主の愛してやまない教会とその信徒たちが、神ならざるものを神としていくような、あらゆる世のサタン的勢力に取り囲まれても、イエスさまが荒れ野で自ら示されたように、神の御言葉、命の言葉を固く守り、生きてゆくところに本当の勝利、最終的勝利が約束されているということです。
この牢から解放されて出てきたサタンの勢力が拡散していく状況を想像しますとき、それはまさに今日の時代において世界の各地で、また国内において起こっている悲惨な紛争、テロ、凶悪な犯罪、又科学技術や経済主義を神のように讃え、それに依存し神格化ている文明の罪を見るようです。まさに終末は近くに来ているという感がありますが。しかしそのように、人を滅びへと向かわせて来た勢力は、9節後半から10節に記されていますように、「天から火が降って来て、彼ら(サタンの勢力)を焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は、火と硫黄の池に投げ込まれた。そこにはあの獣と偽預言者がいる。そして、この者どもは昼も夜も世々限りなく責めさいなまれる。」
そのような終末が待っているのです。
神から人間を引き離し、罪を犯させていく働きはおびただしいのでありますが。しかしそれは終りのときが来ますと、、主が天から再び来臨なさるそのときがきますと、世に拡散し攻撃をしかけていたサタンの勢力はあっという間に敗れはてるのです。主のご支配のもとにすべてがあるということを、私たちはここから知らなければなりません。
さて、聖書はそのことを経たうえで、11節以降の「最後の裁き」の記述へと移ります。
ヨハネが見た「大きな白い玉座と、そこに座っておられる方」とは再臨の主イエス・キリストを示しています。再臨の主イエスさまによって最後の裁きがなされるのです。
ヨハネはその玉座の前において、死者たちが、大きな者も小さな者も立っていているのを見ます。そこでは幾つかの書物が開かれるのですが、そこで開かれたもう一つの書は「命の書」であり、「死者たちは、これらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれた」というのです。
これが再臨の主イエスによる「最後の審き」であります。すべての死者は例外なくこの最後の裁きを主の玉座の前で受けるというのです。主を信じて地上の生涯を全うした者も、そうでない者も、すべてが主の玉座の前に裁きを受けます。
ここで重要なことは、その裁きが「『命の書』に記録された彼らの行いに応じて裁かれる」ということです。命の書については、旧約の時代の民に向けても語られてきたものです。主の義に生きる人は命の書に名を連ねることが許されていたのです。旧約時代の義人はその義の行いによって主の裁きを受けるということでありますが。一方、新約の主イエスの御救いに与る者は、主イエスの義を身にまとうことによって、命の書にその名が記されるのです。そうして霊による新生にあずかり、主イエスに従って生きた信仰者もまた「命の書」に基づき、その行いに応じて裁かれるのですね。
しかしその行いとは何でしょうか?クリスチャンは自分の正しさや義によっては救い難い者でありますから、主イエス・キリストの義の救いに与かっる外ない存在なのです。ですから、私たちは逆に自分たちには自分を救い得るような力も愛もないという事を日々日常において思い知らされる事の方が多いのではないでしょうか。
そのようにして、自分の正しい行いによっては主の裁きの御座にでることはできないことを知っているクリスチャン、私たちでありますが。しかしだからこそ、救いの主イエスを信頼し、望みをもって従って生きていくとき、感謝のうちに証しとなる生涯とされていくのではないでしょうか。
ルカの福音書7章36節以降に、罪深い女がイエスさまの足を涙でぬらし自分の髪で拭い接吻して香油を塗ったエピソードが記録されています。イエスさまは、「この人が多くの罪を赦されたことは、わたしに示した愛の大きさで分かる」と言われました。又、「はっきり言っておく、世界中どこでも福音が宣べ伝えられる所では、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう」とおっしゃいました。
私たちそれぞれの「命の書」の記録も又、唯主の恵みによる以外ありません。その主の恵みのもとで、私たち一人ひとりがどう行動し生きていくか、その事が問われるということですね。信仰の恵みに応えて行動し、生きるその原動力は、救いの喜びをもって、主を主として生き抜く信仰です。賜物は各々に与えられており、身体が不自由になっても「祈るり」「とりなす」事はできます。それらは主の御前に意義ある尊い働き、行動です。大切なのは「何をなしたか」ではなく、「主の恵みにどう応えて生きるか」です。
今日の聖書の箇所は、私たちに終末の備えをするように促します。その日その時は誰にも分かりません。だからこそ目を覚まして祈り続け、与えられた時を生かしていきましょう。主の義を身にまとって日々生きる者には、来るべき日の希望があるということを心に留めて、主と共に命の道を歩んでまいりましょう。
「天地は滅びるが、わたしの言葉は決して滅びない。」マルコ13章31節