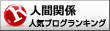礼拝宣教 Ⅰコリント1章15-31節
今日から3ヶ月の予定で、コリント信徒への手紙を読んでいきます。本日は1章18-31節より、「十字架の言葉」と題し、み言葉を聞いていきたいと思います。
はじめに少し当時のコリントの教会とその背景について申しますと。コリントは紀元前の古い時代から優れた文化をもっていた都市でした。その後ローマ帝国がギリシャを征服しようとしたとき、コリントがローマに抵抗したため、紀元前146年に滅ぼされ、後にユリウス・カエサルによって再建され、新約聖書の時代には、その南部の海沿いの地形に面したことで諸外国からの船も出入りし、様々な民族が行き交う都市として、工業、文化、商業等の交易が栄え、宗教的にも、多様に繁栄していて、その当時約60万人の人口があったということです。
しかしその繁栄は、一方で道徳的退廃につながっていき、ギリシャ神話の偶像の神殿には1000人の神殿娼婦が常駐し、賭博等も盛んであったようです。
そのようなコリントの地に使徒パウロが足を運んだのが第二伝道旅行の途中でした。使徒言行録18章によれば、小アジアのマケドニアからギリシャのアテネを通って、そのコリントで1年半滞在したようです。
そこでパウロは、同じ天幕造りで生計を営んでいたアキラとプリスキラ夫妻の家に住み込み、一緒に仕事をしながら、福音伝道に励むのですが、なかなかその成果があがらなかったようです。
けれども、そういう行き詰まったような中で、今日の14節に出てきます、ユダヤ会堂長のクリスポなどの有力者、資産家が救われ働きに加わって、コリントでの福音伝道は大きな実を結んでいくことになるのです。
しかしその後、パウロがコリントを離れますと、徐々にコリントの信徒たちの間で、様々な問題が生じてまいります。この第一の手紙は、クロエという女性の家で信仰の生活を共にしていた人たちが、そういった問題についてパウロに手紙を書き送るのです。それに対するパウロの返信ということであります。前置きはこれくらいにいたしまして。
本日の箇所は、前の10~17節をご覧になると分かりますように、コリントの教会の中に生じていた「分派争い」についてであります。
パウロはまず、「皆、勝手なことを言わず、仲たがいせず、心を一つにして、固く結びあいなさい」と勧告します。
コリントの信徒たちの間で、私はパウロ派、自分はアポロにつく、いやペトロだなど、指導者とその教えを偏って見たり、遂には党派心から分裂までもが生じていきました。
まあ、コリントの教会には様々な国籍や当時の社会背景の中で立場の違いなどもありましたから、そういった意味で、パウロは異邦人の信徒らに、アポロは知識人の信徒らに、ペトロはユダヤ人の信徒らに人気があったと考えることもできるでしょう。
問題は、コリントの信徒たちの心が、キリストの福音と教えとに未だ一致を見ず、その思いが割れていたということです。
人が増え次第に制度や組織化されていきますと、派閥や主導権争いが起っていくのは、これはもう人間の性ともうしますか。ただそれが救いの場であるはずの教会でとなりますと、それは非常に残念なことです。けれど、だからといって「教会も人間の組織に過ぎない。わずらわしい。教会など行かなくてもよい」となると、それも独り善がりの、信仰生活も薄っぺらなものになりかねません。
パウロはこの手紙の12章において、キリストを信じる群、教会を「キリストのからだ」として示し、その本来のゆたかさについて述べていますが。それは、キリストによって救われ、神の民とされた兄弟姉妹とともに祈り合い、支え合い、励まし合う教会のかたちであります。
自己完結の信仰に陥らないため必要なこと。それは信仰の友、兄弟姉妹との出会いです。教会にはいろんな立場の方、モノの見方や考え方、人生経験を持つ方が様々おられます。それがある意味大事なことなのです。なぜなら、自分と考えや見方の異なる兄弟姉妹との出会いや対話を通してこそ、主にある気づきや発見が与えられ、互いが配慮し合うことを学び、心を通わすことにもなるからです。
又、救いの証し、主の恵みのゆたかさ、奥深さを知ることが出来るからです。主イエスがお教えになった互いに足を洗い合い、ゆるし、ゆるされ、祈り、互いを大切にしていく。そういった信仰の地盤を築いていく場は、やはり教会のつながりにおいてでしょう。教会は単なる建物ではありません。生ける主とその救いを信じる一人ひとりの集まりです。
私たち一人ひとりは同じではなく、それぞれ違いをもち、個性や特徴をもっているものであります。それが主によって神の共同体とされていること自体が奇跡であり、主はそのつながりを通して、福音をさらに分かち合い、証しするという働きを教会に託しておられるのです。そういう意味では「全国のバプテスト連盟諸教会」「関西のバプテストの地方連合諸教会」という連帯と協力関係も感謝なことであります。
そういうことですから、一人ひとりみな違う者であっても、主にあってつながり、心を一つにし、思いを一つにして、人の力でなく、主にあって固く結び合っていくことが大切なのですね。
さて、パウロは17節で「キリストがわたしを遣わされたのは、バプテスマを授けるためではなく、福音を告げ知らせるためであり、しかも、キリストの十字架がむなしいものになってしまわぬように、言葉の知恵によらないで、告げ知らせるためだ」と述べます。
それは、自身の救いの体験からなる伝道の働きです。一方、アポロという人物は大変雄弁家であったようですが。どちらにせよ、主の救いの御業よりも人が権威ある者のように注目され、生きておられる主、主イエスの十字架の救いがかすんで見えなくなってしまうような事態がコリントの教会に生じていたといえるのでしょう。パウロはそのことを恐れながら、このように警告したのではないでしょうか。
18節以降で、パウロは、人の言葉の知恵によらず、「神の力、神の知恵」であるキリストの十字架の救いについて述べます。
「十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、わたしたち救われる者には神の力です。」
現代では十字架は、信仰とは関係ないところでも飾り物になっていたりしますが。
元はといえば、とてもそんなものではありません。それはローマ帝国が奴隷の反乱を防ぐために長時間十字架に架け、苦しみながら衰弱死するのを見せしめにする、そんな残酷な刑具であったのです。
ですから、ユダヤ人はもとより、それを知る者にとっては、十字架刑による無残な死を遂げた者が神の子だというのは到底ありえないことであり、その事をして「神の救い」とするなど実に愚かとしか思われないことでした。
律法や行いによる救いを守ってきたユダヤ人にとっては、旧約聖書の「木に架けられた者は呪われる」という言葉そのもののイエスの十字架の死は、躓き以外の何ものでもありませんでした。
しかし、そのイエスの十字架の死は、私たちの罪とその代償としての呪いをその身に負われた、神の救いの御業であるのです。
パウロは「十字架の言葉は・・・・わたしたち救われる者には神の力です」と言うのですね。まさに2000年を経た私共も、その十字架の事実に救われているわけでありますが。
まあ、使徒パウロは何かアポロのように雄弁に色々なことを語るわけでなく、ひたすらこの「十字架につけられたキリスト」の救いについてとつとつと語り続けておられたのではないか、と想像いたします。
そのパウロは21節で「そこで神は、宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうと、お考えになったのです」と言うのです。
普通それを「愚かな手段」などとは言わないと思うのですが。それは、この十字架そのものが、知恵を探す異邦人には愚か、しるしを求めるユダヤ人にはつまずき以外の何ものでもなかったからです。
それにしても彼はどうしてそこまで「十字架のイエス」の宣教にこだわったのでしょうか。
パウロ自身キリストと出会う前はユダヤ人のエリートとしての人生をひたすら走り抜いていました。彼は宗教的にも学問的にもエリートであり、又熱心さもありました。そして選民としての自意識とともに、神に従っているという誇りと自負を強く持っていたのです。
しかしその自分の知恵や能力、誇りというものが、キリスト教徒とその信徒を目の敵のようにして排除し、激しい迫害行為へ至らせたのです。そういう中彼はダマスコの途上で、あの神の子、復活の主イエスの「サウロ、サウロ、なぜ、わたしを迫害するのか。わたしはあなたが迫害している主である」というみ声を聞くのですね。
それは、パウロが神のため、神のためにと、その熱心さと強い誇りと使命感によってキリスト教徒たちを激しく迫害してきたことが、実は彼の信じ従っていた主、神の子を迫害していたのだということを知る事になるのですね。これがパウロの回心です。
この出来事を通してパウロは、この自分こそが神の子イエス・キリストを十字架につけ、殺害したのだと自らの罪をほんとうに思い知らされるのですね。こうして彼も自分の深く重たい罪の身に代わって、十字架で贖いの業を遂げられたイエス・キリストを救い主と信じてキリスト者となり、異邦世界に福音を告げ広めていくというまさに神の証人として、貴い働きをなしていくことになるのですが。
実にこのパウロの罪と救いの経験が、彼の信仰のベースになっているのです。
ですから彼がコリントの信徒たちに「十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、わたしたち救われる者には神の力です」と言った言葉は、自らの体験による証言であるのです。
本日の聖書の「分派争い」の問題について、パウロは自らの体験から、人の誇りや自負、又それが高じて人を裁き、見下すことの愚かさを語ります。
21節「世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は、宣教(これは十字架のメッセージということでありますが)そういう愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。」
神さまはそのように人の目に愚かとしか見えないような手段によって信じる者をお救いになられるお方なのです。
どんな立派な話、ためになる話が聞けるかと思って教会に来てみたら、十字架にかけられた人を救い主と信じ、毎回そんな話ばっかりしている。それは世には愚かに見えるでしょう。けれどまさにそこに、神のみ恵みと救いの業が示されているのですね。
23節でパウロは、「わたしたちは、十字架につけられたキリストを宣べ伝えています」と言っていますが。
ここは、何度か礼拝でもお話しましたが。正確に原語に則して訳せば、「わたしたちは、十字架につけられ給いしままなるキリストを宣べ伝えています」となります。
すなわち、キリストは十字架につけられたという単なる過去の出来事ではなく、今も十字架につけられ給いしままなるお方として、私たち人間の弱さと罪をあがない執り成し続けていて下さる。共におられる神の救いなのです。
今日は26節以降も読まれましたが。
ここで私が改めて気づかされましたのは、神の御救いのご計画が、旧約聖書の時代も新約聖書の今も全く同様であるという発見です。
主がイスラエルの民を神の宝の民として選ばれたのは、申命記7章にあるように「イスラエルの民が他のどの民より数が多かったからではなく、他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに彼らは選ばれた」というわけですね。
イスラエルの民が立派だとか優れていたとかではなく、ただ主の深い御憐み以外の何ものでもないと主は言われるのです。
そして今日のここでも、その救いに到底与ることができないような罪深い私たちを、神は十字架のあがないの業によって救い出し給うのです。もはや、どのような知識人も権力者も血筋の者も、そのことによって救われ得ないし、誇ることはできません。ユダヤ人も、私たち主の御救いに与っている者も、誰一神の前で誇ることはできません。パウロがここで「誇る者は、主を誇れ」と言っているとおりです。
エレミヤ9章22-23節にはこう記されています。
「主はこう言われる。知恵ある者は、その知恵を誇るな。力ある者は、その力を誇るな。富ある者は、その富を誇るな。むしろ誇る者は、この事を誇るがよい。目覚めてわたしを知ることを。わたしこそ主」。ハレルヤ。
キリストのからだなる教会は、世の知恵、能力や才能を基準にするのではなく、「十字架の言葉」、神の知恵をもって呼び集められた群れであるということを、私たちはもう一度確認しつつ、今日もここから遣わされてまいりましょう。