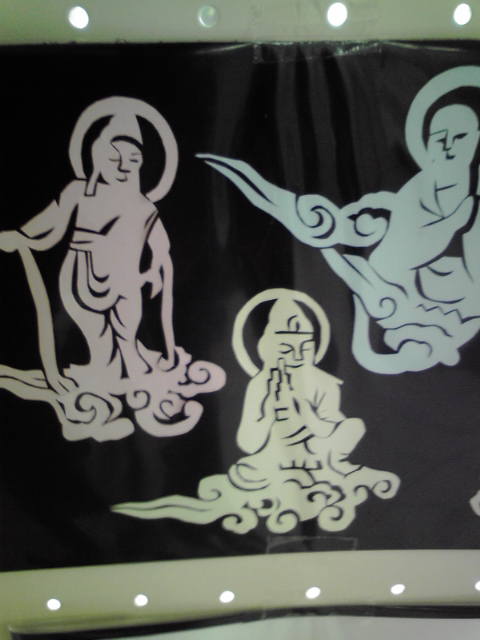あなたのブログも広告非表示に!gooブログフォトは初月無料でお試しできます。
@@@@@
このブログの冒頭のメッセージ
自分で勝手に広告を載せておいて、
こんどは、それを載せないようにしてやるからお金払えですって!
それはないでしょう 笑い
広告大歓迎!! 嘘 いや本当
どっちでもいい
ともかく、もう5年以上続いているこのブログ
毎月200円払っている
突然、サービス終了しますなんてことにならないように
してくださいね
たった200円でのこのサービス
真から感謝してますから
真から生きがいになってますから

@@@@@
このブログの冒頭のメッセージ
自分で勝手に広告を載せておいて、
こんどは、それを載せないようにしてやるからお金払えですって!
それはないでしょう 笑い
広告大歓迎!! 嘘 いや本当
どっちでもいい
ともかく、もう5年以上続いているこのブログ
毎月200円払っている
突然、サービス終了しますなんてことにならないように
してくださいね
たった200円でのこのサービス
真から感謝してますから
真から生きがいになってますから