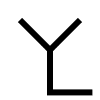2015年4月14日(火)
「ほんなら先生、槙の実、食べたことあるか?あれ、美味しいんやで」
「槙って、庭木にする、あの槙ですか?」
「そうそう、あの槙や、実ぃがな、赤と青と、玉が二つくっついたような形してるんや。青の方は食べられへん、赤いところだけ食べるとな、これが甘くて美味しいんや。季節?さぁて、あれは何月頃やったかな、おかしなもんや、あれだけ馴染んでて、季節いわれたら、すぐには分からんな~」
Iさんは先頃「肺年齢、90歳代」と宣告され、以来「寝返り打ってもしんどい」とぼやいている。客をないがしろにする店員だのマナーの悪い乗客だのに、一言いわずには済まない性分だが、最近は「口利くのがしんどい」と文句も言わず、それでストレスがたまるのだそうだ。
が、
この日はよくしゃべって、息切れする風もない。結構なことだ。
槙の実について調べてみたら、Iさんの語る通りだった。多言するよりも、下記のサイトが素敵なのでこれに譲る。
夢見る農園 http://blog.murablo.jp/inomura/kiji/345191.html
「受け継いだ田畑の管理が十分できない状態が続いていました。時間を見つけては、その再生に取りかかろうとしています。」
同じ志の人々が全国に散らばっている。簡単に地方が消滅したりするものではない。消滅の危機を孕んでいるのは、悟らない都会人の方だ。
Iさん言うところの青い部分が種、赤い部分が果肉であるらしい。いつ味わえるかな。