2024年3月4日(月)
> 1933年3月4日、アメリカ合衆国第32代大統領にフランクリン・ルーズベルトが就任した。大恐慌真っ只中のアメリカは、不況による深刻な失業問題や社会不安を抱えていた。51歳の新大統領は、ニューディール政策を掲げて選挙戦を勝ち抜き、大統領に選ばれると、史上例のない四期在任を成し遂げたのである。
アメリカ歴代大統領には二人のルーズベルトがいる。一人は第26代大統領のセオドア・ルーズベルト、そしてその従兄弟にあたるのがフランクリンである。ただし、セオドアは共和党、フランクリンが民主党出身の大統領だった。
彼の掲げたニューディール政策の目玉は、学者を中心とした若いスタッフによるブレイン・トラストであった。大規模公共事業や労働者の地位向上、団体交渉権の確保など、失業者対策と社会保障の充実を図る政策を次々と繰り出したが、経済の回復を実現させたのは皮肉なことに、第二次世界大戦による軍需拡大であった。
(後略)
晴山陽一『365日物語』(創英社/三省堂書店) P.69
***
フランクリン・デラノ・ルーズベルト(1882年1月30日 - 1945年4月12日)。
敬愛するアメリカの友人たちには申し訳ないが、こればかりはどうにもこうにもいただけない。この男はどういうわけか日本と日本人が大嫌いで、国益や政治信条が合理化し得る限度をはるかに超えて、日本を追い詰め日本人を痛ぶり続けた。日系人(アメリカ市民の一員!)に対しても同様である。一方、中国に対してはこれまたなぜか、常に過度に好意的だった。母方のデラノ一族は清朝時代にアヘンを含む貿易で財を成したというから、中国文化への畏敬とともに中国民衆への罪責感情をも引き継いだかもしれない。中国を煩わす日本を目の敵にすることは、その両面を同時に満足させたことだろう。
ルーズベルトが在任中に病没して、事情を知らないトルーマンに判断が委ねられることがなければ、原爆投下は避けられたのではないかと憶測する向きがあるが、僕は信じない。1945年2月の英米軍事会議でチャーチルが「戦争を一年でも半年でも短縮できるなら」として降伏条件の緩和を提案した時、この男はあっさり一蹴している。日本人に対する驚くべき見解は以下の通り。
> 駐米イギリス公使ロナルド・キャンベル(Ronald Hugh Campbell)との私的な会話でルーズベルトは、スミソニアン博物館の研究者であるアレス・ハードリチカによる、日本人の頭蓋骨は「われわれのより約2000年、発達が遅れている」という見解を紹介したうえで、「人種交配によって文明が進歩することを踏まえ、インド系やユーラシア系とアジア人種、欧州人とアジア人種などを交配させるべきだ。ただし日本人は除外する」と語っている。
このような自らの人種差別的感情とアメリカ社会における反日感情を背景に、1941年12月の対日開戦後には妻エレノアらの反対を押しきって、アメリカ国内と中南米諸国における日系人の強制収容政策を推し進め、彼らの自由を束縛するとともに財産を放棄せざるを得ない状況に追い込んだ。
このような自らの人種差別的感情とアメリカ社会における反日感情を背景に、1941年12月の対日開戦後には妻エレノアらの反対を押しきって、アメリカ国内と中南米諸国における日系人の強制収容政策を推し進め、彼らの自由を束縛するとともに財産を放棄せざるを得ない状況に追い込んだ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/フランクリン・ルーズベルト
この男を好きになれない ~ 日本人として好きになれるわけがない ~ 理由は要するにそういうもので、いくらでも追加できるが吐き気がしてくるからやめておく。それとは別に4期12年の長きにわたる任期の終盤、このあっぱれな大統領氏は健康状態の悪化に伴う判断力の低下によって、国際政治に甚大な悪影響を残している。健康問題の本質は高血圧であり、それが進行した結果としての脳軟化症(血管性認知症)であった。
> (1944年)8月になってルーズヴェルトは太平洋方面から帰ってきたが、演説中に狭心痛を起こしている。この頃の大統領は紅茶にクリームを入れる時に、カップではなく受け皿に注いでいた。手は震え、話すのも困難であり、肉体的にぼろぼろだった。秋には血圧は260/150mmHgに上がった。
> 1945年1月20日には4期目の大統領に就任したが、就任式でも狭心痛を訴え、やつれた姿は聴衆に衝撃と不安を与えた。2月4日から一週間にわたるヤルタ会談では、ドイツ降伏後2~3か月経った時点でソ連が日本に宣戦すること、東ヨーロッパをソ連の支配下に入れること、日ソ中立条約を破棄し千島列島と南樺太をソ連が併合することなど、ソ連にきわめて有利な密約が多数とり交された。ルーズヴェルトが全く精彩を欠き、スターリンの言うがままに押し切られたのである。チャーチルの主治医だったモラン男爵は回想録に書いている。
「大統領は老け込み、痩せてやつれて見えた。肩にケープをかけ、しなびた様子で、口をポカンと開け、まっすぐ前を見て座っていた。何も分かっていないかのようで、皆が彼の様子にショックを受けた。(中略)体の衰えだけではない、彼は口を開けて座っているだけで、討議にはほとんど加わらないのだ。彼がこの場にいるのがふさわしいかどうか疑問だった。進行した脳動脈硬化症のさまざまな症状を呈しており、数か月はもつまいという印象だった。」
冷戦時代にソ連の激しい攻勢にさらされたアメリカでは、ヤルタ会談でアメリカの権益を主張せずソ連に利益を与えたルーズヴェルトを、史上最低の大統領と酷評する者もあった。
小長谷正明『世界史を動かした脳の病気 ー 偉人たちの脳神経内科』(2018)P134-5から
モランの予測通り、その2か月後にローズヴェルトは高血圧性脳出血で急死する。権益を主張するどころか、目の前に示された文書を十分理解することもなく、ただ機械的に署名していたとすら思われる。廃人同様のルーズヴェルトを前にしてチャーチルは切歯扼腕、スターリンは笑いが止まらなかっただろう。
もっとも、健康を害する以前からスターリンとの間に「親交」のあったルーズヴェルトは、日独伊の侵略行為を敵視する一方で、フィンランド・ポーランド・バルト三国へのソ連の侵略をひたすら黙認していた。結果的にソ連は、西側では戦後の「鉄のカーテン」に至るまで突出し、極東では火事場泥棒的な対日参戦で易々と満州を征し千島を奪った。アメリカの原爆投下には、南下東進するソ連への示威の意味があったとも推測されるが、そもそもソ連の進出を招いた最大の原因はヤルタでの椀飯振舞だったのだから、つくづくルーズヴェルトは本朝にとっての疫病神である。
これ以上は書くのもバカバカしいが、八つ当たり的にもう一つだけ。『自由からの逃走』で知られるエーリヒ・フロム(ドイツ出身ユダヤ系の社会心理学者、1900-1980)に『悪について』という著作があり、「悪」とは何ぞやを「心理学的に」分析している。その一部。
「フランクリン・D・ローズヴェルトは適度な母親固着とナルチシズムをもち、非常にバイオフィラスな人物であった。それと対照をなすのはヒットラーで、彼はほとんど完全に近いネクロフィラスで、ナルチスティックで、近親相姦的な人物であった。」
エーリッヒ・フロム/鈴木重吉訳『悪について』紀伊國屋書店書店(1965)P.142
都合の良い対照を見つけたもので、アメリカ人には大いに喜ばれるだろうが、根拠を示して論じてほしいものである。「息子の学業の為なら大学一つまるごと買い与えることも辞さなかっただろう」と評される溺愛の母サラ・デラノ(1854-1941)へのローズヴェルトの固着が「適度で健康なもの」であり、ヒトラーのそれが「近親相姦的」であるという根拠は何なのか、その説明がまったく不足している。20代で読んだ時から釈然としなかったが、今は呆れるばかりで『自由からの逃走』と同じ人物の著作とは信じがたい。
一方には、こんな書籍どももあることを付記しておく。いずれもアメリカ人が執筆したものである。
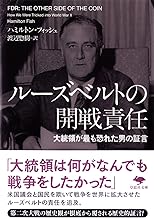
ハミルトン・フィッシュ (著), 渡辺惣樹 (翻訳)
『ルーズベルトの開戦責任』草思社(2017)
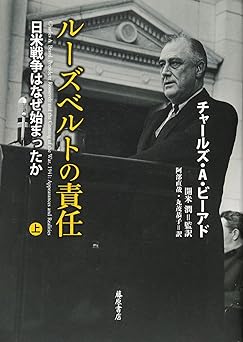
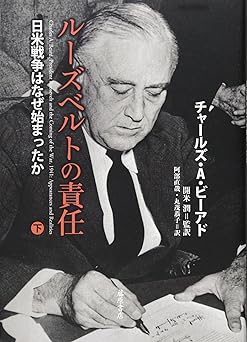
チャールズ・A・ビーアド (著)、粕谷一希 他(訳)
『ルーズベルトの責任 - 日米戦争はなぜ始まったか』(上・下) 藤原書店(2012)
Ω









