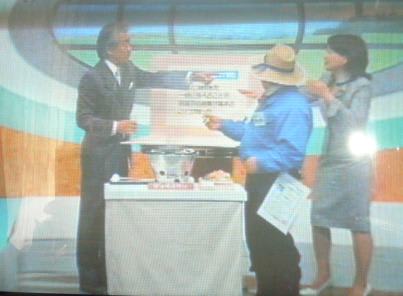遠野郷舘調査第2弾・・・今季2度目となる城館跡探訪は附馬牛町の火渡舘
今日も空模様は怪しい、午前中は少しだけ残業、また長女が自動車教習所卒検ということでお昼前にドライビングスクールへ・・・なんとか合格ということでまずは一安心、後は運転免許センターにての学科試験で晴れて免許取得となります・・・ということで本題の舘めぐりへ・・・。
午後2時、今回で2度目となる附馬牛の火渡舘へ、前回は2003年の晩秋、東京都の稲用氏、八戸の睦月庵氏を遠野へお迎えしての探訪であったが、自身のサイトには火渡舘は掲載していなかったのである。
画像が上手く撮れていないということと、地元ということでいつでも来れるといった甘さがありましたが、以来なかなか再訪に至っていない事実でもありました。
この冬あたりから、遠野阿曽沼時代、附馬牛地区を治めていたといわれる火渡氏を少し調べたい、そんな思いもあって、この春には早期のうちに舘跡探訪含み考察を加えたいと考えていたところでもあります。

火渡舘・・・・地元では日渡(ひわたし)と呼称する。
それともう一点気になることが・・・・
2003年の舘跡探訪の際、稲用氏が日本城郭体系に掲載の火渡舘の簡略図をコピーしたものを持参しておりましたが、その際、我々が踏み込んだ山野の他にまだまだ舘が繋がっていることや、頂上の神社の存在等を確認していなかったこと、それらから舘にしては小規模であること、遺構の確認が極めて少なかったことで資料と違うといった点が不審でもありました。
しかし、帰り際に空堀跡を発見したことにより、長らく先に訪ねた山野が主郭であると思っていた事実もあります。
が・・しかし、私自身も日本城郭体系を手に入れたことから、よくよく現地の地形なり、聞き込み調査をした結果、実は前回の探訪箇所は北西側の突端の郭に過ぎないことが判明、実は本郭は上の画像の中央の一段高い山野であり、前回の探訪箇所は画像の左端の山野である。
よって今回の調査の結果、日本城郭体系2に掲載の図面通りの遺構をほぼ確認いたしました。

本郭(頂部)の神社

神社下の空堀跡(うねるように駆け下っている)

北西側の階段状の平場

三重の空堀を確認・・・画像は内側(三重目)の空堀

背面の空堀・・・
資料のとおり、三重の空堀が判然と残されている、しかもかなりの深さもあり見応えは十分でもあります。
知られざる舘跡・・・といいたいところですが、舘跡にある神社をみてもわかるとおり、結構立派な社が建てられ、おそらくお祭りなんかもあったり、お参りする方々もいるとのことで、地域では空堀跡なんかはよく目にしていたものと思われます。
知らぬは附馬牛町以外の人間ということになりますかね・・・笑
阿曽沼忠臣、火渡玄浄広家(舘主)、非業の最期を遂げた激しい戦いがあった曰く付きの場所柄ながら、今回は誰かに見られているといった感覚はありませんでしたが、やはり西門舘同様、一番良いショットに白い球体が・・・・毎回、一枚は写り込んでますから気にしないようにしてますが、今回はあまりにもはっきりクッキリでしたので涙をのんで削除いたしました。
火渡舘と火渡氏・・・後日、遠野松崎じぇんご弐にその考察を含み掲載したいと思います。
いずれ、綾織の西門舘と類似していると日本城郭体系で記載されてますが、まさに空堀の数、背面の作り等、類似点も認められます。
やはり同時代に築舘された可能性が大で、これら遠野規格と呼ばれる舘跡調査によっても、謎とされる遠野阿曽沼時代の諸氏の歴史について何かしら明らかになる糸口がみつかる可能性を秘めていると私は感じます。
足で稼ぐ、つまり現地調査がかなり重要と最近は認識しております。
今後は、まずは青笹町の花(鼻)舘、さらに土淵町の角城館、山口館、本宿館、附馬牛町の大萩館、大野館を連休までに踏破したいと考えております。
それにしても、この火渡館、遠野郷内の館としてはかなりの遺構残存率、規模であると思われ、往時の火渡氏を偲ばせます。
こちらもすばらしい舘跡でこざいました。
今日も空模様は怪しい、午前中は少しだけ残業、また長女が自動車教習所卒検ということでお昼前にドライビングスクールへ・・・なんとか合格ということでまずは一安心、後は運転免許センターにての学科試験で晴れて免許取得となります・・・ということで本題の舘めぐりへ・・・。
午後2時、今回で2度目となる附馬牛の火渡舘へ、前回は2003年の晩秋、東京都の稲用氏、八戸の睦月庵氏を遠野へお迎えしての探訪であったが、自身のサイトには火渡舘は掲載していなかったのである。
画像が上手く撮れていないということと、地元ということでいつでも来れるといった甘さがありましたが、以来なかなか再訪に至っていない事実でもありました。
この冬あたりから、遠野阿曽沼時代、附馬牛地区を治めていたといわれる火渡氏を少し調べたい、そんな思いもあって、この春には早期のうちに舘跡探訪含み考察を加えたいと考えていたところでもあります。

火渡舘・・・・地元では日渡(ひわたし)と呼称する。
それともう一点気になることが・・・・
2003年の舘跡探訪の際、稲用氏が日本城郭体系に掲載の火渡舘の簡略図をコピーしたものを持参しておりましたが、その際、我々が踏み込んだ山野の他にまだまだ舘が繋がっていることや、頂上の神社の存在等を確認していなかったこと、それらから舘にしては小規模であること、遺構の確認が極めて少なかったことで資料と違うといった点が不審でもありました。
しかし、帰り際に空堀跡を発見したことにより、長らく先に訪ねた山野が主郭であると思っていた事実もあります。
が・・しかし、私自身も日本城郭体系を手に入れたことから、よくよく現地の地形なり、聞き込み調査をした結果、実は前回の探訪箇所は北西側の突端の郭に過ぎないことが判明、実は本郭は上の画像の中央の一段高い山野であり、前回の探訪箇所は画像の左端の山野である。
よって今回の調査の結果、日本城郭体系2に掲載の図面通りの遺構をほぼ確認いたしました。

本郭(頂部)の神社

神社下の空堀跡(うねるように駆け下っている)

北西側の階段状の平場

三重の空堀を確認・・・画像は内側(三重目)の空堀

背面の空堀・・・
資料のとおり、三重の空堀が判然と残されている、しかもかなりの深さもあり見応えは十分でもあります。
知られざる舘跡・・・といいたいところですが、舘跡にある神社をみてもわかるとおり、結構立派な社が建てられ、おそらくお祭りなんかもあったり、お参りする方々もいるとのことで、地域では空堀跡なんかはよく目にしていたものと思われます。
知らぬは附馬牛町以外の人間ということになりますかね・・・笑
阿曽沼忠臣、火渡玄浄広家(舘主)、非業の最期を遂げた激しい戦いがあった曰く付きの場所柄ながら、今回は誰かに見られているといった感覚はありませんでしたが、やはり西門舘同様、一番良いショットに白い球体が・・・・毎回、一枚は写り込んでますから気にしないようにしてますが、今回はあまりにもはっきりクッキリでしたので涙をのんで削除いたしました。
火渡舘と火渡氏・・・後日、遠野松崎じぇんご弐にその考察を含み掲載したいと思います。
いずれ、綾織の西門舘と類似していると日本城郭体系で記載されてますが、まさに空堀の数、背面の作り等、類似点も認められます。
やはり同時代に築舘された可能性が大で、これら遠野規格と呼ばれる舘跡調査によっても、謎とされる遠野阿曽沼時代の諸氏の歴史について何かしら明らかになる糸口がみつかる可能性を秘めていると私は感じます。
足で稼ぐ、つまり現地調査がかなり重要と最近は認識しております。
今後は、まずは青笹町の花(鼻)舘、さらに土淵町の角城館、山口館、本宿館、附馬牛町の大萩館、大野館を連休までに踏破したいと考えております。
それにしても、この火渡館、遠野郷内の館としてはかなりの遺構残存率、規模であると思われ、往時の火渡氏を偲ばせます。
こちらもすばらしい舘跡でこざいました。