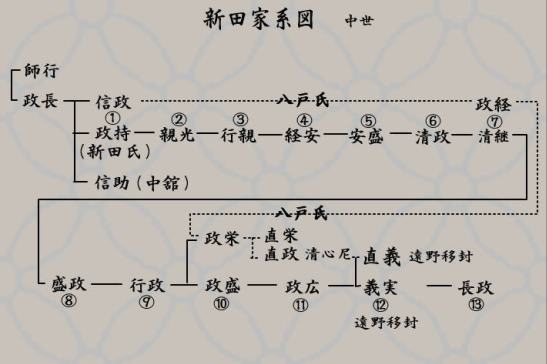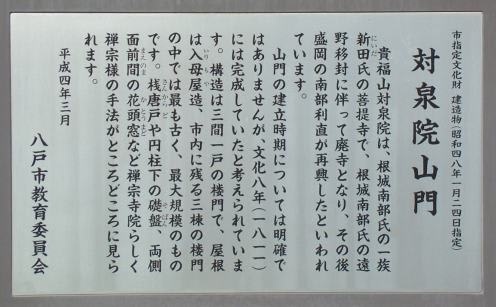遠野阿曾沼時代、伝承によれば大きな戦乱がいくつか伝えられますが、その多くは守勢にまわる戦いであり、他領からの侵略であったと語られます。
そのひとつは、永享9年(1437)の室町初期に気仙の豪族、岳波太郎、唐鍬崎兄弟に率いられた気仙勢と阿曾沼支族といわれる大槌孫三郎の大槌勢が呼応して横田城に押し寄せた戦い、永享事件(三戸の南部守行が援軍として遠野勢に加勢して侵略軍を大いに打ち破ったと伝えられる)。
さらに、同じく室町時代の宝徳2年(1450)には、葛西氏の武将といわれる金成右京太夫政実に率いられた気仙勢が宇夫方氏の篭る綾織谷地館を急襲、しかし、鱒沢氏、宮森氏、達曽部氏といった遠野西側の館主達が来援し、葛西勢を退けたと伝えられる。
他に葛西勢と語られるが、弘治3年(1557)宇夫方一族の主館である西風館が突如として夜襲され、館主一族が壊滅的打撃を受ける戦いがあったとも伝えられます。
このように伝えられる戦いは他領、しかも葛西領から攻め込まれた内容であるが、遠野から撃って出た戦いが数度とあったとも伝えられ、そのひとつに遠野阿曾沼第13代とされる遠野孫次郎こと阿曾沼広郷の江刺岩谷堂攻めがあったと伝えられている。
広郷は遠野歴代でも英傑と伝えられ、遠野郷内の半独立的な小領主達を服従させ、遠野における封建君主制を本格的にもたらした惣領とも思われますが、ただひとつ、一族である鱒沢氏を服従させるには至っていなかったようでもある。
鱒沢氏との対立については、別の機会にエントリーする予定といたします。
さて、天正年間、隣接する江刺領は、岩谷堂城主、江刺重恒の時代で、江刺はふたつの江刺氏が存在していたが、当初の江刺領主は千葉氏の流れを汲み、葛西宗家と婚姻等を重ねるうちに葛西氏の一族化が進み、葛西七党に組み込まれるほどの武威を誇っていたといわれます。
天正年間当時の領主、重恒は伊達家の後盾で葛西宗家を継いだ葛西宗清の系統で、天正年間に江刺郡の惣領となったといわれますが、阿曾沼家乗で記述されるように「葛西の族江刺重恒、政を失して境内擾乱す・・・」すなわち民心は離れ、家臣となっていたかつての江刺氏族の館主、小領主達の多くが離反していたことが伺われます。
また住田町史では、江刺重恒は女癖が悪く、家臣である菊池右近に命じて気仙世田米の姫君を室と迎えたいと下命し、室としたが1年もしないうちに世田米の姫を疎んじ、実家に送り返す所業があり、右近が諌言するもかえって右近は疎んじられ、右近の面目が丸つぶれとなり、世田米氏と共に遠野孫次郎を江刺領に引き入れ江刺重恒を討つ段取りをつけたとも言われます。
このことが遠野にあまりにも多い菊池姓の遠野流入のひとつとも考えられますが、結局は、気仙、遠野連合軍は江刺勢に破れ、菊池右近は江刺に居ることが叶わず遠野へ落ちたことになっている。

阿曾沼主家が抑えていた松崎地域・・・・昨年同時期の画像です。(耳切から)
江刺郡内の争乱、これは葛西領内で頻発した各郡内の勢力争いのひとつと考えられ、遠野孫次郎は期を逃さず、領土拡大の目論みとあわせ、江刺菊池一族の離反、そして気仙世田米の呼応を得ての侵攻戦と考えられていたが、葛西領内の秩序を乱す江刺重恒の態度が葛西宗家の逆鱗となるも、葛西領内の各郡内でも肥大した家臣団同士の争乱が相次ぎ、宗家による鎮圧は難航を極めていたことが想像される。
遠野阿曾沼氏と葛西氏は親密な関係があったことは、資料等でも若干明らかになっているが、葛西宗家との内密な交渉があって、気仙勢の一部との共同作戦にての岩谷堂侵攻が決定され、葛西宗家から江刺領の一部を遠野へ割譲する条件にて、遠野孫次郎は岩谷堂に攻めいったものと推測いたします。
結局は、阿曾沼家乗にあるように「広郷、弊に乗じて岩谷堂城を攻む、克たずして還る」・・・敗戦だったことが伺われ、多くは語られていない。
この岩谷堂攻め、大義名分は、放蕩無頼で政を失して民心を失った江刺兵庫守重恒を討伐して、郡内の治世回復をと江刺配下の土豪達からの出馬要請を受諾しての侵攻であったものと推測されます。
遠野市史では天正13年から15年と考察されているが、この頃と思われます。
遠野勢、気仙勢の連合軍が江刺領に入ると、政を失し、民心、家中が離反したはずの江刺重恒は、家中をまとめ、迎撃戦を演じる、遠野勢に見方するはずの土豪の一部は、重恒に降り、逆に遠野勢に攻撃を加え、その勢いは郡内各地に波及し、遠野勢は敵地で四面楚歌の状態に陥りかけ、撤退を余儀なくされ、夜陰に紛れて陣を引き払い、遠野へ帰還したものと推測されます。
この時、上郷在の細越氏は殿軍となり、敵の反撃を引き受け、最後は手兵と共に討死にと伝えられる。

敗戦で撤退となったが、遠野領内に入り、早池峰山を再び見た孫次郎以下の将兵はどんな思いだったのだろう・・・・。
この後、江刺氏や気仙郡内の土豪による仕返しと思われる遠野領内侵攻が語られますが、天正7年ともいわれ、先の岩谷堂攻めが天正13年以降とする説との矛盾点もあり、このことは本編サイトにて詳しく考証記述の予定です。