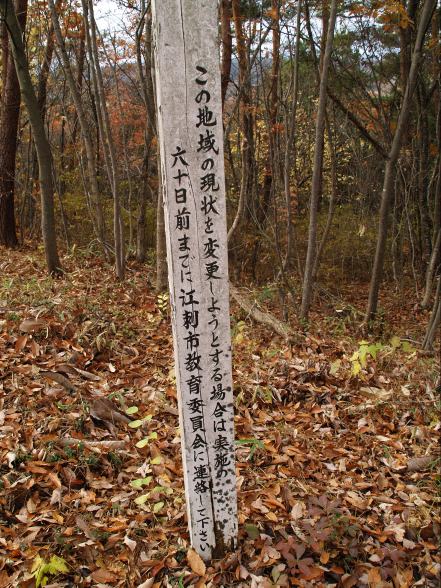たまたま飲み忘れた無濾過が冷蔵庫の野菜庫の底に・・・クリスマスまで取っておいてその時にいただこうかと考えております。

高校生の長男が関西方面に修学旅行中、コンデジを持っていかれたので、一眼デジで一発撮影となりました。
くすっこ団子(串団子)

ごま団子が好物です・・・。
おまけ
ネネ2連発





























遠野の菊池姓、その広がりの中において、ひとつの流れとして江刺(奥州市江刺区)からの菊池一族の遠野流入が一部ささやかれますが、歴史的な何かがあったものだろうという推測的雰囲気が大いに感じられるも、実際はその痕跡を示す資料等は皆無に等しく、ただその思惑のみというのが現実でもあると思います。
ここでは江刺における菊池氏の流れ等を中心に、遠野菊池一族との関連を少しですが紐解いてみたいと思ってます。
○江刺角懸菊池一族
「岩手県史 巻1」より
岩手県内における代表的な菊池系図である角懸菊池系図(江刺)
江刺人首川下流地帯に、九州菊池氏の裔と称する菊池一族がみられる。
菊池肥後守武重七世の孫氏恒を祖とし、その祖先は応永年中奥州葛西家の許に下向、葛西家に出仕、江刺郡の田谷、伊手の2邑を采地に給され、角懸邑に住したという・・・・。
関連する系図には、江刺での祖を蔵人武恒の裔としている。
江刺郡内に散見する菊地一族は、この角懸菊池氏から分派したものといわれ、角懸菊池氏は江刺郡における菊池一党の惣領との位置付と考察されており、史家達による考察の多くも角懸近在に在住した菊池武恒の存在は史実であろうという大方の見方でもある。
武恒四代の孫、右近丞定恒の代に郡主江刺家の重臣となっていたことは葛西晴信からの書状により明らかであるとされ、先にエントリーしております当ブログでの「青篠館」の説明板にもあるように江刺氏の執権職、家老という表記に間違いはないものと思われる。
ここでの疑問は、他資料に多く登場の菊池右近恒邦の存在、遠野における新谷菊池系図に記されその祖とされる菊池右近、角懸菊池系図に示される人物に右近恒邦の名はみられない・・・・。
「岩手県史 巻3」
こちらも角懸菊池系図と同様に引用される代表的な菊池系図「立花菊池系図」
和賀氏に仕えた菊池氏の系図であるが、江刺角懸菊池氏からの分流といわれ、祖先の中に角懸菊池系図にみられる武恒(菊池蔵人)の名がみられ、歴代やその兄弟の名の相違もありますが、ほぼ同系統の系図である雰囲気が大いに感じられる。
菊池蔵人武恒の弟、恒光を祖とし、少なくても永禄元年(1558)に和賀郡立花郷(北上市)を和賀主馬により菊池重長が給されたとする見解でもある。
和賀主馬とは少し代が下るが和賀忠親であると見解が示されている。
立花菊池氏は、恒光の代に江刺から和賀領へ移住、立花郷主である和賀氏家臣、高橋宮内少輔の家老となったと伝えられ、立花郷17貫文を和賀氏より給されたのが始まりとも伝えられる。
そして遠野への流入、その関連はとなりますが・・・・
「遠野市史 巻1・・・等より抜粋、一部加筆」
○菊池右近
菊池右近とは角懸菊池氏当主である菊池右近恒邦といわれている。
各系図には見えない名ではあるが、他資料等では右近恒邦の名が散見され、その多くは天正末期における江刺氏の内訌に関わる主要人物として登場する人物である。
また、江刺青篠館の舘主であり、江刺氏執権職、さらに角懸郷主、角懸菊池一族惣領という極めて重要な立場でもあった。
年代に関する見解はまちまちながらも天正15年(1587)、右近は主君である江刺兵庫頭重恒に諫言を入れるも、逆麟に触れ、角懸郷は江刺重恒勢に攻められ、右近の子と伝えられる太田代伊予は討たれ、右近は九死一生を得て遠野へ逃れたとされる事件である。
この時、菊池右近の呼びかけに応じた遠野孫次郎(阿曽沼広郷)や気仙郡世田米勢が江刺岩谷堂攻めに江刺郡内へ侵攻するも、郡内の諸勢力が江刺氏に合力したことにより遠野勢等は敗れ撤退、残された菊池右近は成す術もなく郡内より逃亡といった内容だったと推察される。
遠野市史では、菊池右近は南部信直に以来仕えたと記しているが、南部領とは遠野のことで、遠野の小友に一時的に隠遁、匿ったのは平清水景光(後の新谷禅門)であったのではないのか・・・と思われる。
角懸菊池系図には恒元(左近)・・・天正18没・・・と記されているが、この人物が右近恒邦か?・・・江刺郡内より逃がれ、江刺菊池党の権限一切を失ったが為に天正末期に亡くなったことにされたのか?或いは系図の信憑性はともかく、後に伊達藩時代の江戸期に書かれたであろう角懸菊池系図、南部領との関わりを知る術もなく、そのまま記した可能性も大いにあるものと推測もできます。
然らば・・・
「安俵菊池系図」・・・現花巻市東和町
旧和賀郡東和町も菊池姓が繁華な土地でもありますが、上記の系図に菊池右近恒邦の名が示されている。
遠野においては小友平清水家や上郷板沢家の祖と記される菊池右近ではあるが、遠野での足跡がほとんど不明である点、角懸菊池氏に関しては「恒」「武」の字が多く用いられているが、何故平清水氏は「景」なのか?
遠野菊池党(入内島氏 著)で見解が述べられておりますが、菊池右近は菊池一族である遠野の小友平清水氏に草鞋を脱ぐも、豊臣秀吉による奥州仕置により葛西氏と共に江刺氏も没落し、江刺郡が後に伊達領となってから故郷に帰ったものかもしれないと記している。
新谷菊池系図は遠野菊池氏である平清水氏と江刺角懸菊池氏の合作系図であること、これは大いに考慮すべき内容でもあると私も考えますし、安俵菊池系図に示される菊池右近恒邦の存在、これも大いに興味が覚えることでもある。
菊池右近は遠野菊池一族である平清水氏に家系的な何か、大いなる影響を及ぼし、後年遠野を後にして同じ南部領となった安俵に移住したのではないのか、つじつまが合いそうにありませんが、旧和賀郡土沢近在は、史実として右近のかつての主家、江刺恒重が南部信直に仕え、給された地でもあり、この時、江刺氏の家臣達の中には菊池一族もいたものだろうと推測もでき、その筆頭的立場であった菊池右近は江刺氏に許されたものかもしれません。
ということで、江刺からの菊池一族の流れの概略を少し掲載してみましたが、遠野への流入に関する事項は、ほとんど見えてこないが現状でもあります。
葛西氏没落、これに合わせて江刺郡からも遠野へ入っただろう諸氏・・・栃内氏、下川原氏、男沢氏、及川氏、高屋氏・・・・等・・・多くの武家の名が散見されますが具体的な菊池氏の名はほとんど出て来ないのは何故なのか?
平倉氏、平原氏、駒木氏、内城氏、切懸氏・・・これらの諸氏は一応に遠野では館主となっていた史実も伺えますが、こちらもどのような経緯でひとつの地域やら館を領有するに至ったか不明でもあり、江刺からの菊池氏遠野流入への説、天正末期から葛西、大崎一揆の後年説、これが第一に考えられるという思いが、仕切り直しという場面に変わりつつある現状に陥ってしまったようです・・・・。
さらなる精進と、少し頭を切り替えて、そして改めて原点に返って、今一度調べ直しが必要と痛感しているところです。