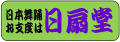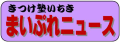年令や職業によって異なる衿合わせ
大正、昭和の時代を生きた新橋の芸者さんが、次のように書いていらっしゃいました。
「帯揚げの出し具合を見ただけで、新橋の芸者か、柳橋の芸者かわかったものよ。」
それほど花街の着付けは厳格だったのかもしれません。
一般の世界でも、着付けは自分の仕事や身分をあらわす周りへの自己表現なのです。
今でもそれは変わりません。
以前、結婚式に呼ばれた時の花嫁衣裳の着付けにビックリしたことがあります。
衿は下町の女将さん風、衣紋の抜き加減は花魁(おいらん)調なのです。
つまり衿をシャープに下ろして合わせ、衣紋を思い切って下ろして肩甲骨まで見えるほど。
これが今のプロ着付け?…あいた口が…
せめて、きものを着付ける時の衿合わせでは、若いお譲さんと、既婚の女性の区別くらいはしたいものですね。
多くの皆さまにお力添えいただきました。
1980年(昭和55年)、宮崎市の大塚町で生まれた「宮崎きもの学院」は、来春で創立35周年を迎えます。
当初、日常の着付けを中心に教室をすすめていましたが、三年目あたりから約三十年間、「プロの専門着せ付け」も併合した学院づくりにまい進してまいりました。
現在は、①自装の着付け ②正装の着せ付け ③振袖の着せ付け ④花嫁の着せ付け ⑤舞踊の着せ付け ⑥十二単の着せ付け が教室の内容になっています。
(①は自分の着付け ②~⑥までは、プロ着せ付け)
教室以外には、「日本舞踊(衣裳方)」で、文化ホールなどの舞台裏の着付けに伺ったり、「美容室や成人式の振袖などの着せ付け(着付け師)」をお受けして仕事をすることも日常の業務となっています。
本年度も、宮崎・鹿児島・福岡のお稽古場では、多くの皆さまのお力添えを頂き、着付けのプロ育成など、来年への地歩を築かせていただきました。本当にありがとうございました。
来年は新たな装いを凝らして、スタッフ一同まい進してまいりたいと考えています。
今年の、皆さまのご協力に心から感謝申し上げるとともに、来年もよろしくお願い申し上げる次第です。
今年の成人式が終わって以来、来年の成人式の着せ付けを目指してお勉強してきた生徒さんたち。
それぞれが、着付け技術の成長をされています。
一年間という期間を通して学ぶというのは簡単ではなく、ご本人の信念がないとなかなか続きません。
例えば、昨年の10月末から振袖のお勉強を始めたMさん。
わずか7カ月の間にメキメキ腕をあげて、今では帯結び専門のコースも学ばれています。

今日のMさんは、初めの一時間を「帯専科(帯結び専門のおけこ)」にあてて、残りの一時間は着せ付け専門のお勉強をされていました。
持ち前のセンスの良さと、呑み込みの速さも手伝って、来年は一人前の着付け師として、その活躍が期待されています。
 ●
● ●
●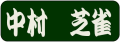 ●
●
 ●
●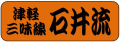 ●
● ●
●
 ●
● ●
● ●
●