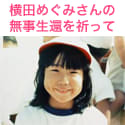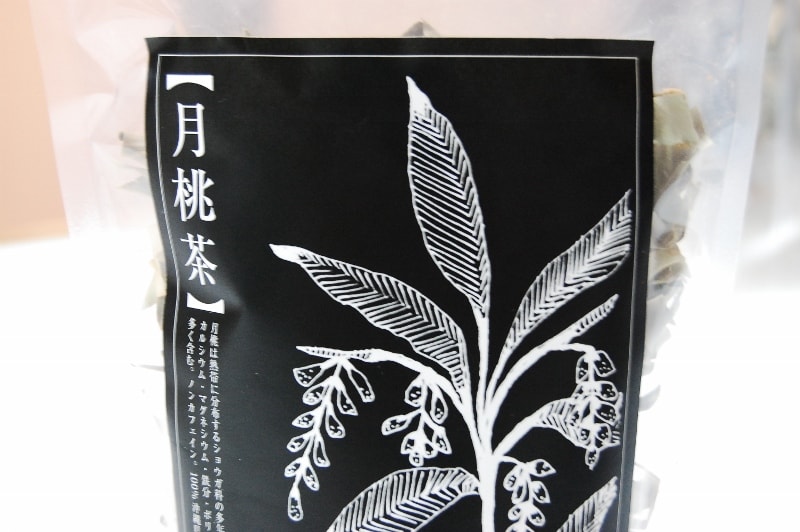本当に久しぶりの更新となりました。
皆さまにはお変わりなくお過ごしのことと思います。
季節は秋の土用にはいり、冬の準備が本格的になってきましたね。
薬膳(中医学)の世界では、日本の四季に土の季節(日本では梅雨にあたります)がプラスされて、自然界の廻りを五季に区分していますが、さらに、四季の移り変わりの時、土用という節目を設け、細やかに自然の享受のあり方を示しています。
8月8日の立秋に始まった秋は10月20日に終わり、10月21日から立冬(11月8日)の前日までが「秋の土用」となります。
土用とは、まさに「土」に「用」のある時期で、秋の土用はご先祖様から受けつがれて来た米作りの集大成でもある稲刈りに忙しい時期となります。
また、冬野菜の土寄せやお世話もこの時期の大切な仕事になります。
このところよいお天気が続き、毎日秋晴れですがすがしい日々ですが、この週末休み明けの大潮(満月の前後)には一降り来るころでしょうか。
先に書きましたように、五季の土の季節は湿の季節でもあります。
土用も同じで、農作業に関わる中で、土の湿を受けることになります。
ですから、私達のカラダは、消化吸収の要となり、水分代謝を調節する役割を担う『脾』の働きの影響を受けることになります。そして、『脾』と深く関わるのが、『胃』です。
食欲の秋だからと暴飲暴食したり、「消化吸収・水分代謝」を妨げるような食生活をしていると、『脾』『胃』の働きが鈍り、思わぬ不調を招くことになります。
年末に向けて、忙しい時期を迎えますが、早食いなども胃に負担をかけてしまいます。
ゆっくりよく噛んで、水はけのいいカラダを目指してくださいね。
『脾』が好む味は「甘味」です。
これは砂糖の入ったスイーツなどのことではなく、穀類を自身の臼の歯(臼歯)ですりつぶし、よく噛んで唾液と混ぜ合わせてブドウ糖に分解して得られる甘味のことです。
まさに、新米(出来るだけ未精製のもの)をありがたく良く噛んで、食べることが大切です。
よく、米粉のパンはどうですかと聞かれますが、自分の力で製粉していない米粉は、100点とは言い難いのではないでしょうか。
夏に欲した苦味はもうほどほどにし、秋の辛味、冬の備えである鹹味(塩から味)を添えた焼きさんまや焼きさばなど、季節のご馳走をおともに、おいしい炊きたての玄米ごはんが嬉しい季節ですね。
相克にあたる酸味は、季節のスダチやゆずなどの柑橘を少しいただく程度で充分です。
もちろん、体調如何では、この限りではありませんので、専門の方のご指導をお受け下さいね。
季節の変わり目、ご自愛されてください。
昨日は、岡山のWaRaの船越先生からいただいた、自家栽培の原木椎茸を頂きました。
焼いて、塩、スダチ、醤油といろいろ試してみましたが、シンプルに塩だけが一番おいしいと思いました。
何もつけなくっても、おいしいことに、びっくりもしました。
おいしい秋のご馳走を、ありがとうございます。

皆さまにはお変わりなくお過ごしのことと思います。
季節は秋の土用にはいり、冬の準備が本格的になってきましたね。
薬膳(中医学)の世界では、日本の四季に土の季節(日本では梅雨にあたります)がプラスされて、自然界の廻りを五季に区分していますが、さらに、四季の移り変わりの時、土用という節目を設け、細やかに自然の享受のあり方を示しています。
8月8日の立秋に始まった秋は10月20日に終わり、10月21日から立冬(11月8日)の前日までが「秋の土用」となります。
土用とは、まさに「土」に「用」のある時期で、秋の土用はご先祖様から受けつがれて来た米作りの集大成でもある稲刈りに忙しい時期となります。
また、冬野菜の土寄せやお世話もこの時期の大切な仕事になります。
このところよいお天気が続き、毎日秋晴れですがすがしい日々ですが、この週末休み明けの大潮(満月の前後)には一降り来るころでしょうか。
先に書きましたように、五季の土の季節は湿の季節でもあります。
土用も同じで、農作業に関わる中で、土の湿を受けることになります。
ですから、私達のカラダは、消化吸収の要となり、水分代謝を調節する役割を担う『脾』の働きの影響を受けることになります。そして、『脾』と深く関わるのが、『胃』です。
食欲の秋だからと暴飲暴食したり、「消化吸収・水分代謝」を妨げるような食生活をしていると、『脾』『胃』の働きが鈍り、思わぬ不調を招くことになります。
年末に向けて、忙しい時期を迎えますが、早食いなども胃に負担をかけてしまいます。
ゆっくりよく噛んで、水はけのいいカラダを目指してくださいね。
『脾』が好む味は「甘味」です。
これは砂糖の入ったスイーツなどのことではなく、穀類を自身の臼の歯(臼歯)ですりつぶし、よく噛んで唾液と混ぜ合わせてブドウ糖に分解して得られる甘味のことです。
まさに、新米(出来るだけ未精製のもの)をありがたく良く噛んで、食べることが大切です。
よく、米粉のパンはどうですかと聞かれますが、自分の力で製粉していない米粉は、100点とは言い難いのではないでしょうか。
夏に欲した苦味はもうほどほどにし、秋の辛味、冬の備えである鹹味(塩から味)を添えた焼きさんまや焼きさばなど、季節のご馳走をおともに、おいしい炊きたての玄米ごはんが嬉しい季節ですね。
相克にあたる酸味は、季節のスダチやゆずなどの柑橘を少しいただく程度で充分です。
もちろん、体調如何では、この限りではありませんので、専門の方のご指導をお受け下さいね。
季節の変わり目、ご自愛されてください。
昨日は、岡山のWaRaの船越先生からいただいた、自家栽培の原木椎茸を頂きました。
焼いて、塩、スダチ、醤油といろいろ試してみましたが、シンプルに塩だけが一番おいしいと思いました。
何もつけなくっても、おいしいことに、びっくりもしました。
おいしい秋のご馳走を、ありがとうございます。