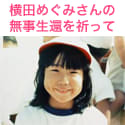歯科でよくご相談をされることの一つに、「口移し」があります。
まだ消化器官などが発達していない子供のために、親が先に食べ物をを噛み砕いたり柔らかくして食べやすくして与える食事の方法です。まれに、病人に対して取る場合もありますね。映画『もののけ姫』でサンがアシタカに干し肉を噛んで与えるシーンで、そんな方法があると知った方もおられるかもしれません。
さて、この「口移し」ですが、昨今、菌やウイルスが感染するということで、してはいけない育児法のトップに上げられてしまうようになりました。
唾液を介して、ピロリ菌や虫歯菌、歯周病菌が移ったり、胃がんになるなどと言われているようです。
おや、これが本当なら、大変なことになりますね。
まず、会話する時も唾がとばないようにマスクが必要になりますし、外部との接触も極力控えなくてはなりませんね。使ったスプーンや食器は、滅菌、殺菌し、消毒、消毒ということになってしまいます。
あ、でも、世間ではもうすでに『滅菌消毒ウイルス』に感染しているのかもしれませんね。
ホテルの部屋には必ずといっていいくらい、○ァブリーズを置いてますし、各種消毒系の家庭日用品であふれていますものね。
でも、でも、冷静に考えてみてください。
赤ちゃんは、お母さんのおなかの中で破水とともに産道を潜り抜け始めたところから、様々な細菌や微生物に暴露されていきます。
しかしこれと同時に、細菌や、微生物の感染を受けながら生きていくために必要な免疫力も付けていくのですよね。私たち、様々な細菌・微生物と共存し、互いに恩恵を受けることで、正常な営みができています。言い換えれば、細菌や微生物との共存なくして生きていくことは不可能なことなのです。
なのに、細菌を全て悪者に仕立てあげて、殺菌消毒に精を出していては、この地球上の生体の秩序や循環のサイクルが狂ってしまいます。今、取り立てて、エボラ出血熱やデング熱などで、必要以上に騒いで、各公園では殺虫剤などがまかれてまたどんどんイノチの輪を壊して行っています。何か、腑に落ちない、厭な気を感じるのは私だけでしょうか。
話はそれてしまいましたが、私たちの口腔内には、たくさんの菌が住んでいます。虫歯菌もその一種で、誰しも保菌しています。ですから、たとえ口移しで物を与えなくても感染する機会はいくらでもあります。親に限らず、他人の唾液に接触する機会はいくらでもあるのですから。
口移しで食べ物を与える習慣は、動物学的にはいかがでしょう?他の哺乳類や霊長類では当然の事のように繰り返し行われていることですよね。ヒト科においては、特別で例外なのでしょうか?
また、「口移し」と言う行為は、直接であれ、スプーンを使ってであれ、親と子のコミュニケーションであり、熱いものを親の口に当てて確認し、やけどしないようにしてやったり、噛み砕いて親の唾液と混ぜ合わせ、消化を助けてやったりと、肌を通して、デリケートな加減をしてやることができる、大切なプロセスなのではないでしょうか?子どもの情操教育にも一役担っているのではないかと思います。
子どもには口唇期と呼ばれる精神発展段階があり、どうしても口唇による接触が精神発達上必要な時があります。歯が生え始めた生後半年目くらいに必ず誰もが取る「なめまわし行動」はまさに口による心と脳の発達に欠かせないものなのです。
これが十分に行われないケースでは、感受性の未発達に陥ることが知られています
いろいろ考えてもやはり、愛情を深めることのできる「口移し」というスキンシップは、親にも子供にも、ある程度必要なことなのではないでしょうか。
もちろん親の口腔内の状態には気を付けてほしいと思います。
しっかりとした歯科知識を持って口腔内のケアを行っていれば、口移しでも問題はないと思います。たとえ、口移しをしなかったとしても、虫歯菌の感染は避ける事はできないですしね。
仮に、口移しをして、虫歯菌が赤ちゃんの口腔内に進入したとしても、虫歯菌が口の中で定着し増殖しない限りは虫歯菌の感染が成立しません。要は、虫歯菌の餌になるようなものを与えなければ大丈夫だということです。
外部から進入してくる虫歯菌が定着できないような生活習慣を作り、子供が自立して自己管理ができる6才くらい(6歳臼歯と言う初めての大人の歯が生える頃です)までの間は、親が歯科教育とともに子どもの口腔内管理をしていくことが大切になポイントになります。
常に子供さんの口腔衛生に気をつけて管理をしてあげるなら(主食のごはんをしっかり与え、むやみに甘い物を与えない)、口移しについてそれほど神経質にこだわることもないと思います。
『口移し』は自然の節理だと思います。
親の口腔衛生レベルは、確実に子供は引き継ぎます。
いくら子供だけ気をつけていても、お母さんの口腔内がよろしくなければ、その口腔内を作った生活習慣を子供が受け継ぎ、同じような口腔内になることをよく知っておいてください。
結論から言いますと、『口移し』はしてもいい、むしろした方がいいということです。
ただし、親の口腔内に問題がある場合は、やはり、問題解決したほうがいいに決まってます。
ぜひ、細菌やウイルスに負けないような免疫力の高いカラダ作りの方を目指してほしいものです。
口腔内の問題を引き起こすような食生活こそ、子育てにおいてやめるべきことではないでしょうか?

まだ消化器官などが発達していない子供のために、親が先に食べ物をを噛み砕いたり柔らかくして食べやすくして与える食事の方法です。まれに、病人に対して取る場合もありますね。映画『もののけ姫』でサンがアシタカに干し肉を噛んで与えるシーンで、そんな方法があると知った方もおられるかもしれません。
さて、この「口移し」ですが、昨今、菌やウイルスが感染するということで、してはいけない育児法のトップに上げられてしまうようになりました。
唾液を介して、ピロリ菌や虫歯菌、歯周病菌が移ったり、胃がんになるなどと言われているようです。
おや、これが本当なら、大変なことになりますね。
まず、会話する時も唾がとばないようにマスクが必要になりますし、外部との接触も極力控えなくてはなりませんね。使ったスプーンや食器は、滅菌、殺菌し、消毒、消毒ということになってしまいます。
あ、でも、世間ではもうすでに『滅菌消毒ウイルス』に感染しているのかもしれませんね。
ホテルの部屋には必ずといっていいくらい、○ァブリーズを置いてますし、各種消毒系の家庭日用品であふれていますものね。
でも、でも、冷静に考えてみてください。
赤ちゃんは、お母さんのおなかの中で破水とともに産道を潜り抜け始めたところから、様々な細菌や微生物に暴露されていきます。
しかしこれと同時に、細菌や、微生物の感染を受けながら生きていくために必要な免疫力も付けていくのですよね。私たち、様々な細菌・微生物と共存し、互いに恩恵を受けることで、正常な営みができています。言い換えれば、細菌や微生物との共存なくして生きていくことは不可能なことなのです。
なのに、細菌を全て悪者に仕立てあげて、殺菌消毒に精を出していては、この地球上の生体の秩序や循環のサイクルが狂ってしまいます。今、取り立てて、エボラ出血熱やデング熱などで、必要以上に騒いで、各公園では殺虫剤などがまかれてまたどんどんイノチの輪を壊して行っています。何か、腑に落ちない、厭な気を感じるのは私だけでしょうか。
話はそれてしまいましたが、私たちの口腔内には、たくさんの菌が住んでいます。虫歯菌もその一種で、誰しも保菌しています。ですから、たとえ口移しで物を与えなくても感染する機会はいくらでもあります。親に限らず、他人の唾液に接触する機会はいくらでもあるのですから。
口移しで食べ物を与える習慣は、動物学的にはいかがでしょう?他の哺乳類や霊長類では当然の事のように繰り返し行われていることですよね。ヒト科においては、特別で例外なのでしょうか?
また、「口移し」と言う行為は、直接であれ、スプーンを使ってであれ、親と子のコミュニケーションであり、熱いものを親の口に当てて確認し、やけどしないようにしてやったり、噛み砕いて親の唾液と混ぜ合わせ、消化を助けてやったりと、肌を通して、デリケートな加減をしてやることができる、大切なプロセスなのではないでしょうか?子どもの情操教育にも一役担っているのではないかと思います。
子どもには口唇期と呼ばれる精神発展段階があり、どうしても口唇による接触が精神発達上必要な時があります。歯が生え始めた生後半年目くらいに必ず誰もが取る「なめまわし行動」はまさに口による心と脳の発達に欠かせないものなのです。
これが十分に行われないケースでは、感受性の未発達に陥ることが知られています
いろいろ考えてもやはり、愛情を深めることのできる「口移し」というスキンシップは、親にも子供にも、ある程度必要なことなのではないでしょうか。
もちろん親の口腔内の状態には気を付けてほしいと思います。
しっかりとした歯科知識を持って口腔内のケアを行っていれば、口移しでも問題はないと思います。たとえ、口移しをしなかったとしても、虫歯菌の感染は避ける事はできないですしね。
仮に、口移しをして、虫歯菌が赤ちゃんの口腔内に進入したとしても、虫歯菌が口の中で定着し増殖しない限りは虫歯菌の感染が成立しません。要は、虫歯菌の餌になるようなものを与えなければ大丈夫だということです。
外部から進入してくる虫歯菌が定着できないような生活習慣を作り、子供が自立して自己管理ができる6才くらい(6歳臼歯と言う初めての大人の歯が生える頃です)までの間は、親が歯科教育とともに子どもの口腔内管理をしていくことが大切になポイントになります。
常に子供さんの口腔衛生に気をつけて管理をしてあげるなら(主食のごはんをしっかり与え、むやみに甘い物を与えない)、口移しについてそれほど神経質にこだわることもないと思います。
『口移し』は自然の節理だと思います。
親の口腔衛生レベルは、確実に子供は引き継ぎます。
いくら子供だけ気をつけていても、お母さんの口腔内がよろしくなければ、その口腔内を作った生活習慣を子供が受け継ぎ、同じような口腔内になることをよく知っておいてください。
結論から言いますと、『口移し』はしてもいい、むしろした方がいいということです。
ただし、親の口腔内に問題がある場合は、やはり、問題解決したほうがいいに決まってます。
ぜひ、細菌やウイルスに負けないような免疫力の高いカラダ作りの方を目指してほしいものです。
口腔内の問題を引き起こすような食生活こそ、子育てにおいてやめるべきことではないでしょうか?