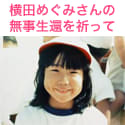平成11年、私が39歳で結婚した時、主人の母はすでに88歳でした。
主人は母が40歳の時の子どもでしたから、主人の歳が48歳。
その頃から、少しずつ、いろいろなものをひとつひとつ時間の中に忘れていくという生活でした。
松見の家に嫁いだ初日、39歳の私に、トイレの掃除の仕方を丁寧に教えてくれました。
母からしたら、私は20歳の娘となんら変わらない歳の差だったのかもしれません。
もちろん40近くの私がトイレの掃除の仕方がわからないわけではありません。
その時に「あ~、介護が始まるんだなぁ」って思ったのをつい昨日のように思い出されます。
母は明治43年生まれ。
明治女は気丈夫で、一筋縄ではいきません。
こうと思ったら頑として動きませんから、お世話を始めてすぐに困ったことが起きました。
「ごはんはお茶碗に一杯まで!」
これを頑なに守り、お代わりを勧めてもこの決めごとは決して譲りませんでした。
当時、前年に父が他界したばかりで、それまでは、主人と息子は玄米、両親は白米という生活だったのですが、実は、父と母は夫婦逆転で、父が主夫で、母が歯医者で生計をたてていましたので、父がいなくなって、料理が苦手な母は、泣く泣く玄米生活を始めたところでした。
硬いね、硬いね、といつもこぼしていたのが、不憫でした。
それでも、お薬を両手に余るくらい飲んでいましたので、なんとか薬から解放できないかとひそかに玄米に期待をしていました。
なんとか、玄米ご飯を食べてもらおうと、お代わりは?と聞くと「いえ、お茶碗一杯で結構」と毅然と答える母は、おかずをたくさん食べてご飯は少しというまさに一日30品目の食スタイルでした。(その後平成12年3月24日に食生活指針の中の大黒柱的スローガンの一日30品目は取り消され「ごはんなどの穀類をしっかりと」に変わりました)
その頃の母は、毎年冬になると一番に風邪を引き、酷いときは入院。カーテンを一人で変えようとして台から落ちて骨折、両手に余るほどのお薬をもらいに月に一度は通院する生活で、口癖は「寒いの」という言葉でした。
健康づくりの一環ではありますが、86歳までは毎日診療室に顔を出して、患者さんと会話したり、調子のいい時には院長の補佐的役割も果たしておりましたが、年齢も年齢なので引退。
それからというもの、家事は苦手な分野なのですることがなくなり、父も他界するなどで、いよいよ、毎日ご飯を食べたら自分の部屋で寝るという状態。
私が嫁に来た時には、認知症が始まっておりました。
そして、件の「寒いの」ということで、冬は床の上に断熱材を敷いて絨毯、穿きだしのガラス戸には腰まで発泡スチロールを張り、ベッドにはマットの上に敷布団、電気シーツ、肩腰足にそれぞれソフトあんか、電気毛布、毛布、肌布団、本布団、かいまき布団、毛糸のベッドカバー、足元にも足温器、パジャマの下には肌着を3枚、その上に暖房をして、それで「まだ寒い」と申してました。よくお布団の重みで、窒息しないの?と笑ったものです。
そんな母でしたが、食欲はありましたので、唯一の楽しみが食べること。
ご飯ばかりはやっぱり厭だったようです。
小さな女茶碗一杯の玄米ご飯ではなかなか体質改善は難しく、明治女と昭和女の攻防戦が始まったわけですが、あるとき、名案が浮かびました!
それは、お茶碗を大きくすることです。
大きくてもお茶碗一杯ですから♪
で、お茶碗を割ることにしました。「うっかり割れたので、お茶碗を新しくしました」ということで、明治女の決めごと「お茶碗一杯」を遂行することに成功したのでした。
それから、事あるごとにお茶碗を大きくしていきました。
お誕生日のプレゼントにお茶碗。新年明けましておめでとうということで新しいお茶碗・・・。
みるみる母のお茶碗は男茶碗を上回る大きさになりました。
それでも「お茶碗一杯」としてくれた母にどれほど感謝したことでしょうか。
そんな玄米ご飯を一杯食べる生活を始めた母は、みるみる健康になりました。
風邪ひとつひくことなく、薬も、認知症が少し手伝ってくれて、「飲んだかねぇ?」と尋ねられると飲んで無くても「飲んだよ」って具合に、少しずつ減薬して、そのうちに一錠も飲むことなく暮らすことができるようになりました。
その頃には、絨毯は足を躓かせて危ないということで、フローリングの部屋に移り、冬でも室内温度は18度に保ち、パジャマ一枚、湯たんぽくらいで、布団と毛布くらいの寝間となりました。
あれほど寒かった母でしたが、夏はあっぱっぱ一枚で、素足にソックス。91歳のときには釧路川でカヌーで川下り出来るほど元気に。
亡くなる前も薬一錠も飲むことなく、天国に召されました。
今日は母の命日。
88歳からの玄米食で96歳まで元気に頑張ってくれました。
歯は26本。自前の歯を持っていました。
8年という母との短い時間は、介護という嫁の仕事で終始しましたが、歳をとっても食べ物がもたらす心身への影響はすごいものなんだと感じる毎日でした。
早いものであれからもう、母と過ごした時間とおなじだけ月日が流れました。
昨日までそこに座っていたように思います。
天国から、どうぞ、私たち家族を見守ってくださいね。

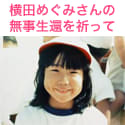
主人は母が40歳の時の子どもでしたから、主人の歳が48歳。
その頃から、少しずつ、いろいろなものをひとつひとつ時間の中に忘れていくという生活でした。
松見の家に嫁いだ初日、39歳の私に、トイレの掃除の仕方を丁寧に教えてくれました。
母からしたら、私は20歳の娘となんら変わらない歳の差だったのかもしれません。
もちろん40近くの私がトイレの掃除の仕方がわからないわけではありません。
その時に「あ~、介護が始まるんだなぁ」って思ったのをつい昨日のように思い出されます。
母は明治43年生まれ。
明治女は気丈夫で、一筋縄ではいきません。
こうと思ったら頑として動きませんから、お世話を始めてすぐに困ったことが起きました。
「ごはんはお茶碗に一杯まで!」
これを頑なに守り、お代わりを勧めてもこの決めごとは決して譲りませんでした。
当時、前年に父が他界したばかりで、それまでは、主人と息子は玄米、両親は白米という生活だったのですが、実は、父と母は夫婦逆転で、父が主夫で、母が歯医者で生計をたてていましたので、父がいなくなって、料理が苦手な母は、泣く泣く玄米生活を始めたところでした。
硬いね、硬いね、といつもこぼしていたのが、不憫でした。
それでも、お薬を両手に余るくらい飲んでいましたので、なんとか薬から解放できないかとひそかに玄米に期待をしていました。
なんとか、玄米ご飯を食べてもらおうと、お代わりは?と聞くと「いえ、お茶碗一杯で結構」と毅然と答える母は、おかずをたくさん食べてご飯は少しというまさに一日30品目の食スタイルでした。(その後平成12年3月24日に食生活指針の中の大黒柱的スローガンの一日30品目は取り消され「ごはんなどの穀類をしっかりと」に変わりました)
その頃の母は、毎年冬になると一番に風邪を引き、酷いときは入院。カーテンを一人で変えようとして台から落ちて骨折、両手に余るほどのお薬をもらいに月に一度は通院する生活で、口癖は「寒いの」という言葉でした。
健康づくりの一環ではありますが、86歳までは毎日診療室に顔を出して、患者さんと会話したり、調子のいい時には院長の補佐的役割も果たしておりましたが、年齢も年齢なので引退。
それからというもの、家事は苦手な分野なのですることがなくなり、父も他界するなどで、いよいよ、毎日ご飯を食べたら自分の部屋で寝るという状態。
私が嫁に来た時には、認知症が始まっておりました。
そして、件の「寒いの」ということで、冬は床の上に断熱材を敷いて絨毯、穿きだしのガラス戸には腰まで発泡スチロールを張り、ベッドにはマットの上に敷布団、電気シーツ、肩腰足にそれぞれソフトあんか、電気毛布、毛布、肌布団、本布団、かいまき布団、毛糸のベッドカバー、足元にも足温器、パジャマの下には肌着を3枚、その上に暖房をして、それで「まだ寒い」と申してました。よくお布団の重みで、窒息しないの?と笑ったものです。
そんな母でしたが、食欲はありましたので、唯一の楽しみが食べること。
ご飯ばかりはやっぱり厭だったようです。
小さな女茶碗一杯の玄米ご飯ではなかなか体質改善は難しく、明治女と昭和女の攻防戦が始まったわけですが、あるとき、名案が浮かびました!
それは、お茶碗を大きくすることです。
大きくてもお茶碗一杯ですから♪
で、お茶碗を割ることにしました。「うっかり割れたので、お茶碗を新しくしました」ということで、明治女の決めごと「お茶碗一杯」を遂行することに成功したのでした。
それから、事あるごとにお茶碗を大きくしていきました。
お誕生日のプレゼントにお茶碗。新年明けましておめでとうということで新しいお茶碗・・・。
みるみる母のお茶碗は男茶碗を上回る大きさになりました。
それでも「お茶碗一杯」としてくれた母にどれほど感謝したことでしょうか。
そんな玄米ご飯を一杯食べる生活を始めた母は、みるみる健康になりました。
風邪ひとつひくことなく、薬も、認知症が少し手伝ってくれて、「飲んだかねぇ?」と尋ねられると飲んで無くても「飲んだよ」って具合に、少しずつ減薬して、そのうちに一錠も飲むことなく暮らすことができるようになりました。
その頃には、絨毯は足を躓かせて危ないということで、フローリングの部屋に移り、冬でも室内温度は18度に保ち、パジャマ一枚、湯たんぽくらいで、布団と毛布くらいの寝間となりました。
あれほど寒かった母でしたが、夏はあっぱっぱ一枚で、素足にソックス。91歳のときには釧路川でカヌーで川下り出来るほど元気に。
亡くなる前も薬一錠も飲むことなく、天国に召されました。
今日は母の命日。
88歳からの玄米食で96歳まで元気に頑張ってくれました。
歯は26本。自前の歯を持っていました。
8年という母との短い時間は、介護という嫁の仕事で終始しましたが、歳をとっても食べ物がもたらす心身への影響はすごいものなんだと感じる毎日でした。
早いものであれからもう、母と過ごした時間とおなじだけ月日が流れました。
昨日までそこに座っていたように思います。
天国から、どうぞ、私たち家族を見守ってくださいね。