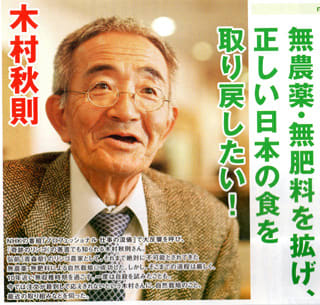今日は、鹿児島から中平ちほ先生をお招きして、
マクロビオティックのお菓子作りを楽しみました。
今日のメニューは「夏のお菓子」がテーマ。
可愛い「飾りまきビスケット2種類」とおしゃれな「トマトのブランマンジェ」、ほっこり「とうもろこしの蒸し饅頭」を作りましたよ。







今回は土曜日だったので、小学生と中学生のご参加もあってうれしかったです。
飾り巻きビスケットは、スイカとヨットを作ったのですが、なんだか、工作しているみたい!
可愛い出来上がりで、大満足でした。
トマトのブランマンジェも美味しかったですよ。
ワタシ個人的には、とうもろこしの蒸しまんじゅうが好き!
こちらは、ちほ先生からのお土産です。





こんどは、カエルくんも作ってみたいですね。
講座が終わってから、ちほ先生とおしゃべり。
3年後くらいに、本を出したいというちほ先生。
どんな切り口がいいかなぁって話になって、
ちょっと提案してみました。
「毎日のおやつと、たまにうれしいお菓子」の本。
おやつって、本当の意味はスイーツとかお菓子とかっていうのではなく、「八つ時の食事」という意味なんです。成長期の子どもたちは、3回の食事では足りないので、もう一回、八つ時の食事で補う必要があるんです。ですから、成長を助けるものでなくてはいけません。
スイーツで成長しますか?
答えは「NO」です。
お砂糖は脳の栄養素って言う方がいらっしゃるかもしれませんが、
それは、ブドウ糖が必要ということで、砂糖ではありません。
そして、人間に歯と唾液があるのは、穀類を口の中に入れてよく噛み、唾液の消化酵素によりブドウ糖に分解して体内に取り入れるためです。つまり、口の前にすでに糖化されているものを食べる動物ではないということなのです。
スイーツは、ココロの栄養って反論する方もいるかもですね(笑)
でも、甘いものは、身体を酸化させますので、身体のPH(ペーハー)、約7.4という弱アルカリ性を保つためには、体内のアルカリ性である骨を溶かして(骨粗鬆症になるということ)中和させます。つまり、カルシウムが不足するということです。イライラの原因になります。
また、砂糖などの精製度の高いものを食べると、代謝の過程で、体内に取りこんでいたビタミンB群を奪い取って代謝します。ビタミンB群は、ココロの栄養素と言われ、不足すると、躁・うつ病、引きこもり、パニック障害、自傷行為、統合失調症などを引き起こす要因となります。
さらに、血糖値の乱高下が起こり、低血糖になった時、肝臓に貯蔵しているグリコーゲンをブドウ糖に分解して血中に送り込むのですが、その際に肝臓に刺激を与えるため、体内にアドレナリン、ノルアドレナリンを充満させるのです。怒りのホルモン、恐怖のホルモンと言われるそれらは、凶暴になったり、不安になったりさせるものなので、またまたココロの不安定を招くのです。
このように折り重なってココロの問題を引き起こす糖類は、決してココロの栄養素とは言い難いのです。
だから、子どもたちに必要な「おやつ」は食事になるもの。
一番は「ごはん」です。
さつま芋やかぼちゃ、トウモロコシなど、デンプン質なものがいいですね。
昆布や切干大根をそのまま食べるのも、子どもたちは大好きです。
穀類や豆、野菜でつくる「毎日のおやつ」、そしてたまに(松見歯科では一週間に1回)食べるお菓子。
そんな住み分けのできる、本があるといいなぁ。
もちろん、「毎日のおやつ」だって見た目はとってもオシャレな方がいいに決まってる!
そこで、ちほ先生の出番ですね。
ちほ先生の本、早くでるといいですね。
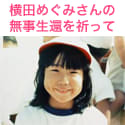
マクロビオティックのお菓子作りを楽しみました。
今日のメニューは「夏のお菓子」がテーマ。
可愛い「飾りまきビスケット2種類」とおしゃれな「トマトのブランマンジェ」、ほっこり「とうもろこしの蒸し饅頭」を作りましたよ。







今回は土曜日だったので、小学生と中学生のご参加もあってうれしかったです。
飾り巻きビスケットは、スイカとヨットを作ったのですが、なんだか、工作しているみたい!
可愛い出来上がりで、大満足でした。
トマトのブランマンジェも美味しかったですよ。
ワタシ個人的には、とうもろこしの蒸しまんじゅうが好き!
こちらは、ちほ先生からのお土産です。





こんどは、カエルくんも作ってみたいですね。
講座が終わってから、ちほ先生とおしゃべり。
3年後くらいに、本を出したいというちほ先生。
どんな切り口がいいかなぁって話になって、
ちょっと提案してみました。
「毎日のおやつと、たまにうれしいお菓子」の本。
おやつって、本当の意味はスイーツとかお菓子とかっていうのではなく、「八つ時の食事」という意味なんです。成長期の子どもたちは、3回の食事では足りないので、もう一回、八つ時の食事で補う必要があるんです。ですから、成長を助けるものでなくてはいけません。
スイーツで成長しますか?
答えは「NO」です。
お砂糖は脳の栄養素って言う方がいらっしゃるかもしれませんが、
それは、ブドウ糖が必要ということで、砂糖ではありません。
そして、人間に歯と唾液があるのは、穀類を口の中に入れてよく噛み、唾液の消化酵素によりブドウ糖に分解して体内に取り入れるためです。つまり、口の前にすでに糖化されているものを食べる動物ではないということなのです。
スイーツは、ココロの栄養って反論する方もいるかもですね(笑)
でも、甘いものは、身体を酸化させますので、身体のPH(ペーハー)、約7.4という弱アルカリ性を保つためには、体内のアルカリ性である骨を溶かして(骨粗鬆症になるということ)中和させます。つまり、カルシウムが不足するということです。イライラの原因になります。
また、砂糖などの精製度の高いものを食べると、代謝の過程で、体内に取りこんでいたビタミンB群を奪い取って代謝します。ビタミンB群は、ココロの栄養素と言われ、不足すると、躁・うつ病、引きこもり、パニック障害、自傷行為、統合失調症などを引き起こす要因となります。
さらに、血糖値の乱高下が起こり、低血糖になった時、肝臓に貯蔵しているグリコーゲンをブドウ糖に分解して血中に送り込むのですが、その際に肝臓に刺激を与えるため、体内にアドレナリン、ノルアドレナリンを充満させるのです。怒りのホルモン、恐怖のホルモンと言われるそれらは、凶暴になったり、不安になったりさせるものなので、またまたココロの不安定を招くのです。
このように折り重なってココロの問題を引き起こす糖類は、決してココロの栄養素とは言い難いのです。
だから、子どもたちに必要な「おやつ」は食事になるもの。
一番は「ごはん」です。
さつま芋やかぼちゃ、トウモロコシなど、デンプン質なものがいいですね。
昆布や切干大根をそのまま食べるのも、子どもたちは大好きです。
穀類や豆、野菜でつくる「毎日のおやつ」、そしてたまに(松見歯科では一週間に1回)食べるお菓子。
そんな住み分けのできる、本があるといいなぁ。
もちろん、「毎日のおやつ」だって見た目はとってもオシャレな方がいいに決まってる!
そこで、ちほ先生の出番ですね。
ちほ先生の本、早くでるといいですね。
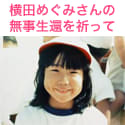





















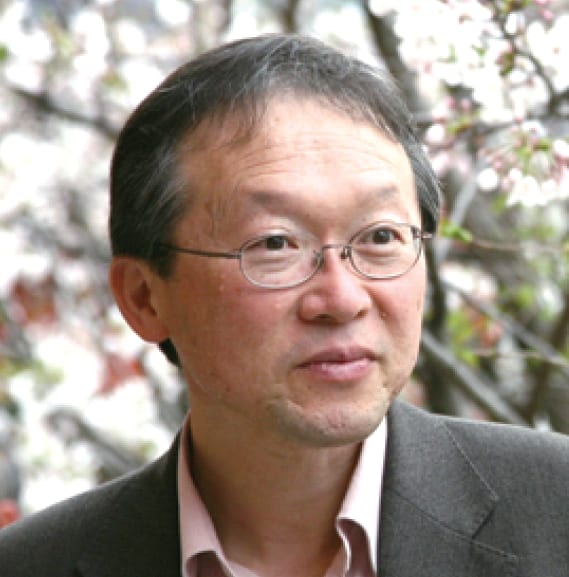



 』
』