■12月22日から23日にかけて関電工の前橋バイオマス発電所・燃料チップ製造施設の見学会が4回にわたり実施されました。その際に参加された地元住民のかたがたから報告が届きましたので、それらをまとめたものをここに掲載します。なお、関電工は写真撮影を一切禁止としたため、情報開示で群馬県から入手した、補助金支払いに先立って2017年6月頃作成された県による検査報告書に掲載された写真を参考用に文中に掲載してあります。

↑2月1日から予定されているという稼働開始に向けて準備に余念のない関電工らによる亡国事業現場。↑

*****関電工の亡国事業見学会報告*****
近所のかたがたと一緒に最後の4回目の視察会に参加しました。
午後1時半から開始ということで、車に乗り合わせて入口のゲートを通り、坂を上ると施設に到着しました。最初に待合室に案内されました。

↑貯木場・作業用建物・燃料保管倉庫↑
壁にかかった予定表には、「12月6日産廃、同16日発電所北側フェンス修理、同16日産廃午前1台午後2台、同25日産廃最終日現場内清掃」、そして「運転開始日平成30年2月1日」と書いてありました。どうやら、年内に構内の不要物を搬出し、年明けも残工事と調整運転を続け、来年2月1日から運転開始(運開)に入る模様です。
まもなく関電工の担当者がやってきて、「お疲れ様です。本日はバイオマス発電所の見学会に参加していただきありがとうございます。希望者がかなりあったため、全員が参加できるように調整しました。そのため人数が多いので細かい説明が行き届かないかもしれないが、ご容赦願います。全体で45分程度での見学会を予定しています。その中で都度聞きたいことがあれば、お聞かせください。細かな説明はシロタのほうから行います」と挨拶がありました。
続いてシロタ担当による説明が始まりました。
「この待合室から向かって右手に見える銀色の鉄骨の中に入っているのが前橋バイオマス発電所です。燃料は木質チップ専用の発電所となっています。燃料は基本的にはチップだけとなっており、化石燃料は基本的には使用しません。ただし非常時には一部使うこともありますが、通常は木質チップのみとなります。
能力は発電出力6750kwで、年間発電量は約4300万kw時となります。この近辺を例にとると旧宮城村の電力をこの発電所で賄えるイメージです。
そしてあちらの奥に見える白っぽい建物が燃料チップの貯蔵・製造所です。本日の見学会はこのあと、この2つの主な設備を回りながら説明します」
そして「この後、屋外に出て、一緒に移動してもらいますが、見学に際して3点ほどお願いがあります。1つ目は、まだ工事関係の作業員が何人もおり、そういった場所では作業中なので歩きにくいことがあり、ご容赦下さい。2つ目は、手前の方は砂利道になっており、足元の悪いところがあるので留意ください。最後にもう1点は、構内での写真・動画等の撮影は遠慮していただきます」と、情報秘匿体質の関電工らしい注意コメントがありました。
さらに「発電所では階段で2階部分まで上がっていただきますが、階段を上がるのが大変だというかたは、別途行程で対応させていただきます。あくまでも発電設備なので急な階段もあり無理せずに、安全に注意して見学してください」と注意喚起がありました。
そして、「一人1着ずつ防寒着を用意したのでよかったらお使いください。ほこりなどで洋服が汚れないようにするためにも使っていただきたいと思います。また、ヘルメットは必ず着用するようにお願いします」とのアドバイスもありました。
そのあと、(赤城の自然と環境を守る会の)会長さんから次の質問が投げかけられました。
「先日12月7日に、私が関電工の本社まで行って森戸社長と前橋バイオマス発電の野本社長に要望書を渡したがその回答は知っていますか?」
すると関電工の担当者は「(要望書を)いただいていることはうかがっています。まだ、今日の見学会は一般住民向けレベルの見学会なので、それ以上はわかりません」と答えました。どうやら地元市民団体向けの見学会開催について関電工は積極的ではなさそうです。
「荷物はすべてお持ちいただいて見学をお願いします。寒い中、45分のコースで案内しますので暖かい格好でお願いしたいと思います。荷物はできれば車のほうにしまってもらい、忘れ物無いようにお願いします」という声に促されて、見学が開始されました。
ボイラの銘板を見ると、「富士コンストラクション」と「三菱日立パワーシステムインダストリー」の文字が見えました。どうやら、前者がボイラの組立据付工事をおこない、後者が設計と機材調達を行ったようです。(注:両社のデータは記事の末尾参照)
最初の見学場所はチップ工場からでした。「足元が砂利道なので気を付けて」と言われながら歩くと防音壁が見えてきました。参加者から、「防音壁の工事はこれでおしまいなのでしょうか?上のほうは空いていますけど」と質問がでました。すると関電工は「設定では高さ4mですが、まだ上に足せるようにしています」との回答でした。どうやら、今後、実際に本格稼働させてみて、さらに騒音レベルがオーバーしてしまう場合は、壁の上にさらに防音板を継ぎ足そうというつもりのようです。いかにも付け焼刃というイメージがしてきます。

↑管理棟・台貫↑
そして、チップ工場に到着しました。関電工の担当から「こちらの後方の建物は燃料チップ製造所の管理棟です。入ってくるチップあるいは木材の管理を行う施設です。こちらの緑色の鉄板の部分が台貫です。トラック1台ごとのチップあるいは丸太の重量計測、入りの管理をきちんとやっています。重さを軽量するときに併せて、こちらのポールに付いている機器が放射線の測定モニターです。台貫で重さを計測中に有意な変動があるかどうかを計測します。大きな変動があった場合には、よろしくないチップあるいは丸太なので中には入れずにそのまま帰ってもらうという対策をとります」と説明がありました。






↑管理棟↑






↑計量装置(台貫)↑
ここで参加者から「(放射能を検知すると)どこでアラームが立つのでしょうか」と質問したところ、関電工は「発電所の管理室の中の中央管理室です」と答えました。
さらに別の参加者からは「間伐材でチップを搬入する時は、トラックの荷台の外側は鉄板で覆われているのだから、(放射能が)検知できないのでは?」と質問がありました。関電工は「それはないと思います。大丈夫」というので、「どうやって確認したのですか?」と念押したところ「鉄板では放射能は遮蔽できないので」と関電工の担当が回答しました。
後方にあるモニタリングポストを見ると、「0.045」という数値が表示されていました。これで施設構内の空間線量を計っているようです。関電工に説明よると、「あれの3倍に振れたら(入りを)止めます。今、0.05なので、あれが0.15になれば入れないということです」なのだとか。
また、トラックが出ていく時にも台貫で計測し、入って来た時の重さとの差で、搬入した木材の量を測るそうです。(注:これは見学会の最後のほうで、関電工の別の担当者から否定された。搬入トラックは1、2回台貫を入りと出で重量差を測るだけで、あとはナンバー読み取りだけで正味重量を自動計算するため、出るときはフリーパスなのだとか。これでは中から何を持ち出しても自由自在ではないか)
参加者から「40ベクレルについては、放射能はこれでは測れないのではないでしょうか?」と質問が出ました。40ベクレルのような少ない放射能の量を測ることが困難に思えたからです。すると関電工は「ここに運ばれる前にゲルマニウム半導体でサンプリング計測してそこで40ベクレルを検知すれば、そこの土場からは外に運ばせないという対策を取っています」と参加者の質問の真意をはぐらかして答えました。本当にそのやり方で大丈夫なのかどうか、参加者には判断できませんでした。
なお、放射能の測定のため、台貫の上で2分程度ここにトラックを止めるのだそうです。なお、モニタリングポストは0.04と0.05の数値を示しており、事務所の南側20mの地点に設置してあります。また、防音壁の裏側に排水溝が設けてあります。






↑作業用建物兼燃料貯蔵庫↑
次に燃料チップ製造・貯蔵施設に移動しました。関電工からは「こちらが燃料チップ製造所・チップ貯蔵エリアです。入って来た木質燃料は、台貫で計量した木質チップはすべてこちらに一度貯蔵します。今ご覧いただいている木質チップの量はおおむね定格運転した場合、1日強程度使用する木材の量となります。それから、チップのほか丸太の形で燃料を搬入するときは、この外側に積んでおきます」と説明がありました。参加者から「破砕はこの中でやるのですか?」と質問があり、関電工は「はい。でも、まだ今は破砕については調整が済んでいません。当面の間、チップ化する作業はここで行われません」と答えました。

↑燃料乾燥装置(脱水プレス機のこと)↑
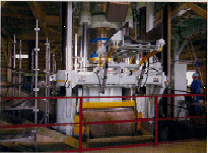
↑燃料乾燥装置(チップのプレス中)↑

↑燃料乾燥装置(チップのプレス機)↑
※当会注:見学会参加者によれば、実際のチップの脱水プレス機の塗装色は緑色であり、上記の写真はどこか別の施設を撮影した写真を流用している可能性がある。
参加者から「当面とは具体的にいつごろまでのことを指しますか」と質問がありました。関電工は「私からは申し上げられません。最終的にはここに入れますが、防音対策をとったあとになります」と答えました。確かに、チップ貯蔵施設はよく音が反響します。これでは騒音がスピーカーのように増幅して今います。こうしてしゃべっている声だけでもすごい反響音がします。
参加者が「破砕する場所は?」と訊くと、関電工は「(建物の)中でやります」と答えました。しかし、実際に破砕機を入れて稼働させてみた場合、どのくらいの騒音になるのかわからないため、防音壁の上を開けておいて、必要に応じて高さを継ぎ足す対策をとるようです。すなわち、現在の防音壁の高さは計算値にもとづく基準だが、将来的に余裕を持たせないといけないのでこのように上を開けておいてさらに壁を高くできるようにしているのだそうです。
関電工いわく「計算値はありますので、ご不満はあるかと思いますが、これでしばらく騒音測定をさせていただきたい」ということです。発電所の稼働時の騒音レベルをみたうえで、そのあと、破砕用のチッパーを稼働してみて、結局あとで同時稼働になるので、その結果を見て防音壁の高さを最終的に決めるようです。関電工としては柔軟な対応ぶりをアピールを演出したいようですが、言い換えれば付け焼刃的な対応という見方もできます。




↑貯木場↑
貯木スペースについて参加者から「最大で3日分しか置けない感じがしますけど?」と聞かれた関電工は「MAXで5日分くらいだと(トーセンが)言っていました」と答えました。参加者は「チップは何日分ぐらいを1日でできるのですか。稼働時間は?」と質問すると、「フル稼働すれば1日分といってもスペックとしてはもう少し余裕があります。要するにチップは大量につくっておくことはしません。1日ちょっとの分くらい」なのだそうです。なお、チッパーは現在、県内各地の森林組合や素材協の土場で稼働中のようです。参加者からチッパーの稼働場所を訊かれた関電工は「わからない」としらばくれていました。
次に乾燥施設に来ました。3億7500万円もする脱水プレス機ですが、搬入される木質チップのすべてをこのプレス機にかけるわけではなさそうです。含水率の高いチップのみ、プレス機で圧縮処理をして水分を絞り出して乾燥させてからボイラに送ることになります。なお、プレス機は諸々調整中で、まだ稼働状態にはなっていないとのことです。そのため、ここにあるチップは渋川で加工した水分量のたかい端材をそのまま搬入しているそうで、しばらく保管しているうちに含水率が低くなるとのことです。であれば、プレス機は不要なのではないでしょうか。
それ以外の木材はチッパーで粉砕するわけですが、現在、チッパーの姿は構内には見当たりませんでした。移動式のため、おそらく県内北部の沼田地域あたりの土場で稼働させている可能性があります。そこで丸太を砕いたチップがこの施設に持ち込まれているようです。しかし、前述のとおり関電工は稼働場所について口をつぐんでいます。
木質燃料の含水率は都度簡単に測定可能とのことです。また、生木をそのままプレス機にかけることはないとの説明です。プレス機にかけるのは、含水率の高い製材の端材だけで、製材時に水をかけてカットされた端材はビショビショになっているので、そのままプレス機に投入するのだそうです。
したがって、製材のチップと間伐材のチップは混ぜることはなく、混ぜるのは、ボイラ投入前のコンベアの段階で混ぜるのだそうです。
再度参加者が、脱水プレス機の稼働開始時期を関電工に尋ねましたが、「今の段階では、なんとも申し上げられません。準備が整い次第というしかありません」と言葉を濁しました。やはり実用に課題があるのかもしれません。
関電工は「次、先に行きます」と我々参加者らをせかせました。チップ貯蔵施設の天井を見ると火災探知機の有無が分からないので聞いてみると、あるのだそうです。しかし、煙感知器ではなく熱感知器のアラームだと言います。また、参加者が「脱水機はトーセンですか?」と聞くと、関電工は「燃料会社です」と返事しました。
参加者が「脱水した水の量や(処理用の)浄化槽の水量とかはどれくらいでしょうか?」と訊きました。関電工は「1日の処理能力は45トンの水を処理する能力は有しています」と答えました。
黄色の筒のようものは燃料工場のほうから発電所へのベルトコンベアだそうです。このベルトコンベアは密閉型で屋根がついています。だから、風でも飛散せず、雨天でもチップが濡れる心配はないということです。チップのベルトコンベアへの投入はフォークリフトになっているようです。





↑フォークリフト↑
次にボイラの視察となりました。10段くらいの階段は傾斜が急なため、足元が悪いとして、上に上がると大変な人は下のほうを迂回して案内されました。二次加熱器とか一次空気などの銘板が見えました。すると関電工の担当者が説明を始めました。
「それではこれが発電所のボイラです。ボイラは燃料チップをあちらから中に投入し、燃焼することにより高温高圧の蒸気を作るのがボイラの役割です。このボイラは流動床式と言って、特徴としてはボイラの火炉の底の部分で約30トンの砂が入っていて、下から一次空気とよばれる燃焼用空気を吹き付けて、バブリングとよばれる、つまり常にボイラの中の砂を巻き上げてやることにより、砂が常に回っている感じとなります。その中に燃料チップを入れて無駄なく燃焼させ切るのが特徴です。その他、このボイラの火炉の部分については、前後・左右・上下に水管という水の入った管があり、その中の水が熱を吸って蒸発して高温高圧の水蒸気になります。それを6面にきちんと張り巡らしてあるため、発生した熱をできる限り無駄なく吸収させることができます。こちらが発電所のボイラです。タービンは向こう側にあります」
参加者からタービンの騒音について質問がありました。関電工は「回転しているとき、50-60デシベルくらいになります」と言いました。なお、ボイラ施設から発生する音の一番の原因は水の流れる音だそうです。なお、関電工によれば「施設境界における夜間の騒音規制は45デシベルなので十分に達成しています」と鼻高々でした。
また、参加者が、「この燃焼室では燃料チップは上から落とす形になるのですか?」と質問したところ、関電工の担当者は「そうです」と答えました。参加者が「あれほど落差が必要なのですか?」と質問したところ、関電工は「もうしわけありません。技術的なことはちょっと(わからないので)」と言いました。一般住民への見学会だとタカをくくっているのでないか、と思われる対応です。
参加者から、「あそこは何が出るのでしょうか?煙突はわかるのですが」と質問がありました。すると関電工は「あそこは脱気器といい、缶水から溶存酸素を取り除くためのものです。酸素があるとボイラの腐食の原因となるため、蒸気と缶水を触れさせて中に溶けている酸素を取り除くための装置です。そのためにごく微量の蒸気を使っています」と答えました。参加者は、「それによって排水として外部に出てくるのでしょうか?」と質問したところ、関電工は「いいえ、取り除くものは酸素だけなので、一緒に空気中に放出されてしまいます」と言いました。
参加者からは「ここからずいぶん煙が出ますね。このエルボウ(曲り管)からでしょうか?」と質問がありました。すると関電工担当は「大気放出弁があり、起動停止の時に一部開けるところがあります。出ているのは単なる蒸気です」と答えました。参加者は、試運転時に大量の白煙が出ていることを知っているため「ここからずいぶん(白煙が)出ていましたが・・・」と質問したところ、関電工は「試運転なのでずいぶん開けたり閉めたりするので・・・。通常は締めています。だから実際に運転しているときは(白煙)はでません」と言いました。
また、最近、試運転時にバイオマス発電施設から漂ってくる異臭に関連して参加者から「点火時の助燃剤として重油を使うのですか?」と質問したところ、関電工からは「重油で点火するのでなくて、灯油を使います。」と返事がありました。参加者から「その排ガスも出ますよね?」と質問された関電工担当者は「火を点ける時は小さなバーナーを使います。石油ストーブのようなものです」と言いかけましたが、それをさえぎるように、関電工の案内者は「はい、すいません、次に移りますので」と述べました。
続いて中央操作室に移動しました。関電工から次の説明がありました。
「営業運転を開始すると24時間運転になります。こちらには2名4班の体制を組み、昼夜2交代勤務で、常時運転員が常駐することになります。発電所の各パラメーターに関する数々のセンサーはこちらで監視ができるようになっています。万一、異常等々が発生した場合は所員により適正に対応します。壁に付いているテレビ画面が、燃料チップの受入ホッパーの映像で、あちらからチップをベルトコンベアでボイラに投入しますが、その貯留状況もここで管理しています」
参加者から「監視カメラは何か所あるのですか」と質問がありました。関電工は「上の受入ホッパーを見れば、あの1か所だけです。なお、(ボイラ燃焼室内の)燃焼状況は4か所で見られます」と回答しました。
関電工は次にタービン建屋を案内しました。急な階段を手摺につかまりながら降りていきました。さっそくタービン建屋の説明が始まりました。
「発電に使った蒸気は、基本的にはボイラにまた戻る仕組みになっています。タービンの後ろに復水器があり、復水器に蒸気を当てることにより温度が下がると水になります。復水器の中に冷却水を送り、冷却水を冷やすという原理になっています。こちらのタービン建屋の中央にある緑色の箱のような機械がタービンです。中には羽根車が入っています。先ほどのボイラで発生させた高温高圧の蒸気をそこに送り付けて、羽根にぶつけて羽根を回転させます。その生じた回転エネルギで手前の発電機が回されて約6750kwの電力を発生させるという形になります。こちらにタービンに入ってくる高温高圧の蒸気は、温度が約475度C、気圧が約6メガパスカル、大気圧の60倍という高温高圧の蒸気が入ってきます。タービンから出ていく時の温度は約50度C、圧力はほぼ0気圧になります。それだけのエネルギがとられて、それが6750kwの電力を生む源になります。タービンで仕事して低温低圧になった蒸気は、今度はタービンの中に復水器という設備があり、そこには別系統から送られてくる冷却水で冷やされて再び液体の水に戻されます。低温の水に戻り、またボイラに入り加熱されるというサイクルを繰り返します」
参加者から「内側に貼ってあるのは防熱材料なのでしょうか?」と質問があり、関電工は「防音材です」と答えました。また「失われる水分は1割?2割?どれくらいですか?」と参加者が質問したところ、関電工いわく「タービンの中では水分は失われない」とのことでした。また「排水はどれくらいですか?」との質問には、「タービンでは排水は出ない」として、「このあと冷却塔を見学しますが、蒸気を冷やすのに使った冷却水が外に排水されます。後で説明します」との説明でした。
参加者から「高温高圧なので配管をステンレス鋼というか、高温高圧対応の材料を使っているのですか?」との質問に、関電工は「材質にはステンレスの配管は使いません。普通鋼です」と答えました。
次にタービン建屋から外に出て、冷却塔へいきました。
「こちらの大きな黒い箱のような設備が冷却塔と呼ばれるものです。先ほど申し上げました復水器で蒸気を水に戻すために使った水が熱を受け取って温度の上がった水となってこちらに流れて来るので、それを冷却塔の中で吹きかけてやり空気と熱交換をさせて、また冷却水の温度を下げて、また復水器に戻るというサイクルになっています。車のラジエータと同じです。よくビルの屋上とかにこういった設備があると思いますが、そういったものと基本的な原理は同じです」
参加者から「この発電所に入ってくる水は地下水と言いましたか?」との質問に、関電工は「はい、地下水です。1時間当たり65トン、それが24倍なので、すいませんちょっと。1000・・・」と答えました。(当会注:65×24=1560となる計算です)
参加者と関電工のやり取りは続きます。特に水については周辺の住民にとって非常に重大な問題を抱えているからです。参加者の懸念事項と関電工の回答を詳しく見ていきましょう。
―それがサイクルするとおっしゃいましたよね?
「はい」
―どんどん65×24(トンの水)が地下水から入っているのですか?
「それはまず、地下水を汲み上げさせていただいていますが、だいたい1時間当たり65トンです」
―循環しているとおっしゃいましたよね?
「循環しているのはこの中ですね」
―では常にどんどん、地下水を使っているわけではないのですか?
「違います。1時間当たり1700トンの水がぐるぐる循環しています。24時間汲み上げるんで」
―そんなに使うのですか?水を入れるということは、同じ量が出ていくことでしょう?無くなるから出るんでしょう?
「・・・」
―そんなに水を使って、井戸水を使っているのでしょう?はっきりさせてもらいたいです。
「循環水系統ですが、1時間1400トンが循環していて、冷却等のところで一部僭越として奪われるので、つまり、蒸気として蒸発するとそれが半分の30トンくらいあるので、その減った分を補充します。残った水にもミネラルが含まれているので、あまり循環するとミネラル分が濃くなりすぎるので、残った分も半分をそのまま放水します。なので、65トンを1時間入れて、30トンは蒸発で大気中に出て、残りはブローという形で処理して排水する。もちろん水質チェックしてから排水します。
―65トン入って、30トン蒸発して、残りは排水というけれども、循環するのが無くなるのでは?
「入りと出ではそうなんです。300トンくらいの水をプールに持っていて、このプールの中から建屋の内外を回っているうちに、1時間あたり30トン(の水)が無くなり、途中で30トンが系外に排水として排出されます。全体の水の量は1700トンで、このうち30トンが蒸気となります」
―それはもう予め大丈夫だと確認しているのですか?地下水を使って生活している住民も多数いるので、水が出なくなってしまったよ、という心配はないのでしょうか?
「はい。近隣の井戸の深さも調べてそれよりもっと深い層から採水しており影響はないと考えております」
―影響が100パーセントないとは確実に言えないでしょうから、これが稼働した時、もし苦情があったらどうするのですか?
「適切に対応させていただきます」
―適切に、とアバウトに言われても、生活している人は水がないと生きていけないので。
「それは非常に大事なことだと、我々も認識していますので、はい」
―毎日1500トンくらい水を汲み上げることになりますよね?
「はい、そうなりますね」
―1500トンといえばかなりの量ですね。
「これくらいは普通だと聞いていますので。当社の実績で」
―そんなに大量の水を使ってわざわざ木質チップを発電するなんて、無駄がいっぱいあるんでは?
「エネルギという観点では、水を使うのに要するエネルギより多くのエネルギを発電していますので、エネルギ源という観点では1を超える設備であると考えています」
―だけど木を燃やしてエネルギを作るといいながら、他のエネルギも水も使っていますよね?」
「使っていますが、発生する分に較べたらわずかです」
―僅かとか、そういうイイ加減というと失礼だけど、昔からここより先に住んでいる人ばかりなので。では、水が出なくなったら苦情を言ってもいいのでしょうか?(その場合)うちのせいではないと言うのではないでしょうね?」
「ご連絡いただければ、きちんと調査等々をしたうえで、適切に対処する所存ではございます」
―だけど今、雨の量も少ないそうなので、このへんは渇水の心配があります。なので、こんなにこっち(の事業)に水を取られたら、とても心配です。適切な対処といっても、では(そのような事態の際には)水をくれるのですか?
「そういうケースも考えられます。必要であれば、この発電所を止めざるを得ないことということも有り得ます」
―そんなことをしますか?
「その話をここでしても長くなるので、今、プラントのほうの説明をしているので、急がせてもらえますか?」
なるべく早く見学会を切り上げたい様子で、関電工は参加住民らに次の場所への移動を促しました。
参加者からは「300トンのプールがあれば(冷却用水を)完全循環できると思いますか、ダメですか?せっかくの水を捨てることはないと思いますが」と提案がありましたが、関電工は「増減があるのでやはり運用上、バッファー・タンクがないと厳しいので」などと意味不明の回答をしてお茶を濁そうとしました。
それに対して参加者からは「捨てるということをしなくていいのではないでしょか?無くなったらその分だけ足せばよいのではないでしょうか?」と更に突っ込んだ質問が出ました。すると関電工は「それはさきほども説明したように、地下水のミネラル分の濃縮が発生するので、そうすると配管等に悪さをするので、ミネラルの濃度を一定値以内に保つように(水の)入れ替えをする必要があります」と説明しました。
参加者は「それは排水しても問題はないのですか?飲んでも影響はないのでしょうか?(入れ替えは)機械を守るために?」と言うと、関電工は「はい、そうです」と、環境よりも人命を重視する返事をしました。
それを聞いた参加者からは「濾過は可能ですか?」と少しでもミネラル分を濾し取って、貴重な地下水の排水量を少なくするための方策について質問が出ました。しかし、関電工の返事は「濾過ではちょっと・・」という連れないものでした。「技術的に難しいのでしょうか?」との質問にも「はい」と答えた後、さらに「ヒトにはミネラル分はよいのですが、機械にはちょっとダメなもので。ミネラルウォーターというのは、プラントにはよくないので」として、地元や周辺の住民の生活環境よりも、機械の稼働状況の保全のほうを重視している姿勢を示しました。(当会注:通常は、冷却水量の低減をできる限り図るため、ミネラル分の増加した排水をさらにマイクロフィルターや逆浸透膜などにかけて、さらにミネラル分を除去して冷却水をリサイクルし、環境負荷を最小限にするのが適切なエンジニアリングです。しかし、住民の生活環境や周辺の自然環境の保全より、営利を重視する関電工は、そうした対策を取るつもりは毛頭なさそうです)
さらに参加者からは「地下水のミネラル成分はきちんと計測したのですか?」と質問が出ましたが、関電工は「はい。ただしボイラに影響あるものだけですが」と答えて、ここでも自分のことしか考えていないことを露呈しました。
粘り強く質問したい参加者の意向と裏腹に、関電工は「では、次の説明に入らせてもらいまーす」といって、それ以上の質問を遮りました。
「最後に排気関係のご説明をさせていただきます。ボイラでチップを燃焼させた後、当然、排気ガス等々が発生します。木質チップの重量のうちの4割程度は水分なので、それを燃焼させることで水蒸気や、或いは木そのものを燃やしたことによって発生する煤塵、そういったものがボイラから発生します。最終的にはこの煙突から、高さ30mありますが、ここから排出させていただきます。その前段階として、手前の大きな箱のようなものをバグフィルターといいます。こちらのフィルターの濾紙のようなものを通すことによって煤塵関係のものを濾し取ってやる設備です。あの箱の中に長さ6mの筒が約448本、面積にすると1300平方メートル程度になります。それだけのフィルターが入っています。そちらでチリを濾し取っています。フィルターの部分でチリが溜まりますが、定期的に逆洗浄、定期的に空気を逆に流して、下側から筒のすぼまっているほうに煤を落とし、青いコンテナのほうに溜めるという流れになっています。燃焼させた後の灰は乾燥でカラカラになっており、空気で飛散し易いので、その上に灰加湿器が見えますが、そちらで水分を加えてやり、飛散することの無いようにして、コンテナに溜めるようになっています」
さっそく参加者から質問が出ました。
―フィルターは定期的に交換するのですか?
「検査のたびに判断します」
―上のほうは茶色くなっているがあれは何ですか?
「出口温度が165度くらいあって、ちょっと熱の部分があのような色に変色しているだけです。純粋な熱です。なお、(バグフィルターの箱の)外板の化粧板はステンレス製です」
―フィルターにかけるのは飛灰だと思いますが、主灰はどうするのですか?
「流動床(式ボイラ)の特徴で、主灰は殆ど出ません。全部完全燃焼して主灰は出ないのです。(出るのは)飛灰のみです。燃焼灰はすべてこのバグフィルターを通します。灰以外の石だとか釘だとか、異物については、別途取ります」
―これはエア洗浄の灰ですか?
「はい。フィルターに付いた灰はフィルターに残るので、下から空気を当ててやると排ガスの下のほうに落ちます。あそこに2つ、一つの箱に同じものが2つに分けて入っているのは、単純にひとつだと灰の量がたくさんになった時に、スムースにいちおう通れないので、2つ用意しています。中には1対になっている長さ6m、直径15センチのフィルターが448本入っており、定期的に下から空気を吹き上げて、灰が下に落ちで、それに灰加湿器で水を吹きかけて、最終的に青いコンテナに行きますが、今日のように風が強い日でも、灰が舞わないような設備にしています。すべて灰は青色のコンテナに集約しています」
―で、フィルターを通ったものは煙突に抜けているということですか?
「そうです」
―煙というと上にいくと思うが、いったん下に行ったり上から下に行ったりしているのは?
「煙の方向は配管のルートで上に行ったり下に行ったりいろいろしています」
―設計的なものですか?
「そうです。あと、煙突に向かって上下すると灰がくるのに遅いことがあり、実は、煙突の少し手前に誘引の通風機というものがあり、煙突のほうに全部引っ張るような風を起こすことで、すべて軌道に乗るような設計をしています」
―あれがないと更に煙突をさらに高くしなければないのでしょうか?
「そうです」
ここでもまた、参加者からのさらなる質問を遮るかのように、関電工の案内者の声が聞こえました。「すいません。時間的に時間が押してきているので・・・」それにも拘らず参加者からは不安や疑問が関電工に寄せられ続けます。
―灰加湿器の働きは?
「流動床には30トンの砂が、800度まで上がるので、基本的に(投入された木質燃料は)完全燃焼させて灰となり、燃えないものは外に出られないしくみになっています。灰は外部に取り出すため、取り扱いの際に水を加えて埃の発生を抑制します」
―点検とは年間何回やるのでしょうか?
「定期点検は1年に1回予定しています。法定点検でボイラのまわりやタービンのまわりは、2年に1回、あるいは4年に1回、法廷点検にならって、期間は20日から1か月くらいかかります」
―そんなに(点検に時間が)かかるものなのですか?
「やはりボイラの点検は、全部を止めて配管が全てしっかりしているかどうかをチェックします。そのため、1年に20日間程度間違いなく止めます。ボイラの場合は2年に一度の周期なので2年目は40日くらい(運転を)止めます」
―毎年、一般検査で20日くらい止めるのですか?
「我々としては、なるべくそこを短くしたいが、法定で決められたものについてはしっかりとやらないといけないので、それなりの予定をしています」
―運転を止めた後、再開する際に重油で火を点けるのでしょうか?最初はこれだけですか?
「最初にボイラを立ち上げる時は非常に冷えているので、いきなりチップを入れても燃えません。バグフィルターの手前にタンクのようなものが見えます。煙突と大きいフィルターの間に小さいタンクがあります。5000リットルと書いてあるが、あそこに灯油が入っています。そこから灯油を送り、(ボイラの)起動バーナーで砂を最初に200度Cまで温めてあげます。200度Cまで上がるとチップを燃やしても、少しずつ燃えることになるので、起動するときのみに使用する設備になっています。(灯油タンクをボイラの)燃焼場所から遠い場所に設置しているのは安全のためです。あまり近いと引火など火災のおそれがあるので」
―事務所の浄化槽というのは、さきほどの45トン(の浄化槽)とは別にあるのですか?
「あくまで、生活排水のものはまったく別です。あれ(45トンの浄化槽)はあくまでも脱水チップ用です。まだ稼働はしていませんが・・・」
―汲み上げる水の量がやはり心配です。
「たとえおひとかたであってもご連絡をいただければ対応します。一応ここの代表電話も入っているし、連絡先に携帯のも入っているのでどちらかでも対応はします。水の汲み上げ量が心配だとおっしゃっていますが、それなりに事前のボーリング調査を何か所もやって埋蔵する水の量は把握していますので、そのへんは・・・」
―だってここは何年も稼働するのでしょう?今後の展望というのは、今までのようなわけにはいきません。そうでなくても水が足りない傾向になっている事態の中で事業をやろうとしているんですよ。そういうことを考えると、水の不足について応対してもらえるのでしょうか?いままで井戸が出ていたところが、出なくなったらどうするのですか?
「まあ、ご連絡いただければきちんと対応します」
最後に、入口の燃料木材の受入れ場所に向けて歩く途中で、早く見学会を終了させたい関電工は、早くも参加者からヘルメットを回収するとともに「つまらないものですがお餅を用意させていただきました」と、参加者に手土産を配り始めました。
しかし参加者からは全般にわたる質問が出ました。
―搬入木材の放射能の管理はモニタリングが十分なのでしょうか?
「そういったところにつきましては、入ってくる木材に含まれる放射線の量は基本的に計測します。そういったことで放射線量の高いものは受け入れないという対応をします。それはしっかりやります。そうですね。ご心配な点が何かあれば連絡ください。よろしくお願いします」
―貯木はここだけですか?アスファルトの上はすべて貯木場ですか?
「基本的にはチップの状態であればあの中です。それで、防音壁の前のほうに丸太を積んで、少しでも防音軽減効果を狙って積むことも一応考えています。この(防音壁の)板のままでよいのか、木があのように積み重ねれば軽減するのかどうか、それを確かめてからにしたい」
―ここは浸透性のアスファルトでしょうか?
「えーと・・」
―水はどこから流れていくのでしょうか?アスファルトの上を通った水が入るのですか?
「基本的には雨水を集めているところだと思います。弁で切り替えて3分岐になっています。水を散らばせています。深さは2mくらいあります。結構な深さです。それも計算値でやっていますので。で、ヘルメットも無い状態なので、ここまででご遠慮ください。またいろいろありましたら、またご連絡ください」
―池に入るようになっていないですね。ここを抜けるように作っているだけのようですが、これでは全然浸透しないね。ところであの木はどこからの持ってきたのでしょうか?
「あの木は、具体的にここにあった木というのは、まず群馬県内の県の森林組合さんから持ってきただいた木があちらに貯留されてあります」
―違いますよ。トーセンが持ってきたって聞いていますけど?
「はい、すいまでん。あそこに見えているのが森林組合で、あちらの裏側に置いてあるのはおっしゃるとおり、あの丸太は株式会社トーセンさんの群馬県にある土場から持ってきたものです」
―なんか、(トーセンが)借りていた土地がもう返さなければならなくなったからここに持ってきたと言っていましたけど?
「はい、そうですね。裏にあるものはトーセンの丸太をこちらに持ってきました」
―日光のほうから持ってきているのではないでしょうか?
「群馬県内の木でやっているので、そこは証明書で確認しました。マニフェストで、具体的に間伐材で県有林の場合は売買契約書でトーセンさんが何とか森林組合から買ったというマニフェストがあります」
―それはチップであってもどこの木が元の木だというのがわかるのでしょうか?牛肉のように出身地が?
「はい、チップの状態であのように混ざってしまうと何がなんだがわからなくなりますが、チップで入っても、大もとの木がどこの木でいつ買い付けたというのは、全部分かるようになっています。それが再生可能エネルギ法によるFIT認定で必ず守らなければなりませんので、そちらで確認が可能です」
―あの丸太は重量を測るだけで、(台貫に)乗っかるところだけでいいのですか?
「えーとですね。ちょっとのシロタのほうが、毎回(トラックの出入りごとに台貫に)アップ、ダウン(ごとに係争する)と説明したのですが、通常はここに入ってくるトラックはだいたい決まっているため、実は、車でナンバーは1回、2回で登録するという形をとっている燃料の会社でありますので、最初は1回、2回くらいしっかりと重さを測っておけば、(その後は)その車が来れば、その車の重量何トンだと分かれば、このナンバー(トラックの正味重量は)2トンだというふうにわかるからです。その後は、いちいち出るときの重量は測りません」
―だけど例えば、燃料のガソリンタンクが満タンか空かは、誤差のうちなのですか?
「すいません、そこまでは・・・というので、逆に言うとそれは燃料を買う我々側とトーセンさんの間で、それは我々もちょっと懸念するところですが、今のところそこを確認する技術はなくて・・・」
ここでとうとう痺れを切らせた関電工は「ではすいません。あの、作業がまた始まってしまうので、申し訳ありません。年末の忙しい時期なので本当に恐縮です。短い時間で申し訳ありません。名札と防寒着をまだ返却されていないかたがいらっしゃれば、お願いします」
最後に参加者の皆さんから、この施設が建設された場所の勾配が急であることの感想が述べられました。これでは貯水池に入らず、周辺や下流に水問題でなにか問題が及びそうだということで、懸念の声が相次ぎました。
また、木質燃料は間伐材のチップと製材端材のチップの2種類に区分されて保管されていましたが、製材端材は乾燥済みのようでした。脱水プレス機は排水の浄化槽の工事中で、まだ稼働させていない、というより稼働できないことも明らかになりました。
このほかにも、ボイラの騒音や、冷却装置からの騒音、燃焼灰の扱い等々が2月1日からの運転開始を前に、懸念材料として参加者から指摘がありました。
さらに肝心のチッパーなどはどこにあるのか見当たらず、他に転用されているのではないかとい指摘もありました。





↑移動式チッパー、トレーラー・グラップル↑
**********
■こうして12月23日の午後に開催された施設見学会では、当初45分の予定でしたが、参加者の皆さんはいろいろな懸念や不安を含めて多くの質問を行いました。そのため予定を30分ほどオーバーしましたが、関電工側では、しきりに早く切り上げようという姿勢が目立ち、真摯に住民の皆さんの抱く懸念や不安の払しょくを最優先にするという対応がいまひとつだったのが気になります。
また、12月22~23日の見学会は、一般住民向けであり、この問題に当初から取り組んできた住民団体向けの見学会は別途必須です。
このことについて見学会でも参加者から関電工に要請の声が伝えられましたが、12月27日に住民団体のメンバーに対して、「12月4日付の関電工社長宛の住民団体向けの視察会開催要請について、見学会は計画しない」と口頭で回答がありました。
これは以前、関電工が住民説明会で、3段階での見学会の開催を約束したことと明らかに反します。
※住民説明会における関電工の見学会開催に関する約束と現時点での進捗状況:PDF ⇒ 20180108wj.pdf

■住民団体の皆さんは、このことについて、前橋市長にも強く申し入れていますが、12月28日付で山本市長からの回答書が届きました。内容は次の通りです。
*****前橋市長からの回答書*****PDF ⇒ 20171228os.pdf
平成29年12月28日
赤城山の自然と環境を守る会 横川 忠重 様
赤城南麓の環境と子供達を守る会 井上 博 様
前橋市長 山 本 龍
(環境政策課)
バイオマス発電事業について、本市へのご要望事項について回答いたします。
まず、事業者・行政・守る会の三者による話合いについては、各者の合意が前提となることから、各者少人数による話合いができるかどうか事業者に対し提案しているところであります。
環境配慮計画の内容に関しましては、事業者に自主管理基準をしっかりと守っていただけるよう、様式を整え報告いただけるような取り決めについて事業者と協議wてまいりたいと考えております。
事業者は、各種の環境モニターを設置し監視を行うなど環境に配慮した事業計画となっておりますので、まずは事業者に対しまして自主管理基準が守られているかを確認するとともに、大気関係、騒音・振動関係に該当する事項については法令に基づき対応してまいりたいと考えております。
**********
■このように前橋市は事業者である関電工に対して、地元住民団体との話合いについて申入れをしている様子ですが、いまのところ、何も具体的な進展は見られません。
また群馬県は、前橋地裁における裁判でも、県で定めた環境影響評価条例に基づくアセスメント実施について、相変わらず排ガス量を根拠もなく大幅に棒引きしたことについて、正当化する発言を繰り返しています。
さらに原価がせいぜい3千万円程度の脱水プレス機を、事業者であるトーセンと関電工らが出資する前橋バイオマス燃料というペーパー会社に対して補助金として3億5千万円(税抜き)もの金額を支払ったりしていることについても、請求書通りに支払っただけだとして、一向に精査をしようとしません。
引き続き、裁判所の法廷での攻防を通じて、なんとか環境アセスの実施と補助金の返還を事業者にさせるよう群馬県を相手取り、裁判に注力していく所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考URL「株式会社富士コンストラクション」↓
http://fuji-csr.co.jp/guide/company.html
社名 株式会社富士コンストラクション
住所 〒290-0043 千葉県市原市出津西1-2-10
設立 昭和42年7月28日
資本金 50,000,000円
建設業者登録 (般-11)第5386号、管工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、鳶工事
業種 火力発電ボイラー石油化学の各プラントの機器、鉄構造物、タンク配管等の据付保全工事
役員 顧問相談役 伊藤 幸雄
代表取締役社長 平井 誠
専務取締役 長岡 敏郎
常務取締役 小倉 雅彦
取締役事業部長 有馬 誠見
監査役 内田 稔
取引銀行 千葉銀行五井支店、京葉銀行五井支店
年間工事受注高 2,000,000,000円
従業員数 事務職員/6名、技術職員/50名、協力会社/250名(20社)、合計316名
※参考URL「三菱日立パワーシステムズインダストリー」↓
https://www.ids.mhps.com/
商号 三菱日立パワーシステムズインダストリー株式会社(Mitsubishi Hitachi Power Systems Industries Co., Ltd)
登録所在地 横浜市中区相生町三丁目56番1号JNビル
設立年月日 1961年(昭和36年)10月10日
社長 牧浦 秀治
資本金 10億円
株主 三菱日立パワーシステムズ株式会社(100%)
年間売上高 226億円(2016年度)
従業員数 約620名(2017年4月1日現在)
取引銀行 三菱東京UFJ銀行 横浜支店
保有資格 建設業者登録 特定建設業(電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業):国土交通大臣許可(特-24)第24597号、特定建設業(建築工事業):国土交通大臣許可(特-25)第24597号、特定建設業(清掃施設工事業):国土交通大臣許可(特-26)第24597号
ISO 9001 : 2015認証 登録番号 : JBA-005
計量証明事業 濃度(広島県知事登録 第K-29)
音圧レベル(広島県知事登録 第K-48)
作業環境測定機関 広島労働局長登録 34-30
本社 〒231-0012横浜市中区相生町三丁目56番1号JNビル
TEL:(045)227-4950
FAX:(045)227-7569
事業内容 ○産業用ボイラ・中小型火力発電プラント・地熱発電プラントの基本計画、詳細設計、 調達、建設、試運転
○既設プラントの改造工事、アフターサービス、保全工事
○メカトロ、コンピュータ制御装置の設計製作
○各種訓練設備・監視計測装置の設計製作
**********

↑2月1日から予定されているという稼働開始に向けて準備に余念のない関電工らによる亡国事業現場。↑

*****関電工の亡国事業見学会報告*****
近所のかたがたと一緒に最後の4回目の視察会に参加しました。
午後1時半から開始ということで、車に乗り合わせて入口のゲートを通り、坂を上ると施設に到着しました。最初に待合室に案内されました。

↑貯木場・作業用建物・燃料保管倉庫↑
壁にかかった予定表には、「12月6日産廃、同16日発電所北側フェンス修理、同16日産廃午前1台午後2台、同25日産廃最終日現場内清掃」、そして「運転開始日平成30年2月1日」と書いてありました。どうやら、年内に構内の不要物を搬出し、年明けも残工事と調整運転を続け、来年2月1日から運転開始(運開)に入る模様です。
まもなく関電工の担当者がやってきて、「お疲れ様です。本日はバイオマス発電所の見学会に参加していただきありがとうございます。希望者がかなりあったため、全員が参加できるように調整しました。そのため人数が多いので細かい説明が行き届かないかもしれないが、ご容赦願います。全体で45分程度での見学会を予定しています。その中で都度聞きたいことがあれば、お聞かせください。細かな説明はシロタのほうから行います」と挨拶がありました。
続いてシロタ担当による説明が始まりました。
「この待合室から向かって右手に見える銀色の鉄骨の中に入っているのが前橋バイオマス発電所です。燃料は木質チップ専用の発電所となっています。燃料は基本的にはチップだけとなっており、化石燃料は基本的には使用しません。ただし非常時には一部使うこともありますが、通常は木質チップのみとなります。
能力は発電出力6750kwで、年間発電量は約4300万kw時となります。この近辺を例にとると旧宮城村の電力をこの発電所で賄えるイメージです。
そしてあちらの奥に見える白っぽい建物が燃料チップの貯蔵・製造所です。本日の見学会はこのあと、この2つの主な設備を回りながら説明します」
そして「この後、屋外に出て、一緒に移動してもらいますが、見学に際して3点ほどお願いがあります。1つ目は、まだ工事関係の作業員が何人もおり、そういった場所では作業中なので歩きにくいことがあり、ご容赦下さい。2つ目は、手前の方は砂利道になっており、足元の悪いところがあるので留意ください。最後にもう1点は、構内での写真・動画等の撮影は遠慮していただきます」と、情報秘匿体質の関電工らしい注意コメントがありました。
さらに「発電所では階段で2階部分まで上がっていただきますが、階段を上がるのが大変だというかたは、別途行程で対応させていただきます。あくまでも発電設備なので急な階段もあり無理せずに、安全に注意して見学してください」と注意喚起がありました。
そして、「一人1着ずつ防寒着を用意したのでよかったらお使いください。ほこりなどで洋服が汚れないようにするためにも使っていただきたいと思います。また、ヘルメットは必ず着用するようにお願いします」とのアドバイスもありました。
そのあと、(赤城の自然と環境を守る会の)会長さんから次の質問が投げかけられました。
「先日12月7日に、私が関電工の本社まで行って森戸社長と前橋バイオマス発電の野本社長に要望書を渡したがその回答は知っていますか?」
すると関電工の担当者は「(要望書を)いただいていることはうかがっています。まだ、今日の見学会は一般住民向けレベルの見学会なので、それ以上はわかりません」と答えました。どうやら地元市民団体向けの見学会開催について関電工は積極的ではなさそうです。
「荷物はすべてお持ちいただいて見学をお願いします。寒い中、45分のコースで案内しますので暖かい格好でお願いしたいと思います。荷物はできれば車のほうにしまってもらい、忘れ物無いようにお願いします」という声に促されて、見学が開始されました。
ボイラの銘板を見ると、「富士コンストラクション」と「三菱日立パワーシステムインダストリー」の文字が見えました。どうやら、前者がボイラの組立据付工事をおこない、後者が設計と機材調達を行ったようです。(注:両社のデータは記事の末尾参照)
最初の見学場所はチップ工場からでした。「足元が砂利道なので気を付けて」と言われながら歩くと防音壁が見えてきました。参加者から、「防音壁の工事はこれでおしまいなのでしょうか?上のほうは空いていますけど」と質問がでました。すると関電工は「設定では高さ4mですが、まだ上に足せるようにしています」との回答でした。どうやら、今後、実際に本格稼働させてみて、さらに騒音レベルがオーバーしてしまう場合は、壁の上にさらに防音板を継ぎ足そうというつもりのようです。いかにも付け焼刃というイメージがしてきます。

↑管理棟・台貫↑
そして、チップ工場に到着しました。関電工の担当から「こちらの後方の建物は燃料チップ製造所の管理棟です。入ってくるチップあるいは木材の管理を行う施設です。こちらの緑色の鉄板の部分が台貫です。トラック1台ごとのチップあるいは丸太の重量計測、入りの管理をきちんとやっています。重さを軽量するときに併せて、こちらのポールに付いている機器が放射線の測定モニターです。台貫で重さを計測中に有意な変動があるかどうかを計測します。大きな変動があった場合には、よろしくないチップあるいは丸太なので中には入れずにそのまま帰ってもらうという対策をとります」と説明がありました。






↑管理棟↑






↑計量装置(台貫)↑
ここで参加者から「(放射能を検知すると)どこでアラームが立つのでしょうか」と質問したところ、関電工は「発電所の管理室の中の中央管理室です」と答えました。
さらに別の参加者からは「間伐材でチップを搬入する時は、トラックの荷台の外側は鉄板で覆われているのだから、(放射能が)検知できないのでは?」と質問がありました。関電工は「それはないと思います。大丈夫」というので、「どうやって確認したのですか?」と念押したところ「鉄板では放射能は遮蔽できないので」と関電工の担当が回答しました。
後方にあるモニタリングポストを見ると、「0.045」という数値が表示されていました。これで施設構内の空間線量を計っているようです。関電工に説明よると、「あれの3倍に振れたら(入りを)止めます。今、0.05なので、あれが0.15になれば入れないということです」なのだとか。
また、トラックが出ていく時にも台貫で計測し、入って来た時の重さとの差で、搬入した木材の量を測るそうです。(注:これは見学会の最後のほうで、関電工の別の担当者から否定された。搬入トラックは1、2回台貫を入りと出で重量差を測るだけで、あとはナンバー読み取りだけで正味重量を自動計算するため、出るときはフリーパスなのだとか。これでは中から何を持ち出しても自由自在ではないか)
参加者から「40ベクレルについては、放射能はこれでは測れないのではないでしょうか?」と質問が出ました。40ベクレルのような少ない放射能の量を測ることが困難に思えたからです。すると関電工は「ここに運ばれる前にゲルマニウム半導体でサンプリング計測してそこで40ベクレルを検知すれば、そこの土場からは外に運ばせないという対策を取っています」と参加者の質問の真意をはぐらかして答えました。本当にそのやり方で大丈夫なのかどうか、参加者には判断できませんでした。
なお、放射能の測定のため、台貫の上で2分程度ここにトラックを止めるのだそうです。なお、モニタリングポストは0.04と0.05の数値を示しており、事務所の南側20mの地点に設置してあります。また、防音壁の裏側に排水溝が設けてあります。






↑作業用建物兼燃料貯蔵庫↑
次に燃料チップ製造・貯蔵施設に移動しました。関電工からは「こちらが燃料チップ製造所・チップ貯蔵エリアです。入って来た木質燃料は、台貫で計量した木質チップはすべてこちらに一度貯蔵します。今ご覧いただいている木質チップの量はおおむね定格運転した場合、1日強程度使用する木材の量となります。それから、チップのほか丸太の形で燃料を搬入するときは、この外側に積んでおきます」と説明がありました。参加者から「破砕はこの中でやるのですか?」と質問があり、関電工は「はい。でも、まだ今は破砕については調整が済んでいません。当面の間、チップ化する作業はここで行われません」と答えました。

↑燃料乾燥装置(脱水プレス機のこと)↑
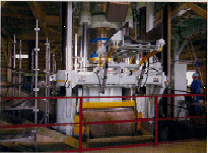
↑燃料乾燥装置(チップのプレス中)↑

↑燃料乾燥装置(チップのプレス機)↑
※当会注:見学会参加者によれば、実際のチップの脱水プレス機の塗装色は緑色であり、上記の写真はどこか別の施設を撮影した写真を流用している可能性がある。
参加者から「当面とは具体的にいつごろまでのことを指しますか」と質問がありました。関電工は「私からは申し上げられません。最終的にはここに入れますが、防音対策をとったあとになります」と答えました。確かに、チップ貯蔵施設はよく音が反響します。これでは騒音がスピーカーのように増幅して今います。こうしてしゃべっている声だけでもすごい反響音がします。
参加者が「破砕する場所は?」と訊くと、関電工は「(建物の)中でやります」と答えました。しかし、実際に破砕機を入れて稼働させてみた場合、どのくらいの騒音になるのかわからないため、防音壁の上を開けておいて、必要に応じて高さを継ぎ足す対策をとるようです。すなわち、現在の防音壁の高さは計算値にもとづく基準だが、将来的に余裕を持たせないといけないのでこのように上を開けておいてさらに壁を高くできるようにしているのだそうです。
関電工いわく「計算値はありますので、ご不満はあるかと思いますが、これでしばらく騒音測定をさせていただきたい」ということです。発電所の稼働時の騒音レベルをみたうえで、そのあと、破砕用のチッパーを稼働してみて、結局あとで同時稼働になるので、その結果を見て防音壁の高さを最終的に決めるようです。関電工としては柔軟な対応ぶりをアピールを演出したいようですが、言い換えれば付け焼刃的な対応という見方もできます。




↑貯木場↑
貯木スペースについて参加者から「最大で3日分しか置けない感じがしますけど?」と聞かれた関電工は「MAXで5日分くらいだと(トーセンが)言っていました」と答えました。参加者は「チップは何日分ぐらいを1日でできるのですか。稼働時間は?」と質問すると、「フル稼働すれば1日分といってもスペックとしてはもう少し余裕があります。要するにチップは大量につくっておくことはしません。1日ちょっとの分くらい」なのだそうです。なお、チッパーは現在、県内各地の森林組合や素材協の土場で稼働中のようです。参加者からチッパーの稼働場所を訊かれた関電工は「わからない」としらばくれていました。
次に乾燥施設に来ました。3億7500万円もする脱水プレス機ですが、搬入される木質チップのすべてをこのプレス機にかけるわけではなさそうです。含水率の高いチップのみ、プレス機で圧縮処理をして水分を絞り出して乾燥させてからボイラに送ることになります。なお、プレス機は諸々調整中で、まだ稼働状態にはなっていないとのことです。そのため、ここにあるチップは渋川で加工した水分量のたかい端材をそのまま搬入しているそうで、しばらく保管しているうちに含水率が低くなるとのことです。であれば、プレス機は不要なのではないでしょうか。
それ以外の木材はチッパーで粉砕するわけですが、現在、チッパーの姿は構内には見当たりませんでした。移動式のため、おそらく県内北部の沼田地域あたりの土場で稼働させている可能性があります。そこで丸太を砕いたチップがこの施設に持ち込まれているようです。しかし、前述のとおり関電工は稼働場所について口をつぐんでいます。
木質燃料の含水率は都度簡単に測定可能とのことです。また、生木をそのままプレス機にかけることはないとの説明です。プレス機にかけるのは、含水率の高い製材の端材だけで、製材時に水をかけてカットされた端材はビショビショになっているので、そのままプレス機に投入するのだそうです。
したがって、製材のチップと間伐材のチップは混ぜることはなく、混ぜるのは、ボイラ投入前のコンベアの段階で混ぜるのだそうです。
再度参加者が、脱水プレス機の稼働開始時期を関電工に尋ねましたが、「今の段階では、なんとも申し上げられません。準備が整い次第というしかありません」と言葉を濁しました。やはり実用に課題があるのかもしれません。
関電工は「次、先に行きます」と我々参加者らをせかせました。チップ貯蔵施設の天井を見ると火災探知機の有無が分からないので聞いてみると、あるのだそうです。しかし、煙感知器ではなく熱感知器のアラームだと言います。また、参加者が「脱水機はトーセンですか?」と聞くと、関電工は「燃料会社です」と返事しました。
参加者が「脱水した水の量や(処理用の)浄化槽の水量とかはどれくらいでしょうか?」と訊きました。関電工は「1日の処理能力は45トンの水を処理する能力は有しています」と答えました。
黄色の筒のようものは燃料工場のほうから発電所へのベルトコンベアだそうです。このベルトコンベアは密閉型で屋根がついています。だから、風でも飛散せず、雨天でもチップが濡れる心配はないということです。チップのベルトコンベアへの投入はフォークリフトになっているようです。





↑フォークリフト↑
次にボイラの視察となりました。10段くらいの階段は傾斜が急なため、足元が悪いとして、上に上がると大変な人は下のほうを迂回して案内されました。二次加熱器とか一次空気などの銘板が見えました。すると関電工の担当者が説明を始めました。
「それではこれが発電所のボイラです。ボイラは燃料チップをあちらから中に投入し、燃焼することにより高温高圧の蒸気を作るのがボイラの役割です。このボイラは流動床式と言って、特徴としてはボイラの火炉の底の部分で約30トンの砂が入っていて、下から一次空気とよばれる燃焼用空気を吹き付けて、バブリングとよばれる、つまり常にボイラの中の砂を巻き上げてやることにより、砂が常に回っている感じとなります。その中に燃料チップを入れて無駄なく燃焼させ切るのが特徴です。その他、このボイラの火炉の部分については、前後・左右・上下に水管という水の入った管があり、その中の水が熱を吸って蒸発して高温高圧の水蒸気になります。それを6面にきちんと張り巡らしてあるため、発生した熱をできる限り無駄なく吸収させることができます。こちらが発電所のボイラです。タービンは向こう側にあります」
参加者からタービンの騒音について質問がありました。関電工は「回転しているとき、50-60デシベルくらいになります」と言いました。なお、ボイラ施設から発生する音の一番の原因は水の流れる音だそうです。なお、関電工によれば「施設境界における夜間の騒音規制は45デシベルなので十分に達成しています」と鼻高々でした。
また、参加者が、「この燃焼室では燃料チップは上から落とす形になるのですか?」と質問したところ、関電工の担当者は「そうです」と答えました。参加者が「あれほど落差が必要なのですか?」と質問したところ、関電工は「もうしわけありません。技術的なことはちょっと(わからないので)」と言いました。一般住民への見学会だとタカをくくっているのでないか、と思われる対応です。
参加者から、「あそこは何が出るのでしょうか?煙突はわかるのですが」と質問がありました。すると関電工は「あそこは脱気器といい、缶水から溶存酸素を取り除くためのものです。酸素があるとボイラの腐食の原因となるため、蒸気と缶水を触れさせて中に溶けている酸素を取り除くための装置です。そのためにごく微量の蒸気を使っています」と答えました。参加者は、「それによって排水として外部に出てくるのでしょうか?」と質問したところ、関電工は「いいえ、取り除くものは酸素だけなので、一緒に空気中に放出されてしまいます」と言いました。
参加者からは「ここからずいぶん煙が出ますね。このエルボウ(曲り管)からでしょうか?」と質問がありました。すると関電工担当は「大気放出弁があり、起動停止の時に一部開けるところがあります。出ているのは単なる蒸気です」と答えました。参加者は、試運転時に大量の白煙が出ていることを知っているため「ここからずいぶん(白煙が)出ていましたが・・・」と質問したところ、関電工は「試運転なのでずいぶん開けたり閉めたりするので・・・。通常は締めています。だから実際に運転しているときは(白煙)はでません」と言いました。
また、最近、試運転時にバイオマス発電施設から漂ってくる異臭に関連して参加者から「点火時の助燃剤として重油を使うのですか?」と質問したところ、関電工からは「重油で点火するのでなくて、灯油を使います。」と返事がありました。参加者から「その排ガスも出ますよね?」と質問された関電工担当者は「火を点ける時は小さなバーナーを使います。石油ストーブのようなものです」と言いかけましたが、それをさえぎるように、関電工の案内者は「はい、すいません、次に移りますので」と述べました。
続いて中央操作室に移動しました。関電工から次の説明がありました。
「営業運転を開始すると24時間運転になります。こちらには2名4班の体制を組み、昼夜2交代勤務で、常時運転員が常駐することになります。発電所の各パラメーターに関する数々のセンサーはこちらで監視ができるようになっています。万一、異常等々が発生した場合は所員により適正に対応します。壁に付いているテレビ画面が、燃料チップの受入ホッパーの映像で、あちらからチップをベルトコンベアでボイラに投入しますが、その貯留状況もここで管理しています」
参加者から「監視カメラは何か所あるのですか」と質問がありました。関電工は「上の受入ホッパーを見れば、あの1か所だけです。なお、(ボイラ燃焼室内の)燃焼状況は4か所で見られます」と回答しました。
関電工は次にタービン建屋を案内しました。急な階段を手摺につかまりながら降りていきました。さっそくタービン建屋の説明が始まりました。
「発電に使った蒸気は、基本的にはボイラにまた戻る仕組みになっています。タービンの後ろに復水器があり、復水器に蒸気を当てることにより温度が下がると水になります。復水器の中に冷却水を送り、冷却水を冷やすという原理になっています。こちらのタービン建屋の中央にある緑色の箱のような機械がタービンです。中には羽根車が入っています。先ほどのボイラで発生させた高温高圧の蒸気をそこに送り付けて、羽根にぶつけて羽根を回転させます。その生じた回転エネルギで手前の発電機が回されて約6750kwの電力を発生させるという形になります。こちらにタービンに入ってくる高温高圧の蒸気は、温度が約475度C、気圧が約6メガパスカル、大気圧の60倍という高温高圧の蒸気が入ってきます。タービンから出ていく時の温度は約50度C、圧力はほぼ0気圧になります。それだけのエネルギがとられて、それが6750kwの電力を生む源になります。タービンで仕事して低温低圧になった蒸気は、今度はタービンの中に復水器という設備があり、そこには別系統から送られてくる冷却水で冷やされて再び液体の水に戻されます。低温の水に戻り、またボイラに入り加熱されるというサイクルを繰り返します」
参加者から「内側に貼ってあるのは防熱材料なのでしょうか?」と質問があり、関電工は「防音材です」と答えました。また「失われる水分は1割?2割?どれくらいですか?」と参加者が質問したところ、関電工いわく「タービンの中では水分は失われない」とのことでした。また「排水はどれくらいですか?」との質問には、「タービンでは排水は出ない」として、「このあと冷却塔を見学しますが、蒸気を冷やすのに使った冷却水が外に排水されます。後で説明します」との説明でした。
参加者から「高温高圧なので配管をステンレス鋼というか、高温高圧対応の材料を使っているのですか?」との質問に、関電工は「材質にはステンレスの配管は使いません。普通鋼です」と答えました。
次にタービン建屋から外に出て、冷却塔へいきました。
「こちらの大きな黒い箱のような設備が冷却塔と呼ばれるものです。先ほど申し上げました復水器で蒸気を水に戻すために使った水が熱を受け取って温度の上がった水となってこちらに流れて来るので、それを冷却塔の中で吹きかけてやり空気と熱交換をさせて、また冷却水の温度を下げて、また復水器に戻るというサイクルになっています。車のラジエータと同じです。よくビルの屋上とかにこういった設備があると思いますが、そういったものと基本的な原理は同じです」
参加者から「この発電所に入ってくる水は地下水と言いましたか?」との質問に、関電工は「はい、地下水です。1時間当たり65トン、それが24倍なので、すいませんちょっと。1000・・・」と答えました。(当会注:65×24=1560となる計算です)
参加者と関電工のやり取りは続きます。特に水については周辺の住民にとって非常に重大な問題を抱えているからです。参加者の懸念事項と関電工の回答を詳しく見ていきましょう。
―それがサイクルするとおっしゃいましたよね?
「はい」
―どんどん65×24(トンの水)が地下水から入っているのですか?
「それはまず、地下水を汲み上げさせていただいていますが、だいたい1時間当たり65トンです」
―循環しているとおっしゃいましたよね?
「循環しているのはこの中ですね」
―では常にどんどん、地下水を使っているわけではないのですか?
「違います。1時間当たり1700トンの水がぐるぐる循環しています。24時間汲み上げるんで」
―そんなに使うのですか?水を入れるということは、同じ量が出ていくことでしょう?無くなるから出るんでしょう?
「・・・」
―そんなに水を使って、井戸水を使っているのでしょう?はっきりさせてもらいたいです。
「循環水系統ですが、1時間1400トンが循環していて、冷却等のところで一部僭越として奪われるので、つまり、蒸気として蒸発するとそれが半分の30トンくらいあるので、その減った分を補充します。残った水にもミネラルが含まれているので、あまり循環するとミネラル分が濃くなりすぎるので、残った分も半分をそのまま放水します。なので、65トンを1時間入れて、30トンは蒸発で大気中に出て、残りはブローという形で処理して排水する。もちろん水質チェックしてから排水します。
―65トン入って、30トン蒸発して、残りは排水というけれども、循環するのが無くなるのでは?
「入りと出ではそうなんです。300トンくらいの水をプールに持っていて、このプールの中から建屋の内外を回っているうちに、1時間あたり30トン(の水)が無くなり、途中で30トンが系外に排水として排出されます。全体の水の量は1700トンで、このうち30トンが蒸気となります」
―それはもう予め大丈夫だと確認しているのですか?地下水を使って生活している住民も多数いるので、水が出なくなってしまったよ、という心配はないのでしょうか?
「はい。近隣の井戸の深さも調べてそれよりもっと深い層から採水しており影響はないと考えております」
―影響が100パーセントないとは確実に言えないでしょうから、これが稼働した時、もし苦情があったらどうするのですか?
「適切に対応させていただきます」
―適切に、とアバウトに言われても、生活している人は水がないと生きていけないので。
「それは非常に大事なことだと、我々も認識していますので、はい」
―毎日1500トンくらい水を汲み上げることになりますよね?
「はい、そうなりますね」
―1500トンといえばかなりの量ですね。
「これくらいは普通だと聞いていますので。当社の実績で」
―そんなに大量の水を使ってわざわざ木質チップを発電するなんて、無駄がいっぱいあるんでは?
「エネルギという観点では、水を使うのに要するエネルギより多くのエネルギを発電していますので、エネルギ源という観点では1を超える設備であると考えています」
―だけど木を燃やしてエネルギを作るといいながら、他のエネルギも水も使っていますよね?」
「使っていますが、発生する分に較べたらわずかです」
―僅かとか、そういうイイ加減というと失礼だけど、昔からここより先に住んでいる人ばかりなので。では、水が出なくなったら苦情を言ってもいいのでしょうか?(その場合)うちのせいではないと言うのではないでしょうね?」
「ご連絡いただければ、きちんと調査等々をしたうえで、適切に対処する所存ではございます」
―だけど今、雨の量も少ないそうなので、このへんは渇水の心配があります。なので、こんなにこっち(の事業)に水を取られたら、とても心配です。適切な対処といっても、では(そのような事態の際には)水をくれるのですか?
「そういうケースも考えられます。必要であれば、この発電所を止めざるを得ないことということも有り得ます」
―そんなことをしますか?
「その話をここでしても長くなるので、今、プラントのほうの説明をしているので、急がせてもらえますか?」
なるべく早く見学会を切り上げたい様子で、関電工は参加住民らに次の場所への移動を促しました。
参加者からは「300トンのプールがあれば(冷却用水を)完全循環できると思いますか、ダメですか?せっかくの水を捨てることはないと思いますが」と提案がありましたが、関電工は「増減があるのでやはり運用上、バッファー・タンクがないと厳しいので」などと意味不明の回答をしてお茶を濁そうとしました。
それに対して参加者からは「捨てるということをしなくていいのではないでしょか?無くなったらその分だけ足せばよいのではないでしょうか?」と更に突っ込んだ質問が出ました。すると関電工は「それはさきほども説明したように、地下水のミネラル分の濃縮が発生するので、そうすると配管等に悪さをするので、ミネラルの濃度を一定値以内に保つように(水の)入れ替えをする必要があります」と説明しました。
参加者は「それは排水しても問題はないのですか?飲んでも影響はないのでしょうか?(入れ替えは)機械を守るために?」と言うと、関電工は「はい、そうです」と、環境よりも人命を重視する返事をしました。
それを聞いた参加者からは「濾過は可能ですか?」と少しでもミネラル分を濾し取って、貴重な地下水の排水量を少なくするための方策について質問が出ました。しかし、関電工の返事は「濾過ではちょっと・・」という連れないものでした。「技術的に難しいのでしょうか?」との質問にも「はい」と答えた後、さらに「ヒトにはミネラル分はよいのですが、機械にはちょっとダメなもので。ミネラルウォーターというのは、プラントにはよくないので」として、地元や周辺の住民の生活環境よりも、機械の稼働状況の保全のほうを重視している姿勢を示しました。(当会注:通常は、冷却水量の低減をできる限り図るため、ミネラル分の増加した排水をさらにマイクロフィルターや逆浸透膜などにかけて、さらにミネラル分を除去して冷却水をリサイクルし、環境負荷を最小限にするのが適切なエンジニアリングです。しかし、住民の生活環境や周辺の自然環境の保全より、営利を重視する関電工は、そうした対策を取るつもりは毛頭なさそうです)
さらに参加者からは「地下水のミネラル成分はきちんと計測したのですか?」と質問が出ましたが、関電工は「はい。ただしボイラに影響あるものだけですが」と答えて、ここでも自分のことしか考えていないことを露呈しました。
粘り強く質問したい参加者の意向と裏腹に、関電工は「では、次の説明に入らせてもらいまーす」といって、それ以上の質問を遮りました。
「最後に排気関係のご説明をさせていただきます。ボイラでチップを燃焼させた後、当然、排気ガス等々が発生します。木質チップの重量のうちの4割程度は水分なので、それを燃焼させることで水蒸気や、或いは木そのものを燃やしたことによって発生する煤塵、そういったものがボイラから発生します。最終的にはこの煙突から、高さ30mありますが、ここから排出させていただきます。その前段階として、手前の大きな箱のようなものをバグフィルターといいます。こちらのフィルターの濾紙のようなものを通すことによって煤塵関係のものを濾し取ってやる設備です。あの箱の中に長さ6mの筒が約448本、面積にすると1300平方メートル程度になります。それだけのフィルターが入っています。そちらでチリを濾し取っています。フィルターの部分でチリが溜まりますが、定期的に逆洗浄、定期的に空気を逆に流して、下側から筒のすぼまっているほうに煤を落とし、青いコンテナのほうに溜めるという流れになっています。燃焼させた後の灰は乾燥でカラカラになっており、空気で飛散し易いので、その上に灰加湿器が見えますが、そちらで水分を加えてやり、飛散することの無いようにして、コンテナに溜めるようになっています」
さっそく参加者から質問が出ました。
―フィルターは定期的に交換するのですか?
「検査のたびに判断します」
―上のほうは茶色くなっているがあれは何ですか?
「出口温度が165度くらいあって、ちょっと熱の部分があのような色に変色しているだけです。純粋な熱です。なお、(バグフィルターの箱の)外板の化粧板はステンレス製です」
―フィルターにかけるのは飛灰だと思いますが、主灰はどうするのですか?
「流動床(式ボイラ)の特徴で、主灰は殆ど出ません。全部完全燃焼して主灰は出ないのです。(出るのは)飛灰のみです。燃焼灰はすべてこのバグフィルターを通します。灰以外の石だとか釘だとか、異物については、別途取ります」
―これはエア洗浄の灰ですか?
「はい。フィルターに付いた灰はフィルターに残るので、下から空気を当ててやると排ガスの下のほうに落ちます。あそこに2つ、一つの箱に同じものが2つに分けて入っているのは、単純にひとつだと灰の量がたくさんになった時に、スムースにいちおう通れないので、2つ用意しています。中には1対になっている長さ6m、直径15センチのフィルターが448本入っており、定期的に下から空気を吹き上げて、灰が下に落ちで、それに灰加湿器で水を吹きかけて、最終的に青いコンテナに行きますが、今日のように風が強い日でも、灰が舞わないような設備にしています。すべて灰は青色のコンテナに集約しています」
―で、フィルターを通ったものは煙突に抜けているということですか?
「そうです」
―煙というと上にいくと思うが、いったん下に行ったり上から下に行ったりしているのは?
「煙の方向は配管のルートで上に行ったり下に行ったりいろいろしています」
―設計的なものですか?
「そうです。あと、煙突に向かって上下すると灰がくるのに遅いことがあり、実は、煙突の少し手前に誘引の通風機というものがあり、煙突のほうに全部引っ張るような風を起こすことで、すべて軌道に乗るような設計をしています」
―あれがないと更に煙突をさらに高くしなければないのでしょうか?
「そうです」
ここでもまた、参加者からのさらなる質問を遮るかのように、関電工の案内者の声が聞こえました。「すいません。時間的に時間が押してきているので・・・」それにも拘らず参加者からは不安や疑問が関電工に寄せられ続けます。
―灰加湿器の働きは?
「流動床には30トンの砂が、800度まで上がるので、基本的に(投入された木質燃料は)完全燃焼させて灰となり、燃えないものは外に出られないしくみになっています。灰は外部に取り出すため、取り扱いの際に水を加えて埃の発生を抑制します」
―点検とは年間何回やるのでしょうか?
「定期点検は1年に1回予定しています。法定点検でボイラのまわりやタービンのまわりは、2年に1回、あるいは4年に1回、法廷点検にならって、期間は20日から1か月くらいかかります」
―そんなに(点検に時間が)かかるものなのですか?
「やはりボイラの点検は、全部を止めて配管が全てしっかりしているかどうかをチェックします。そのため、1年に20日間程度間違いなく止めます。ボイラの場合は2年に一度の周期なので2年目は40日くらい(運転を)止めます」
―毎年、一般検査で20日くらい止めるのですか?
「我々としては、なるべくそこを短くしたいが、法定で決められたものについてはしっかりとやらないといけないので、それなりの予定をしています」
―運転を止めた後、再開する際に重油で火を点けるのでしょうか?最初はこれだけですか?
「最初にボイラを立ち上げる時は非常に冷えているので、いきなりチップを入れても燃えません。バグフィルターの手前にタンクのようなものが見えます。煙突と大きいフィルターの間に小さいタンクがあります。5000リットルと書いてあるが、あそこに灯油が入っています。そこから灯油を送り、(ボイラの)起動バーナーで砂を最初に200度Cまで温めてあげます。200度Cまで上がるとチップを燃やしても、少しずつ燃えることになるので、起動するときのみに使用する設備になっています。(灯油タンクをボイラの)燃焼場所から遠い場所に設置しているのは安全のためです。あまり近いと引火など火災のおそれがあるので」
―事務所の浄化槽というのは、さきほどの45トン(の浄化槽)とは別にあるのですか?
「あくまで、生活排水のものはまったく別です。あれ(45トンの浄化槽)はあくまでも脱水チップ用です。まだ稼働はしていませんが・・・」
―汲み上げる水の量がやはり心配です。
「たとえおひとかたであってもご連絡をいただければ対応します。一応ここの代表電話も入っているし、連絡先に携帯のも入っているのでどちらかでも対応はします。水の汲み上げ量が心配だとおっしゃっていますが、それなりに事前のボーリング調査を何か所もやって埋蔵する水の量は把握していますので、そのへんは・・・」
―だってここは何年も稼働するのでしょう?今後の展望というのは、今までのようなわけにはいきません。そうでなくても水が足りない傾向になっている事態の中で事業をやろうとしているんですよ。そういうことを考えると、水の不足について応対してもらえるのでしょうか?いままで井戸が出ていたところが、出なくなったらどうするのですか?
「まあ、ご連絡いただければきちんと対応します」
最後に、入口の燃料木材の受入れ場所に向けて歩く途中で、早く見学会を終了させたい関電工は、早くも参加者からヘルメットを回収するとともに「つまらないものですがお餅を用意させていただきました」と、参加者に手土産を配り始めました。
しかし参加者からは全般にわたる質問が出ました。
―搬入木材の放射能の管理はモニタリングが十分なのでしょうか?
「そういったところにつきましては、入ってくる木材に含まれる放射線の量は基本的に計測します。そういったことで放射線量の高いものは受け入れないという対応をします。それはしっかりやります。そうですね。ご心配な点が何かあれば連絡ください。よろしくお願いします」
―貯木はここだけですか?アスファルトの上はすべて貯木場ですか?
「基本的にはチップの状態であればあの中です。それで、防音壁の前のほうに丸太を積んで、少しでも防音軽減効果を狙って積むことも一応考えています。この(防音壁の)板のままでよいのか、木があのように積み重ねれば軽減するのかどうか、それを確かめてからにしたい」
―ここは浸透性のアスファルトでしょうか?
「えーと・・」
―水はどこから流れていくのでしょうか?アスファルトの上を通った水が入るのですか?
「基本的には雨水を集めているところだと思います。弁で切り替えて3分岐になっています。水を散らばせています。深さは2mくらいあります。結構な深さです。それも計算値でやっていますので。で、ヘルメットも無い状態なので、ここまででご遠慮ください。またいろいろありましたら、またご連絡ください」
―池に入るようになっていないですね。ここを抜けるように作っているだけのようですが、これでは全然浸透しないね。ところであの木はどこからの持ってきたのでしょうか?
「あの木は、具体的にここにあった木というのは、まず群馬県内の県の森林組合さんから持ってきただいた木があちらに貯留されてあります」
―違いますよ。トーセンが持ってきたって聞いていますけど?
「はい、すいまでん。あそこに見えているのが森林組合で、あちらの裏側に置いてあるのはおっしゃるとおり、あの丸太は株式会社トーセンさんの群馬県にある土場から持ってきたものです」
―なんか、(トーセンが)借りていた土地がもう返さなければならなくなったからここに持ってきたと言っていましたけど?
「はい、そうですね。裏にあるものはトーセンの丸太をこちらに持ってきました」
―日光のほうから持ってきているのではないでしょうか?
「群馬県内の木でやっているので、そこは証明書で確認しました。マニフェストで、具体的に間伐材で県有林の場合は売買契約書でトーセンさんが何とか森林組合から買ったというマニフェストがあります」
―それはチップであってもどこの木が元の木だというのがわかるのでしょうか?牛肉のように出身地が?
「はい、チップの状態であのように混ざってしまうと何がなんだがわからなくなりますが、チップで入っても、大もとの木がどこの木でいつ買い付けたというのは、全部分かるようになっています。それが再生可能エネルギ法によるFIT認定で必ず守らなければなりませんので、そちらで確認が可能です」
―あの丸太は重量を測るだけで、(台貫に)乗っかるところだけでいいのですか?
「えーとですね。ちょっとのシロタのほうが、毎回(トラックの出入りごとに台貫に)アップ、ダウン(ごとに係争する)と説明したのですが、通常はここに入ってくるトラックはだいたい決まっているため、実は、車でナンバーは1回、2回で登録するという形をとっている燃料の会社でありますので、最初は1回、2回くらいしっかりと重さを測っておけば、(その後は)その車が来れば、その車の重量何トンだと分かれば、このナンバー(トラックの正味重量は)2トンだというふうにわかるからです。その後は、いちいち出るときの重量は測りません」
―だけど例えば、燃料のガソリンタンクが満タンか空かは、誤差のうちなのですか?
「すいません、そこまでは・・・というので、逆に言うとそれは燃料を買う我々側とトーセンさんの間で、それは我々もちょっと懸念するところですが、今のところそこを確認する技術はなくて・・・」
ここでとうとう痺れを切らせた関電工は「ではすいません。あの、作業がまた始まってしまうので、申し訳ありません。年末の忙しい時期なので本当に恐縮です。短い時間で申し訳ありません。名札と防寒着をまだ返却されていないかたがいらっしゃれば、お願いします」
最後に参加者の皆さんから、この施設が建設された場所の勾配が急であることの感想が述べられました。これでは貯水池に入らず、周辺や下流に水問題でなにか問題が及びそうだということで、懸念の声が相次ぎました。
また、木質燃料は間伐材のチップと製材端材のチップの2種類に区分されて保管されていましたが、製材端材は乾燥済みのようでした。脱水プレス機は排水の浄化槽の工事中で、まだ稼働させていない、というより稼働できないことも明らかになりました。
このほかにも、ボイラの騒音や、冷却装置からの騒音、燃焼灰の扱い等々が2月1日からの運転開始を前に、懸念材料として参加者から指摘がありました。
さらに肝心のチッパーなどはどこにあるのか見当たらず、他に転用されているのではないかとい指摘もありました。





↑移動式チッパー、トレーラー・グラップル↑
**********
■こうして12月23日の午後に開催された施設見学会では、当初45分の予定でしたが、参加者の皆さんはいろいろな懸念や不安を含めて多くの質問を行いました。そのため予定を30分ほどオーバーしましたが、関電工側では、しきりに早く切り上げようという姿勢が目立ち、真摯に住民の皆さんの抱く懸念や不安の払しょくを最優先にするという対応がいまひとつだったのが気になります。
また、12月22~23日の見学会は、一般住民向けであり、この問題に当初から取り組んできた住民団体向けの見学会は別途必須です。
このことについて見学会でも参加者から関電工に要請の声が伝えられましたが、12月27日に住民団体のメンバーに対して、「12月4日付の関電工社長宛の住民団体向けの視察会開催要請について、見学会は計画しない」と口頭で回答がありました。
これは以前、関電工が住民説明会で、3段階での見学会の開催を約束したことと明らかに反します。
※住民説明会における関電工の見学会開催に関する約束と現時点での進捗状況:PDF ⇒ 20180108wj.pdf

■住民団体の皆さんは、このことについて、前橋市長にも強く申し入れていますが、12月28日付で山本市長からの回答書が届きました。内容は次の通りです。
*****前橋市長からの回答書*****PDF ⇒ 20171228os.pdf
平成29年12月28日
赤城山の自然と環境を守る会 横川 忠重 様
赤城南麓の環境と子供達を守る会 井上 博 様
前橋市長 山 本 龍
(環境政策課)
バイオマス発電事業について、本市へのご要望事項について回答いたします。
まず、事業者・行政・守る会の三者による話合いについては、各者の合意が前提となることから、各者少人数による話合いができるかどうか事業者に対し提案しているところであります。
環境配慮計画の内容に関しましては、事業者に自主管理基準をしっかりと守っていただけるよう、様式を整え報告いただけるような取り決めについて事業者と協議wてまいりたいと考えております。
事業者は、各種の環境モニターを設置し監視を行うなど環境に配慮した事業計画となっておりますので、まずは事業者に対しまして自主管理基準が守られているかを確認するとともに、大気関係、騒音・振動関係に該当する事項については法令に基づき対応してまいりたいと考えております。
**********
■このように前橋市は事業者である関電工に対して、地元住民団体との話合いについて申入れをしている様子ですが、いまのところ、何も具体的な進展は見られません。
また群馬県は、前橋地裁における裁判でも、県で定めた環境影響評価条例に基づくアセスメント実施について、相変わらず排ガス量を根拠もなく大幅に棒引きしたことについて、正当化する発言を繰り返しています。
さらに原価がせいぜい3千万円程度の脱水プレス機を、事業者であるトーセンと関電工らが出資する前橋バイオマス燃料というペーパー会社に対して補助金として3億5千万円(税抜き)もの金額を支払ったりしていることについても、請求書通りに支払っただけだとして、一向に精査をしようとしません。
引き続き、裁判所の法廷での攻防を通じて、なんとか環境アセスの実施と補助金の返還を事業者にさせるよう群馬県を相手取り、裁判に注力していく所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考URL「株式会社富士コンストラクション」↓
http://fuji-csr.co.jp/guide/company.html
社名 株式会社富士コンストラクション
住所 〒290-0043 千葉県市原市出津西1-2-10
設立 昭和42年7月28日
資本金 50,000,000円
建設業者登録 (般-11)第5386号、管工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、鳶工事
業種 火力発電ボイラー石油化学の各プラントの機器、鉄構造物、タンク配管等の据付保全工事
役員 顧問相談役 伊藤 幸雄
代表取締役社長 平井 誠
専務取締役 長岡 敏郎
常務取締役 小倉 雅彦
取締役事業部長 有馬 誠見
監査役 内田 稔
取引銀行 千葉銀行五井支店、京葉銀行五井支店
年間工事受注高 2,000,000,000円
従業員数 事務職員/6名、技術職員/50名、協力会社/250名(20社)、合計316名
※参考URL「三菱日立パワーシステムズインダストリー」↓
https://www.ids.mhps.com/
商号 三菱日立パワーシステムズインダストリー株式会社(Mitsubishi Hitachi Power Systems Industries Co., Ltd)
登録所在地 横浜市中区相生町三丁目56番1号JNビル
設立年月日 1961年(昭和36年)10月10日
社長 牧浦 秀治
資本金 10億円
株主 三菱日立パワーシステムズ株式会社(100%)
年間売上高 226億円(2016年度)
従業員数 約620名(2017年4月1日現在)
取引銀行 三菱東京UFJ銀行 横浜支店
保有資格 建設業者登録 特定建設業(電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業):国土交通大臣許可(特-24)第24597号、特定建設業(建築工事業):国土交通大臣許可(特-25)第24597号、特定建設業(清掃施設工事業):国土交通大臣許可(特-26)第24597号
ISO 9001 : 2015認証 登録番号 : JBA-005
計量証明事業 濃度(広島県知事登録 第K-29)
音圧レベル(広島県知事登録 第K-48)
作業環境測定機関 広島労働局長登録 34-30
本社 〒231-0012横浜市中区相生町三丁目56番1号JNビル
TEL:(045)227-4950
FAX:(045)227-7569
事業内容 ○産業用ボイラ・中小型火力発電プラント・地熱発電プラントの基本計画、詳細設計、 調達、建設、試運転
○既設プラントの改造工事、アフターサービス、保全工事
○メカトロ、コンピュータ制御装置の設計製作
○各種訓練設備・監視計測装置の設計製作
**********














