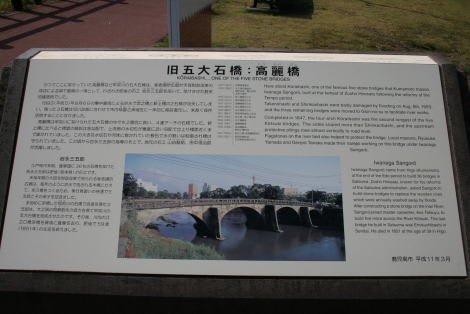那覇市壷屋の「すーじー小(ぐわ)」を抜けて突き当たると、
そこに「うちなー茶屋ぶくぶく」がある。
ぶくぶく茶は沖縄にしかないお茶であり、
ソフトクリームのような泡を飲む、珍しいお茶です。
古くから歴史のあるお茶ですが、戦後40年以上姿を消していたため、
「幻のお茶」と呼ばれていました。
○ ぶくぶく茶の名前の由来
ぶくぶく茶という名前は、泡がぶくぶくしていることから付けられたようです。
ちなみに、沖縄の方言では泡のことを「アーブク」といいます。
さらに調べてみますと、安次富順子先生著書の「ブクブクー茶」では、
鹿児島徳之島の振り茶である、「フィチャ」を徳之島では「ブク」と呼ぶことから
振り茶の一種であるぶくぶく茶の名前が沖縄で変容したのか…などと書かれています。
○ ぶくぶく茶はいつどこで、どのように飲まれていたのか
ぶくぶく茶は、明治時代から昭和の戦前まで、沖縄県の那覇だけで飲まれていました。
那覇の東町の布売り市場で、頭にチリデー(お盆)をのせたぶくぶく茶売りが、
ぶくぶく茶を売り歩いていました。とくに夏場は人気があったそうです。
また、中流以上の家庭において、家族の誕生日祝いや出産祝い、
新築祝いなどといった 内輪のお祝いに、ぶくぶく茶が飲まれていました。
「旅立ちの日に ぶくぶくのお茶や旅の嘉利(かり)なむん 立ててみぐらしばもとの泊」 という歌もあり、
船で旅立つときには、ぶくぶく茶を立てて再会を願ったそうです。
嘉利(かーりー)とは、縁起が良いという意味です。
ぶくぶく茶を立てる「ブクブクタティヤー」という専門家もいて、
床にタライをおいて そのなかにブクブクー皿をおいて、泡立てることもありました。
ぶくぶく茶を立てるには、時間がかかり疲れるので、
右足をたてて、右ひざの上に手を乗せてぶくぶく茶を立てていました。
ぶくぶく茶には、油っぽい食事の消化を助ける働きもあります。
多い人では、ぶくぶく茶を10杯、20杯とおかわりしたそうです。
第二次世界大戦前はよく飲まれていたぶくぶく茶でしたが、戦後はすたれてしまいました。
ぶくぶく茶がすたれてしまったのは、ぶくぶく茶を作る道具が戦争で焼けてしまったり、
ぶくぶく茶を立てる水を選ぶのが難しかったり、
煎り米を作るのに時間がかかるなどの理由があげられています。
○ 復活したぶくぶく茶
第二次世界大戦後、姿を消していたぶくぶく茶が復活したきっかけとは、
今は亡くなってしまったのですが沖縄に住んでいたAさん(仮名)が、
ブクブクー皿と茶せんを東京の知人にプレゼントしました。
その後、ブクブクー皿と茶せんが戦争で焼けてなくなってしまったことを知り、
知人がAさんに返してくれたそうです。
そして、Aさんがぶくぶく茶を家で 立てて楽しんでいたのを、
のちに沖縄伝統ブクブクー茶保存会の会長となる方が知り、
研究や情報収集を重ねて、ぶくぶく茶を復興させたそうです。
たった一つ残っていたブクブクー皿と茶せんを同じ寸法で復元させたり、
茶せんの振り方やお米、水のことなどたくさんの研究を重ね、
ついに沖縄のさんご礁(琉球石灰岩)が含まれた硬度の高い水でないと
良い泡がたたないことが分かりました。
日本の名水百選に選ばれた、玉城村の垣花樋川(かきのはなひーじゃー)の水が
とくに良い泡が出るそうです。
ぶくぶく茶は泡が命なので、この発見はとても大きなものだったでしょう。
沖縄の硬度が高い水のほかにも、市販の高度が高いミネラルウォーターも利用できるそうです。
沖縄伝統ブクブクー茶保存会の方がおっしゃっていましたが、
フランスのエビアン(硬度250以上)などのミネラルウォーターが合うと話されていました。
こうして、ぶくぶく茶は再び沖縄で広まることになったのです。