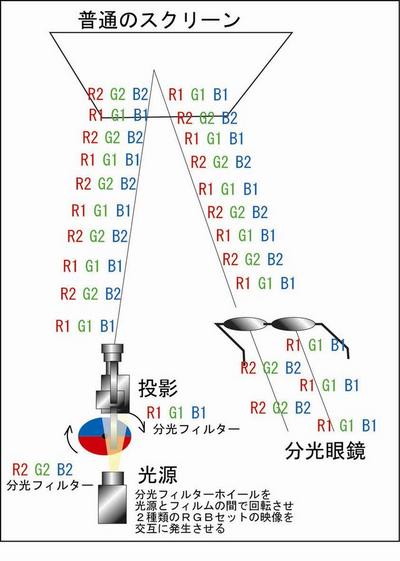■ もはや体感アトラクション? ■
前回は3D映画の原理説明になってしまいましたが、アバターは映画としてはどうなのでしょうか?
アバターはSF映画ですから、最大もポイントは「センス・オブ・ワンダー」に尽きると思います。「今まで見たことも無い何か」が科学のギミックで表現されていなければばSF映画としては失格です。かつて、「スター・ウォーズ」や「エイリアン」や「ジュラシック・パーク」を初めて見たときの驚きを与えてくれらかどうかが重要です。
その意味では、アバターは素晴らしい映画です。観客は3D映像の効果により、衛星パンドラの巨大な樹林を、大空を自在に飛び回っているかの様な体験をします。顔にパンドラの大気が叩き付けられるような錯覚すら覚えます。
キャメロンの演出も素晴らしく、大きく引いた構図でかつてのSF小説のカバーイラストの様な風景を描き出したかと思えば、主人公達の視点で急降下する映像に切り変わったりします。
特に主観目線の映像は、3Dの効果も相まって絶大です。最早映画は「体感アトラクション」に進化しています。
■ ストーリーは単純 でもツボは押さえている ■
一方、ストーリーは至って単純です。開発侵略に加担する「海兵隊」を思わせる軍と、自然を崇拝する原住民との戦い。そして原住民との間に生まれるロマンス。
「ダンス・ウィズ・ウルブス」と比較される方も多いようですが、むしろ「ポカポンタス」に近い、ロマンス重視の映画ではないでしょうか?
単純に映像を楽しむ為には、難しいストーリーなど邪魔なだけです。善と悪がはっきりと分かり易く、そして愛が悪に打ち勝つという「ファンタジー・ゲーム」程度の内容が馴染むようです。
ターミネーター2でもそうでしたが、キャメロン監督は観客を喜ばせる事に全力を投入しています。監督がそれだけ割り切っているのですから、ストーリーや構成についてとやかく言うのは野暮というものです。
ディズニーやユニバーサル・スタジオに遊びに行った感覚で、楽しめば良いのです。
■ バットマンの新シリーズ ■

それでは現代の技術で、ストーリーや内容にまで拘った映画を製作したらどうなるでしょう?その最良の回答が「ダークナイト」、そうバットマンの最新作です。
ティム・バートンのバットマンもそのダークで病的な雰囲気は良く出ていましたが、ジャック・ニコルソン演じるジョーカーを始め、マーベルのコミックを実体化する事にその魅力がありました。しかし、シリーズを重ねる毎に、驚きは薄れて行きました。結局、「あのキャラクターを映像化するとこうなるのか!!」というだけの映画に成り下がってしまいました。
「バットマン・ビギニング」以降の新シリーズは、従来のバットマンの路線から決別し、ゴッザム・シティーも現代のNYに近い街とする事で、スーパーヒーローにリアリティーを付与しようと試みています。「苦悩するヒーロー像」の創出に心血を注いでいます。普通に考えたら「ありえない」ジョーカーですら、実在しそうに思える演出は素晴らしいとしか言いようがありません。
■ エンタテーメントの抱えるジレンマ ■
バットマンの最新作「ダークナイト」は、エンタテーメントとしても充分良く出来ています。しかし、ストーリーに重みを与える為、その映像は控えめです。奈落の様なビルの底にダイブし、翼を広げるバットマンを追うカメラは、ビルの上に固定され、ダイブの迫力を際立たせる事はありません。闇を背景にコウモリの翼が開く、その一瞬の官能を描き切ろうとします。
コミックの映像を映画的に再現しただけとも言えますが、全編においてカメラは過度に寄る事は無く、冷静に対象を追って行きます。これはドキメントの手法です。
この抑制の効いた演出と相まって、「ダークナイト」はSF娯楽映画の枠を大きく逸脱して、人間が本来持つ「闇」に迫って行きます。サムライミーのスパイダーマンは最早子供のおとぎ話にしか見えなくなってしまいます。
しかし、良く考えてみると、映画は所詮娯楽です。デートで「ダークナイト」を見た後のカップルの話が弾むとはあまり思えません。・・・これが娯楽映画の限界です。ミニシアター的な作品であれば別ですが、収益が確保出来なければCGをふんだんに使う事すら出来ません。
■ コロシアムとしての映画 ■
TVや映画はローマ時代のコロシアムと同じ機能を持っています。人々を興奮させ、熱狂させ、楽しませて社会的なストレスを解消させる役目を担っています。
映画を見に行って、「大衆」が政治意識に目覚めてしまっては困ります。ですから映画は、脳内麻薬がバンバン出まくるアトラクションに進化して行きます。
アバター以降、映画は益々この傾向を強めるでしょう・・・。行き着く先は、ウイリアム・ギブソンが既に予見しています。
ツアイスの高性能カメラを眼に嵌め込んだ「女優」が演じる世界を、バーチャルリアリティーで体感するドラマに没入して、不幸な生活を一時忘れる主婦達。
どんな学者の予測よりも、優れたSF作家の小説は正しく未来を予見します。
■ アバターの原点「繋がれた女」 ■
アバターはリモートコントロールの肉体を使ってコミニケーションを試みる内容ですが、この原点はジェームス・テュプトリー・Jrの名作、「繋がれた女」まで遡上します。「繋がれた女」は現代は"Wired woman"だったように記憶しています。テクノ系のミュージッシャンが好む"Wired"の原点も実はこのタイトルでしょう。
有名な女優は、実は軌道上の衛星内で「繋がれた」醜い女によってコントロールされた偽りの肉体であった・・・そんな内容のシンプルな短編です。
テュプトリー・Jrには他に「聖なる3倍体の伝説」(ちょっと題名がオボロゲ)という名著もあります。ある星で迫害される小型の生命体は、その星を支配する種族を生み出す生殖体であり、支配する種族は、彼らの3倍体に過ぎず生物学的にその種族代表出来る存在では無かった・・。ちょと難解ですが、迫害されている種族を救うべきが、放置すべきかを調査にやってきた調査官がこの事実を突き止め、迫害されている種族こそが本来この星を代表する存在であると発見する物語です。
さて、こんな難解なストーリーを映画にして人は集まるでしょうか?集まらないに決まっています。
70年代、イギリスやアメリカの有能な作家達が、SFという手法を用いて社会の歪みや人間の本質に迫って行きます。共産圏の言論統制を受けた作家達も、SFという架空の世界を利用して、体制を批判して行きます。
この流れを「ニュー・ウェーブSF」と呼び、ジェームス・テュプトリー・ジュニアとアーシュラ・クラクス・ルグインという2大女性作家を生み出します。さらに、フィリップ・K・ディックやJ・G・バラード、スワニスラフ・レム、ストゥルガスキー兄弟などといった異能の作家達が活躍しました。
彼らは、フェミニストであったり、コミュニストだったり、あるいは反社会主義体制派であったりしますが、共通するのは体制に反発する姿勢です。冷静な眼で社会を観察し、何百年後か何千光年の彼方にその姿を投影してゆきました。彼らの作品には社会の真実が透けて見えます。
ところが、何故かディックの作品も映画になると、薄っぺらでつまらないものになってしまいます。(ブレードランナーは例外でしょう)。あたかも誰かの悪意が働いているかの如く・・・・。
googleでテュプトリーを調べてみて、あまりに検索が引っかからない事に驚愕しました。CIAのエージェントであったと噂され、謎の覆面作家としてデビューし、へミング・ウェイの再来と言われ、本人が明かすまで女性であるとは誰も思いもせず、旦那の頭をライフルで打ち抜き本人も自殺した、この偉大な作家はどうやら歴史の影に消え去ろうしているようです。
アバターを見て、SFが反体制であった時代が懐かしくなりました・・・。