「I love him」や「泣かないで アマテラス」が収録されているのは「10WINGS」というアルバムです。このアルバムは1990年から1994年の夜会の中で歌われたのが9曲,そして夜会のテーマソング1曲の10曲からなっています。僕はどんな楽曲もそれ単独で聴きますが,夜会というのはストーリー仕立てとなっていますから,実際にはこのアルバムに収録されている楽曲を理解するためには,その楽曲がストーリーの中でどのように歌われているのかということまでみておくべきだとはいえます。
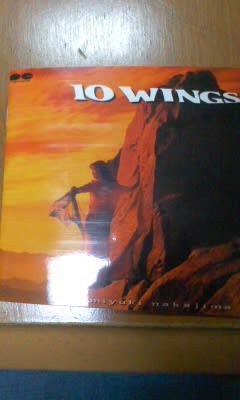
これら9曲のうち,1993年の夜会で歌われたものは1曲だけで,それがアルバムの最後に収録されている「人待ち歌」という曲です。文字通りに人を待つ歌です。
来る,来ない,来る,来ない,
待つ,待たない,待つ,待たない,
逢う,逢えない,逢う,逢えない,
これはこの楽曲の最後の方のフレーズです。花占いを連想させます。そしてこの楽曲はそのほとんどが,来る,来ない,と,待つ,待たない,で構成されているきわめてシンプルな歌です。ですが中ほどで以下のフレーズが繰り返されます。
荒野を越えて 銀河を越えて
戦さを越えて 必ず逢おう
ここの部分はとても力強く歌われます。僕はこの部分が好きで,この曲を聴くことがあります。
第五部定理二七は,次のようにいっています。
「この第三種の認識から,存在しうる限りの最高の精神の満足(summa Mentis acquiescentia)が生ずる」。
これはスピノザによる証明Demonstratioと異なるのですが,この定理Propositioは,僕たちが第三種の認識cognitio tertii generisによって何かを認識するcognoscereことがあれば,第二部定理四三により,自分がそれを認識しているということも知るということから明らかだといえます。なぜならそれは他面からいえば,第三種の認識によって何かを認識している自分自身あるいは自分の精神mensを知るという意味なので,第三部諸感情の定義二五により,僕たちはこのときに自己満足Acquiescentia in se ipsoを感じるからです。一方,第四部定理五二では,存在し得る最高の満足は,理性ratioから生じる自己満足であるといわれています。したがって厳密にいうと第四部定理五二と第五部定理二七は矛盾するのですが,自己満足が最高の満足であるという点に留意するなら,僕たちが第三種の認識で何事かを認識する場合に,最高の精神の満足が生じるということ自体は明らかだといえるでしょう。
矛盾していると思われる部分についても追及しておきましょう。まず徳と満足と至福の関係からです。
第五部定理四二から分かるように,スピノザは人間にとっての至福beatitudoを徳virtusの報酬としてではなく,徳そのものとみなします。したがって最高の至福というのは最高の徳でなければなりません。では最高の徳とは何かといえば,第四部定理二八で,それは神Deiを認識することであるとスピノザはいっています。第二部定理四七は,僕たちが理性によって神を認識し得るということを明らかに意味し得ます。ですから僕たちが理性によって最高の徳いい換えれば最高の至福に達し得ることは間違いありません。同時にその認識はそれを認識している自分自身の認識でもあるので,第四部定理五二は最高の徳を伴い得ます。
一方,第五部定理二四は,個物res singularesを認識するほどそれだけ神を多く認識するといっています。僕たちが個物を認識する,十全に認識するのは第二種の認識cognitio secundi generisすなわち理性によってではなく,第三種の認識cognitio tertii generisによってです。スピノザがいう理性の限界というのはその点にあったからです。したがって僕たちは第三種の認識で何かを認識すればするほど神を認識するのです。
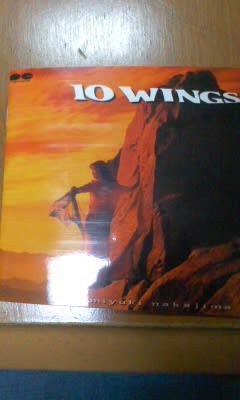
これら9曲のうち,1993年の夜会で歌われたものは1曲だけで,それがアルバムの最後に収録されている「人待ち歌」という曲です。文字通りに人を待つ歌です。
来る,来ない,来る,来ない,
待つ,待たない,待つ,待たない,
逢う,逢えない,逢う,逢えない,
これはこの楽曲の最後の方のフレーズです。花占いを連想させます。そしてこの楽曲はそのほとんどが,来る,来ない,と,待つ,待たない,で構成されているきわめてシンプルな歌です。ですが中ほどで以下のフレーズが繰り返されます。
荒野を越えて 銀河を越えて
戦さを越えて 必ず逢おう
ここの部分はとても力強く歌われます。僕はこの部分が好きで,この曲を聴くことがあります。
第五部定理二七は,次のようにいっています。
「この第三種の認識から,存在しうる限りの最高の精神の満足(summa Mentis acquiescentia)が生ずる」。
これはスピノザによる証明Demonstratioと異なるのですが,この定理Propositioは,僕たちが第三種の認識cognitio tertii generisによって何かを認識するcognoscereことがあれば,第二部定理四三により,自分がそれを認識しているということも知るということから明らかだといえます。なぜならそれは他面からいえば,第三種の認識によって何かを認識している自分自身あるいは自分の精神mensを知るという意味なので,第三部諸感情の定義二五により,僕たちはこのときに自己満足Acquiescentia in se ipsoを感じるからです。一方,第四部定理五二では,存在し得る最高の満足は,理性ratioから生じる自己満足であるといわれています。したがって厳密にいうと第四部定理五二と第五部定理二七は矛盾するのですが,自己満足が最高の満足であるという点に留意するなら,僕たちが第三種の認識で何事かを認識する場合に,最高の精神の満足が生じるということ自体は明らかだといえるでしょう。
矛盾していると思われる部分についても追及しておきましょう。まず徳と満足と至福の関係からです。
第五部定理四二から分かるように,スピノザは人間にとっての至福beatitudoを徳virtusの報酬としてではなく,徳そのものとみなします。したがって最高の至福というのは最高の徳でなければなりません。では最高の徳とは何かといえば,第四部定理二八で,それは神Deiを認識することであるとスピノザはいっています。第二部定理四七は,僕たちが理性によって神を認識し得るということを明らかに意味し得ます。ですから僕たちが理性によって最高の徳いい換えれば最高の至福に達し得ることは間違いありません。同時にその認識はそれを認識している自分自身の認識でもあるので,第四部定理五二は最高の徳を伴い得ます。
一方,第五部定理二四は,個物res singularesを認識するほどそれだけ神を多く認識するといっています。僕たちが個物を認識する,十全に認識するのは第二種の認識cognitio secundi generisすなわち理性によってではなく,第三種の認識cognitio tertii generisによってです。スピノザがいう理性の限界というのはその点にあったからです。したがって僕たちは第三種の認識で何かを認識すればするほど神を認識するのです。














