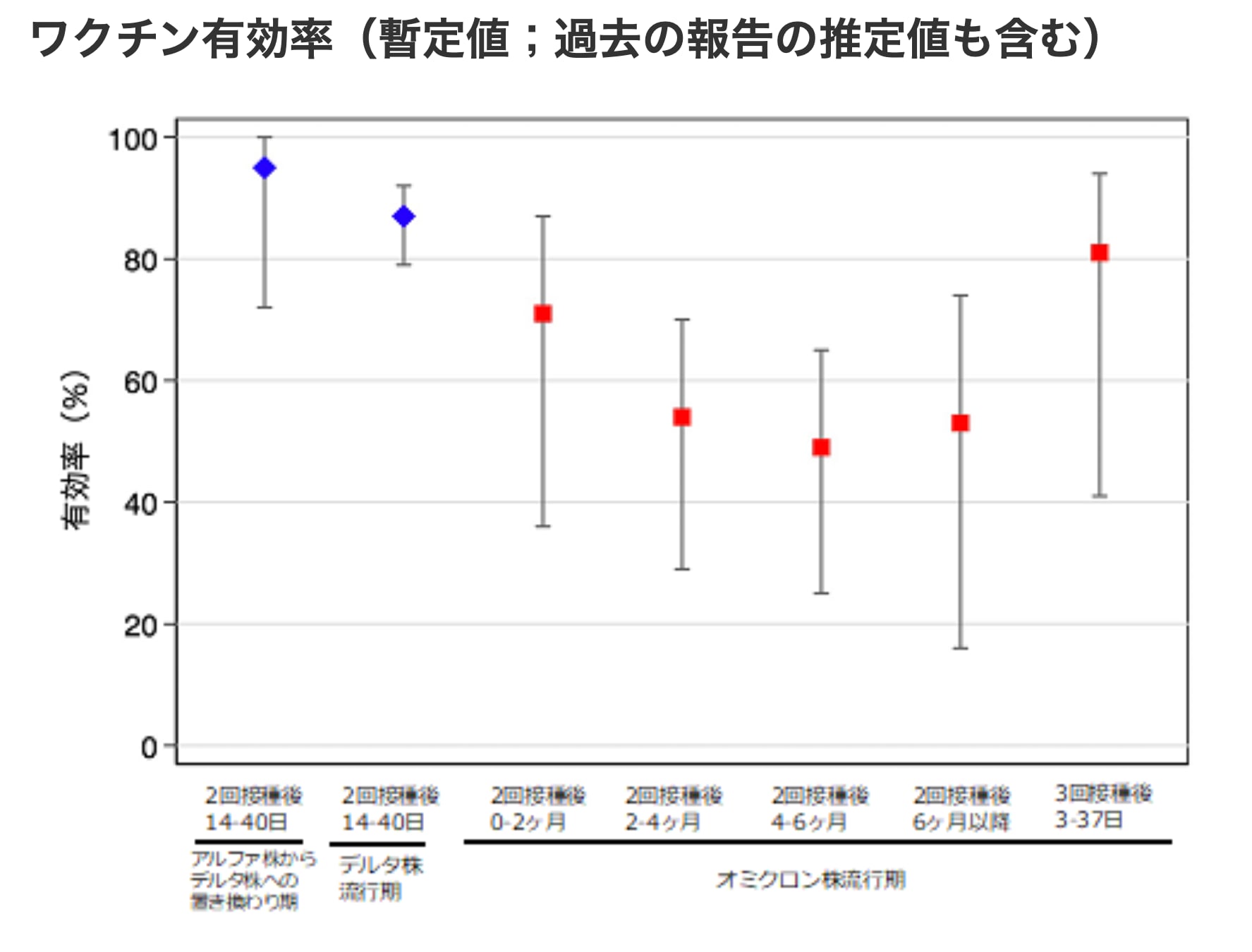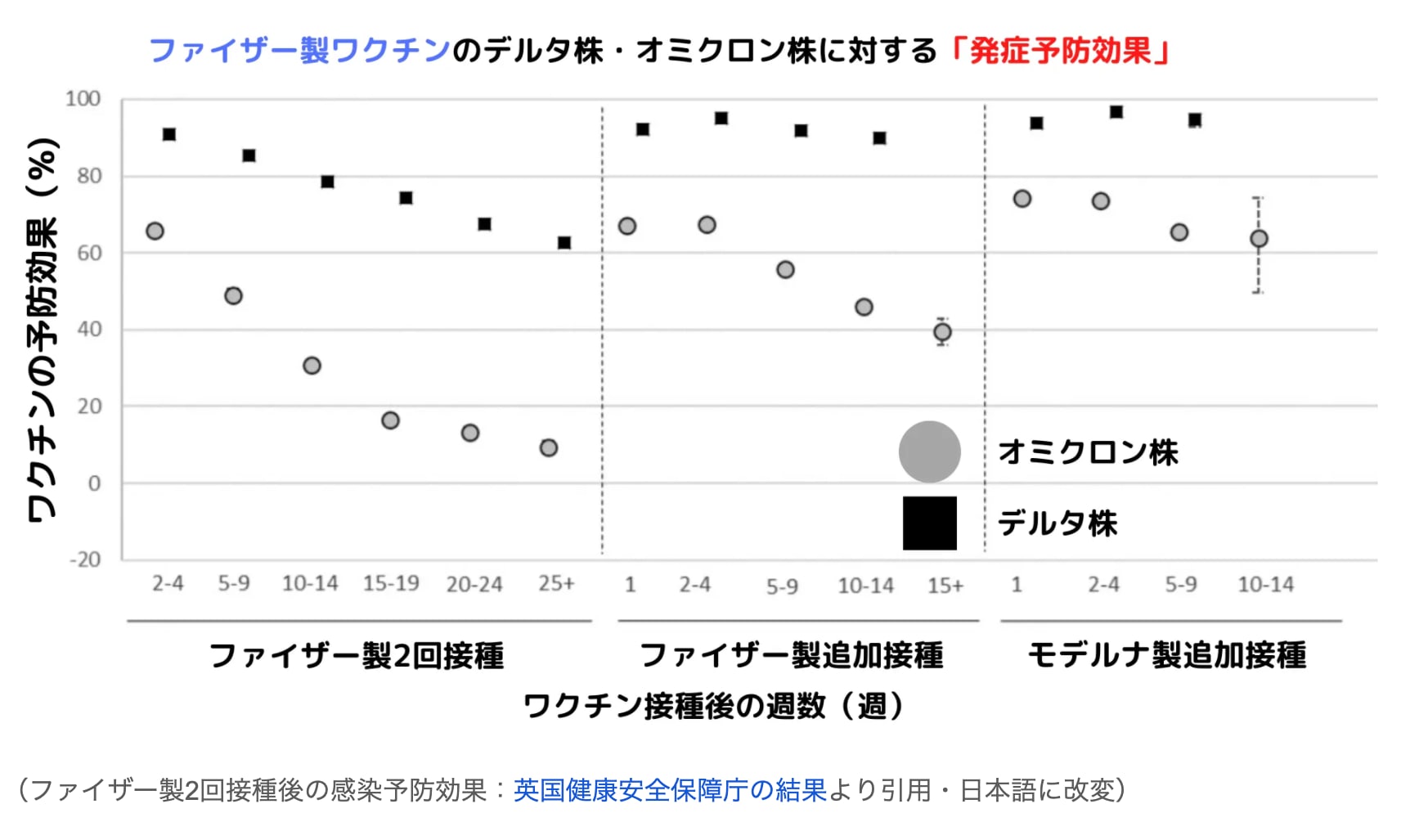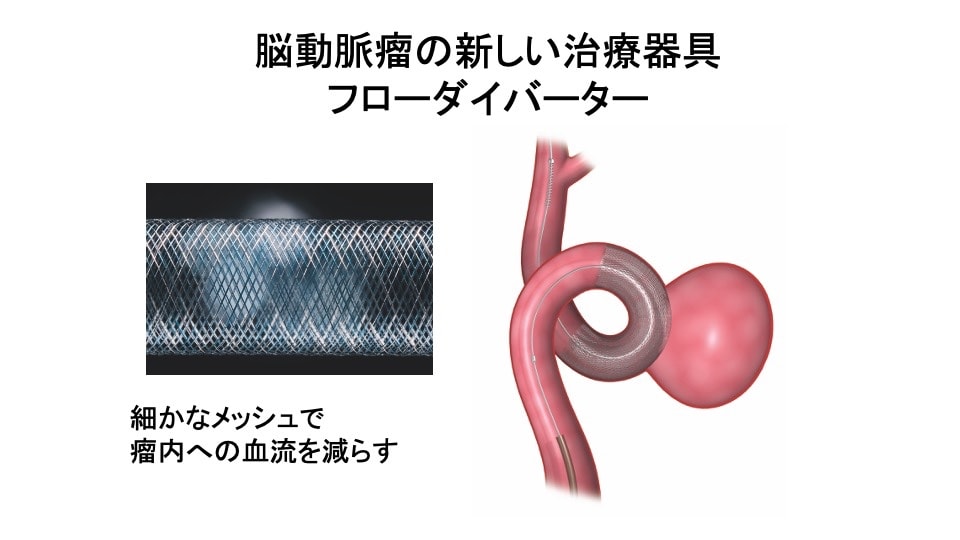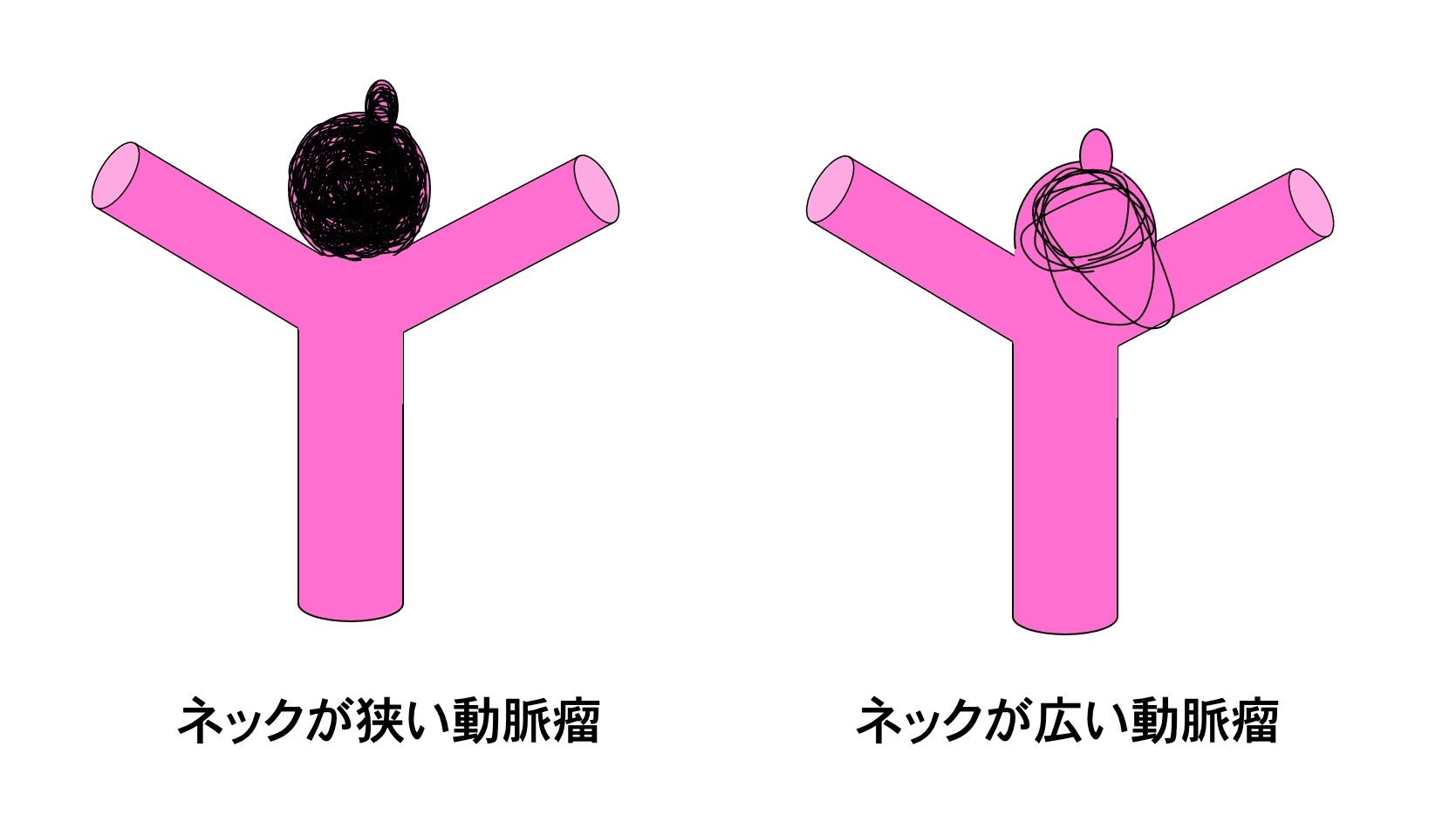みなさんこんにちは!
血液サラサラの薬(抗血栓薬)を内服している人が手術などを受ける際、担当医から薬を中止して欲しいと言われることがあります。では、その場合にはやめてしまっていいのでしょうか?
実はそう簡単ではありません。薬を中止すれば、手術などの際の出血を減らすことはできますが、一方で脳梗塞を起こすリスクが増えてしまうのです。
ではどうしたらいいのでしょうか?
今回はこの疑問にお答えするため、手術などの際に血液サラサラの薬を止めるタイミングなどについてお話ししたいと思います。
最初に結論を言うと、「各薬剤の特性や、手術の種類、個々の患者さんの状態に合わせてお薬をやめるタイミングを決定する」ということになります。
まず血液サラサラの薬には大きく分けて2種類あります。( )内は商品名です。
1)抗血小板薬:アスピリン(バイアスピリン)、シロスタゾール(プレタール)、クロピドグレル(プラビックス)、プラスグレル(エフィエント)など。
血液の中を流れる血小板という成分の働きを抑えることで、血栓の形成を防ぐ薬です。
2)抗凝固薬:ワルファリン(ワーファリン)、ダビガトラン(プラザキサ)、リバーロキサバン(イグザレルト)、アピキサバン(エリキュース)、 エドキサバン(リクシアナ)
ワルファリンや直接経口抗凝固薬(Direct Oral Anticoagulant: DOAC)は血液が固まる(凝固する)のを防ぐ薬です。
これらの薬をどのタイミングでやめるか?薬によって推奨が変わってきます。
抗血小板薬について、ざっくりと言えばマイルドな薬(アスピリンやシロスタゾール)は継続が可能なことが多く、強めの薬(クロピドグレルやプラスグレル)は1週間前後前から中止することが多いです。
一方、抗凝固薬はワルファリンはその効き具合が数値でわかるので(PT-INR)、その数値によって出血リスクが変わります。またDOACの場合には当日朝からの中止で良いとされています。
今回の動画で詳しく解説していますのでぜひご覧ください!