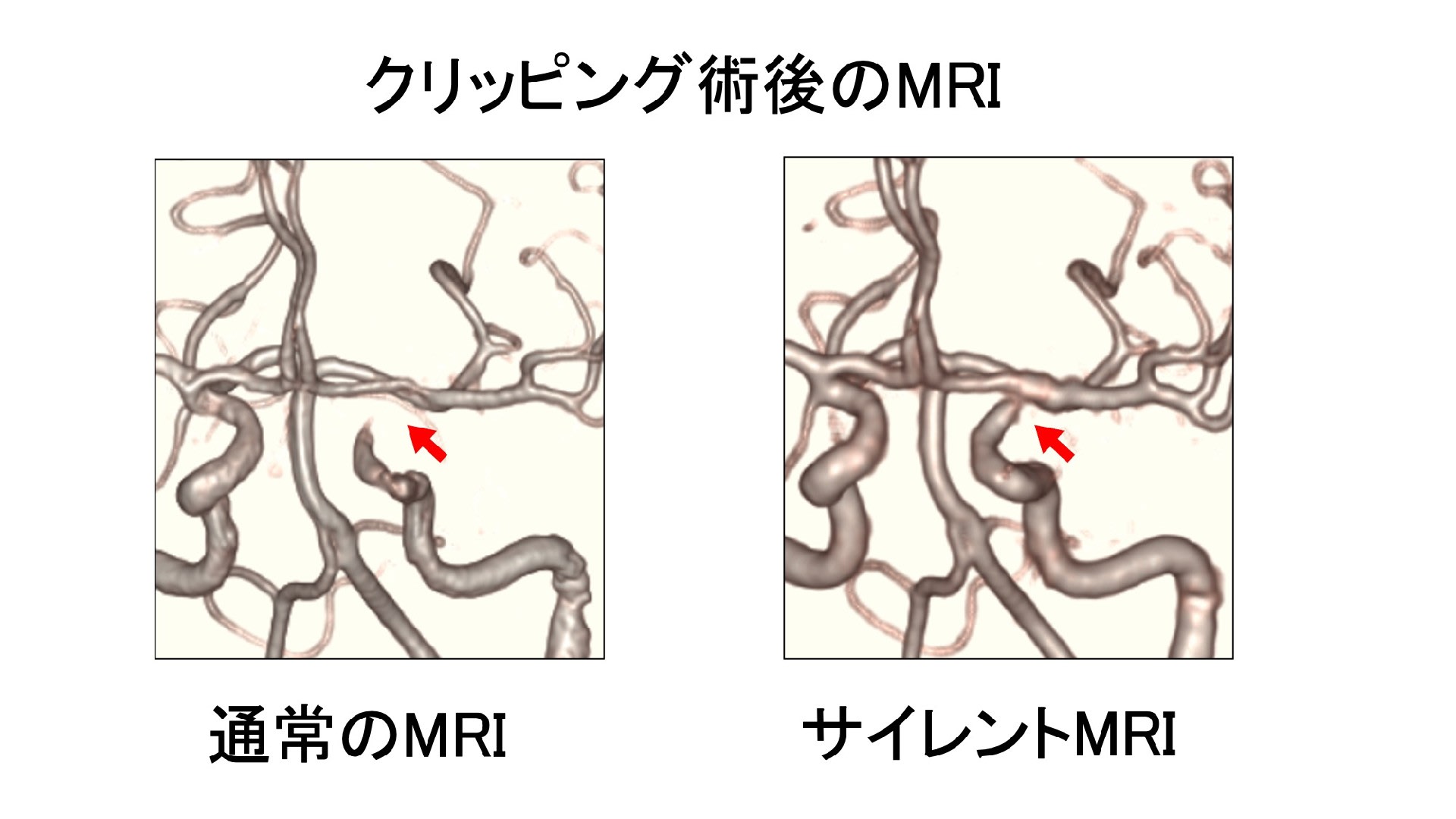未破裂脳動脈瘤患者さんに「アルコールを飲んでも良いですか?」と良く質問されます。今回はこの質問にお答えしたいと思います。
アルコール摂取と脳卒中との関連性については1989年に報告がなされています(Stroke 1989;20:741-746)。この論文の中で、「過度のアルコール摂取はくも膜下出血を増やす」ことが報告されています。
では「過度」とはどの程度を指すのでしょうか?
この研究では、アルコールの摂取量によって、1)非飲酒者、2)過去の飲酒者、3)1本/日未満、4)1−2本/日、5)3本以上/日に分けています。お酒の種類は多岐にわたっており、ウイスキー, ジン, ラム, カクテル, ブランデー, ウォッカ, etcでした。この論文では、「過度の飲酒」を「5)3本以上/日」としています。
解析の結果、5)3本以上/日の飲酒者は非飲酒者に比べ出血性脳卒中が3.64倍多いという結果でした(RR=3.64,95% confidence interval [CI] = 1.11-11.92)。また血圧での補正をしないとさらに増えていました(3.85倍)。飲酒者に多い高血圧という要素を除いても大量の飲酒(3本以上/日)は出血性脳卒中を増やすことが示されました。
出血性脳卒中には脳出血とくも膜下出血が含まれています。このため、それぞれを分けた解析も行われています。その結果、過度の飲酒者は脳出血が6.82倍多く(RR=6.82 and 95% CI= 1.48-31.44.)、くも膜下出血が1.6倍多いという結果でした(RR=1.62 and 95% CI=0.22- 11.82)。
以上の結果から過度の飲酒は主に脳出血を増やし、くも膜下出血も増やすということになります。
過度のアルコール摂取は血管の壁を弱くするとする報告があり、これが動脈瘤の形成や破裂に寄与しているのかもしれません。
しかし、適度なアルコール摂取はあまりリスクはないようで、この研究では2)3)4)のグループでは脳卒中が増えていませんでした。
以上が米国のガイドラインで過度の飲酒がくも膜下出血を増やす、と記載されているデータになります。
しかし、この研究は未破裂脳動脈瘤を持つ人の破裂率が上がるかどうかを解析したものではありません。また、飲むアルコールの種類が規定されておらず、ワインやウォッカとビールなどが同等に扱われています。確かに1日ワインをボトル3本以上飲むということは「過度」と思いますが、ビール350ml3本であれば随分違う印象です。
またこの研究からすでに35年が経過しており、ライフスタイルや他の危険因子の管理もずいぶん変わってきています。このことから、未破裂脳動脈瘤のある方の飲酒については、厳格な制限をするほどの質の高いデータはなく、常識的に適量と言える程度なら許容可能かもしれません。
ちなみに厚生労働省が示す指標では、適度な飲酒は「1日平均純アルコール20g程度」とされています。具体的には、ビール 中ビン1本、日本酒 1合、チューハイ(7%)350ml缶 1本などです。
ただし、飲酒者は血圧が上がりやすいため、その管理は極めて重要です。
次回は飲酒についてもう少しお話ししたいと思います。