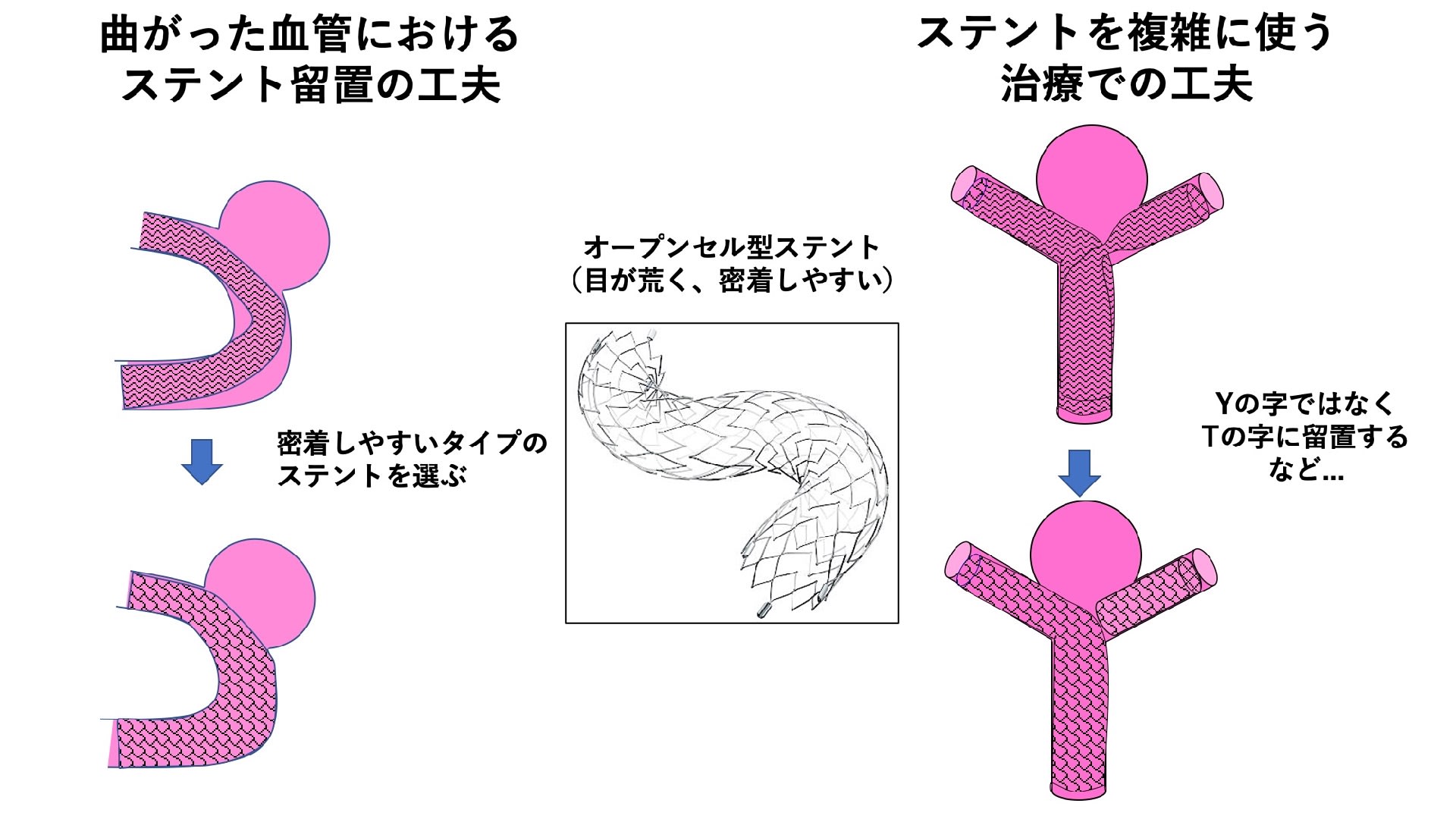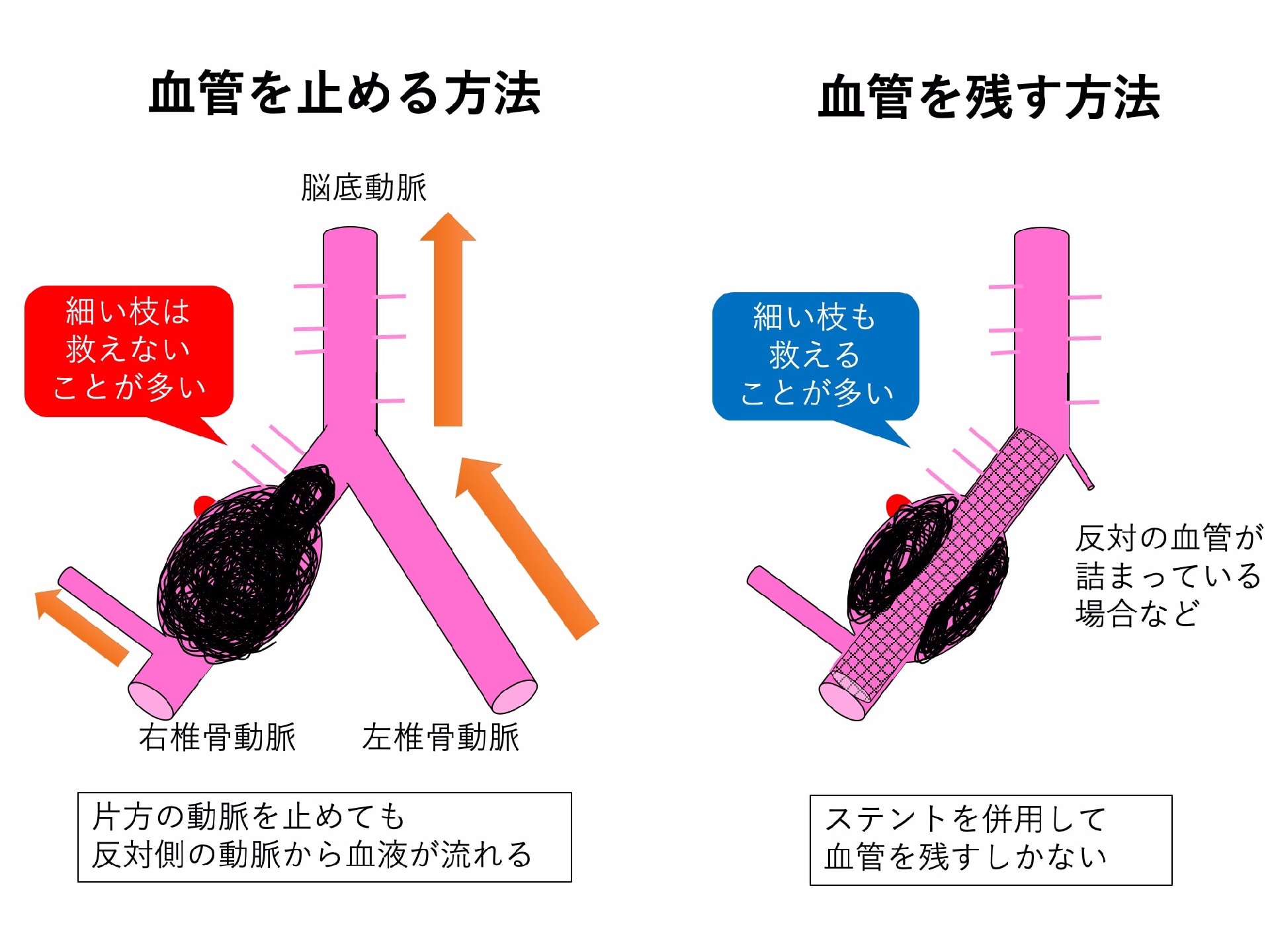未破裂脳動脈瘤をお持ちの患者さんから、下記のようなお問い合わせをいただきました。
「5ミリの未破裂脳動脈瘤もちです。経過観察中です。最近コロナの後遺症の話がニュースで報道されていますがその中にくも膜下出血を起こすというものがありました。
未破裂もちはコロナにかかると破裂する可能性が高いのでしょうか?もちろん気をつけて生活はしていますが特に気をつけないといけないのでしょうか?」
調べた範囲でお答えしたいと思います。
まず、「コロナ感染が脳動脈瘤破裂を増やす」という報道はどんなものだったのでしょうか。
ご存知の方がおられればぜひ教えていただければと思います。
私はGoogleなどでうまく見つけられませんでした。
私が想定するのは、
1)コロナ感染で通院をやめてしまい、血圧の薬などを自己中止してしまった
2)自粛中にタバコを再開してしまった
3)お酒が増えてしまった
4)脳動脈瘤の定期検査を辞めてしまった
5)自粛で太ってしまい、それにともなって血圧が上がった
といったようなことがあれば、動脈瘤の破裂率が上がると考えます。
なぜなら脳動脈瘤の破裂に関連する因子は、1)高血圧、2)喫煙、3)大量の飲酒、とされているからです。
このため、不確かな情報に振り回されず、これまで通りの危険因子管理をきっちりと継続すること。これが私からのアドバイスです。
予防の詳細については、拙書「脳卒中をやっつけろ!」(三輪書店)をお読みください。
さて、コロナとくも膜下出血、あるいは、コロナの後遺症とくも膜下出血として医学文献検索(Pubmed)をしたところ、むしろフランスからは「くも膜下出血患者さんが激減している」と報告されていました。(J Neurosurg Sci. 2020 Apr 29. doi: 10.23736/S0390-5616.20.04963-2. )
ではコロナウイルス蔓延で、くも膜下出血は減っているのでしょうか?
実際はそうではないと考えられています。
この論文では、くも膜下出血患者さんの搬入が減っている原因として、「コロナ感染を恐れて患者さんが病院を受診しない」ことが想定されています。つまり、病院でのコロナ感染を恐れるあまり、本来早期に受診して治療を受ければ救われるはずの方が、自宅で命を落としているのではないか、と想定されているのです。
マスコミでは毎日のようにコロナ感染の増加や、院内感染が報道されています。注意喚起のためなのでしょうが、全国の病院数から考えれば院内感染が起きたのはごく一部で、ほとんどの病院では院内感染を起こさずうまく診療ができていることになります。
しかも一旦院内感染を起こした病院は、再発予防が徹底されますから、むしろ安全になっていると考えられます。
以上を考えれば、脳卒中の症状が出ているのに、極めて低い感染リスクを恐れて病院にかからず、手遅れになるというのでは本末転倒だと思います。
私は毎日病院に勤務していますし、他の病院にも訪問しますが、救急患者さんの診療以外で不安を感じることはまずありません。外来でも皆さん、熱を測り問診に答えていただいた上で、マスク、手指の消毒をしてもらっていますので、リスクは極めて低いと考えています。
私にとっては、外来診察よりも、混んだお店や公共交通機関の方が不安です。(ですから、できるだけお店には行かず、車で通勤しています。)
これは、どこの病院も院内感染が起きないよう徹底的なチェックと隔離が行われていることを知っているからです。私たち病院関係者は、『感染症のプロフェッショナル』とともに、医療者と患者さんを守るために頑張っています。
ですから、脳卒中を疑う症状(手足や顔の麻痺、言語障害、激しい頭痛など)がある場合には、ためらわずに救急車を呼びましょう。
「5ミリの未破裂脳動脈瘤もちです。経過観察中です。最近コロナの後遺症の話がニュースで報道されていますがその中にくも膜下出血を起こすというものがありました。
未破裂もちはコロナにかかると破裂する可能性が高いのでしょうか?もちろん気をつけて生活はしていますが特に気をつけないといけないのでしょうか?」
調べた範囲でお答えしたいと思います。
まず、「コロナ感染が脳動脈瘤破裂を増やす」という報道はどんなものだったのでしょうか。
ご存知の方がおられればぜひ教えていただければと思います。
私はGoogleなどでうまく見つけられませんでした。
私が想定するのは、
1)コロナ感染で通院をやめてしまい、血圧の薬などを自己中止してしまった
2)自粛中にタバコを再開してしまった
3)お酒が増えてしまった
4)脳動脈瘤の定期検査を辞めてしまった
5)自粛で太ってしまい、それにともなって血圧が上がった
といったようなことがあれば、動脈瘤の破裂率が上がると考えます。
なぜなら脳動脈瘤の破裂に関連する因子は、1)高血圧、2)喫煙、3)大量の飲酒、とされているからです。
このため、不確かな情報に振り回されず、これまで通りの危険因子管理をきっちりと継続すること。これが私からのアドバイスです。
予防の詳細については、拙書「脳卒中をやっつけろ!」(三輪書店)をお読みください。
さて、コロナとくも膜下出血、あるいは、コロナの後遺症とくも膜下出血として医学文献検索(Pubmed)をしたところ、むしろフランスからは「くも膜下出血患者さんが激減している」と報告されていました。(J Neurosurg Sci. 2020 Apr 29. doi: 10.23736/S0390-5616.20.04963-2. )
ではコロナウイルス蔓延で、くも膜下出血は減っているのでしょうか?
実際はそうではないと考えられています。
この論文では、くも膜下出血患者さんの搬入が減っている原因として、「コロナ感染を恐れて患者さんが病院を受診しない」ことが想定されています。つまり、病院でのコロナ感染を恐れるあまり、本来早期に受診して治療を受ければ救われるはずの方が、自宅で命を落としているのではないか、と想定されているのです。
マスコミでは毎日のようにコロナ感染の増加や、院内感染が報道されています。注意喚起のためなのでしょうが、全国の病院数から考えれば院内感染が起きたのはごく一部で、ほとんどの病院では院内感染を起こさずうまく診療ができていることになります。
しかも一旦院内感染を起こした病院は、再発予防が徹底されますから、むしろ安全になっていると考えられます。
以上を考えれば、脳卒中の症状が出ているのに、極めて低い感染リスクを恐れて病院にかからず、手遅れになるというのでは本末転倒だと思います。
私は毎日病院に勤務していますし、他の病院にも訪問しますが、救急患者さんの診療以外で不安を感じることはまずありません。外来でも皆さん、熱を測り問診に答えていただいた上で、マスク、手指の消毒をしてもらっていますので、リスクは極めて低いと考えています。
私にとっては、外来診察よりも、混んだお店や公共交通機関の方が不安です。(ですから、できるだけお店には行かず、車で通勤しています。)
これは、どこの病院も院内感染が起きないよう徹底的なチェックと隔離が行われていることを知っているからです。私たち病院関係者は、『感染症のプロフェッショナル』とともに、医療者と患者さんを守るために頑張っています。
ですから、脳卒中を疑う症状(手足や顔の麻痺、言語障害、激しい頭痛など)がある場合には、ためらわずに救急車を呼びましょう。