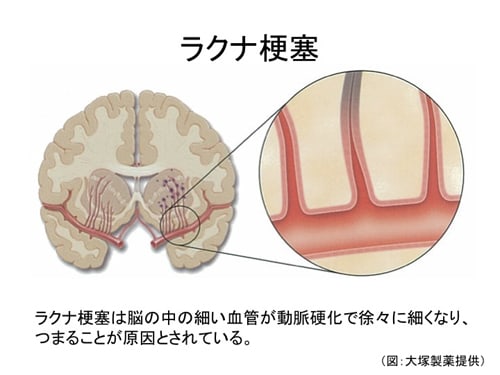瀬木さん、コメントありがとうございました。
瀬木さんは、私の患者さんですが、楽しいブログを書かれているということで紹介させて頂きます。
寅次郎の徒然草
http://blog.livedoor.jp/torajiro0421/
先日外来に来られた時に、このブログの話から、ふと思いつき、
「だいぶ前のことですけど、瀬木さんという人に、ダイナランドでスキーを教えてもらったのですがお知り合いですか?」
とお聞きしたところ、「はい、それは私の弟です」とのこと!!
私は大学1-2年生の頃、体育学科の徳重君とスキーにハマっていて、「一度スキー教室に入ってみようか?」ということになりました。
自信過剰の我々は、こともあろうにダイナランドの「上級コース」を受けることにしたのですが、その指導員が「瀬木さん」という日焼けしたカッコいい人でした。
片足での直滑降など、瀬木さんがされると簡単そうに見えるのですが、われわれがやるとあっちへふらふら、こっちへふらふら。
「背伸びしてすいませんでした...」という感じでしたが、我々はこれでスキー熱に火がつき、その後、頻繁にスキー教室に通いました。その後は「中級コース」にしましたが、そこでも瀬木さんに教えて頂いたことがあります。
その後、われわれは「岐阜アルペンスキークラブ」という社会人の団体に属し、SAJ 1級をなんとか取ることができました。
瀬木さんは現在、高鷲スノーパークのスキー学校で校長先生をされているとのこと。また教えてもらいたいです。
しかしあの「瀬木さん」のお兄さんだったとは!
世の中狭いですねー。
冬はお願いします。m(_ _)m
瀬木さんは、私の患者さんですが、楽しいブログを書かれているということで紹介させて頂きます。
寅次郎の徒然草
http://blog.livedoor.jp/torajiro0421/
先日外来に来られた時に、このブログの話から、ふと思いつき、
「だいぶ前のことですけど、瀬木さんという人に、ダイナランドでスキーを教えてもらったのですがお知り合いですか?」
とお聞きしたところ、「はい、それは私の弟です」とのこと!!
私は大学1-2年生の頃、体育学科の徳重君とスキーにハマっていて、「一度スキー教室に入ってみようか?」ということになりました。
自信過剰の我々は、こともあろうにダイナランドの「上級コース」を受けることにしたのですが、その指導員が「瀬木さん」という日焼けしたカッコいい人でした。
片足での直滑降など、瀬木さんがされると簡単そうに見えるのですが、われわれがやるとあっちへふらふら、こっちへふらふら。
「背伸びしてすいませんでした...」という感じでしたが、我々はこれでスキー熱に火がつき、その後、頻繁にスキー教室に通いました。その後は「中級コース」にしましたが、そこでも瀬木さんに教えて頂いたことがあります。
その後、われわれは「岐阜アルペンスキークラブ」という社会人の団体に属し、SAJ 1級をなんとか取ることができました。
瀬木さんは現在、高鷲スノーパークのスキー学校で校長先生をされているとのこと。また教えてもらいたいです。
しかしあの「瀬木さん」のお兄さんだったとは!
世の中狭いですねー。
冬はお願いします。m(_ _)m